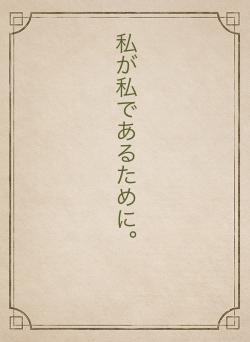ただ、天井を眺めていた。何もない、真っ白な。
「……元気にしてる、かな」
俺は無意識にスマホを開いた。もう開かなくたって分かってるのに。結衣莉とのメールの最後は俺が送った『ごめん』。
もう、終わった、はずなのに。自分で、終わらせた、はずなのに。
どうしても離れない、結衣莉の笑顔が頭から。思い出すと胸が苦しくなる。
コンコン、というノックが聞こえた。一瞬結衣莉ではないか、というどうしようもない期待を抱いたがそんなわけはない。
「おはようございます、今日はお変わりないですか?」
「はい」
入ってきたのはいつもの看護師の人。点滴を変えに来たらしい。結衣莉は、今の俺を見たら、どう思うだろうか。
あの家には、結衣莉との「思い出」がたくさん詰まっていた。だからこそ、俺はこうしたのだ。あんなに思い出が詰まった場所にいると、「さよなら」が言えなくなる。それはいずれ俺だけじゃなくて結衣莉を苦しめてしまうものだった。
だから、俺は『ごめん』って一言残して出て行った。今だから思えることだけど、もっと何かなかったのかなって。
何も直接話さずに『ごめん』だなんて、そっちの方が苦しめたに決まってる。
俺は看護師の人が出て行った後、ベッドから上半身を起こして横に置いていた鏡を持つ。俺は人工的な硬い髪にそっと手を触れる。それ、を外した俺は俺ではなかった―—。
「……元気にしてる、かな」
俺は無意識にスマホを開いた。もう開かなくたって分かってるのに。結衣莉とのメールの最後は俺が送った『ごめん』。
もう、終わった、はずなのに。自分で、終わらせた、はずなのに。
どうしても離れない、結衣莉の笑顔が頭から。思い出すと胸が苦しくなる。
コンコン、というノックが聞こえた。一瞬結衣莉ではないか、というどうしようもない期待を抱いたがそんなわけはない。
「おはようございます、今日はお変わりないですか?」
「はい」
入ってきたのはいつもの看護師の人。点滴を変えに来たらしい。結衣莉は、今の俺を見たら、どう思うだろうか。
あの家には、結衣莉との「思い出」がたくさん詰まっていた。だからこそ、俺はこうしたのだ。あんなに思い出が詰まった場所にいると、「さよなら」が言えなくなる。それはいずれ俺だけじゃなくて結衣莉を苦しめてしまうものだった。
だから、俺は『ごめん』って一言残して出て行った。今だから思えることだけど、もっと何かなかったのかなって。
何も直接話さずに『ごめん』だなんて、そっちの方が苦しめたに決まってる。
俺は看護師の人が出て行った後、ベッドから上半身を起こして横に置いていた鏡を持つ。俺は人工的な硬い髪にそっと手を触れる。それ、を外した俺は俺ではなかった―—。