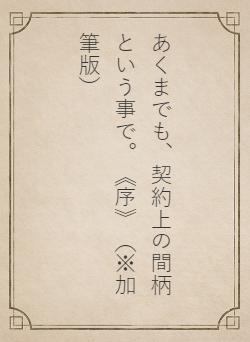何かに躓いたような感覚があった。まるで雲の上でたたらを踏んだような感触の後、周りががらりと変わっていた。四方を岩壁に囲まれた空間。足元に揺蕩う澄んだ水。その中央には、抜身の日本刀が刺さっていた。
「うっわ危ない上に錆びっ錆びになるやん」
そして冒頭の呟きに至る。
誰もいないとは言え、抜身の刃なんて見るからに危険だし、潮の香りがしないから恐らく足元は真水なのだろうけど、とにかく水に触れているなんて刀剣に良くない。日本刀は繊細なのだ。これが真剣であったらの話だけど。しかも刺さった刀剣って何だ。アーサー王の聖剣か。いや。アーサー王の聖剣は、岩に刺さっていたとか湖の妖精に鍛え直してもらったとか、諸説あり過ぎるけど。
彼女は腕組みをして仁王立ちで、まじまじと刀剣を見つめた。続いて腕を解き、水に服の裾が触れないように気を付けながら、膝をつくようにして刀身を観察する。
「綺麗だなあ」
彼女は呼気が刀身にかからぬように両手で口をおさえながら、感嘆の息をついていた。この石室において自ら光を放つような、同時に流れるような輝きを見せる刀剣は、まるで生きているようだ。鍔や柄の意匠も繊細そのもの。何より、虎だとか龍だとか、あからさまに強い存在をモチーフとしていない所が、彼女は個人的に気に入った。単眼鏡を持っていたら、じっくりと観察している所だ。
さて、これを管理している人は誰だろう。どういう意図かはわからないけれど、こんなに素敵な刀剣を錆びるかもしれない状況に置いておく訳にはいかない。普段から博物館や美術館で厳重かつ丁重に管理・保管されている武器武具や工芸品の類いを目にしているから、尚更そう思う。
「あのう。すみません。どなたかいらっしゃいませんか。ごめんください」
周囲を見渡すと、丁度自分の背後に通路があった。つまり人の出入りはあると確信していいだろう。なので呼びかけたのだが、彼女の声が反響して消えていくだけだった。誰もいないか、声が届かぬ程に通路が長いかのどちらかと見なしていいだろう。
人を探して状況を伝えるか、それともこの刀剣を持って進むか。彼女は考えた。一拍の間だけだった。
「決めた。持っていこう。抜けたらだけど」
見れば、それは頑丈そうな台座にしっかりと刺さっているように見える刀。自分の腕力で抜く事ができるかはわからない。抜けたら持って行って、持ち主なり管理人なりを見付けたら状況を説明して、持ち出した事をきちんと謝る。抜けなかったら抜けなかったで、彼女単独で通路を進んで持ち主あるいは管理人を探して状況を説明する。そうすれば同時に、ここが一体何処なのかもわかるだろう。
さて刀剣に向き直った彼女だが、唐突に思い出した。『刀剣を扱う時は、素手で触ってはいけません』という、刀剣専門の雑誌か何かで読んだ注意書きを。なので彼女は予備に持っていた、未使用のタオルハンカチを取り出した。流石に手袋の代わりにはならないと思うが、素手で触るよりかは良いであろうと判断したのだ。
柄をタオルハンカチでそっと包み込み、滑らないように両手でしっかりと掴む。足を思い切り踏ん張り、腰に重心をかけて両腕に力を込めた。
「せーの!」
抜けた。
刀は、あまりにもすんなりと抜けた。まるで豆腐に刺した竹串を抜くかのようにあっけない手応えだった。
途端に、周囲が明るくなった。石室に広がる優しい光は人の形を取り、彼女の前に降りてきた。温かい手が、刀の柄を握る彼女の両手を包み込む。
目の前には青年が浮かんでいた。銀の髪に、白を基調に銀糸で縫い取りをした豪奢な和装。輝くような容姿の青年は、無上の僥倖に巡り会えたかのような笑顔で彼女を見つめている。
驚きはしたが、何とか刀を取り落とさずに握り締めた彼女は、ぱちぱちと瞬きをした。
「わあびっくりした。こんにちは。とても明るくて綺麗ですね。ええと、貴方はどなた?」
『私はこの刀に宿る者。人は私を銀刀、あるいは銀大神と呼ぶ』
「付喪神という解釈で合っていますか?器物に宿る神様なんて、私、生まれて初めて見ましたよ」
当たり前である。
付喪神は妖にもカテゴライズされるが、きっと神様により近い存在なのだろうなと彼女は解釈した。
銀大神と名乗った彼は『うむ』と鷹揚に頷き、彼女の顔を覗き込んだ。
『そなたをずっと待っていたのだ。会いたかったぞ。我が鞘よ』
「鞘?」
決して悪意は感じない、しかし人に呼びかけるにしては違和感がある言葉に鸚鵡返しをすると、銀大神は『そうだ』と頷いた。
『私と共に在り、私を振るう使い手の事だ。そうでなければ、私を手にする事すら叶わぬ』
イングランドの件の聖剣ではないが、どうやら伝説の剣の類を彼女は手にしてしまったらしい。この物言いだと、そう判断できる。
「私、家に帰る途中だったんですけど、気付いたらここにいました。もしかして、私がここに来たのは、銀の神様…って呼ばせてもらいますね。銀の神様が私を呼んだからですか?ここは私がいた『日本』って国じゃないんでしょうか?」
全然別の世界に来てしまったのだろうか。空き部屋の衣装箪笥を潜り抜けた訳ではないのだが。
とりあえず訊きたかった事を口にすると、銀大神はただ笑った。
『ここは葦原の中津国。外の巫女達からも話を聞くといいだろう。さあ。共に参ろう』
「わかりました」
『葦原の中津国』とは日本神話における日本の名だが、やはり彼女がいた日本とは別物だと考えた方がいいかもしれない。
他に人がいるらしい事はわかったし、ひとまずは情報を得る事を考えるべきだろう。
彼女は刃や鋒が自分に当たらないよう慎重に銀刀を持つと、これまた慎重に通路を進み始めた。
彼女はこの時点で既に、とても不思議な事が起こっている現状を受け入れていた。
「うっわ危ない上に錆びっ錆びになるやん」
そして冒頭の呟きに至る。
誰もいないとは言え、抜身の刃なんて見るからに危険だし、潮の香りがしないから恐らく足元は真水なのだろうけど、とにかく水に触れているなんて刀剣に良くない。日本刀は繊細なのだ。これが真剣であったらの話だけど。しかも刺さった刀剣って何だ。アーサー王の聖剣か。いや。アーサー王の聖剣は、岩に刺さっていたとか湖の妖精に鍛え直してもらったとか、諸説あり過ぎるけど。
彼女は腕組みをして仁王立ちで、まじまじと刀剣を見つめた。続いて腕を解き、水に服の裾が触れないように気を付けながら、膝をつくようにして刀身を観察する。
「綺麗だなあ」
彼女は呼気が刀身にかからぬように両手で口をおさえながら、感嘆の息をついていた。この石室において自ら光を放つような、同時に流れるような輝きを見せる刀剣は、まるで生きているようだ。鍔や柄の意匠も繊細そのもの。何より、虎だとか龍だとか、あからさまに強い存在をモチーフとしていない所が、彼女は個人的に気に入った。単眼鏡を持っていたら、じっくりと観察している所だ。
さて、これを管理している人は誰だろう。どういう意図かはわからないけれど、こんなに素敵な刀剣を錆びるかもしれない状況に置いておく訳にはいかない。普段から博物館や美術館で厳重かつ丁重に管理・保管されている武器武具や工芸品の類いを目にしているから、尚更そう思う。
「あのう。すみません。どなたかいらっしゃいませんか。ごめんください」
周囲を見渡すと、丁度自分の背後に通路があった。つまり人の出入りはあると確信していいだろう。なので呼びかけたのだが、彼女の声が反響して消えていくだけだった。誰もいないか、声が届かぬ程に通路が長いかのどちらかと見なしていいだろう。
人を探して状況を伝えるか、それともこの刀剣を持って進むか。彼女は考えた。一拍の間だけだった。
「決めた。持っていこう。抜けたらだけど」
見れば、それは頑丈そうな台座にしっかりと刺さっているように見える刀。自分の腕力で抜く事ができるかはわからない。抜けたら持って行って、持ち主なり管理人なりを見付けたら状況を説明して、持ち出した事をきちんと謝る。抜けなかったら抜けなかったで、彼女単独で通路を進んで持ち主あるいは管理人を探して状況を説明する。そうすれば同時に、ここが一体何処なのかもわかるだろう。
さて刀剣に向き直った彼女だが、唐突に思い出した。『刀剣を扱う時は、素手で触ってはいけません』という、刀剣専門の雑誌か何かで読んだ注意書きを。なので彼女は予備に持っていた、未使用のタオルハンカチを取り出した。流石に手袋の代わりにはならないと思うが、素手で触るよりかは良いであろうと判断したのだ。
柄をタオルハンカチでそっと包み込み、滑らないように両手でしっかりと掴む。足を思い切り踏ん張り、腰に重心をかけて両腕に力を込めた。
「せーの!」
抜けた。
刀は、あまりにもすんなりと抜けた。まるで豆腐に刺した竹串を抜くかのようにあっけない手応えだった。
途端に、周囲が明るくなった。石室に広がる優しい光は人の形を取り、彼女の前に降りてきた。温かい手が、刀の柄を握る彼女の両手を包み込む。
目の前には青年が浮かんでいた。銀の髪に、白を基調に銀糸で縫い取りをした豪奢な和装。輝くような容姿の青年は、無上の僥倖に巡り会えたかのような笑顔で彼女を見つめている。
驚きはしたが、何とか刀を取り落とさずに握り締めた彼女は、ぱちぱちと瞬きをした。
「わあびっくりした。こんにちは。とても明るくて綺麗ですね。ええと、貴方はどなた?」
『私はこの刀に宿る者。人は私を銀刀、あるいは銀大神と呼ぶ』
「付喪神という解釈で合っていますか?器物に宿る神様なんて、私、生まれて初めて見ましたよ」
当たり前である。
付喪神は妖にもカテゴライズされるが、きっと神様により近い存在なのだろうなと彼女は解釈した。
銀大神と名乗った彼は『うむ』と鷹揚に頷き、彼女の顔を覗き込んだ。
『そなたをずっと待っていたのだ。会いたかったぞ。我が鞘よ』
「鞘?」
決して悪意は感じない、しかし人に呼びかけるにしては違和感がある言葉に鸚鵡返しをすると、銀大神は『そうだ』と頷いた。
『私と共に在り、私を振るう使い手の事だ。そうでなければ、私を手にする事すら叶わぬ』
イングランドの件の聖剣ではないが、どうやら伝説の剣の類を彼女は手にしてしまったらしい。この物言いだと、そう判断できる。
「私、家に帰る途中だったんですけど、気付いたらここにいました。もしかして、私がここに来たのは、銀の神様…って呼ばせてもらいますね。銀の神様が私を呼んだからですか?ここは私がいた『日本』って国じゃないんでしょうか?」
全然別の世界に来てしまったのだろうか。空き部屋の衣装箪笥を潜り抜けた訳ではないのだが。
とりあえず訊きたかった事を口にすると、銀大神はただ笑った。
『ここは葦原の中津国。外の巫女達からも話を聞くといいだろう。さあ。共に参ろう』
「わかりました」
『葦原の中津国』とは日本神話における日本の名だが、やはり彼女がいた日本とは別物だと考えた方がいいかもしれない。
他に人がいるらしい事はわかったし、ひとまずは情報を得る事を考えるべきだろう。
彼女は刃や鋒が自分に当たらないよう慎重に銀刀を持つと、これまた慎重に通路を進み始めた。
彼女はこの時点で既に、とても不思議な事が起こっている現状を受け入れていた。