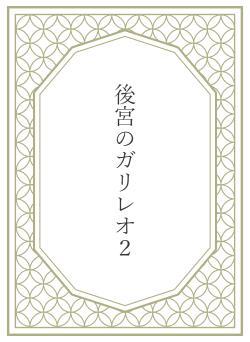目に入ったのは、湖の青。
巳の国の背後にそびえる山。その山頂の湖に、沢山の駕籠が止まっていた。
担ぎ手の男たちは、駕籠の中からずるり、と何かを引きずり出した。……人だ。駕籠の中に折り重なるようにして、数多の人が運ばれてきているのである。
男たちは人を引きずり出すと、そのまま湖へと放り投げた。まるで物のように扱われた人は、手足が千切れ、赤黒い血を巻き散らしながら湖へと沈んでいく。
それが何を意味するか。
理解した瞬間。リツは小さく叫び声を漏らした。
――弔いもせず水を穢し、流れを澱め……。
頭の中で、ミツハの声が木霊する。
「……なんてことを」
流行りやまいで、数多の者が死んだという。その死んだ者たちを弔うこともせず、物のように扱うばかりか、死体を湖に沈めて……。
あまりのことに、リツは口を押え、嘔吐いた。
こんなことが、許されているのか。
あれほどの数の死者。誰かひとりの考えではあるまい。湖に住まう蛟龍のことは、巳の国に住まう全ての者が知っている。不敬を働くことをよしとする者はそう多くはないだろう。
しかし、それを一蹴できる立場の者がいる。
――大王……。
へなへなとくずれ落ち、リツは滂沱する。
「申し訳ありません」
涙が止まらない。どんなに謝っても足りない気がした。
「申し訳……ありません……」
「……リツさま」
イダがそっと手を背に回す。幼子の高い体温が、リツの強張った心を解していく。
「ごめんなさい。イダが見せたから。謝らないでください、リツさま」
リツは首を左右に振った。流れ落ちる涙を手の甲で拭い、ゆっくりと立ち上がる。
「……イダ、ありがとう。知ることができて、良かった」
「リツさま」
リツはイダに頷いてみせる。
――私に何ができるか、わからないけれど。
「戻りましょう。……ミツハさまにお会いしとうございます」
***
「リツ?」
戻ったリツを見て、ミツハは眉を寄せた。無理もない、とリツは思う。きっと今のリツは、泣きはらした瞳をしているに違いないのだ。
「どうしたのです? また何か……思い出したのですか?」
リツは無言で首を左右に振ると、ミツハの衣をそっと握りしめた。
言の葉がうまく出ない。もつれる舌を何とか動かして、リツはミツハに言いつのる。
「私……私にできることはありませんか」
「リツ? なにを……?」
「私は、ミツハさまを【お救いしたい】。道すがら考えたのですが、私には何も……」
現世に戻り、大王に陳情するのは無理がある。そもそも大王に会う手立ても知らぬのだ。楼主に話を通すことも考えたが、そう巧くはいかないであろう。
リツの表情に何かを感じたのであろう、ミツハはす、と息を吸い、背後に控えていたイダに声をかける。
「イダ」
切りつけるような氷のような声に、イダがびくりと体を震わせた。
「お前、言いつけを破ったのか」
「ミツハさま!」
リツはたまらず声を挙げる。
「ちがいます。イダに頼み込み、教えを乞うたのは私です。イダを叱るのはおやめください!」
衣を掴み、必死に述べるリツを見て、ミツハはふ、と息を吐く。
「イダ。控えなさい。わたしはつまと話したい」
「……承知しました」
イダが消えるのを確認すると、ミツハは腰掛にリツを誘う。手を引かれ、隣に座らされたリツの体は硬直していた。
先程の、氷のような冷たい声。
あのような声も出せるのだ、ということも、その声に明らかな怒りが含まれていることも、リツには恐ろしいことであった。
「リツ」
叱られる……!
思わず目をぎゅっと瞑ったリツの唇に、何かやわらかなものが押し付けられた。
「ん……っ」
「口を開けなさい」
言われておずおずと口を開くと、やわらかなものがぎゅっと口の中に押し込まれる。
――甘い……。
舌先で転がすように味わう。何かの果物のようである。蕩けるように甘く、かぐわしい香りが口いっぱいに広がって、リツはゆっくりと体のこわばりを解いた。
目を開くと、思いがけず優しい笑顔を浮かべたミツハの顔。
「お味は?」
「……美味しいです」
ミツハは傍らの小卓の上に手を伸ばし、細い指先で果物を摘まんだ。細長く切りそろえられている果物は黄金色で、瑞々しく果汁を滴らせている。
「もうひとつ」
す、と差し出されて、リツは困惑する。これは、口を開けろ、ということなのだろうか。
おずおずと唇を開くと、きゅっと押し込まれる。舌で少し押すだけで、とろとろと溶けてしまう。口の中に果汁が広がり、頭の中まで蕩けてしまいそうに、甘い。
「これは……瓜、ですか」
ミツハは目を細めて笑うと、自らの指についた果汁をちろりと舐めとった。ひとつひとつの仕草の艶やかさに、リツの鼓動は益々激しくなる。
「まくわがちょうどよい頃合いでしたので。気に入ってもらえてよかった」
またひとつ、摘まんで口へと運ばれそうになるその手を、リツは慌ててきゅっと抑えた。
「じ、自分で食べられます」
「わたしが食べさせたいのです」
「あの、どうか……」
心の臓が、破裂しそうだ。顔が火照って赤くなるリツに、ミツハはくすりと笑いを零した。
「よかった。……緊張は解けましたか」
問われて、リツははっとする。
――ミツハさまは、私のこわばりを解こうとしてくださったんだ。
「安心してください。イダを頭ごなしに叱ることはいたしません。ほんの少しだけ、お灸はすえねばですが……」
ちらりと鋭さを見せた瞳をまた和らげて、ミツハはリツの髪を梳く。
「わがつま。あなたが何を見たのかを聞くのはよしましょう。しかし、気になさることはない。あなたがわたしの隣にいてくれるのであれば、それ以上のことは望みません」
「でも」
リツは言いつのる。
「私はあなたに救われました……」
どんな言の葉でも口にしていい、と言われたこと。自らの苦しみを分かってくれる存在に、リツがどれだけ救われたかしれない。
「ミツハさまが苦しまれているのであれば、私はその苦しみを解く手助けをしとうございます。……それが、あなたさまに捧げられた贄の役目でございます」
次の瞬間、リツは背筋が凍るような恐ろしさを覚えた。ミツハの、赤い、血のような瞳が鋭く光っている。
「贄などいらぬ」
氷のような声。
リツは慌てて口を開き、何も言えず、唇を噤んだ。
「あとは、お好きなように。案内が必要であればイダを呼びなさい」
氷の鋭さを纏ったまま、ミツハは立ち上がる。そのまま一瞥もせずに部屋から出ていく後ろ姿を、リツは青い顔で追った。
――怒らせてしまった……。
血を流し込んだ瞳の鋭さを思い出し、リツは体を強張らせる。自分の、いったい何が彼をここまで怒らせたのか。考えても答えは出ない。
どうしよう、どうしたらいい。
ぐるぐると回る頭を冷やそうと、リツは小卓の瓜を手に取り、ひとつ口へと含む。
――不味い。
あれほど甘く、蕩けるような味だったのに。口の中に広がる果汁をごくりと嚥下し、リツは俯く。手の甲にほたりと落ちた涙が、指先を伝って床に落ちるのを、ただ茫然と眺めていた。
そのまま昼を過ぎ、夜になってもミツハは姿を現さなかった。
リツは一人で昼餉を取り、夜は要らぬとイダに告げ、与えられた自室でぼんやりと丸窓の外を眺めている。
自分のなにかがミツハを怒らせたことはわかっている。しかし、丸一日考えても答えは出なかった。
風に揺れる木々の騒めきを聞きながら、リツは深呼吸する。
――怖いけれど。
直接、聞きに行こう。やってしまったことは取り消せない。しかし、リツの何に怒りを覚えたのかを聞かねば、リツとて対処することが難しい。
自らを見つめる、優しい瞳。涼やかな声、温かな笑顔を思い出し、リツは頷いた。
夜着の上に肩掛けを羽織り、そっと部屋を抜け出す。
本当は、案内にイダを呼ぶべきだったかもしれない。しかし、これ以上イダにミツハの怒りが向くことも避けたい。
宮の廊下は石でできている。なるべく音を立てないように、リツはそっとミツハを探した。
頼れるのは丸窓から差し込む月明かり。薄青く伸びる光を頼りに廊下を渡ると、不意に何かが倒れる音が聞こえた。
同時に、呻き声。地の底から這いあがるような苦しげな声が、廊下に響き渡る。
「……ミツハさま……?」
嫌な予感がした。
リツは急ぎ音の方へ駆ける。廊下を渡り、角を曲がると、昨日リツが寝かされていた部屋に出る。
その中央で、ミツハが倒れていた。
「ミツハさま!」
慌てて駆け寄り、抱き起こすと、酷い汗を掻いている。薄い夜着が捲れ上がり、露わになった胸元に鱗のようなものがびっしりと浮き始めていた。
「ミツハさま、どうなさいました!?」
ミツハはその声には答えない。辛うじて瞳を開けリツを認めると、強い力で突き飛ばす。
「――っ……」
「近……づく……な」
「ミツハ……さま……?」
「自分でも……何をするか、わから……ぬ!」
言うなり、ミツハは体をくの字に折った。腕にも、首筋にも青銀に光る鱗が浮き、赤の瞳は炯々と輝きを増している。そのままのたうち回るように床に転がり、赤黒い血を吐いた。
「ミツハさま……!」
痛む体を無理矢理起こし、リツは床を蹴る。男の体を抱き抱えようと手を伸ばし――その体がぐるりと反転した。
青い文様が描かれた天井が見える。リツは腕を取られ、床にぎりりと押し付けられていた。目の前には赤い双つの光。獰猛な光を宿し、リツをぎらぎらと睨みつけている。掴まれた腕が熱い。普段はひんやりとしているミツハの手が、炎を抱き込んでいるかのような熱さを伴っている。
色の白い、美しい顔に浮かぶ青銀の鱗。口の端からぞろりとはみ出た鋭い牙から、ほたほたと血が落ちている。
「リ……ツ、逃げ……ろ」
赤い目が揺らぐ。狂気と理性を同時に宿しながら、ミツハは呻いた。
――お苦しみなのだ。
怖くないと言えば嘘になる。けれど、リツの胸を占めるのは恐怖だけではなかった。
――助けて差し上げたい。この方を……。
「……ひふみよ、いむなや、ここのたり」
リツは唇に歌を乗せた。
「いつとせ、むとせ、ななとせと……」
母から教わった、言霊。神を鎮める言の葉が、石造りの宮に静かに木霊する。
「ももとせたてばゆらゆらと」
ミツハの顔から、鱗がすう、と消えていく。
「いめにくちなは、あらはるる」
リツを抑え込んでいたミツハの手から、力が抜けた。
「かためひらきて……あひみたし」
がくり、と意識を手放したミツハを、リツは懸命に抱き起した。鱗も、牙も、引いている。しかしその体は依然として熱く、燃えるようである。
「イダ!」
たまらず呼ぶと、くるりとイダが現れる。イダはミツハを見て、一瞬立ちすくむと、心得たように頷いた。
イダが敷布を敷き、二人で力を合わせてその上にミツハを横たえる。起きる気配はない。ミツハは苦し気に眉を寄せ、小さく呻いた。
「リツさま……」
イダが不安そうに声を挙げる。リツはその声には応えず、ミツハの顔を見つめ続ける。
額にびっしりと浮かんだ汗。鎮め歌で窮地は脱したものの、苦しまれていることには変わりがないのだ。
「イダ、衣を用意して頂戴」
「リツさま!? いったい何を……!」
「現世へ行きます」
イダが小さく悲鳴を挙げた。
「お願い、止めないで。イダ」
リツの胸に、小さな炎が宿る。
生れて始めて感じた、胸の中の炎。戸惑いながらも、リツは自らの心の声に従おうと決意する。
自分は、ミツハを助けたい。そのためにできることをやるしかない。
***
洞窟の泉の前に着くと、リツは息を整えた。
髪を結い、化粧を施し、衣は白銀。腰紐も、飾り紐も深紅を選んだ。……少しでもミツハを近くに感じていたいがゆえの色である。
イダの話では、この泉が現世と繋がっているとのことであった。
リツはそっと足先を泉に乗せた。ふわりと体が浮遊し、風景がまるで水に溶けた油のように歪んでいく。
その光景を冷静に見つめながら、リツは心の中で笑みを零す。自分の行動力に我ながら驚いている。
ミツハの苦しみを間近で見たからかもしれない、とリツは思う。ミツハはああやって、湖の死穢に侵され続けているのだろう。
神聖な湖を死穢で満たすなど、あってはならないこと。ましてやそれを、国の祭祀を司る大王が行っているのだ。
水が澱み、神が苦しむ。その代償として数多の命が失われるかもしれない。その大義もさることながら、リツはもう、ミツハが苦しむところは見たくなかったのである。
――止めなければ。
リツは静かに拳を握りしめた。不思議と気持ちが凪いでいる。胸の中に燃え上がる炎が、リツを静かに導いてくれるようであった。
揺らぐ景色が落ち着きを取り戻す。体の中から流れ出たものが、再び自分の中に戻ってくる感覚を覚え、リツは目を瞬かせた。
見覚えのある景色。
湖のほとりに、リツは立っている。
まだ暗い。夜であるからか、と思ったが、低く垂れこむ雲が光を遮っているのだ。時折轟く雷が、嵐の予感を告げている。
ミツハが怒っているのだ。
リツは唇を噛み締めると、ゆっくりと歩きだした。
大王の住まう宮は、巳の国の奥に構えられている。その門を叩き、名を告げ門番に案内を乞う。
あれよあれよという間に、リツは大王の御前へと罷り通ることになった。
控えの間に通されたリツは、髪を整え、衣を直す。
下へと置かない待遇である。そのことにリツは引っ掛かりを覚えた。何かがおかしい。大王が、自分のような者の意見を直に聞くような賢君であれば、あのようなことはなさらないはずである。
で、あれば。何か問題が起こっているのだ。
意を決して、扉の前に立つ。入室を告げ、扉を開いた瞬間――。
「……え」
リツの腹に、鋭いものが突き刺さっている。遅れて、激痛が体中を蝕む。
ずるりと抜き取られた刃が血に濡れ、鈍い光を放つ。たまらず倒れ込むと、目の前に見知った顔があった。
「――旦那……さま」
「やはり、お前、逃げおおせていたのだな」
なにを言っているのか、リツには理解できない。瞳で問いかけると、ジタはリツに唾を吐きかけた。
「畏れ多くもお役目を棄て、今までどこで何をしていた」
「お役目を、棄て……?」
息をするだけで、体中に痛みが走る。
「雨は止んだが晴れが戻らぬ。やまいも収まる気配がない。おかしいと思っていたのだ」
上座から、氷のような声が降る。その声の主は大王であろう。同じ氷でも、ミツハの声とは違う、血の通っていないような冷たい声である。
楼主ジタはリツの横に跪くと、上座に向かって最敬礼を取る。
「お許しください。大王。むすめはこのとおり、自らの行いを悔い、再度お役目を果たすために戻ってまいりました」
かたかたと震える楼主ジタを横目で見ながら、リツは薄れゆく頭で考える。
――そうか。
この方たちは、リツが逃げたものだと思っているのだ。
「――連れていけ」
引き倒され、髪を掴まれ、駕籠に籠められ運ばれる。
じくじくと熱い液体がリツの腹を濡らしている。痛みはもはや感じなかった。
遠雷。
その音がようよう近づき、リツは瞠目する。
駕籠は、湖に向かっているのであろう。
――儀式をやり直すおつもりなのだ。
リツは青ざめた唇を噛み締めた。
――許せない……。
自らの行いを顧みようともせず、むすめを差し出せばすべて丸く収まるとお考えなのだ。この大王は、湖を穢すことの意味すら考えたことはないのだろう。
心の炎が燃えている。これは怒りだ。リツは生まれて初めて、自らの中に生まれた感情を怒りだと理解した。
駕籠が降ろされ、ジタに手を掴まれ引きずり降ろされる。
祭壇はない。ただ滔々と黒い水を湛える湖が、リツの眼前に迫っている。
このまま沈められてたまるものか。
リツは決死の力を込めて手を振り払うと、大王のいるであろう駕籠に向かって声を挙げた。
「私はあなたを【許さない】」
駕籠の中からくすりと笑みが零れる。
「あなたは自分が犯した罰を知らない。いったい何人をこの湖に捨てたのです!? 神聖な湖を死穢で満たし、守り神である蛟龍を穢した。蛟龍はお苦しみでいらっしゃる。その苦しみはほかでもない、あなたの行いによるものです!」
「ほう」
駕籠からごとり、と音がする。
ゆっくりと姿を現した大王に、リツは瞠目した。
怜悧な顔立ち。抜き身の刃を思わせるような細い瞳は、残忍さと冷静さを余すところなく同居させ、冷たい光で満ち満ちていた。
思わずひれ伏しそうになるほどの威厳に、リツは体が震え始める。
――この方が、巳の国の大王……。
負けるものか。リツは歯を食いしばる。
「畏れ多くも、大王に申し上げます。湖を穢すのをやめていただきますよう、この通り――!」
言葉を最後まで発することはできなかった。
無造作に抜かれた刃が、リツの右目を貫いている。
「……あ」
ずるり、と引き抜かれた刃の感触。同時に温かなものが顔面を多い、視界が赤に染まっていく。
「あああ、ああああああっ……!!」
焼け付くような痛み。そのリツの手を乱暴に掴むと、大王はリツを引きずりながら湖につかつかと近寄った。
「去ね」
どん、と体を押され、リツは宙に浮く。
――私……死ぬの……?
黒い湖面が、ゆっくりと近づいてくる。
――……ごめんなさい。
ミツハのことを思い出す。このような自分にも、優しくしてくださった。言祝ぎをしてくださった。そのミツハの苦しみを取り除いて差し上げられないことが、リツは悲しい。
――最期に、お会いしたかった。
願いむなしく、隻眼のむすめは湖に落ちる。
その微かな音が、山の間に木霊した。
そのときである。
「ひゃあ!」
耳を劈くような雷鳴に、ジタが腰を抜かした。
黒き叢雲が湧き上がり、雷鳴と共に風が吹く。天の底が抜けたかのような豪雨が男たちを襲った。
「何事だ……!」
「大王、さ、駕籠へ……!」
「いかん!」
殴りつけるような容赦のない雨風が、駕籠を吹き飛ばす。
大王も目を見張った。これほどのまでの嵐、いったい何故。
「お……大王」
ジタが湖を指さし、喘ぐ。
湖の中央が、大きく盛り上がっている。栓を外した水の如き水流に乗り、巨大な蛇体が囂々と現れたのである。
血を流し込んだかのような赤い双眸が、男たちを捉えた。
「ひっ……」
雷鳴。
目を焼く光と共に、大地が裂ける。
「み……蛟龍……」
――許さぬ。
地の底から響くような声が、大地を揺るがし轟いた。
――許さぬ……!
ごう、と音を立て。
光の矢が、大王めがけて鋭く走った。
リツは沈みながらも、夢うつつにその声を聞いていた。
心に流れ込んでくるのは、黒く染まった怒り。
ミツハが怒っている。心を黒く染め、苦しみ、絶望に打ち震えている。
――苦しまないで。ミツハさま……。
「……ひふみよ、いむなや、ここのたり」
リツは唇に歌を乗せた。歌えているのかももはや分からぬ。立ち上る泡が、稲光を受けて輝いている。
「いつとせ、むとせ、ななとせと……」
母から教わった、言霊。神を鎮める言の葉が、水にじわりと溶けていく。
「ももとせたてばゆらゆらと」
ふ、と体を引き上げられる。温かな腕に抱かれて、リツは微睡みにも似た幸福感に包まれる。
「いめにくちなは、あらはるる……」
右目の痛みも、もはや感じない。
「かためひらきて……あひみたし」
温かな水に包まれて、リツは意識を手放した――……。
***
ひやりと冷たいものが、額に添えられている。そのまま頬をたどり、唇を撫でるともう一度額へ。
頬にさらりとした感触を受け、リツはゆっくりと目を開く。
「……おはようございます」
涼やかな声が耳朶を擽った。ぼんやりとした視界に人の顔が映り、リツは目を瞬かせた。
「えっ……!」
身をかがめるようにして、リツの顔をのぞきこんでいる一人の男。ばちり、と目が合った。
流れるのは銀色の髪。血を流し込んだような赤い瞳は不思議と温かな光を湛え、リツの顔を映し込んでいる。すっと通った鼻筋に、薄い唇。ひやりとした冷たさを感じるものの、表情は柔らかく温かい。
ミツハはリツを見つめると、その右目に口づけを落とした。
瞬時にリツは思い出す。慌てて起き上がろうとした体をぐっと押さえつけられて、そのまま男の腕の中へとすっぽりおさめられてしまう。
「あの、私……」
はっと、自らの手を右目に添えると、固く結ばれた布の感触。片目を塞がれているようであった。
「よかった」
リツを背後から抱きしめる男の腕が、細かく震えている。
「あなたを失うかと……わたしは……」
助かったのだ、とリツはぼんやりと思う。ミツハはリツの首筋に顔をうずめると、絞り出すような声で囁いた。
「生きていてくださって、ありがとうございます……」
その真情あふれる声色に、リツは涙を飲みこむことができなかった。ほたほたと頬に落ちる涙を指で掬い上げると、ミツハはリツの顎を取る。
初めての口づけは、蕩けるように優しく、甘い。頭の芯まで侵されそうな心地よさに、リツはうっとりと目を細めた。
「リツさま! お目覚めですか!? ……て、ちょっと! ひゃあ!」
くるりと回転して現れたイダは慌てたように声を挙げ、小さな手で目を隠す。
「……のぞき見は良くないですよ、イダ」
「見せつけてるのはミツハさまの方ではありませんか!」
くすりと笑うと、ミツハはリツを解放した。
「……リツ?」
動かないリツに疑問を持ったのであろう、ミツハはきょとんと眼を瞬かせた。
一拍遅れてやってきた羞恥が、リツを襲う。頭の先からつま先まで朱に染まったむすめは、ふにゃりと力の抜けた体をミツハの胸にあずけたものだ。
「ミ、ミツハさま……」
「はい、なんでしょう。わがつま」
綺麗に笑うミツハの顔を見て、リツもゆるりと口元を引き上げた。
「いいえ。なんでもございません」
***
大王、崩御の報せは巳の国を稲妻のように走った。
その死に蛟龍の呪いあり。止まぬ雨も、やまいもすべて大王の悪行が元である。そのようなことが口すさまれ、行われていた悪事も暴かれたと聞く。
楼主ジタ、そのつまヤソは新たな大王によって裁かれた。彼らは大王に従っただけというが、やまいで死したおんなを湖へ棄てていたのは間違いのないことである。
一連の事のあらましにより、形骸化された儀式の数々も見直されるとのこと。
巳の国の民は囁く。
湖に蛟龍あり。蛟龍は治世を見る。良き行いが多ければ蛟龍は国を豊かにし、悪し行いが多ければ国を亡ぼす。その者が怒り嘆くときは長雨が続くのだ。
しかし、その蛟龍に、隻眼の巫が寄り添っていること。
己が声で蛟龍を言祝ぎ、怒りを鎮め、共に巳の国を見守っていること。
そのことを知っている者は、誰もいない。
「そういえば」
ミツハに髪を梳かれながら、リツはことりと首を傾げた。
「一度だけ、ミツハさまがお怒りになられたときがありました。あれは、なぜです……?」
尋ねると、ミツハは一瞬眉を寄せ、困ったように笑った。
「あなたが、自らを贄と言うから……」
リツの髪をひと房取ると、ミツハはそっと口づけを落とす。
「あなたはわたしを助けてくれた。正気を失いかけていたとき、鎮め歌に託された祈りとともに、あなたの心の声を聞きました。あなたの祈りが、わたしを悪し寝目より呼び戻してくれたのですよ」
そのままミツハの唇は失われた右目を辿り、頬を辿り、やがて唇へ。
「あなたは贄などではない」
そうだ、とリツは眦を緩ませる。この美しい人は、最初から自分のことを。
――わがつま、と呼んでくださっていた。
「死が二人を分かつまで。あなたのことをずっと言祝ぎ続けましょう」
リツの眦に溜まった涙を吸い上げて、ミツハは花が綻ぶように微笑んだ。