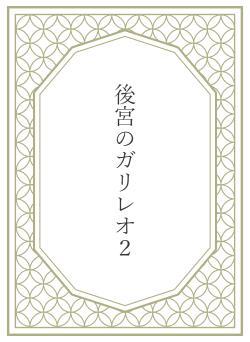***
ひやりと冷たいものが、額に添えられている。そのまま頬をたどり、唇を撫でるともう一度額へ。
頬にさらりとした感触を受け、リツはゆっくりと目を開く。
「おはようございます」
涼やかな声が耳朶を擽った。ぼんやりとした視界に人の顔が映り、リツは目を瞬かせる。
「えっ……!」
身をかがめるようにして、リツの顔をのぞきこんでいる一人の男。ばちり、と目が合った。
流れるのは銀色の髪。血を流し込んだような赤い瞳は不思議と温かな光を湛え、リツの顔を映し込んでいる。すっと通った鼻筋に、薄い唇。ひやりとした冷たさを感じるものの、表情は柔らかく温かい。
見目麗しいという言の葉がこれほど似合う者もいないだろう。
「あ、あの……!」
慌てて身を起こすと、おっと、と男はのけぞった。男に膝枕をされていたという事実にリツは混乱し、羞恥に体を熱くする。
「もう少し寝ていてもよいのですよ」
残念そうに言の葉を落とす男の横で、リツはぶんぶんと首をふる。
「あの、ここは……!? 私、湖に……」
リツは周りを見渡した。自分は湖に身を投げたはずなのに、いったいここはどこなのだろう。
石造りの宮のようであった。東屋のような作りになっているようだ。瑞々しい木々の緑が眩しい。吹き込む風も清涼で、さやさやと梢を鳴らす音が聞こえている。
「どうぞ。足元に気をつけて」
男は立ち上がると、リツにすっと手を差し伸べた。おずおずと手を取り、立ち上がる。姿が良いと思っていたが、上背もある。立ち上がったリツの頭二つ分はある長身で、結髪をしていない銀の髪が純白の袍の上をさらさらと絹糸のように流れ落ちていた。
「名はなんと?」
「は……リツ、と……」
リツ、と男は口の中で呟いて、花が綻ぶように微笑んだ。
「良い名です。特に響きがいい。我が水を正常に保つ、清らかな流れを意味する音ですね」
「あの、あなたは」
リツの声に、男はすっと手を組み、リツに拝する。
「名を告げる前に。礼を言わせてください。あなたの鎮め歌のおかげで、わたしは目を覚ますことができました」
「鎮め歌の……?」
ええ、と男性はにこりと笑い、リツの手をそっと握る。指先の冷たさに、リツはぴくりと体を震わせた。
「わたしの名は、ミツハと言います。しかし、この名を名乗ってもあまり意味がない。現世では、わたしのことを湖の主、蛟龍と呼んでいるでしょう」
リツは目を見張った。
「――蛟龍……!?」
目の前の男は頷いた。
「あの歌を知っているということは、あなたは巫なのですね。言の葉に力が宿る、とても心地の良い歌でした」
そのままリツの衣に手を這わせ、眉を寄せる。金糸銀糸で織られた衣は水を吸い、重たく体に纏わりついたままだ。
「人は本当に愚かなことをする。贄など要らぬと言っても聞く耳を持たないから困るのだ。いや、それよりも聞く力がないということか」
言の葉に鋭さを纏わせたミツハは、安心させるようにリツに微笑んだ。
「まずは着替えを」
細く口笛を吹くと、柱の影から一人の幼子が現れた。髪をみずらに結い、ミツハと同じような白い袍。くりっとした瞳は黄金で、こちらも見目麗しい御子である。
「この者は、イダ。身の回りの手伝いに使ってください」
イダはさっそくと言わんばかりにリツの手を取った。
「リツさま。イダがご案内差し上げます。どうぞこちらへ!」
そのままあれよあれよと連れていかれ、リツは部屋の一室に通された。
白い石造りの床に、同じく白い壁。天井には青い染料で複雑な文様が描かれている。丸くくりぬかれた窓から見える瑞々しい木々の緑に目を落とし、リツはほうと息を吐いた。
鼻歌を歌いながらイダは奥の部屋から衣を数枚持ちだすと、同じく白い石でできた卓子の上に並べた。
「リツさまは何色がお好きでしょうか? 金青、浅葱、白縹……」
一枚一枚を手に取って、くるくると回りながらイダはリツに衣を合わせていく。
「あの、イダ……さま」
リツの言の葉に、イダは目を丸くし、ふにゃりと微笑んだ。
「リツさま。イダのことは『イダ』と呼び捨てになさってくださいまし」
「でも、初めてあった方にそのような」
「お優しいのですね」
イダは目を細めてにこりと笑う。
「ですが、そのように呼んでもらわないと困ります。イダがミツハさまに叱られてしまいますゆえ」
「そう……それなら、イダ。私、今、あまり状況が分かっていないのだけれど」
混乱するリツに、さもありなんとイダは頷いた。
「そうでしょうとも。身支度をしながらでよろしければ、イダがご説明差しあげます」
イダは丸椅子を用意すると、リツをそこに座らせた。手巾で髪の水気を叩くように吸い取ると、丁寧に髪を梳いていく。
「ここは臥龍の宮でございます」
「臥龍の宮……」
リツはくるりと部屋を見渡した。煌びやかさはないが、静謐な美しさを保つ宮である。
「臥龍の宮は、湖の主たる蛟龍、ミツハさまがお住まいになる宮にございます」
髪を梳き終わると、イダは慎重な手つきで結い上げていく。
「最近のミツハさまは大層お苦しみでした。リツさまの鎮め歌をお聞きになり、ミツハさまは目を覚まされたのでございます。その御礼をするべくリツさまをお救いになると決められました。それで、この宮までお連れした、と」
――それでは。
リツは考える。この宮は本当に蛟龍の住まう宮なのだろうか。だとすれば、自分は……。
震え始めた手を己が掌で包み込み、リツは口に言の葉を乗せる。
「私のいのちは、どうなってしまったのでしょうか?」
「リツさまは、きちんと生きておいでですよ。心の臓も動いております。ご安心ください」
そこまで言うと、イダはリツを立ち上がらせた。いつのまにか、髪が結い上げられている。
「リツさまはきれいな黒髪でいらっしゃる。以前お見かけした際の紅の衣もお似合いですが、ミツハさまの横に立たれるお方だもの。こちらの、白銀の衣にしてみましょうか」
卓子の上の衣をリツに合わせ、にこりと笑うイダの言の葉に、リツは引っ掛かりを覚えた。
「あの、どこかでお会いしたことが……?」
このような印象的な御子。どこかで見たなら忘れるはずがないのだが、リツにはその覚えはない。
「さ、リツさま、お召し替えを」
リツの問いには答えずに、イダは衣をリツに手渡した。触れるだけで分かる、上質な絹である。細い銀糸が編み込まれた衣は滑らかで、さらさらと手の上を泳ぐ水のような手触りであった。
「イダがお手伝いをしてもよいのですが、こう見えてイダもおのこでございますゆえ、ミツハさまにお叱りを受けてしまいます。さ、早く」
急かされて、奥の部屋へと向かう。
袖を通した衣は震えがくるほどの良いものだった。着替えを終えて現れたリツを見て、イダはほうっと息を吐く。
「大変よくお似合いでいらっしゃいます」
「そう……でしょうか?」
イダはこくりとうなずくと、リツの前に跪き、頭を垂れた。
「ようこそ……ようこそいらしてくださいました」
真情があふれ出るような丁寧な礼に、リツはあわてて手を振った。
「イダ、顔を挙げてください。私は、そのように礼を取られるものではありません」
リツの声に、イダは顔を挙げてにかっと笑う。
「イダはリツさまを一度拝見したことがございます。痛ましいお姿ではありましたが、それでもイダには分かっておりました。この方はいずれミツハさまを救ってくださる。穢れなき魂の持ち主であると」
どういうことか、と問いかけようとするリツの口に、イダはすっと人差し指を立てる。
「ミツハさまがお待ちです。さ、参りましょう」
リツの先導で、宮の廊下を渡り、元の東屋まで戻る。
ミツハは石造りの腰掛に体を横たえ、目を閉じていた。さらりと流れる銀の髪が床に落ち、風に揺られてさらさらと衣擦れのような音を立てている。
イダに促され、リツはそっとミツハに近寄った。眠っているのであろうか、時折長い睫毛がぴくりと動く。隙のない美しさに、リツはほうっと息を吐いた。
――この方が、蛟龍……。
信じられない。
蛟龍のことは、巳の国に生まれた者なら誰でも知っている。湖に住まう、巳の国の守り神。巨大な蛇の体を持つあやかしで、いずれは龍になるという。
まじまじと見てしまったからであろうか、ミツハはぱちりと目を開けた。鋭い赤の瞳に囚われて、リツはびくりと体を震わせる。
「ああ、すみません。驚かせてしまいました」
気怠げな動きで、ミツハは腰掛から体を起こす。目には先ほどまでの鋭さはない。やわらかな光を湛えて、リツを見つめている。
衣を変え、髪を結い直したリツを見て、ミツハは花が綻ぶように微笑んだ。
「とてもうつくしい。リツには銀がよく似合います」
正面から褒められて、リツは顔に熱が上るのを感じていた。
「イダ、暫く外すように。わたしはこのうつくしいつまと話す時間を持ちたいのです」
「承りました!」
元気よく答えたイダは、くるっと宙返りをすると、空気に溶け込むように消えてしまう。
「さあ、御手を」
ミツハにすっと手を差し出され、リツは困惑する。まだ夢の中にいるような心持であった。
神が傍で息づいているとはいえ、その姿を見た者は少ない。リツとて巫の母を持ち、幼き頃から身近な存在であったはずの神である。しかし、その姿や声などを聴いたことは一度もない。
湖に身を投げたときは、死ぬものだとばかり思っていた。それなのに……。
なかなか手を取らないリツに、ミツハは首を傾げ、ややあって微笑う。
「緊張されているのですね。無理もない」
「は、あの……申し訳ありません……」
「大丈夫ですよ。あなたを取って食らうわけでなし。ただ、目の前のうつくしいつまを隣に座らせて、語り合いたいだけなのです」
赤い瞳が柔らかく揺れている。リツはかちこちに固まった体が、少しほぐれたような気がした。
目の前の美しい人が、蛟龍であるという事実はともかく。この方は、自分を決して怖がらせたりはしないだろう。
そっと手を取ると、そのままぐいっと引っ張られる。
「も、申し訳ありません!」
あろうことか神の膝上に乗り上げる形になってしまい、リツは大いに焦った。
「謝る必要などありませんよ。わがつま」
ミツハは破顔すると、リツの頬にそっと親指を這わせた。冷たい指先の感触に、リツは体を震わせる。
「あ、あの……お聞きしてもよろしいでしょうか」
「なんなりと」
「あなたさまは……本当に、わが巳の国の守り神……蛟龍であらせられるのですか」
ミツハは目を瞬かせる。
「おや、信じられないのですか?」
「いえ、そうではありません! そうではなくて……」
リツはごくりとつばを飲み込んだ。
「もしあなたさまが蛟龍であらせられるのであれば、お聞きしとうございます。……雨は、どうなりましたでしょうか? 私はそのためにあなたさまに捧げられた贄でございます。きちんとお役目を果たせているのか、それが気になっているのです」
ミツハは赤い目を丸くし、困ったように眉を下げた。
「わたしは、贄など所望しておりません」
「……そんな!」
その言葉を聞いて、リツは戦慄いた。それでは、自分は何のためにこの湖に身を投げたのであろうか。
震え始めたリツをなだめるように、ミツハはリツの手を取った。
「現世では、そのように伝えられているのでしょう。しかし、わたしはこの方、贄など一度も所望したことはないのです。わたしが望んでいるのは、その歌……」
目に柔らかな光を浮かべたまま、ミツハはすっとリツの首に指を這わせた。
「巫の心からの祈りと、鎮め歌。リツ、あなたのおかげでわたしは正気を取り戻すことができました」
ミツハはリツの体に手を回すと、くるりと向きを変えてみせた。背面から抱きこまれる形になり、リツは目を白黒させる。
「あ、あの……!」
「悪しやまいの流行りもあって、死穢が蔓延るのは仕様のないこと。しかし、弔いもせず水を穢し、流れを澱め、我が眷属を死の淵に追いやった。この身を焼くほどの穢れと怨嗟で、わたしは我を忘れてしまっていたのです」
首筋に氷のような声色を受け、リツはぞっとする。体が硬くなったことに気づいたのであろう、ミツハは口調を和らげた
「そのわたしを鎮めたのはあなただ、リツ。わたしの魂を穢れから救ってくれた。感謝します」
――ご安心なされよ。雨は無事に止んでおります。
囁くように落とされた言の葉に、リツはふっと体の力が抜ける感覚を覚えた。
「よかっ……た……」
役目を果たせたという安堵と、緊張と、混乱。ぐちゃぐちゃになった頭のまま、リツはふ、と意識を手放した。
***
温かくやわらかなものに包まれている。
ゆらゆらと微睡みながら、リツは温かな心持であった。
また、いつもの夢だ。母の腕に抱かれて、とろとろと夢を見ていたころ。
でも、これは夢まぼろし。
――リツ! このうすのろ!
ヤソの怒鳴り声が聞こえる。
――ぬしのその顔がなによりの馳走……。
ジタの下卑た笑い声が木霊する。
早く起きなければ。
一刻も早く、目を覚まして――!
「リツ!」
その声に驚いてリツは跳び起きた。心の臓が跳ねている。体中から汗が吹き出し、リツは喘ぐ。
「あ……私……」
リツは頭を振る。
その顔をのぞきこんでいるのは、ミツハだ。眉を寄せ、心配そうにリツの肩に手をかけている。先程のときよりも砕けた衣で、薄絹一枚という姿である。
周りを見渡すと、先ほどまでの東屋とは別の部屋である。部屋の中央に敷布が敷かれ、そこに寝かされていたようであった。
リツの結髪は解かれていたものの、衣は着替えたときのままである。あのまま気を失っていたところをこの部屋まで運ばれた、ということなのであろう。
既に夜。丸窓から差し込む青い光が、装飾の施された柱や、磨き込まれた床を青く染めている。
「どうしました、顔色が……」
す、と伸ばされた手に、リツは体を震わせた。
――怖い。
ただの夢だ。ヤソも、ジタも、もう自分を脅かすことはない。そう思っていても、体に染みついた恐怖はそう簡単には消えはしない。
かたかたと震えだした掌を己が手で押さえながら、リツは唇に辛うじて笑みを浮かべた。
「大丈夫……です。少し、夢を見ただけなので……」
ミツハは黙ってリツを見つめると、すっと立ち上がり奥の部屋へ消える。
やがて戻ってきた彼の手には、湯気の立つ酒杯が握られていた。
「飲みなさい」
差し出された杯をおそるおそる手に取ると、湯気に乗ってかぐわしい香りがする。手が震えて、中の酒が指先にかかった。
「息を吸って、ゆっくり吐いて」
ミツハはリツの背に手を回すと、ゆっくりと撫でおろす。
「さ、飲んで」
ぐっと飲み干すと、体の奥が熱くなる。同時に手の震えも、体のこわばりもほんの少し和らいだ。
それを見届けると、ミツハは微笑み、酒杯を取り上げ小卓へ置く。
「リツ」
ミツハはやわらかく声を落とすと、そっとリツを抱きしめた。
「あ……あの……!」
落ち着き始めた心の臓が跳ねる。
「あなたの中に澱んでいるもの、そのすべてわたしに吐き出してください」
ミツハの涼やかな声が、リツの耳朶をくすぐった。
「その腕の傷」
片手でリツを抱きしめたまま、ミツハの手がリツの腕を取る。はらりと捲れた衣から見える、縦横に走った鞭の痕にミツハは眉を潜めた。
「腕だけではありませんね。リツ。この傷があなたを苦しめているのですか?」
その涼やかな声が、あまりにも優しく耳に響くものだから。リツはこみ上げてくる涙を飲みこむことができなかった。
「っつ……う……」
いけない。涙を止めなくては。そう思えば思うほど、こんこんと湧き上がる泉のように涙が溢れ出る。
「この傷は、どうしたのです」
「……言えません」
リツは頭を振る。
「リツ……?」
「言えません……私には……」
泣きじゃくるリツの髪を、ミツハは幼子をあやすような手つきではゆっくりと梳いた。
「リツ。澱は吐き出さなければ、毒となり自分を苦しめもしましょう」
とうとうと流れる水のように、ミツハは言の葉を口にする。
「この宮は臥龍の宮。わたしは水の神、蛟龍です。水は澱を流すもの。安心なさい。すべての澱をわたしが流して差し上げます」
――どうして……?
リツは嗚咽を漏らす。
「どうして、そんなにお優しいのですか……」
ミツハは瞳を細める。
「わたしは優しくなどありませんよ」
そう告げる声も、どこまでも優しい。
「しかし、わたしはあなたを助けたいと思っています。リツ、信じなさい」
力強くも温かな響きに、リツは滂沱する。言えるのだろうか、自分はこの人に、言ってしまっていいのだろうか。
「私……私は……」
そう言いかけて、ためらい、再度リツは口を開いた。
「私は、巫の血を引くと……母から言われております」
先を促すように、ミツハはリツの髪を梳き続ける。
「そのせいでしょうか……私は悪し言の葉を口にすることができないのです」
「悪し、言の葉」
こくり、とリツは頷く。
「ですから……お許しください。私には何も言えない……言えないのです」
ミツハは黙ってリツの髪を梳き、ややあって呟いた
「……なるほど。言の葉の呪いにかかっておられるのですね。口にすることが本当のことになってしまう。それがあなたを縛る枷ですか」
真っ青な顔で言葉を失うリツの髪をひと房取ると、ミツハはそっと口づけを落とす。
「それならば、わたしがリツを言祝いで差し上げましょう」
「言……祝ぐ……?」
ミツハはリツから体を放し、腕を取り上げると、鞭の痕に口づける。
「これほどまでにひどい傷……それに耐え、言の葉に乗せられなかったのはさぞつらかったでしょうね」
その時の感情を、リツはどのように表現したらいいか分からなかった。
この人は、理解してくれた。この人は、自分の痛みを、苦しみを、わかってくれている。
一度止まりかけた涙が、再びあふれ出す。
「……【辛かった】」
「よく、耐えましたね」
「【痛かった】のです」
「痛まぬよう、呪いをしましょう」
ミツハは傷口に唇を当て、ふっと息を吹きかけた。すう、と痛みが消えていく。
「よく我慢しましたね、リツ。大丈夫。ここにいる限りは、どんな言の葉でも口にしていいのですよ。すべてわたしが言祝ぎましょう」
「……ミツハさま……!」
まるで幼子のように。わんわんと泣きながら、リツはミツハの胸に顔をうずめた。
「あんなところしか【居場所がなくて】」
「もう戻らなくてよいのですよ」
「【怖くて】【辛くて】……!」
「それも、もうおしまい」
「【死にたかった】……!!」
「生きていてくださって、ありがとうございます」
泣きじゃくるリツの顎を捉え上向かせると、ミツハはその額に口づけを落とす。
「これから先、死が二人を分かつまで。あなたのことをずっと言祝ぎ続けましょう」
やわらかな赤い瞳が、リツの顔を映し出す。
体を引き裂くような痛みも、黒い痣も浮かばない。代わりに広がるのは温かな光であった。ミツハの落とす言の葉がリツの体を駆け巡り、じんわりと広がっていく。
それこそ体の中の澱を全て流すように、リツは泣いた。
もう我慢しなくてもよいのだ。
どんな言の葉でも口にしてよいのだ。
そのことが、これほどまでに安心することなのだと、リツは初めて知ったのである。
***
目覚めると、柔らかなものに包まれている。
それがミツハの腕だと気付き、リツは慌てて体を起こした。
頭がぼんやりとしている。目も腫れているようで、瞼がほのかに熱を持っているのが分かる。
ミツハはまだ眠っているようで、瞼を閉じたままぴくりとも動かない。寝乱れた衣から見える男の肌にどぎまぎし、ぱっと目を逸らした。
――私……昨日……。
自らの行いを思い出し、リツは顔を赤らめる。
人前であんなに泣いたのは初めてだ。ミツハから囁かれた言の葉の数々を思い出し、リツはうう、と頭を抱える。
表向きは妓女であるが、楼主のお抱えであったがゆえに一度も床に上がったことがない。むつごとにはとんと疎いリツである。今さらながら、羞恥で身体が燃え上がりそうになる。
熱くなった体を覚まそうと、リツは敷布を抜け出した。
早朝。丸窓からは朝特有の涼し気な風が吹き込んでいる。その丸窓に手をかけて、リツは外を眺めた。
緑が青々と茂る前庭。その庭を取り囲むようにして木々が連なっている。微かに水の音がするので、小川があるのかもしれない。
改めて、不思議な場所だ。ミツハが「現世」という言葉を使っていたのを思い出す。それではここはリツのいた場所とは違う軸をもつ、「幽世」であるのだろうか。
人ではないものが住まうという幽世は、神の領域だ。もしそうであれば、この宮を包む静謐で涼しげな空気にも納得がいく。
そんなことを考えていたときである。
「ひっ」
突然背後から抱きしめられて、リツは思わず声を挙げた。
「おはようございます、わがつま」
「ミツハさま!」
リツの挙動が面白かったのであろう、ミツハはくつくつと笑う。
「よく眠れたようですね、よかった」
「はい、おかげさまで……」
煩く鳴り始めた心の臓に気づかないふりをして、リツは答える。
「まずゆあみを。それから朝餉にしましょう」
リツの頬に軽く触れると、ミツハは口笛を吹く。
「イダ、リツを泉へ」
「承りました!」
リツはぎょっとする。まるで空気の中から染み出るようにイダが現れ、あれよあれよと連れ出される。
宮の前庭を通り、木々をぬって歩くと、清らかな泉があった。丸窓から聞こえていた水音は、この泉から流れ出る川水の音のようである。
周囲にはやわらかな草が萌え、岩肌を流るる水音が心地よい。泉は水底が見えるほど透き通っている。
「着替えの衣は、この木の枝にかけておきます」
てきぱきとイダは枝に衣を引っかける。
「さ、衣を。お手伝いいたします」
言われて、リツは目を白黒させた。
「……イダ」
「はい!」
「昨日、イダは確か……おのこと」
いくら幼き御子とはいえ、異性の前で衣をはだけるのは抵抗があった。イダはそんなリツを見て、なるほど、と手を打つ。
「失礼いたしました。イダは、今日はおなごにございます」
「えっ!?」
リツはまじまじとイダを見る。確かに、昨日よりも線が細くなっている。胸もかすかに膨らんでおり、丸みを帯びた体つきだ。
「イダ……よね? 昨日と同じ」
「はい。イダにございます。イダはまだくちなわになりますがゆえ、おのこにもおなごにもなることができるのです」
にかっと笑うイダを見て、リツはくらりと眩暈を覚えた。
男にも女にもなることができる、とは……。しかし、ここが幽世であればそのようなこともあろう。
無理矢理自分を納得させて、リツは頷いた。
意を決して衣を脱ぐ。イダは慣れた手つきで衣を受け取ると、同じように木の枝にかけた。
ひんやりとした朝の空気に抱きすくめられ、リツは体を振るわせる。
人前で裸になるのは得意ではない。妓楼では、湯は決められた刻に数人で入るのが常である。しかし、リツはその時間が苦手であった。
妓女たちは、リツを仲間だとは思っていない。背や腕に走った鞭の痕や、醜く痣になるまで抓られ、蹴られた痕をじろじろと見ては、暗い嗤いを零されていたものだ。
しかし、ここではその心配がない。そのことがリツを安堵させる。
足先から泉へ入ると、予想に反してやわらかな水当たりだ。滑らかに肌をすべり落ちる水が心地よく、リツはふうと息を吐いた。
「御髪を梳かせていただきますね」
イダが丁寧な手つきでリツの髪を梳く。体の傷のことには一切触れない優しさが、リツは嬉しかった。
「昨晩はよくお休みになられましたか?」
「ええ、おかげさまで」
「ミツハさまは、お優しかったでしょう」
「……ええ」
思い出して、リツはまた少し体に熱が上る。その様子を見て、イダは嬉しそうに微笑んだ。
「ミツハさまのつまが、あなたのような方でよかった。昨晩はミツハさまもお苦しみになることはなく、落ち着かれておりました。鎮め歌が良く効いたのでありましょう」
イダの言葉に引っ掛かりを覚えて、リツは首を傾げる。
「苦しむ……?」
リツの言葉に、イダははっと口を押える。
「失言でした。お気になさらないでください」
そう言われると、気になるというもの。
「イダ……?」
「いいえ、イダは何も言えません。ミツハさまに叱られてしまいますゆえ」
ということは、やはり何かがあるのだ。
リツは昨晩、ミツハにいただいた言の葉の数々を思い出す。
リツの呪いを言祝いでくれたときの、やわらかな口調。触れる指先の冷たさや、髪を梳く優しい手。
そのことが、どれだけ自分を救ってくれただろう。
「イダ、ミツハさまは何に苦しんでいらっしゃるの?」
「言えません」
「イダ……」
イダは髪を梳く手を止め、眉をへの字に下げた。
「イダは……ミツハさまをお救いしたいのです。でも、それと同時にミツハさまに仕える身でもあります。お言いつけを破ることはできません」
「イダ、お願い」
リツは食い下がった。
――苦しんでいらっしゃる。あのうつくしい方が……。
その苦しみを、取り除いて差し上げたい。自分にできることなら何でもして差し上げたい。リツの中に、このような感情が湧き上がるなど初めてのことである。
――なぜだか、わからないけれど。
「私も……イダと同じ気持ちなの。教えて頂戴、イダ」
イダは口を噤んだ。そのまま黙って髪を梳き終わると、手巾で髪の水気を拭い、高い位置に結い上げる。
「リツさま、そろそろ」
手を差し伸べられて、リツは嘆息した。どうやら教えてはもらえないようだ。
泉から体を引き上げ、水気を拭い、新しい衣を纏う。昨日の衣よりもやや簡素ではあるが、それでもやはり上質な絹。流れ落ちる水のような、涼やかな青い衣である。
イダの先導で、元の道を戻る。その途中で、ぴたり、とイダが足を止めた。
そのまま泣き出しそうな顔でリツを見上げると、イダはぐいっとリツの手を引っ張る。
「イダ!? どうしたの?」
「イダは、今から悪いことをします。お言いつけを破らせていただこうと思います」
ぐいぐいと手を引かれ、リツは木々の奥へと連れ込まれた。しばらく歩くと、高い崖が見えてくる。その下にぽっかりと開いた洞窟があった。
奥は見えない。どのくらい深いのかもわからない洞窟に、リツはごくりと唾を飲みこむ。
イダはぎゅっと手に力を入れると、リツを洞窟の中へといざなう。
予想に反して、洞窟の中は静謐な空気で満たされていた。垂れ下がった岩々からはほたほたと雫が落ち、水音が心地よく木霊する。
「リツさま、着きました」
一番奥は、開けた広場のようになっていた。その中央に、泉がこんこんと湧き出している。
リツは深く息を吸った。洞窟の奥だというのに、空気が整っている。清められた場所であることが分かり、思わず頭を垂れ、手を組み拝する。
「リツさま、泉の前へ」
イダに誘われ、泉の前へと歩を進めた。改めて見ても美しい泉だ。
「この泉は、現世と繋がっているのです」
「現世と!?」
「ええ。その泉を覗きこんでみてください。……それが、ミツハさまのお苦しみの元でございます」
イダは眉を下げ、不安げにリツを見上げた。
「リツさま……。本当にミツハさまをお救いになってくださいますか。何を見ても、本当に?」
まるで捨てられるのを恐れている幼子のような表情だ、とリツは思った。リツは屈むと、イダのまだ幼い頬に手を添える。
「イダ。私はミツハさまに救われました。今度は私が……ミツハさまを【お救いしたい】」
その言葉に反応するかのように、泉が光り輝いた。リツは目を細め、泉をのぞきこんだ。