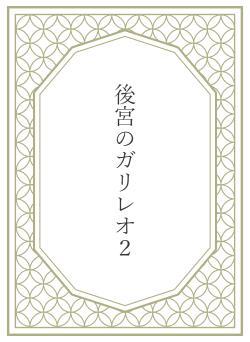ひふみよいむなや
ここのたり
いつとせ
むとせ
ななとせと
ももとせたてばゆらゆらと
いめにくちなは
あらはるる
かためひらきて
あひみたし
思い出すのは幼き頃の母の腕。眠い眼をこすれば歌う、魂の鎮め歌。
「リツ、リツや。賢き吾子よ」
ひふみよいむなや
ここのたり
いつとせ
むとせ
ななとせと
ももとせたてばゆらゆらと
「リツの言の葉には魂があるの。だから良き言葉を使いなさい」
夢うつつ、母の温かい腕に抱かれ、リツはゆらゆらと微睡んだ。子守歌には鎮めの歌を歌って聞かせる母の声。
甘くやわらかな日々。こんな日が永遠に続くものだと思っていた。
でも、これはすべて夢まぼろし。
早く目を覚まさなければ。
一刻も早く。
そして、今日も凄惨な日々が始まる。
***
「リツ! このうすのろ!」
容赦なく振り下ろされた鞭に、リツはくっと歯を食いしばる。仕立てたばかりの衣が破れ、背中にじんわりと血が滲んだ。
「雄鶏四つ鳴くまでに起きるようにとあれほど言っただろうに、どこまでも人を莫迦にしたむすめだよ!」
鞭がしなり、またひとつ。リツは唇を噛みしめた。
いいえ、ちがいます。お方さまは雄鶏六つと仰いました。その一言が言えればどんなにいいか――。
まだ神々が人のすぐ側で息づいていた時代。
人の住まう瑞穂の地、その地にある国のひとつ巳の国は風光明媚。絢爛豪華な佇まいで文化芸事の一等地として名を馳せていた。背後の山上に大きな湖を持ち、扇状に広がった国は湖がもたらす豊かな土と清浄な水の流れでもって栄華を極めていたのである。
巳の国に、青の屋根を持つ妓楼があった。
その妓楼で娼妓見習いとして働くリツは、見目麗しい娘である。
流れるようなたっぷりとした黒髪。憂いを帯びたような瞳も同じく烏の濡羽色。華麗というよりも嫋やかな、吹けば飛びそうな繊細な美しさを持つ娘であった。
「ふん、可愛げもない。もう鞭は慣れっこだろうね? いいだろう。堪忍おし」
楼主のつま、ヤソは目を三日月の形に歪めて嗤った。
「さっさと支度をしな。旦那さまがお呼びだよ」
リツはごくりと喉を鳴らす。
与えられた粗末な自室に、ひと梱の行李。取り出した衣は手の上で蕩けるような極上の絹。それをさらりと素肌に纏い、前はわざときっちり合わせる。色は白。または薄紅。肌に吸い付く絹の衣は、華奢なリツの体に沿って緩やかに床へと流れ落ちた。髪に挿すのは紅梅の玉。化粧を施し紅を入れ、リツは心を落ち着かせた。
――大丈夫。
もう何度も経験したのだから。それでも震える掌を、リツは自らの胸に抱きこんだ。
――私は何も感じない。何も思わない。心を消して痛みを消して。
足早に廊下を渡り楼主の自室の壁を叩くと、銅鑼声で入れと告げられる。
「お待たせしました、旦那さま」
両の手を組み拝すると、すかさずその手に一閃。
皮膚の焼かれる痛みに、リツは顔を歪めた。
「おお、その顔じゃ。リツ、ぬしのその顔がなによりの馳走」
楼主ジタは鞭をにぎりしめ、にやけた顔で舌なめずりをする。二、三、鞭が走り、絹の衣が切り裂かれ、じわりと血が滲みだす。
主は、リツの着る衣が赤に染まるのを楽しんでいるのだ。
やめてくれと、リツは言えない。リツは否を言ってはならない。痛くとも、苦しくとも、リツは唇を噛み締めてうつむき耐える。自分を守るためにも、リツは悪し言の葉を口に乗せてはいけないのだ。
リツが自身の持つ力に気づいたのは、皮肉にも母が亡くなったすぐ後であった。
齢八つの頃である。
母一人、子一人で暮らしてきた身。頼れるものもなく、残されたむすめがその後の生き方を自分で選べるはずもない。気づけばこの妓楼がリツの第二の家となった。
初めて妓楼へ足を踏み入れたときは、少しだけわくわくした心持ちだったことを覚えている。見るものすべてが煌びやかで、艶やかなおんなたちはリツに向かって軽く手を振ってくれる。
しかし、表が艶やかであればあるほど、光が満ちていればいるほど、影は濃くなり澱むもの。リツの器量が純粋に愛されたのは初めだけ。妬み、嫉み、あらゆるおんなの負の感情を一心に背負うようになるまで、大した時間はかからなかった。
ある日のことである。
リツはヤソの言いつけを間違え、ほんのひとさじ、自分の飯を多く盛る。目ざとく見つけた禿に大声で言いふらされ、リツは初めて折檻を受けた。
髪を掴まれ、引きずり倒され、背中と手に鞭を一閃。
「卑しい小むすめ! 親も親なら子も子だよ!」
ヤソは口を歪めてリツを罵った。その言葉に、リツはカッとなる。
「なぜかかさまが出てくるのです! かかさまは関係ありません!」
「あるともさ。おまえは自分の大切な母さまが何をしていたのか知らないのだろうね」
ねっとりとした口調のヤソは口の端に侮蔑の笑みを刻む。
「巫の血を引くだかなんだかしらないが、巫とは名ばかりの民妓じゃないか。邑の男に股開いて食わせてもらったおまんまは美味かったろうね」
リツは口をぽかんと開けた。
「さぞ具合がよかったんだろう、おかげでうちはとんだ大損さ。あたしがおまえを引き取るようにと旦那さまに進言したのはね、おまえの中のみだらがましい性根を見抜いたからなんだよ。母譲りの好きものだ。おまえの母がウチの稼ぎを邪魔したそれ以上に、せいぜい絞れるだけ絞ってやらなければ気がすまないからね!」
幼き頭には言葉の意味の全てまでは分からない。ただ、自分の大切な母が口汚く罵られていることだけはわかったので、リツは眦にぎっと力をこめた。
「かかさまは立派な方です!」
「おだまり!」
好き放題に殴られ、蹴られ、鞭を振るわれ、リツは呻いた。床に倒れ込んだリツに唾を吐き、ヤソは居丈高に部屋を出る。無情にも降ろされた鍵の音が、リツの脳内に木霊した。
折檻部屋に一度入れられたら、丸一日は出られまい。痛む体を丸めて、リツは涙を落とす。
「かかさま……」
優しく温かかった母のぬくもりを思い出して、リツは己が腕で自らの身体を抱きしめた。
腹部を蹴られたからであろう、胃の腑から饐えた匂いの液体がこみ上げて、リツはたまらず嘔吐く。
自分が何をしたのだろう。母が何をしたのだろう。幼い頭では何も分からぬ。ぐしゃぐしゃになった感情のまま、リツは初めて悪し言の葉を口にしたのである。
「……【痛い】」
どくん、と心の臓が波打った。
「痛い」
全身が熱い。ぼこぼこと血が波打つ感覚に、リツはたまらず転げまわった。
「痛い、痛い、痛い……!」
体中が引き攣れるように痛い。蹴られ殴られたからではない。四肢を無理矢理ねじり切られるような痛みに、リツは床をのたうち回る。
そして、リツは目を疑った。
爪先から指へ、指から手首へ、黒い痣が広がっていくのである。
「ひいぃ……!」
あまりの痛みにリツは意識を手放し――起きたときには、痣はすでに消えてなくなっていた。
それからもたびたび同じようなことが起こり、リツはすっかり理解した。
悪し言の葉。【痛い】、【辛い】、【苦しい】。
これらの言の葉を唇に乗せると、リツ自身へと呪いとなって返ってくる。その言の葉の意味する通りのことが、起こってしまう。
――リツの言の葉には魂があるの。だから良き言の葉を使いなさい。
物心つく前からの母の教え。良き言の葉を使いなさい。これは、こういうことだったのだ。
苦しい時に苦しいと言えず、やめてほしいときにやめてほしいと言えないリツは、次第に玩具のような扱いを受けるようになった。
いつからだろうか、リツが楼主ジタの慰みものとなったのは。
売り物である娼妓を傷ものにすることは楼主としては許されぬ。しかし、リツなら話は別だ。口にすることができないということは、助けを求めることができないということ。その呪いに気づいたか否かは別としても、楼主ジタとて何十人もの妓女を抱える身だもの。おんなの特性を見抜くことなど造作もない。
ジタはリツの体そのものをいたぶることはしなかった。嗜虐に満ちた欲望のはけ口として使うことを好むため、齢十八になった今でもリツは未通女のままである。
しかしながら、昼夜を問わず毎日自室へ呼ばれるリツを、同じ家業のおんなたちがどう思うかは火を見るより明らかだ。
良い衣を与えられ、狭いながらも自室を与えられ、特別な扱いを受けるリツは、楼主ジタの家妓である。そのようなことが口ずさまれた。
しなる鞭を体で受け止め、リツはそれでも涙を落とすまいと拳を握って耐え忍ぶ。
毎日毎夜くり返される嗜虐のあそびに、リツの肌は引き攣れ赤く爛れてしまっている。そんなこともお構いなしで、楼主ジタは鞭を振るい、新たな引き攣れをリツの肌に刻むのだ。
ヤソはジタのあそびには口を出さない。しかしながら体に傷を受けているリツを売り物にすることはとうに諦めているようで、ジタとともにリツを苛むことを楽しみとしているようであった。
今日のお勤めを終え、痛む体を引きずってジタの部屋を後にする。
自室へ戻る廊下の道すがら。丸窓の外を見やると豪雨であった。
リツは眉を曇らせる。
特別雨が嫌いなわけではない。しかし、巳の国を守るように聳え立つ山、その山頂の湖の様子が気になっていた。
――なにごとも起きなければいいのだけれど。
湖には、巳の国の守り神である蛟龍が住まうという。巨大な蛇の体を持つあやかしが、長い刻をへて龍になる。その龍になる前の姿を蛟龍と呼ぶ。
蛟龍は治世を見る。良き行いが多ければ蛟龍は国を豊かにし、悪し行いが多ければ国を亡ぼす。その者が怒り嘆くときは長雨が続くのだと、そのように言い伝えられていた。
蛟龍の怒りも怖ろしい。しかし、今専ら巳の国を悩ませているのは雨だけではなかった。
長引く雨で、悪いやまいが流行りを見せているというのである。それはこの楼も例に漏れず、何人ものおんなが罹患し、いのちを落としていた。
そろそろ大王も重い腰を上げるであろう。そのような事をジタやヤソが話しているのを聞いたことがある。
――いけない。
リツは足を早める。
まだ日は昇ったばかりである。着替えて仕事に戻らねば。リツは血に染まった衣をかき抱き、足早に廊下を渡った。
そのリツの背中を見つめる、二対の瞳が丸窓の外にあった。黄金色の宝玉の如き瞳が、きらりと瞬く。
豪雨の中、木に絡まるように体を支え、首をもたげているのは蛇である。蛇はしばらくリツを見つめると、ちろりと先割れの舌を出し、天を仰いだ。
そのままするすると雨にほどけ、まるで夢まぼろしのように姿が掻き消える。
そこには、ただ大地を揺るがすような雨音が残るばかりであった。
***
「リツ。旦那さまがお呼びだよ」
ヤソの声に、リツは驚いた。
刻は中天をほどなく過ぎ、日々の仕事のひとつである床磨きを終えたばかりでのお呼びである。楼主ジタは残忍な男だが、己が立場を弁えている。刻を置かずしてリツをいたぶることは彼女の命に関わると知っているため、お呼びはだいたい日に一度。または刻を開けて朝と夜。それが定石のはずであった。
これほどまでに刻を開けずにお呼びがかかるのは、初めてのことである。
「リツや」
急ぎ自室へ戻ろうとしたリツに、ヤソが声をかけた。やけにのっぺりとした声に、リツはぎくりと足を止める。
「はい、お方さま」
「今持っている衣の中で、一番上質なものを着ていくように」
「……はい、お方さま」
頭の中に、もやもやと疑念が混じる。
ヤソがこのように衣の指定をすることなど、今まであっただろうか。
「化粧は念入りにするんだよ。紅もしっかり引いて。お前は顔だけは見栄えがするんだからね。髪は流すよりも結い上げて、挿しものはなし。その代わりに飾り花をあしらうんだよ」
ヤソは嬉々としてリツの黒い髪をひと房手に取った。
「旦那さまのおあそびでけちのついたお前だもの。体についた醜い痕も、売り物にするにはもう手遅れだ。そんなお前でも役に立つことができる。こっちは厄介払いができるうえに、おあしもたくさんいただけるんだ。こんなおいしいことはない」
そのままヤソはリツの髪をぐいと引っ張る。ぶちぶちと髪の切れる音がして、リツはくっと唇をかみしめた。
「泣きもわめきもしない。痛めつけても何も言わない。お前は化けものさ。化けものには化けものがお似合いだ」
そのまま床に引きたおし、ヤソは唾を吐きかける。
「せいぜいしあわせにおなり。しあわせというのが本当にあるならね」
鼻息も荒く去っていくヤソの背中を、リツは呆然としながら見つめていた。
――お方さまは、いったい何を……。
髪に手をやり、そっと梳く。手の指にごっそりと抜けた髪が絡まるのを見て、リツは天を仰いだ。
――私だって、泣きたい。やめてと言いたい。でも。
こぼれ落ちそうになる涙を嚥下し、リツはゆっくり立ち上がる。
支度をしなければ。ヤソが何を言っているのか、リツには分からないけれど。呼ばれたら行かねばならないのだ。さもなくばもっと酷いことが待っている。
行李の中から取り出したのは鴇羽色の衣。不言色の紐で腰を縛り、飾り紐をすっと垂らした。化粧は丁寧に。眉を抜き、紅を引き、同じく目尻にぽんと紅を置く。たっぷりとした髪は結い上げ、飾り花は紅梅を。
「私は大丈夫」
口には良き言の葉を。痛めつけられていた体にすっと力が宿るような気がして、リツは微笑んでみせた。
少しだけ戻った力を頼りに、自室を出ると廊下を渡る。
雨はしとどに降り続き、丸窓から吹き込む風が湿った土の匂いを運んでいた。
「ただいま参りました」
リツは手を前に組み、丁寧に拝する。すかさず鞭が来るものとして信じて疑わなかったが、予想に反して楼主ジタは何もしなかった。
「表を上げよ。リツ」
リツを虐げているときとは別の楼主としてのジタの口調に、リツはつうと顔を挙げる。楼主ジタの部屋にはジタ本人と、もう一人。ジタの方が一段下がり、客人の方が格上として扱われているのが分かる。
極彩色の絢爛豪華な衣を纏い、瞳に下卑た光を宿した男はリツを見て口を開いた。
「なるほど、そちらが例のおんなであるか」
「はい、間違いございませぬ」
「この器量。本当に未通女であろうな」
ジタは頭を深く垂れる。
「このむすめは少々難儀な性格ゆえ、まだ見世には挙げておりませぬ。条件を満たすむすめはこの楼ではリツだけでございます」
「よい。では明日迎えをよこす。礼は明日、おんなと引き換えに」
それだけを告げると、男はリツの横をすっと抜け、部屋を後にする。鼻を掠める香りにリツは眉を潜めた。
――かかさまと、同じ匂い……。
畏れ多くも神にたてまつる供物として焚きしめられる香の、独特な甘い香りである。
――とても、煌びやかな方だけれど……。
母と同じように、神にお仕えする方なんだろうか。
「リツ」
その声に、リツははっと目を瞬かせる。慌てて礼の形を取り直し、ジタと向かい合った。
「喜べ、おまえは蛟龍のつまに選ばれたのだ」
ジタの声に、リツは目を見張った。
「蛟龍の、つま……」
さよう、とジタは唇を歪めて頷く。
「大変ほまれなことであるからな。楼主としても協力しないわけには参るまい。おまえのようなものでもひとさまの役に立つことができるのだ、ありがたく思うように」
「旦那さま、それはどういう……!」
「わかるな、リツ。雨が長引けば見世が困るんだ。礼もはずむとのことであるしな。わしとておまえを手放すのは惜しいが……」
ジタは好色の光を浮かべリツを舐めるように見やると、口を歪めてこう言った。
「大王の決められたことである。口惜しいが、従うしかあるまい」
話はすんだとばかりに手で追い払われ、リツはジタの部屋を後にする。
廊下を渡り、丸窓を見やると天の底が抜けたかと思うほどの雨である。
リツは決して鈍い娘ではない。蛟龍のつまとジタは言うが、それはつまり。
――贄……。
この長雨である。
湖に祀られる蛟龍は、治水の神。その神におんなをとつがせることで、雨が止むようにと祈願を行うのだろう。
だとすれば、先ほどの男は大王に使える神官だ。
リツは床に崩れ落ちそうになる体を必死で支えた。
――私が、何をしたんだろう。
絶望を胸に抱え、リツは天を仰ぐ。
巫である母を持ち、幼き頃から神がすぐそばにある暮らしをしてきたリツだからこそ。彼女は知っていた。
神にとつぐことは即ち、自らのいのちを差し出すということ。
泣くな。泣いても誰も助けてはくれない。それでも胸に迫る感情は、リツの中で膨らみ続け、ぼろりと一粒涙が落ちる。
雨の音だけが木霊する廊下で、リツは静かに泣き続けた。
***
久しぶりに執り行われる国を挙げてのまつりに、巳の国は大いに沸いた。
雨をものともせずに人びとは歌い、地を踏み鳴らし踊りを捧げる。
駕籠に籠められたリツは人びとの祝りの言の葉を一身に受けながら、山の上の湖を目指す。金糸銀糸でずっしりと重い絹の衣に、花の顔。見るものすべてを魅了するむすめが、妓女であることを知っている人は少ないのであろう。
蛟龍のつまはほまれであると言われるものの、好んで化け物にむすめを差し出す親はなし。手っ取り早く、身寄りのないものを差し出そうとする大王や神官たちの魂胆が、リツには悔しくてたまらなかった。
ゆらゆらと揺れる駕籠の隙間からは、湖までの道を照らす門火が見える。
油を使い囂々と焚かれる門火は、嫁するものを祝る火だ。しかし今のリツにはそれが弔いの火のように見えた。
水を満々と湛えた湖面が雨に濡れている。
湖の岸には祭壇が組まれ、リツはその先へと促される。水を含んだ衣がずっしりと体に絡みついた。
面をつけた神官のおざなりな祝詞を聞きながら、リツは母のことを思い出す。
ひふみよいむなや
ここのたり
いつとせ
むとせ
ななとせと
ももとせたてばゆらゆらと
いめにくちなは
あらはるる
かためひらきて
あひみたし
巫であった母から教わった魂の鎮め歌。この歌を真の祈りとともに奉れば、荒ぶる神をも鎮めることができるという。
――せめて。
リツは祈る。
――せめて私のいのちを捧げることで、蛟龍の怒りが鎮まりますように。
――悪しやまいを食い止めることができますように。
胸を張る。巫である母に恥じぬよう、自らのお役目を勤めよう。
「ひふみよいむなや……ここのたり……」
神官の祝詞に合わせて、リツは鎮め歌を口にした。
「いつとせ、むとせ、ななとせと……」
先導され、祭壇の先端に足を運ぶ。
「ももとせたてばゆらゆらと」
板でできた祭壇は湖のさなかまで伸びていた。
「いめにくちなは……あらはるる」
手足に錘がつけられた。
「かためひらきて……」
神官が一歩下がり、榊を振った。
「あひ……みたし……」
と、と軽く板を蹴り、リツは湖に身を落とす。冷たい水が容赦なく体を包み込み、リツはゆっくりと沈んでいく。
このまま、自分は死ぬのであろう。
――巳の国の民、すべてに幸いがありますように。
こぽりと泡が立ち上った。雨音も、もはや聞こえない。自らの心臓の音と、こぽこぽと立ち上る泡の音に包まれて、リツは静かに意識を手放した――……。
ここのたり
いつとせ
むとせ
ななとせと
ももとせたてばゆらゆらと
いめにくちなは
あらはるる
かためひらきて
あひみたし
思い出すのは幼き頃の母の腕。眠い眼をこすれば歌う、魂の鎮め歌。
「リツ、リツや。賢き吾子よ」
ひふみよいむなや
ここのたり
いつとせ
むとせ
ななとせと
ももとせたてばゆらゆらと
「リツの言の葉には魂があるの。だから良き言葉を使いなさい」
夢うつつ、母の温かい腕に抱かれ、リツはゆらゆらと微睡んだ。子守歌には鎮めの歌を歌って聞かせる母の声。
甘くやわらかな日々。こんな日が永遠に続くものだと思っていた。
でも、これはすべて夢まぼろし。
早く目を覚まさなければ。
一刻も早く。
そして、今日も凄惨な日々が始まる。
***
「リツ! このうすのろ!」
容赦なく振り下ろされた鞭に、リツはくっと歯を食いしばる。仕立てたばかりの衣が破れ、背中にじんわりと血が滲んだ。
「雄鶏四つ鳴くまでに起きるようにとあれほど言っただろうに、どこまでも人を莫迦にしたむすめだよ!」
鞭がしなり、またひとつ。リツは唇を噛みしめた。
いいえ、ちがいます。お方さまは雄鶏六つと仰いました。その一言が言えればどんなにいいか――。
まだ神々が人のすぐ側で息づいていた時代。
人の住まう瑞穂の地、その地にある国のひとつ巳の国は風光明媚。絢爛豪華な佇まいで文化芸事の一等地として名を馳せていた。背後の山上に大きな湖を持ち、扇状に広がった国は湖がもたらす豊かな土と清浄な水の流れでもって栄華を極めていたのである。
巳の国に、青の屋根を持つ妓楼があった。
その妓楼で娼妓見習いとして働くリツは、見目麗しい娘である。
流れるようなたっぷりとした黒髪。憂いを帯びたような瞳も同じく烏の濡羽色。華麗というよりも嫋やかな、吹けば飛びそうな繊細な美しさを持つ娘であった。
「ふん、可愛げもない。もう鞭は慣れっこだろうね? いいだろう。堪忍おし」
楼主のつま、ヤソは目を三日月の形に歪めて嗤った。
「さっさと支度をしな。旦那さまがお呼びだよ」
リツはごくりと喉を鳴らす。
与えられた粗末な自室に、ひと梱の行李。取り出した衣は手の上で蕩けるような極上の絹。それをさらりと素肌に纏い、前はわざときっちり合わせる。色は白。または薄紅。肌に吸い付く絹の衣は、華奢なリツの体に沿って緩やかに床へと流れ落ちた。髪に挿すのは紅梅の玉。化粧を施し紅を入れ、リツは心を落ち着かせた。
――大丈夫。
もう何度も経験したのだから。それでも震える掌を、リツは自らの胸に抱きこんだ。
――私は何も感じない。何も思わない。心を消して痛みを消して。
足早に廊下を渡り楼主の自室の壁を叩くと、銅鑼声で入れと告げられる。
「お待たせしました、旦那さま」
両の手を組み拝すると、すかさずその手に一閃。
皮膚の焼かれる痛みに、リツは顔を歪めた。
「おお、その顔じゃ。リツ、ぬしのその顔がなによりの馳走」
楼主ジタは鞭をにぎりしめ、にやけた顔で舌なめずりをする。二、三、鞭が走り、絹の衣が切り裂かれ、じわりと血が滲みだす。
主は、リツの着る衣が赤に染まるのを楽しんでいるのだ。
やめてくれと、リツは言えない。リツは否を言ってはならない。痛くとも、苦しくとも、リツは唇を噛み締めてうつむき耐える。自分を守るためにも、リツは悪し言の葉を口に乗せてはいけないのだ。
リツが自身の持つ力に気づいたのは、皮肉にも母が亡くなったすぐ後であった。
齢八つの頃である。
母一人、子一人で暮らしてきた身。頼れるものもなく、残されたむすめがその後の生き方を自分で選べるはずもない。気づけばこの妓楼がリツの第二の家となった。
初めて妓楼へ足を踏み入れたときは、少しだけわくわくした心持ちだったことを覚えている。見るものすべてが煌びやかで、艶やかなおんなたちはリツに向かって軽く手を振ってくれる。
しかし、表が艶やかであればあるほど、光が満ちていればいるほど、影は濃くなり澱むもの。リツの器量が純粋に愛されたのは初めだけ。妬み、嫉み、あらゆるおんなの負の感情を一心に背負うようになるまで、大した時間はかからなかった。
ある日のことである。
リツはヤソの言いつけを間違え、ほんのひとさじ、自分の飯を多く盛る。目ざとく見つけた禿に大声で言いふらされ、リツは初めて折檻を受けた。
髪を掴まれ、引きずり倒され、背中と手に鞭を一閃。
「卑しい小むすめ! 親も親なら子も子だよ!」
ヤソは口を歪めてリツを罵った。その言葉に、リツはカッとなる。
「なぜかかさまが出てくるのです! かかさまは関係ありません!」
「あるともさ。おまえは自分の大切な母さまが何をしていたのか知らないのだろうね」
ねっとりとした口調のヤソは口の端に侮蔑の笑みを刻む。
「巫の血を引くだかなんだかしらないが、巫とは名ばかりの民妓じゃないか。邑の男に股開いて食わせてもらったおまんまは美味かったろうね」
リツは口をぽかんと開けた。
「さぞ具合がよかったんだろう、おかげでうちはとんだ大損さ。あたしがおまえを引き取るようにと旦那さまに進言したのはね、おまえの中のみだらがましい性根を見抜いたからなんだよ。母譲りの好きものだ。おまえの母がウチの稼ぎを邪魔したそれ以上に、せいぜい絞れるだけ絞ってやらなければ気がすまないからね!」
幼き頭には言葉の意味の全てまでは分からない。ただ、自分の大切な母が口汚く罵られていることだけはわかったので、リツは眦にぎっと力をこめた。
「かかさまは立派な方です!」
「おだまり!」
好き放題に殴られ、蹴られ、鞭を振るわれ、リツは呻いた。床に倒れ込んだリツに唾を吐き、ヤソは居丈高に部屋を出る。無情にも降ろされた鍵の音が、リツの脳内に木霊した。
折檻部屋に一度入れられたら、丸一日は出られまい。痛む体を丸めて、リツは涙を落とす。
「かかさま……」
優しく温かかった母のぬくもりを思い出して、リツは己が腕で自らの身体を抱きしめた。
腹部を蹴られたからであろう、胃の腑から饐えた匂いの液体がこみ上げて、リツはたまらず嘔吐く。
自分が何をしたのだろう。母が何をしたのだろう。幼い頭では何も分からぬ。ぐしゃぐしゃになった感情のまま、リツは初めて悪し言の葉を口にしたのである。
「……【痛い】」
どくん、と心の臓が波打った。
「痛い」
全身が熱い。ぼこぼこと血が波打つ感覚に、リツはたまらず転げまわった。
「痛い、痛い、痛い……!」
体中が引き攣れるように痛い。蹴られ殴られたからではない。四肢を無理矢理ねじり切られるような痛みに、リツは床をのたうち回る。
そして、リツは目を疑った。
爪先から指へ、指から手首へ、黒い痣が広がっていくのである。
「ひいぃ……!」
あまりの痛みにリツは意識を手放し――起きたときには、痣はすでに消えてなくなっていた。
それからもたびたび同じようなことが起こり、リツはすっかり理解した。
悪し言の葉。【痛い】、【辛い】、【苦しい】。
これらの言の葉を唇に乗せると、リツ自身へと呪いとなって返ってくる。その言の葉の意味する通りのことが、起こってしまう。
――リツの言の葉には魂があるの。だから良き言の葉を使いなさい。
物心つく前からの母の教え。良き言の葉を使いなさい。これは、こういうことだったのだ。
苦しい時に苦しいと言えず、やめてほしいときにやめてほしいと言えないリツは、次第に玩具のような扱いを受けるようになった。
いつからだろうか、リツが楼主ジタの慰みものとなったのは。
売り物である娼妓を傷ものにすることは楼主としては許されぬ。しかし、リツなら話は別だ。口にすることができないということは、助けを求めることができないということ。その呪いに気づいたか否かは別としても、楼主ジタとて何十人もの妓女を抱える身だもの。おんなの特性を見抜くことなど造作もない。
ジタはリツの体そのものをいたぶることはしなかった。嗜虐に満ちた欲望のはけ口として使うことを好むため、齢十八になった今でもリツは未通女のままである。
しかしながら、昼夜を問わず毎日自室へ呼ばれるリツを、同じ家業のおんなたちがどう思うかは火を見るより明らかだ。
良い衣を与えられ、狭いながらも自室を与えられ、特別な扱いを受けるリツは、楼主ジタの家妓である。そのようなことが口ずさまれた。
しなる鞭を体で受け止め、リツはそれでも涙を落とすまいと拳を握って耐え忍ぶ。
毎日毎夜くり返される嗜虐のあそびに、リツの肌は引き攣れ赤く爛れてしまっている。そんなこともお構いなしで、楼主ジタは鞭を振るい、新たな引き攣れをリツの肌に刻むのだ。
ヤソはジタのあそびには口を出さない。しかしながら体に傷を受けているリツを売り物にすることはとうに諦めているようで、ジタとともにリツを苛むことを楽しみとしているようであった。
今日のお勤めを終え、痛む体を引きずってジタの部屋を後にする。
自室へ戻る廊下の道すがら。丸窓の外を見やると豪雨であった。
リツは眉を曇らせる。
特別雨が嫌いなわけではない。しかし、巳の国を守るように聳え立つ山、その山頂の湖の様子が気になっていた。
――なにごとも起きなければいいのだけれど。
湖には、巳の国の守り神である蛟龍が住まうという。巨大な蛇の体を持つあやかしが、長い刻をへて龍になる。その龍になる前の姿を蛟龍と呼ぶ。
蛟龍は治世を見る。良き行いが多ければ蛟龍は国を豊かにし、悪し行いが多ければ国を亡ぼす。その者が怒り嘆くときは長雨が続くのだと、そのように言い伝えられていた。
蛟龍の怒りも怖ろしい。しかし、今専ら巳の国を悩ませているのは雨だけではなかった。
長引く雨で、悪いやまいが流行りを見せているというのである。それはこの楼も例に漏れず、何人ものおんなが罹患し、いのちを落としていた。
そろそろ大王も重い腰を上げるであろう。そのような事をジタやヤソが話しているのを聞いたことがある。
――いけない。
リツは足を早める。
まだ日は昇ったばかりである。着替えて仕事に戻らねば。リツは血に染まった衣をかき抱き、足早に廊下を渡った。
そのリツの背中を見つめる、二対の瞳が丸窓の外にあった。黄金色の宝玉の如き瞳が、きらりと瞬く。
豪雨の中、木に絡まるように体を支え、首をもたげているのは蛇である。蛇はしばらくリツを見つめると、ちろりと先割れの舌を出し、天を仰いだ。
そのままするすると雨にほどけ、まるで夢まぼろしのように姿が掻き消える。
そこには、ただ大地を揺るがすような雨音が残るばかりであった。
***
「リツ。旦那さまがお呼びだよ」
ヤソの声に、リツは驚いた。
刻は中天をほどなく過ぎ、日々の仕事のひとつである床磨きを終えたばかりでのお呼びである。楼主ジタは残忍な男だが、己が立場を弁えている。刻を置かずしてリツをいたぶることは彼女の命に関わると知っているため、お呼びはだいたい日に一度。または刻を開けて朝と夜。それが定石のはずであった。
これほどまでに刻を開けずにお呼びがかかるのは、初めてのことである。
「リツや」
急ぎ自室へ戻ろうとしたリツに、ヤソが声をかけた。やけにのっぺりとした声に、リツはぎくりと足を止める。
「はい、お方さま」
「今持っている衣の中で、一番上質なものを着ていくように」
「……はい、お方さま」
頭の中に、もやもやと疑念が混じる。
ヤソがこのように衣の指定をすることなど、今まであっただろうか。
「化粧は念入りにするんだよ。紅もしっかり引いて。お前は顔だけは見栄えがするんだからね。髪は流すよりも結い上げて、挿しものはなし。その代わりに飾り花をあしらうんだよ」
ヤソは嬉々としてリツの黒い髪をひと房手に取った。
「旦那さまのおあそびでけちのついたお前だもの。体についた醜い痕も、売り物にするにはもう手遅れだ。そんなお前でも役に立つことができる。こっちは厄介払いができるうえに、おあしもたくさんいただけるんだ。こんなおいしいことはない」
そのままヤソはリツの髪をぐいと引っ張る。ぶちぶちと髪の切れる音がして、リツはくっと唇をかみしめた。
「泣きもわめきもしない。痛めつけても何も言わない。お前は化けものさ。化けものには化けものがお似合いだ」
そのまま床に引きたおし、ヤソは唾を吐きかける。
「せいぜいしあわせにおなり。しあわせというのが本当にあるならね」
鼻息も荒く去っていくヤソの背中を、リツは呆然としながら見つめていた。
――お方さまは、いったい何を……。
髪に手をやり、そっと梳く。手の指にごっそりと抜けた髪が絡まるのを見て、リツは天を仰いだ。
――私だって、泣きたい。やめてと言いたい。でも。
こぼれ落ちそうになる涙を嚥下し、リツはゆっくり立ち上がる。
支度をしなければ。ヤソが何を言っているのか、リツには分からないけれど。呼ばれたら行かねばならないのだ。さもなくばもっと酷いことが待っている。
行李の中から取り出したのは鴇羽色の衣。不言色の紐で腰を縛り、飾り紐をすっと垂らした。化粧は丁寧に。眉を抜き、紅を引き、同じく目尻にぽんと紅を置く。たっぷりとした髪は結い上げ、飾り花は紅梅を。
「私は大丈夫」
口には良き言の葉を。痛めつけられていた体にすっと力が宿るような気がして、リツは微笑んでみせた。
少しだけ戻った力を頼りに、自室を出ると廊下を渡る。
雨はしとどに降り続き、丸窓から吹き込む風が湿った土の匂いを運んでいた。
「ただいま参りました」
リツは手を前に組み、丁寧に拝する。すかさず鞭が来るものとして信じて疑わなかったが、予想に反して楼主ジタは何もしなかった。
「表を上げよ。リツ」
リツを虐げているときとは別の楼主としてのジタの口調に、リツはつうと顔を挙げる。楼主ジタの部屋にはジタ本人と、もう一人。ジタの方が一段下がり、客人の方が格上として扱われているのが分かる。
極彩色の絢爛豪華な衣を纏い、瞳に下卑た光を宿した男はリツを見て口を開いた。
「なるほど、そちらが例のおんなであるか」
「はい、間違いございませぬ」
「この器量。本当に未通女であろうな」
ジタは頭を深く垂れる。
「このむすめは少々難儀な性格ゆえ、まだ見世には挙げておりませぬ。条件を満たすむすめはこの楼ではリツだけでございます」
「よい。では明日迎えをよこす。礼は明日、おんなと引き換えに」
それだけを告げると、男はリツの横をすっと抜け、部屋を後にする。鼻を掠める香りにリツは眉を潜めた。
――かかさまと、同じ匂い……。
畏れ多くも神にたてまつる供物として焚きしめられる香の、独特な甘い香りである。
――とても、煌びやかな方だけれど……。
母と同じように、神にお仕えする方なんだろうか。
「リツ」
その声に、リツははっと目を瞬かせる。慌てて礼の形を取り直し、ジタと向かい合った。
「喜べ、おまえは蛟龍のつまに選ばれたのだ」
ジタの声に、リツは目を見張った。
「蛟龍の、つま……」
さよう、とジタは唇を歪めて頷く。
「大変ほまれなことであるからな。楼主としても協力しないわけには参るまい。おまえのようなものでもひとさまの役に立つことができるのだ、ありがたく思うように」
「旦那さま、それはどういう……!」
「わかるな、リツ。雨が長引けば見世が困るんだ。礼もはずむとのことであるしな。わしとておまえを手放すのは惜しいが……」
ジタは好色の光を浮かべリツを舐めるように見やると、口を歪めてこう言った。
「大王の決められたことである。口惜しいが、従うしかあるまい」
話はすんだとばかりに手で追い払われ、リツはジタの部屋を後にする。
廊下を渡り、丸窓を見やると天の底が抜けたかと思うほどの雨である。
リツは決して鈍い娘ではない。蛟龍のつまとジタは言うが、それはつまり。
――贄……。
この長雨である。
湖に祀られる蛟龍は、治水の神。その神におんなをとつがせることで、雨が止むようにと祈願を行うのだろう。
だとすれば、先ほどの男は大王に使える神官だ。
リツは床に崩れ落ちそうになる体を必死で支えた。
――私が、何をしたんだろう。
絶望を胸に抱え、リツは天を仰ぐ。
巫である母を持ち、幼き頃から神がすぐそばにある暮らしをしてきたリツだからこそ。彼女は知っていた。
神にとつぐことは即ち、自らのいのちを差し出すということ。
泣くな。泣いても誰も助けてはくれない。それでも胸に迫る感情は、リツの中で膨らみ続け、ぼろりと一粒涙が落ちる。
雨の音だけが木霊する廊下で、リツは静かに泣き続けた。
***
久しぶりに執り行われる国を挙げてのまつりに、巳の国は大いに沸いた。
雨をものともせずに人びとは歌い、地を踏み鳴らし踊りを捧げる。
駕籠に籠められたリツは人びとの祝りの言の葉を一身に受けながら、山の上の湖を目指す。金糸銀糸でずっしりと重い絹の衣に、花の顔。見るものすべてを魅了するむすめが、妓女であることを知っている人は少ないのであろう。
蛟龍のつまはほまれであると言われるものの、好んで化け物にむすめを差し出す親はなし。手っ取り早く、身寄りのないものを差し出そうとする大王や神官たちの魂胆が、リツには悔しくてたまらなかった。
ゆらゆらと揺れる駕籠の隙間からは、湖までの道を照らす門火が見える。
油を使い囂々と焚かれる門火は、嫁するものを祝る火だ。しかし今のリツにはそれが弔いの火のように見えた。
水を満々と湛えた湖面が雨に濡れている。
湖の岸には祭壇が組まれ、リツはその先へと促される。水を含んだ衣がずっしりと体に絡みついた。
面をつけた神官のおざなりな祝詞を聞きながら、リツは母のことを思い出す。
ひふみよいむなや
ここのたり
いつとせ
むとせ
ななとせと
ももとせたてばゆらゆらと
いめにくちなは
あらはるる
かためひらきて
あひみたし
巫であった母から教わった魂の鎮め歌。この歌を真の祈りとともに奉れば、荒ぶる神をも鎮めることができるという。
――せめて。
リツは祈る。
――せめて私のいのちを捧げることで、蛟龍の怒りが鎮まりますように。
――悪しやまいを食い止めることができますように。
胸を張る。巫である母に恥じぬよう、自らのお役目を勤めよう。
「ひふみよいむなや……ここのたり……」
神官の祝詞に合わせて、リツは鎮め歌を口にした。
「いつとせ、むとせ、ななとせと……」
先導され、祭壇の先端に足を運ぶ。
「ももとせたてばゆらゆらと」
板でできた祭壇は湖のさなかまで伸びていた。
「いめにくちなは……あらはるる」
手足に錘がつけられた。
「かためひらきて……」
神官が一歩下がり、榊を振った。
「あひ……みたし……」
と、と軽く板を蹴り、リツは湖に身を落とす。冷たい水が容赦なく体を包み込み、リツはゆっくりと沈んでいく。
このまま、自分は死ぬのであろう。
――巳の国の民、すべてに幸いがありますように。
こぽりと泡が立ち上った。雨音も、もはや聞こえない。自らの心臓の音と、こぽこぽと立ち上る泡の音に包まれて、リツは静かに意識を手放した――……。