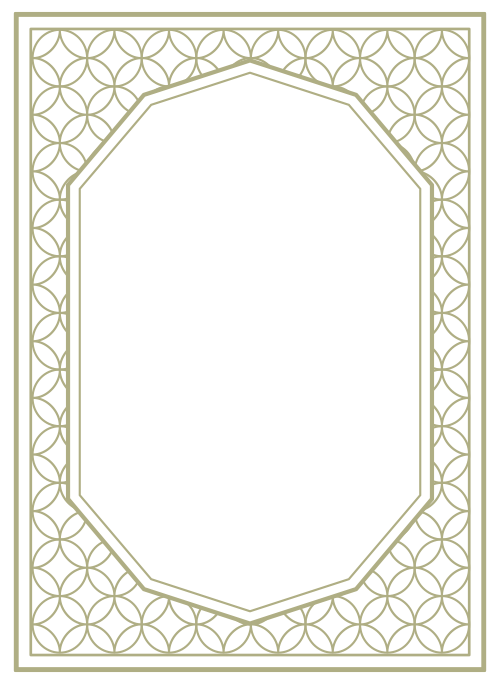自分でも驚いた。どうして私、今、莉子の名前を呼んだんだろう。
莉子の瞳が私を捉える。
「こっち!」
どうしたらいいのかわからない。でも、自分の方へと呼んでいて、走り出している。
莉子もまた同じように走り出し、校舎へと入ってくる。その後ろを渡辺さんたちが追いかけている。
生徒が疎らな廊下をただひたすらに走り、階段を見つけては勢いよく下りていく。
足音が聞こえ、二階の踊り場で莉子を見つけたときは、なにも考えず莉子の手を取っていた。
渡り廊下を突き抜け、無我夢中で走り続ける。目的地なんてどこも当てがない。でも走らないといけないという使命感だけで突き動かされていた。
「ここなら……っ、平気、だと思う」
調理室へと駆け込み、シンク下に隠れるよう身を潜める。息が、吸えない。
何度も肩で呼吸していると「ねえ」と莉子の声が聞こえる。
「なんで、助けて、くれたの」
胸元を抑えながら、必死に酸素を求める莉子の姿。
「なんでって……なんで、ビンタなんてしたの、渡辺さんたちに」
「知らないっ……ムカついたから」
バタバタと、足音が聞こえる。ああ、渡辺さんたちだ。その足音が近くなり、そしてまた急速に遠のいていく。
「謝りたかった」
グラウンドから微かに音楽が聞こえ、生徒の声も混じって賑わっている。
橙色の光を受けた莉子の髪が、艶めくように輝く。
「三春に、謝ろうと思ったの」
「……なんで」
「傷つけたから」
真っ直ぐに見つめられ、息が止まりそうになる。
「中学のときも、卒業してからも、さっきも。ずっと三春のことを傷つけて、それでいいやと思ってた。私には関係ないって思ったし。でも、だめだとも思った」
「……莉子」
「ごめんなさい。たくさん傷つけて。また友達になれるなんて思ってないし、傷つけたことは変わらないけど、それでも謝りたかった。ちゃんと、三春に」
窓から見えた特設ステージがライトアップされている。
莉子の瞳が私を捉える。
「こっち!」
どうしたらいいのかわからない。でも、自分の方へと呼んでいて、走り出している。
莉子もまた同じように走り出し、校舎へと入ってくる。その後ろを渡辺さんたちが追いかけている。
生徒が疎らな廊下をただひたすらに走り、階段を見つけては勢いよく下りていく。
足音が聞こえ、二階の踊り場で莉子を見つけたときは、なにも考えず莉子の手を取っていた。
渡り廊下を突き抜け、無我夢中で走り続ける。目的地なんてどこも当てがない。でも走らないといけないという使命感だけで突き動かされていた。
「ここなら……っ、平気、だと思う」
調理室へと駆け込み、シンク下に隠れるよう身を潜める。息が、吸えない。
何度も肩で呼吸していると「ねえ」と莉子の声が聞こえる。
「なんで、助けて、くれたの」
胸元を抑えながら、必死に酸素を求める莉子の姿。
「なんでって……なんで、ビンタなんてしたの、渡辺さんたちに」
「知らないっ……ムカついたから」
バタバタと、足音が聞こえる。ああ、渡辺さんたちだ。その足音が近くなり、そしてまた急速に遠のいていく。
「謝りたかった」
グラウンドから微かに音楽が聞こえ、生徒の声も混じって賑わっている。
橙色の光を受けた莉子の髪が、艶めくように輝く。
「三春に、謝ろうと思ったの」
「……なんで」
「傷つけたから」
真っ直ぐに見つめられ、息が止まりそうになる。
「中学のときも、卒業してからも、さっきも。ずっと三春のことを傷つけて、それでいいやと思ってた。私には関係ないって思ったし。でも、だめだとも思った」
「……莉子」
「ごめんなさい。たくさん傷つけて。また友達になれるなんて思ってないし、傷つけたことは変わらないけど、それでも謝りたかった。ちゃんと、三春に」
窓から見えた特設ステージがライトアップされている。