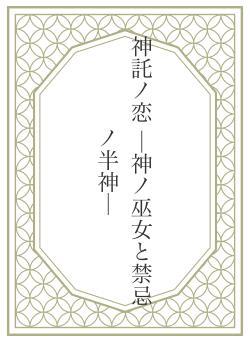梅雨が明ける頃、彼女は眠剤を飲まなくても、馬鹿みたいにアルバムを再生し続けなくても、眠れるようになっていることに気付いた。
そして、ちょうど期末テストの時期にさしかかっていた。
彼女の高校は、県内では進学校と呼ばれる部類に入っているため、生徒も先生も勉強熱心な人が多い。
「ねぇ、数一の二次関数分かる?」
そう言って休憩時間に彼女に話しかけてきたのは、夏実ーー志賀谷さんだ。
最近ではすっかり下の名前で呼び合う仲になっている。
「……や、私そこ全然分かんない。」
テスト前になると「全然わからないよ〜」と言って謙遜という名の嘘をつく人というのは往々として存在するものだが、彼女の場合は事実だった。
授業で二次関数をやっていた頃、学校に通うことだけで精一杯だった彼女は、予習はおろか、復習さえできていなかったのだ。
そろそろテスト勉強頑張らなきゃ。
その日から彼女は、授業が終わった後もすぐに家には帰らず、学校の図書室で勉強をするようになった。
帰ってきた頃にはくたくたで、眠れなかったことがまるで嘘のように一瞬で意識を失っていた。
その頃には、バニラと過ごしたあの時間は、夢の中の話だったのではないかとさえ思うようになっていた。
そして、ちょうど期末テストの時期にさしかかっていた。
彼女の高校は、県内では進学校と呼ばれる部類に入っているため、生徒も先生も勉強熱心な人が多い。
「ねぇ、数一の二次関数分かる?」
そう言って休憩時間に彼女に話しかけてきたのは、夏実ーー志賀谷さんだ。
最近ではすっかり下の名前で呼び合う仲になっている。
「……や、私そこ全然分かんない。」
テスト前になると「全然わからないよ〜」と言って謙遜という名の嘘をつく人というのは往々として存在するものだが、彼女の場合は事実だった。
授業で二次関数をやっていた頃、学校に通うことだけで精一杯だった彼女は、予習はおろか、復習さえできていなかったのだ。
そろそろテスト勉強頑張らなきゃ。
その日から彼女は、授業が終わった後もすぐに家には帰らず、学校の図書室で勉強をするようになった。
帰ってきた頃にはくたくたで、眠れなかったことがまるで嘘のように一瞬で意識を失っていた。
その頃には、バニラと過ごしたあの時間は、夢の中の話だったのではないかとさえ思うようになっていた。