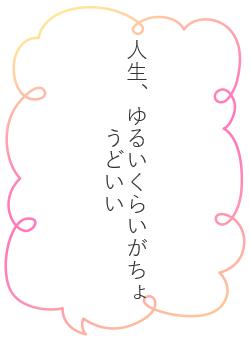6月(湊士パート)
すっかり梅雨入りして雨が続いていた。
その日はたまたま晴れの予報で、やや曇っているとはいえ日光が差していた。
湊士は一応と傘を持って家を出る。
時刻は7時16分。いつもの電車に乗り込んだ。
ゴールデンウィークも明け、すっかりいつもの日常へ。その日常には、ほぼ真横にいる美白の存在も含まれていた。
(やっぱかわいいよなあ)
ゴールデンウィーク明けの時、湊士は久しぶりに美白に会え、感極まっていたがそんな様子を見せるわけにもいかず、平常心を保とうと必死だった。しかし、どうしてもチラチラ見てしまい、しかも結構な頻度で目が合い、気まずくなっていた。
そんな時から約一月が流れ、ようやくいつもどおりに戻っていたが、湊士にとっては由々しき事態だった。
なんせなにも進展がないのだ。まだ出会って2か月ちょっと。焦る必要はないと思いつつも、そろそろ美白も学校に慣れてきて、彼氏の一人や二人、いるんじゃないかと心ここにあらずといった感じだった。
「あら、降ってきた?」
「ん?」
いつものOLが外を見ながら呟く。湊士はその言葉に釣られて外を見ると、さっきまでの陽光が消え、少しだけ雨が降っていた。
「ねえ、傘、持ってる?」
「あ、はい一応」
「じゃあ入らせて。あたし、傘忘れちゃった」
「了解です」
OLとその部下が話し合っている。湊士は内心、それって相合傘じゃね? と思ったが、大人になると緊張したりしないのかと大人の余裕に少し憧れた。湊士は自分が持っている傘を握りしめ、持ってきてよかったと安心していると、美白の様子がおかしいことに気が付く。なにやら鞄を必死で漁っていた。
その様子を見て、湊士は直感的に傘を忘れたのだと気づく。
湊士は悩んでいた。ここで露骨に傘を貸すとすごく怪しまれる。下手に下心があると思われたくない湊士は傘を貸す案を却下する。
とはいえ、さっきから美白はかなり困った様子である。
(なにかできることないかな……)
そうこうしていると雨はさっきより強くなっている。美白が外を見て愕然としている。
(なにか……なにか俺にできることは……)
もう変に思われてもいいから傘を貸そうかと思ったその時、湊士はある妙案を思いつく。
しかし、リスクが大きい案であり、失敗すると二人ともずぶ濡れになる。だが、貸しを与えず、それでいて彼女を助ける方法はもうこれしか思い浮かばなかった。
そうと決まれば湊士は行動を起こした。
もたれかかっていた手すりを離れ、さりげなく外を覗こうと彼女の側に寄る。ちょうどドアの開くところに立った。湊士はあくまで雨を確認するように振舞った。そして次は湊士の降りる駅である。
電車がゆっくり停止し、反対側のドアが開く。いつもならすぐに電車から降車するのだが、この時湊士はまだ車内に残っていた。そしてドアが閉まる汽笛が鳴った瞬間、
「やべっ!」
ちょっとわざとらしく大きな声を出し、傘を残したまま電車を降りた。
電車のドアは閉まり、やがて動き出した。
「気付いてくれるかな……」
湊士の作戦は概ね成功した。
わざと傘を残して電車を降りる。後は残った傘を彼女が使ってくれればそれでよかった。しかし、この作戦は美白が湊士の傘を見つけて使うこと前提の作戦である。もし、美白が傘を使わなかった場合、二人とも雨に打たれることになる。
「とはいえ、こうするしかないよなあ……」
湊士はそう呟いて、学校へ走っていった。
学校に着くと、凌悟がギョッとした表情で湊士を見つめた。
「お前、傘忘れたのか?」
「ああ、まあな」
「さすがに風邪ひくぞ。タオルくらい持ってきてるだろ。拭いとけ」
「そーする」
湊士は運動後に使う予定だったタオルで全身を拭いていく。
「まあ、今日は降るって天気予報でも言ってなかったしな。とはいえ、折り畳み傘くらいは持ってきとけよ」
「そうだな。明日から気を付ける」
「ったく。今日朝練はどうする?」
「見学にするよ。タオル乾かさないと」
「だよな」
そう言って湊士は大人しく見学していた。
昼休み。いつもの3人で昼飯を食べていると、昴にも注意された。
「まったく。さすがのポンコツっぷりね」
「まあね」
「褒めてないんですけど?」
湊士はカラカラと笑って弁当を食べていく。時折、湊士は外の雨を見てはため息をついた。
その様子を見て、凌悟が肘でつついてくる。
「そんなに見ても雨はやまないぞ」
「ん? ああ、まあ、そうだな」
「……?」
心ここにあらずという雰囲気の湊士に、昴はなにか感付いた。
「……なにかあった?」
「……え?」
聞こえていなかったのか、湊士はボーっとした表情からハッと我に返る。
明らかにおかしい様子に、昴はカマをかけてみることにした。
「傘、使ってくれるといいね」
「ああ、そうだな……」
「なるほど、そういうことか」
「……ん? え? なにが?」
女の勘とでもいうのだろうか。昴はおおよその状況を把握した。
「あんた、傘忘れてないでしょ。ってか例の彼女に貸したんでしょ」
「うえ!? スゲーな藤宮! よくわかったな!」
「まあ、なんとなく」
「あー、そういう」
凌悟も理解したようで、冷ややかな視線を送った。
「それでお前がずぶ濡れになってたんじゃ世話ないぜ。ってかその人、拒否らなかったのか?」
「えーっと、それがな――」
湊士は大まかな説明をした。すると、二人に呆れられる。
「お前さあ……。それ貸せてないかもじゃん」
「いや、そうなんだけどさ。前に藤宮が知らない男性から物渡されたらキモって思うって言ってたの思い出しちゃってさ」
「いや、せめて自分は折り畳み傘もあるって言っとけば彼女に確実に貸せたじゃん」
「そうなんだけどさあ。なんか貸しを作るのっていやじゃん? 向こうも負い目を感じるだろうし」
「うーん、難しいわね。確かに折り畳み持ってて傘も持ってるっていうのがすでに不自然なんだよねえ。だから湊士の賭けはある意味正しいのかも」
「え? マジ?」
まさかの高評価に、自分でやっておいて驚く湊士。
「これはある意味チャンスよ。もし向こうが傘を借りてたなら絶対返すはず。だって同じ電車に乗ってるんだからね。そこで当然なにかしら会話するんだからそこで接点を作るのよ」
「おお! そっか、そこで会話を広げれば一気に仲良くなったり――」
思わず身を乗り出す湊士を手で制す昴。それに怯んで湊士は大人しくなる。
「慌てなさんな。そこであんまりがっつくと逆効果よ」
「お、おう……」
逆効果、という言葉に冷静さを取り戻す湊士。
「まあ、今後電車で挨拶する程度のよっ友くらいにはなれそうね」
「マジ!? 十分だって!」
「そうね。3か月で別の学生とそこまでの仲になれれば上出来よ」
「あー! 俺の傘どうなったんだろなー!」
「ほんと、それに尽きるわね」
湊士の傘がどうなったかわからないため、とりあえずこれ以上話しても無駄という流れになったのと、チャイムが鳴ったのでこの話は流れた。
放課後、今日は体育館はバレー部が占領し、バスケ部は外錬の予定だったが、この雨のせいで部活は休みになった。
湊士は学校に予備の傘を借りて帰路についた。
その間、湊士の頭は美白のことでいっぱいだった。
「あー、ちゃんと使ってくれたかなあ……」
そんなことを呟いていると、駅の改札のところに美白がいることに気付く。
最初は申そうかと思ったが、そうではない。毎朝見惚れている女の子が駅に佇んでいた。その手には湊士の傘が握られていた。
湊士は軽くパニクってしばらく棒立ちしてしまった。
(え、なんでここに? 彼女の学校ってここじゃないよな? てか俺の傘。使ってくれたんだ。よかった――けどなんでここに?)
頭がぐるぐるする。しかし、ここにいる以上用事がある以外にない。湊士は覚悟を決めてゆっくりと彼女の方へ向かっていく。
彼女に近づくにつれて、心臓が爆発しそうになる。そして、彼女も湊士のことに気付いた。
確実に目が合った。すると彼女の方から声をかけてくれる。
「あの……」
「お、俺、ですか?」
「はい……」
透き通るような声。湊士はこの季節に似合わない晴れ渡るような声だと思った。
「あの……ごめんなさい!」
「え?」
突然美白に謝られ、困惑する湊士。
「これ、あなたのですよね?」
そいう言って渡されたのは湊士の傘だった。
「勝手に使っちゃいました! ごめんなさい!」
「あ、いや、別にいいっすよ」
「よくないですよ! 絶対雨に濡れたはずです!」
見た目に反して結構ものをはっきり言う子だなあ、などと思っていると強引に傘を返そうとしてきた。
「ちょちょちょ! ストップストップ!」
ぐいぐいくる美白を一旦落ち着かせることに。
「それ今俺に返したら家までどうするの?」
「それは……。親に迎えに来てもらう、とか?」
「なるほど。親にはもう連絡入れたんすか?」
「まだ、です……」
「一回連絡入れてみたらどうっすか? 忙しくて来れないなら結局また困るでしょ?」
「…………そうですね」
美白は携帯を取り出し、親に連絡を入れた。湊士は会話こそ聞こえなかったものの、美白の表情から迎えは難しそうだった。
美白の通話が終わり、声をかける。
「どう?」
「えっと、その……」
歯切れの悪い言葉。湊士はやはりといった感じで声をかける。
「あの、いつも同じ電車に乗ってます、よね? だから明日で大丈夫っすよ」
「……はい。……ごめんなさい」
しゅんとした彼女を見て、元気づけようと湊士はあたふたする。
「か、傘くらいで大げさっすよ? ってか、わざわざそれだけのために来てくれて嬉しいっていうか……」
「……え?」
「あ、いや、何でもないっす!」
湊士は恥ずかしさから顔を反らす。しばらく沈黙が続いたあと、美白からポツリと言葉が漏れた。
「ありがとう、ございます」
「へ? あ、いえ、どういたしまして」
湊士が返事すると、どちらともなく笑い出した。そうこうしていると、帰りの電車がやってくる。
「やべっ、早く乗りましょ」
「そうですね」
こうして湊士は初めて帰宅時に美白と一緒になった。それだけでなく、初めて会話した。
6月22日。この日は記念日になると、心の中でガッツポーズをした。
ところが恥ずかしさからか、帰りの電車での会話はなにもなく、朝と同様黙ったままだった。
(あれ? なにか言ったほうがいいのかな? でも、なんか気まずい!)
会話するための話題も特になく、二人で黙って突っ立っているだけだった。
そうして何もできないまま十数分が経ち、二人は最寄り駅で降りる。
改札を出ると、帰る方向が真逆だったため、ここでお別れとなる。
(なにか、なにか言わないと!)
湊士は内心かなり焦っていた。そして出た言葉は、
「で、では、また明日」
「あ、はい……。また明日」
そう言って美白は帰っていった。彼女の姿が見えなくなるまで立ちすくみ、一人になると盛大な溜息をついた。
「気の利いたこと、なんにも言えなかったな……」
嫌われてはいないと思う。が、好かれている様子もない。それが湊士の思いだった。
「これじゃなんも変わってねーよ……」
雨が降りしきる中、湊士も帰ることにした。
翌日、早めに駅へ向かい、美白を待つ。そして後ろから昨日きいた声がかかった。
「あの……」
「あ、どうも……」
おはようの挨拶すらできないほどギクシャクする二人。
「これ……」
そう言って渡されたのは傘だった。
「あ、はい……」
事務的に受け取る湊士。その後の会話もなし。これで何もないかと思われていたが、電車を降りる際、湊士は意を決して美白に叫ぶ。
「あの!」
「は、はい!」
美白も驚き、背筋が伸びる。
「別に貸しって思わなくていいんで! 困ったときはお互い様っていうか、とにかく!」
言葉をいったん切って、美白の目を見ながらハキハキ話す。
「また困ったことがあれば、いつでも言ってください!」
ポカンとした様子の美白。そしてクスッと笑い、答えてくれた。
「はい。頼りにさせていただきます」
湊士はお辞儀して電車を降りた。その後、友人二人に嬉しそうに報告したが、名前くらい伝えろと突っ込まれた。それでも、少しは距離が近づいたことを実感した湊士は、嬉しくて仕方がなかった。
すっかり梅雨入りして雨が続いていた。
その日はたまたま晴れの予報で、やや曇っているとはいえ日光が差していた。
湊士は一応と傘を持って家を出る。
時刻は7時16分。いつもの電車に乗り込んだ。
ゴールデンウィークも明け、すっかりいつもの日常へ。その日常には、ほぼ真横にいる美白の存在も含まれていた。
(やっぱかわいいよなあ)
ゴールデンウィーク明けの時、湊士は久しぶりに美白に会え、感極まっていたがそんな様子を見せるわけにもいかず、平常心を保とうと必死だった。しかし、どうしてもチラチラ見てしまい、しかも結構な頻度で目が合い、気まずくなっていた。
そんな時から約一月が流れ、ようやくいつもどおりに戻っていたが、湊士にとっては由々しき事態だった。
なんせなにも進展がないのだ。まだ出会って2か月ちょっと。焦る必要はないと思いつつも、そろそろ美白も学校に慣れてきて、彼氏の一人や二人、いるんじゃないかと心ここにあらずといった感じだった。
「あら、降ってきた?」
「ん?」
いつものOLが外を見ながら呟く。湊士はその言葉に釣られて外を見ると、さっきまでの陽光が消え、少しだけ雨が降っていた。
「ねえ、傘、持ってる?」
「あ、はい一応」
「じゃあ入らせて。あたし、傘忘れちゃった」
「了解です」
OLとその部下が話し合っている。湊士は内心、それって相合傘じゃね? と思ったが、大人になると緊張したりしないのかと大人の余裕に少し憧れた。湊士は自分が持っている傘を握りしめ、持ってきてよかったと安心していると、美白の様子がおかしいことに気が付く。なにやら鞄を必死で漁っていた。
その様子を見て、湊士は直感的に傘を忘れたのだと気づく。
湊士は悩んでいた。ここで露骨に傘を貸すとすごく怪しまれる。下手に下心があると思われたくない湊士は傘を貸す案を却下する。
とはいえ、さっきから美白はかなり困った様子である。
(なにかできることないかな……)
そうこうしていると雨はさっきより強くなっている。美白が外を見て愕然としている。
(なにか……なにか俺にできることは……)
もう変に思われてもいいから傘を貸そうかと思ったその時、湊士はある妙案を思いつく。
しかし、リスクが大きい案であり、失敗すると二人ともずぶ濡れになる。だが、貸しを与えず、それでいて彼女を助ける方法はもうこれしか思い浮かばなかった。
そうと決まれば湊士は行動を起こした。
もたれかかっていた手すりを離れ、さりげなく外を覗こうと彼女の側に寄る。ちょうどドアの開くところに立った。湊士はあくまで雨を確認するように振舞った。そして次は湊士の降りる駅である。
電車がゆっくり停止し、反対側のドアが開く。いつもならすぐに電車から降車するのだが、この時湊士はまだ車内に残っていた。そしてドアが閉まる汽笛が鳴った瞬間、
「やべっ!」
ちょっとわざとらしく大きな声を出し、傘を残したまま電車を降りた。
電車のドアは閉まり、やがて動き出した。
「気付いてくれるかな……」
湊士の作戦は概ね成功した。
わざと傘を残して電車を降りる。後は残った傘を彼女が使ってくれればそれでよかった。しかし、この作戦は美白が湊士の傘を見つけて使うこと前提の作戦である。もし、美白が傘を使わなかった場合、二人とも雨に打たれることになる。
「とはいえ、こうするしかないよなあ……」
湊士はそう呟いて、学校へ走っていった。
学校に着くと、凌悟がギョッとした表情で湊士を見つめた。
「お前、傘忘れたのか?」
「ああ、まあな」
「さすがに風邪ひくぞ。タオルくらい持ってきてるだろ。拭いとけ」
「そーする」
湊士は運動後に使う予定だったタオルで全身を拭いていく。
「まあ、今日は降るって天気予報でも言ってなかったしな。とはいえ、折り畳み傘くらいは持ってきとけよ」
「そうだな。明日から気を付ける」
「ったく。今日朝練はどうする?」
「見学にするよ。タオル乾かさないと」
「だよな」
そう言って湊士は大人しく見学していた。
昼休み。いつもの3人で昼飯を食べていると、昴にも注意された。
「まったく。さすがのポンコツっぷりね」
「まあね」
「褒めてないんですけど?」
湊士はカラカラと笑って弁当を食べていく。時折、湊士は外の雨を見てはため息をついた。
その様子を見て、凌悟が肘でつついてくる。
「そんなに見ても雨はやまないぞ」
「ん? ああ、まあ、そうだな」
「……?」
心ここにあらずという雰囲気の湊士に、昴はなにか感付いた。
「……なにかあった?」
「……え?」
聞こえていなかったのか、湊士はボーっとした表情からハッと我に返る。
明らかにおかしい様子に、昴はカマをかけてみることにした。
「傘、使ってくれるといいね」
「ああ、そうだな……」
「なるほど、そういうことか」
「……ん? え? なにが?」
女の勘とでもいうのだろうか。昴はおおよその状況を把握した。
「あんた、傘忘れてないでしょ。ってか例の彼女に貸したんでしょ」
「うえ!? スゲーな藤宮! よくわかったな!」
「まあ、なんとなく」
「あー、そういう」
凌悟も理解したようで、冷ややかな視線を送った。
「それでお前がずぶ濡れになってたんじゃ世話ないぜ。ってかその人、拒否らなかったのか?」
「えーっと、それがな――」
湊士は大まかな説明をした。すると、二人に呆れられる。
「お前さあ……。それ貸せてないかもじゃん」
「いや、そうなんだけどさ。前に藤宮が知らない男性から物渡されたらキモって思うって言ってたの思い出しちゃってさ」
「いや、せめて自分は折り畳み傘もあるって言っとけば彼女に確実に貸せたじゃん」
「そうなんだけどさあ。なんか貸しを作るのっていやじゃん? 向こうも負い目を感じるだろうし」
「うーん、難しいわね。確かに折り畳み持ってて傘も持ってるっていうのがすでに不自然なんだよねえ。だから湊士の賭けはある意味正しいのかも」
「え? マジ?」
まさかの高評価に、自分でやっておいて驚く湊士。
「これはある意味チャンスよ。もし向こうが傘を借りてたなら絶対返すはず。だって同じ電車に乗ってるんだからね。そこで当然なにかしら会話するんだからそこで接点を作るのよ」
「おお! そっか、そこで会話を広げれば一気に仲良くなったり――」
思わず身を乗り出す湊士を手で制す昴。それに怯んで湊士は大人しくなる。
「慌てなさんな。そこであんまりがっつくと逆効果よ」
「お、おう……」
逆効果、という言葉に冷静さを取り戻す湊士。
「まあ、今後電車で挨拶する程度のよっ友くらいにはなれそうね」
「マジ!? 十分だって!」
「そうね。3か月で別の学生とそこまでの仲になれれば上出来よ」
「あー! 俺の傘どうなったんだろなー!」
「ほんと、それに尽きるわね」
湊士の傘がどうなったかわからないため、とりあえずこれ以上話しても無駄という流れになったのと、チャイムが鳴ったのでこの話は流れた。
放課後、今日は体育館はバレー部が占領し、バスケ部は外錬の予定だったが、この雨のせいで部活は休みになった。
湊士は学校に予備の傘を借りて帰路についた。
その間、湊士の頭は美白のことでいっぱいだった。
「あー、ちゃんと使ってくれたかなあ……」
そんなことを呟いていると、駅の改札のところに美白がいることに気付く。
最初は申そうかと思ったが、そうではない。毎朝見惚れている女の子が駅に佇んでいた。その手には湊士の傘が握られていた。
湊士は軽くパニクってしばらく棒立ちしてしまった。
(え、なんでここに? 彼女の学校ってここじゃないよな? てか俺の傘。使ってくれたんだ。よかった――けどなんでここに?)
頭がぐるぐるする。しかし、ここにいる以上用事がある以外にない。湊士は覚悟を決めてゆっくりと彼女の方へ向かっていく。
彼女に近づくにつれて、心臓が爆発しそうになる。そして、彼女も湊士のことに気付いた。
確実に目が合った。すると彼女の方から声をかけてくれる。
「あの……」
「お、俺、ですか?」
「はい……」
透き通るような声。湊士はこの季節に似合わない晴れ渡るような声だと思った。
「あの……ごめんなさい!」
「え?」
突然美白に謝られ、困惑する湊士。
「これ、あなたのですよね?」
そいう言って渡されたのは湊士の傘だった。
「勝手に使っちゃいました! ごめんなさい!」
「あ、いや、別にいいっすよ」
「よくないですよ! 絶対雨に濡れたはずです!」
見た目に反して結構ものをはっきり言う子だなあ、などと思っていると強引に傘を返そうとしてきた。
「ちょちょちょ! ストップストップ!」
ぐいぐいくる美白を一旦落ち着かせることに。
「それ今俺に返したら家までどうするの?」
「それは……。親に迎えに来てもらう、とか?」
「なるほど。親にはもう連絡入れたんすか?」
「まだ、です……」
「一回連絡入れてみたらどうっすか? 忙しくて来れないなら結局また困るでしょ?」
「…………そうですね」
美白は携帯を取り出し、親に連絡を入れた。湊士は会話こそ聞こえなかったものの、美白の表情から迎えは難しそうだった。
美白の通話が終わり、声をかける。
「どう?」
「えっと、その……」
歯切れの悪い言葉。湊士はやはりといった感じで声をかける。
「あの、いつも同じ電車に乗ってます、よね? だから明日で大丈夫っすよ」
「……はい。……ごめんなさい」
しゅんとした彼女を見て、元気づけようと湊士はあたふたする。
「か、傘くらいで大げさっすよ? ってか、わざわざそれだけのために来てくれて嬉しいっていうか……」
「……え?」
「あ、いや、何でもないっす!」
湊士は恥ずかしさから顔を反らす。しばらく沈黙が続いたあと、美白からポツリと言葉が漏れた。
「ありがとう、ございます」
「へ? あ、いえ、どういたしまして」
湊士が返事すると、どちらともなく笑い出した。そうこうしていると、帰りの電車がやってくる。
「やべっ、早く乗りましょ」
「そうですね」
こうして湊士は初めて帰宅時に美白と一緒になった。それだけでなく、初めて会話した。
6月22日。この日は記念日になると、心の中でガッツポーズをした。
ところが恥ずかしさからか、帰りの電車での会話はなにもなく、朝と同様黙ったままだった。
(あれ? なにか言ったほうがいいのかな? でも、なんか気まずい!)
会話するための話題も特になく、二人で黙って突っ立っているだけだった。
そうして何もできないまま十数分が経ち、二人は最寄り駅で降りる。
改札を出ると、帰る方向が真逆だったため、ここでお別れとなる。
(なにか、なにか言わないと!)
湊士は内心かなり焦っていた。そして出た言葉は、
「で、では、また明日」
「あ、はい……。また明日」
そう言って美白は帰っていった。彼女の姿が見えなくなるまで立ちすくみ、一人になると盛大な溜息をついた。
「気の利いたこと、なんにも言えなかったな……」
嫌われてはいないと思う。が、好かれている様子もない。それが湊士の思いだった。
「これじゃなんも変わってねーよ……」
雨が降りしきる中、湊士も帰ることにした。
翌日、早めに駅へ向かい、美白を待つ。そして後ろから昨日きいた声がかかった。
「あの……」
「あ、どうも……」
おはようの挨拶すらできないほどギクシャクする二人。
「これ……」
そう言って渡されたのは傘だった。
「あ、はい……」
事務的に受け取る湊士。その後の会話もなし。これで何もないかと思われていたが、電車を降りる際、湊士は意を決して美白に叫ぶ。
「あの!」
「は、はい!」
美白も驚き、背筋が伸びる。
「別に貸しって思わなくていいんで! 困ったときはお互い様っていうか、とにかく!」
言葉をいったん切って、美白の目を見ながらハキハキ話す。
「また困ったことがあれば、いつでも言ってください!」
ポカンとした様子の美白。そしてクスッと笑い、答えてくれた。
「はい。頼りにさせていただきます」
湊士はお辞儀して電車を降りた。その後、友人二人に嬉しそうに報告したが、名前くらい伝えろと突っ込まれた。それでも、少しは距離が近づいたことを実感した湊士は、嬉しくて仕方がなかった。