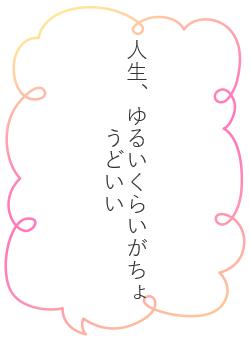5月(美白パート)
ゴールデンウィーク最中。
美白と沙耶は大型デパートにて、湊士をストーキングしていた。
「やっぱりダメだよぉ……。バレたら印象最悪だよぉ……」
「なに言ってんの! せっかく奴の素顔が拝める絶好の機会じゃない! あ、行くわよ!」
「もう、沙耶ちゃんってば……」
時は少し遡り、ゴールデンウィーク突入前の学校にて。
「ねえねえ。今度のゴールデンウィーク、買い物に付き合ってくれない?」
「お買い物? いいよ。何買うの?」
「新しい化粧水が出たんだって。女子としては試さなきゃっしょ?」
「いいよ。私も買おうかな」
「いいじゃん。オソロだ」
美白と沙耶はよくある女子トークで盛り上がっていた。高校生ともなると、お化粧のことなど、女子は大変である。
「あ、じゃあうちの近くのデパートで買わない? 確か数量限定だけど3本買えばもう1本プレゼントっていうのやってた気がする」
「お、いいねー。じゃあ合計4本でわけっこしよ?」
「うん!」
「じゃあ朝11時にそっちの駅に行くから、そのデパートでお昼してからショッピングと洒落こむ?」
「いいよー。じゃあ、また詳しいことは携帯でね」
「オッケー」
かくして二人は、ゴールデンウィークにデパートへ向かった。
二人でランチを食べ、目的の化粧水も買い、どこかで遊べないかウィンドウショッピングをしていると、彼がいた。
「あっ!」
「ん? どしたん――ってみしろん! そんな強く引っ張んないで!」
思わず美白は物影に隠れる。そしてそろりと視線を前の方へ向ける。そこには湊士が人混みにまぎれて歩いていた。普段の制服とは違い、ラフな格好だったが美白にはすぐに湊士だとわかった。
心臓がドクンドクンと脈打つ。
そんな美白を見て、沙耶が心配そうに美白の背中をさする。
「大丈夫? 気分悪くなった?」
美白は首を横に振る。そして、絞り出すようにか細い声で「いる……」とだけ呟いた。
「いる? いるってなにが?」
美白は口をパクパクさせて声にならなかった。
「もしかしてストーカー!? なら警察に電話しないと」
沙耶はスマホを取り出そうとするが、美白に腕を掴まれた。
「そうじゃなくって、彼がいたの!」
顔を真っ赤にして恥ずかしそうにしている美白を見て、沙耶はうーんと考えた後、「あっ」
っと気付いた。
「もしかして電車で一緒だっていう例のやつ?」
美白は黙ってコクっと頷く。
「どれどれ? どんなやつ?」
沙耶は物陰から、どいつが美白の心を射抜いたやつなのか探そうとした。
「……茶色のパーカーに黒いズボン」
ありふれた組み合わせだったが、今前の通路を歩いていて、かつ年齢も近い人は多くない。というか一人しかいなかった。
「あいつかー。なんかパッとしないけど、ほんとにあいつなの?」
「うん……」
入学時から、かわいいということで注目されていた美白が好きになった相手がどんなやつかと思えば、ふっつーの男子で沙耶は少々、というかだいぶ落胆していた。
「えー……。あれのどこがいいの? 見た目は……後ろからじゃよくわかんないけど、普通そう。特別オシャレってわけでもなさそうだし……。どこがいいの?」
改めて沙耶にどこがいいのか聞かれると、ちょっと子どもっぽい笑顔とか、かと思ったら憂いを帯びた大人びた表情だとか。挙げればキリがないが、一番というものはなかった。
しいて言うなら好きだから好きなのだ。理屈じゃない。
「説明できないよぉ……。会った瞬間に私の心にスッと入ってきたと言うか……」
「ほーん。まあいいわ。とりあえずつけるわよ」
「つけるって……それストーカー! 犯罪!」
沙耶は、やる気が起きない美白の肩をガシっと掴む。
「今まで電車の中であいつの何がわかったの?」
「それは……」
言い淀む美白に、沙耶はさらに畳み掛ける。
「これはチャンスよ。あいつの本性を探るのよ!」
沙耶は有無を言わせず、美白の手を引いて尾行を開始する。
「バレたらどうしよう……。嫌われるかなあ……」
「だーいじょうぶだーって。こんな人混みの中バレるはずないって」
「うぅ……。ごめんなさい……」
美白は心の中で謝りながらも、尾行を開始した。
湊士の後をつけると、彼はスポーツショップへ入っていった。
「なに? あいつってなんかスポーツやってんの?」
「そういえば通学の時、いつもスポーツバッグ持ってたよ」
「ふーん。なんの部活やってんだろ?」
「さあ……。そこまでは知らないわ」
二人は湊士の向かう場所に目をやると、そこはバスケのコーナーだった。
「どうやらバスケ部らしいわね」
「そうだね」
湊士はしきりにバッシュをあれこれ物色していた。
「もうゴールデンウィークだってのに、もう新しいのが欲しいの? 変なの」
「もしかしたら中学からやってて、サイズが合わなくなっただけかもよ?」
二人であーだこーだと言っていると、湊士は一人の少年に声をかけていた。
美白たち二人は少し離れていたため、会話の内容は聞き取れなかった。
「あれ? 知り合いかな? なに話してるんだろ?」
「弟……、だったら最初から一緒に行動してるよねえ……」
二人は頭に疑問符を付けていたが、少年がある方向を指さす。美白もその方向に目をやると、なにやらイベントを開催しているようだった。
「なんだろ? ちょっと見に行こ?」
「えー……。もういいでしょ? これ以上は悪いよ」
「なに言ってんの! まだなにも収穫ないじゃない!」
美白は「もう……」とため息をつく。先に歩き出した沙耶についていくと、イベントはバスケのフリースローを連続で決めるというものだった。
「へー、こんなイベントやってるんだ。……お、商品は1万円の商品券だって」
「あの人、これにチャレンジするのかな?」
「さあ、ちょっと離れて様子を見ましょ?」
イベント会場から少し離れて、湊士のことを遠目から観察する。思ったとおり、湊士はこのイベントに参加するようだった。
「お、やるみたいね」
「そうみたいだね」
司会者がこれでもかと会場を盛り上げる。そんな中シュートを連続で決めなければならないのは至難の業だ。なんせ気が散ってしょうがない。
「BGMまでつけて……。これじゃ集中できないよ」
「確かに……。こりゃ無理かな」
そんな二人の思惑とは裏腹に、湊士は1本、また1本とゴールを決めていく。
「すごっ……。集中力パないね」
「うん……」
美白は湊士の真剣な横顔に釘付けだった。視線はゴールに向かい、澄んだ瞳に吸い寄せられそうになる。
美白は胸の鼓動が大きくなるのを感じる。いや、実際に大きくなったのだ。
それは恋心なのか、それとも応援したいという気持ちなのか。それは本人にもわからなかった。
ただ一言。気付けば口からこぼれだしていた。
「頑張って」
もちろん美白の声が届くはずがない。しかし、その応援に応えるかのように、湊士はラスト1本を完璧に決めていた。
周りに歓声が沸く。気付けば美白も拍手していた。
「おめでとう」
そう言った美白を、沙耶も黙って見ていた。
そして、司会者によって湊士にコメントを求められる。
「えっと……平賀湊士です。クリアできてよかったです」
その時が、美白が湊士の名前を知った瞬間だった。
「湊士くん、か」
「名前だけでもわかってよかったじゃん」
「名前だけじゃないよ」
「ん?」
美白は嬉しそうに湊士を見つめる。
「きっと真面目でいい人だって、見てればわかるよ」
「どうだかなあ……。ただのバスケ好きなだけじゃない?」
沙耶が反論すると、湊士は受け取った商品券を少年に渡した。それを見た沙耶が驚きの表情を隠せない様子だった。
「なんで!? もったいな!」
「ね? 優しい人なんだよ」
美白はわかっていたかのように微笑み、嬉しそうにしていた。
「なんでそなな嬉しそうなの?」
「え? うーん……。やっぱり好きな人がいい人だと嬉しいから、かな?」
その言葉を聞き、沙耶はニヤリと口角を歪める。
「おんやぁ~? 認めましたね? 今、好きって言ったよね?」
「え? ……あっ!」
美白は自然と出た好きという言葉に、顔を真っ赤にした。
「はい確定~。やっぱ好きなんじゃん」
「えっとね、これは、その……」
ごにょごにょ言い訳する美白に、沙耶は美白にガバっと抱き着く。
「いいじゃん。好きって気持ちが悪いわけないよ。それより自分の気持ちに嘘つく方が悪いと思うけど?」
「うっ……、うん……。うん」
美白は沙耶の言葉をしっかり受け止めてしばらく心を整理する。自分にとって湊士はどういう存在なのか。改めて自分自身に問いかけると、やはり答えは1つだった。
「うん。やっぱり私、平賀湊士くんのこと、好き。うん。好きなんだ」
「そっか」
沙耶は茶化さなかった。ただそれだけ言うと、二人で湊士に目をやる。すると、ちょうど少年がバッシュを買ったらしく、湊士に見せていた。そしてそのバッシュを、湊士はいきなり踏んだ。
「はあ!? なにやってんのあいつ! やっぱクソ野郎なんじゃね?」
「い、いや、たぶんちゃんと理由があるんだよ」
「どうだかねー。あたしの中ではやつの株価は大暴落よ」
そうして少年は去っていった。ちょうど美白たちの方向に来たので、沙耶は少年に声をかける。
「ねえ君。さっき買ったばっかの靴踏まれてたけど悔しくないの?」
少年は突然知らないお姉さんに声をかけられ、ポカンとしていた。
「ごめんね。私たち、バスケットについてあんまり詳しくなくって」
少年はなるほど、といった様子で説明してくれた。
「新しいバッシュって固いから怪我しやすいんだ。だから踏んでもらって柔らかくするんだよ」
「そうなんだ」
美白が優しく聞き出してくれたおかげで謎が解け、やはり悪いことをしたわけではないと胸を撫でおろす美白。
「お姉ちゃんたち、お兄ちゃんの友達?」
「え? えーっと……」
なんと答えようか迷っていると、沙耶はしれっと答える。
「そうだよ。たまたま見かけてね」
「そうなんだ。じゃあお姉ちゃんたちもバスケ部なの?」
「そうだよ。高校から始めたんだ」
「へー! じゃあバスケ仲間だ!」
美白は内心、沙耶の嘘八百に呆れかえっていた。ただ横で乾いた笑い声を出すことしかできなかった。
「あ、そろそろ帰ってるーてぃーんの練習しないと。じゃあね、お姉ちゃん!」
少年はそう言って去っていった。
「ルーティーンってなんのことだろ?」
「多分あれかな? 特定の行動をすることで平常心を保てるっていう」
「あー、聞いたことあるわ。なるほど、ルーティーン、ね」
沙耶は何か考えている様子だった。しかし、湊士が移動し始めたので慌てて尾行を続行する。
「やばっ、行くわよ!」
「まだ続けるんだ……」
その間、沙耶はずっとなにかを考えていた様子だったが、突然、「あ」と言って美白に提案してみる。
「ねえねえ、さっきのルーティーンの話で思ったんだけど」
「なに?」
「ていうかパブロフの犬の方が近いんだけど」
「だからなに?」
美白はなにか嫌な予感を感じていた。そしてその予想は的中する。
「毎日あいつの写真かなにかを毎朝見て、慣れるっていうのはどう?」
「はぁ……」
ほらやっぱり、と言わんばかりに美白は小さくため息をつく。
「なによー。いいアイデアでしょ?」
「そもそもどうやって写真を撮るの?」
「そりゃ盗撮」
「だから犯罪だって!」
「ごめんごめん。やっぱ無理かー」
「もう!」
そもそもほぼ毎日朝に出会っているにもかかわらず、会うたびに胸がドキドキするのに、そんなことしたら身が持たないと美白は思うのだった。
そうこうしていると湊士は花屋に入っていった。
「花屋? こんな時期に?」
「なんだろうね」
二人はうーんと悩んでいると、沙耶は何かに気付いたようにハッとする。
「これは……ズバリ彼女への誕生日プレゼントなんじゃ?」
「え? そ、そうなのかな……」
「そりゃそうでしょ。男が花に興味あるってなかなか聞かないし」
「やっぱり彼女さん、いるのかなあ……」
美白は見て取れるくらい、肩を落とした。相当ショックだったようで、今にも涙が零れそうになっている。
「まあ、しょうがないよ。でも安心して。みしろんにはあたしがいるじゃん」
「沙耶ちゃん……」
花屋の花が全て百合になりそうな雰囲気だったが、その空気を美白がバッサリ切り捨てる。
「まあ冗談は置いておいて、やっぱりバラとか買うのかなあ」
「えー。冗談じゃないのにー」
「はいはい」
美白に軽く流されたことに落ち込む沙耶だったが、美白はそんなことより湊士に注目する。
どうやら湊士が買ったのは、一輪のカーネーションのようだ。
「カーネーション……。あ、もしかして」
カーネーションで思いつくのは一つ、花屋のポスターにもあるとおり、母の日だった。
「なんだ、母の日のためにお花買ったんだ」
「なーんだ。つまんないなあ。……でも、あれ? なんかピンクのバラも買ってない?」
「え?」
確かに湊士の手にはカーネーションと共に、ピンクのバラが握られていた。
「これは……やっぱり彼女が関係してるのかな?」
「そ、そんなあ……」
お会計を済ませたようで、湊士は店から出てきた。
「さて、このまま彼女のところに行くのかな?」
沙耶が尾行を続行しようとしたことろで、美白が引き留める。
「さすがにもういいよ。これ以上はほんとに悪いって」
「ふーむ……。ま、いいでしょ」
沙耶も納得したようで、これ以上つきまとうことは終わりにする。
「あななたち、うちの店に用事?」
「はい?」
見ると、花屋の店員だった。二人の様子はかなり怪しかったのか、怪訝な顔をされる。
「あ、えーっと、そうじゃなくって……」
なんと答えようと思案していると、店員から質問される。
「もしかして、さっきの彼の知り合い?」
「え? あ、はい。そうです」
またも沙耶が適当なことを言って誤魔化す。そう言うと、店員は表情を明るくした。
「そうだったのね。じゃあ声をかけてあげればよかったのに」
「いや、まあ……恥ずかしくって」
「ふーん……。なるほどねえ」
店員は二人を見比べて、一言質問される。
「で、どっちが彼の彼女さん?」
「ぶっ!」
美白は思わず吹き出し、咳込んでしまう。
「あ、あなたの方なのね。ちゃんとバラをプレゼントされたら知らないフリしなさいよ?」
「あ、はい。そうします……」
美白も否定しづらくなり、誤魔化すことに。
「彼、いい子よね。まだ高校生で母の日のプレゼント買いに来たなんて」
「そ、そうですね」
「で、あなたたちは? 今ならサービスするけど」
「えっと、じゃあせっかくなんで……」
「はい、毎度ありがとうございます」
まるで店員に乗せられたようだったが、嘘がバレるよりマシだと思い、二人ともカーネーションを買うことに。
店を出て、二人は帰ることにした。
「あーあ、痛い出費だったなあ」
「もう! だから尾行なんてやめようって言ったのに」
「でも収穫も大きかったでしょ?」
「それは……まあ」
誰にでも優しいこと。名前。家族思いなこと。湊士のいろんな面が知れた一方で、一抹の不安が残った。
それは彼女がいるかもしれないということ。あのバラは誰の手に渡るのか。美白は気になって仕方なかった。
美白は家に帰った後も、湊士のシュートを決める横顔ににへへと笑ったり、顔も知らない女性にバラを渡している様子を妄想して落ち込んだりと、一人で百面相をしていた。
夕飯の時、親から大丈夫か聞かれたが、まさか尾行してましたとは言えず、口を濁すしかなかった。
ゴールデンウィーク最中。
美白と沙耶は大型デパートにて、湊士をストーキングしていた。
「やっぱりダメだよぉ……。バレたら印象最悪だよぉ……」
「なに言ってんの! せっかく奴の素顔が拝める絶好の機会じゃない! あ、行くわよ!」
「もう、沙耶ちゃんってば……」
時は少し遡り、ゴールデンウィーク突入前の学校にて。
「ねえねえ。今度のゴールデンウィーク、買い物に付き合ってくれない?」
「お買い物? いいよ。何買うの?」
「新しい化粧水が出たんだって。女子としては試さなきゃっしょ?」
「いいよ。私も買おうかな」
「いいじゃん。オソロだ」
美白と沙耶はよくある女子トークで盛り上がっていた。高校生ともなると、お化粧のことなど、女子は大変である。
「あ、じゃあうちの近くのデパートで買わない? 確か数量限定だけど3本買えばもう1本プレゼントっていうのやってた気がする」
「お、いいねー。じゃあ合計4本でわけっこしよ?」
「うん!」
「じゃあ朝11時にそっちの駅に行くから、そのデパートでお昼してからショッピングと洒落こむ?」
「いいよー。じゃあ、また詳しいことは携帯でね」
「オッケー」
かくして二人は、ゴールデンウィークにデパートへ向かった。
二人でランチを食べ、目的の化粧水も買い、どこかで遊べないかウィンドウショッピングをしていると、彼がいた。
「あっ!」
「ん? どしたん――ってみしろん! そんな強く引っ張んないで!」
思わず美白は物影に隠れる。そしてそろりと視線を前の方へ向ける。そこには湊士が人混みにまぎれて歩いていた。普段の制服とは違い、ラフな格好だったが美白にはすぐに湊士だとわかった。
心臓がドクンドクンと脈打つ。
そんな美白を見て、沙耶が心配そうに美白の背中をさする。
「大丈夫? 気分悪くなった?」
美白は首を横に振る。そして、絞り出すようにか細い声で「いる……」とだけ呟いた。
「いる? いるってなにが?」
美白は口をパクパクさせて声にならなかった。
「もしかしてストーカー!? なら警察に電話しないと」
沙耶はスマホを取り出そうとするが、美白に腕を掴まれた。
「そうじゃなくって、彼がいたの!」
顔を真っ赤にして恥ずかしそうにしている美白を見て、沙耶はうーんと考えた後、「あっ」
っと気付いた。
「もしかして電車で一緒だっていう例のやつ?」
美白は黙ってコクっと頷く。
「どれどれ? どんなやつ?」
沙耶は物陰から、どいつが美白の心を射抜いたやつなのか探そうとした。
「……茶色のパーカーに黒いズボン」
ありふれた組み合わせだったが、今前の通路を歩いていて、かつ年齢も近い人は多くない。というか一人しかいなかった。
「あいつかー。なんかパッとしないけど、ほんとにあいつなの?」
「うん……」
入学時から、かわいいということで注目されていた美白が好きになった相手がどんなやつかと思えば、ふっつーの男子で沙耶は少々、というかだいぶ落胆していた。
「えー……。あれのどこがいいの? 見た目は……後ろからじゃよくわかんないけど、普通そう。特別オシャレってわけでもなさそうだし……。どこがいいの?」
改めて沙耶にどこがいいのか聞かれると、ちょっと子どもっぽい笑顔とか、かと思ったら憂いを帯びた大人びた表情だとか。挙げればキリがないが、一番というものはなかった。
しいて言うなら好きだから好きなのだ。理屈じゃない。
「説明できないよぉ……。会った瞬間に私の心にスッと入ってきたと言うか……」
「ほーん。まあいいわ。とりあえずつけるわよ」
「つけるって……それストーカー! 犯罪!」
沙耶は、やる気が起きない美白の肩をガシっと掴む。
「今まで電車の中であいつの何がわかったの?」
「それは……」
言い淀む美白に、沙耶はさらに畳み掛ける。
「これはチャンスよ。あいつの本性を探るのよ!」
沙耶は有無を言わせず、美白の手を引いて尾行を開始する。
「バレたらどうしよう……。嫌われるかなあ……」
「だーいじょうぶだーって。こんな人混みの中バレるはずないって」
「うぅ……。ごめんなさい……」
美白は心の中で謝りながらも、尾行を開始した。
湊士の後をつけると、彼はスポーツショップへ入っていった。
「なに? あいつってなんかスポーツやってんの?」
「そういえば通学の時、いつもスポーツバッグ持ってたよ」
「ふーん。なんの部活やってんだろ?」
「さあ……。そこまでは知らないわ」
二人は湊士の向かう場所に目をやると、そこはバスケのコーナーだった。
「どうやらバスケ部らしいわね」
「そうだね」
湊士はしきりにバッシュをあれこれ物色していた。
「もうゴールデンウィークだってのに、もう新しいのが欲しいの? 変なの」
「もしかしたら中学からやってて、サイズが合わなくなっただけかもよ?」
二人であーだこーだと言っていると、湊士は一人の少年に声をかけていた。
美白たち二人は少し離れていたため、会話の内容は聞き取れなかった。
「あれ? 知り合いかな? なに話してるんだろ?」
「弟……、だったら最初から一緒に行動してるよねえ……」
二人は頭に疑問符を付けていたが、少年がある方向を指さす。美白もその方向に目をやると、なにやらイベントを開催しているようだった。
「なんだろ? ちょっと見に行こ?」
「えー……。もういいでしょ? これ以上は悪いよ」
「なに言ってんの! まだなにも収穫ないじゃない!」
美白は「もう……」とため息をつく。先に歩き出した沙耶についていくと、イベントはバスケのフリースローを連続で決めるというものだった。
「へー、こんなイベントやってるんだ。……お、商品は1万円の商品券だって」
「あの人、これにチャレンジするのかな?」
「さあ、ちょっと離れて様子を見ましょ?」
イベント会場から少し離れて、湊士のことを遠目から観察する。思ったとおり、湊士はこのイベントに参加するようだった。
「お、やるみたいね」
「そうみたいだね」
司会者がこれでもかと会場を盛り上げる。そんな中シュートを連続で決めなければならないのは至難の業だ。なんせ気が散ってしょうがない。
「BGMまでつけて……。これじゃ集中できないよ」
「確かに……。こりゃ無理かな」
そんな二人の思惑とは裏腹に、湊士は1本、また1本とゴールを決めていく。
「すごっ……。集中力パないね」
「うん……」
美白は湊士の真剣な横顔に釘付けだった。視線はゴールに向かい、澄んだ瞳に吸い寄せられそうになる。
美白は胸の鼓動が大きくなるのを感じる。いや、実際に大きくなったのだ。
それは恋心なのか、それとも応援したいという気持ちなのか。それは本人にもわからなかった。
ただ一言。気付けば口からこぼれだしていた。
「頑張って」
もちろん美白の声が届くはずがない。しかし、その応援に応えるかのように、湊士はラスト1本を完璧に決めていた。
周りに歓声が沸く。気付けば美白も拍手していた。
「おめでとう」
そう言った美白を、沙耶も黙って見ていた。
そして、司会者によって湊士にコメントを求められる。
「えっと……平賀湊士です。クリアできてよかったです」
その時が、美白が湊士の名前を知った瞬間だった。
「湊士くん、か」
「名前だけでもわかってよかったじゃん」
「名前だけじゃないよ」
「ん?」
美白は嬉しそうに湊士を見つめる。
「きっと真面目でいい人だって、見てればわかるよ」
「どうだかなあ……。ただのバスケ好きなだけじゃない?」
沙耶が反論すると、湊士は受け取った商品券を少年に渡した。それを見た沙耶が驚きの表情を隠せない様子だった。
「なんで!? もったいな!」
「ね? 優しい人なんだよ」
美白はわかっていたかのように微笑み、嬉しそうにしていた。
「なんでそなな嬉しそうなの?」
「え? うーん……。やっぱり好きな人がいい人だと嬉しいから、かな?」
その言葉を聞き、沙耶はニヤリと口角を歪める。
「おんやぁ~? 認めましたね? 今、好きって言ったよね?」
「え? ……あっ!」
美白は自然と出た好きという言葉に、顔を真っ赤にした。
「はい確定~。やっぱ好きなんじゃん」
「えっとね、これは、その……」
ごにょごにょ言い訳する美白に、沙耶は美白にガバっと抱き着く。
「いいじゃん。好きって気持ちが悪いわけないよ。それより自分の気持ちに嘘つく方が悪いと思うけど?」
「うっ……、うん……。うん」
美白は沙耶の言葉をしっかり受け止めてしばらく心を整理する。自分にとって湊士はどういう存在なのか。改めて自分自身に問いかけると、やはり答えは1つだった。
「うん。やっぱり私、平賀湊士くんのこと、好き。うん。好きなんだ」
「そっか」
沙耶は茶化さなかった。ただそれだけ言うと、二人で湊士に目をやる。すると、ちょうど少年がバッシュを買ったらしく、湊士に見せていた。そしてそのバッシュを、湊士はいきなり踏んだ。
「はあ!? なにやってんのあいつ! やっぱクソ野郎なんじゃね?」
「い、いや、たぶんちゃんと理由があるんだよ」
「どうだかねー。あたしの中ではやつの株価は大暴落よ」
そうして少年は去っていった。ちょうど美白たちの方向に来たので、沙耶は少年に声をかける。
「ねえ君。さっき買ったばっかの靴踏まれてたけど悔しくないの?」
少年は突然知らないお姉さんに声をかけられ、ポカンとしていた。
「ごめんね。私たち、バスケットについてあんまり詳しくなくって」
少年はなるほど、といった様子で説明してくれた。
「新しいバッシュって固いから怪我しやすいんだ。だから踏んでもらって柔らかくするんだよ」
「そうなんだ」
美白が優しく聞き出してくれたおかげで謎が解け、やはり悪いことをしたわけではないと胸を撫でおろす美白。
「お姉ちゃんたち、お兄ちゃんの友達?」
「え? えーっと……」
なんと答えようか迷っていると、沙耶はしれっと答える。
「そうだよ。たまたま見かけてね」
「そうなんだ。じゃあお姉ちゃんたちもバスケ部なの?」
「そうだよ。高校から始めたんだ」
「へー! じゃあバスケ仲間だ!」
美白は内心、沙耶の嘘八百に呆れかえっていた。ただ横で乾いた笑い声を出すことしかできなかった。
「あ、そろそろ帰ってるーてぃーんの練習しないと。じゃあね、お姉ちゃん!」
少年はそう言って去っていった。
「ルーティーンってなんのことだろ?」
「多分あれかな? 特定の行動をすることで平常心を保てるっていう」
「あー、聞いたことあるわ。なるほど、ルーティーン、ね」
沙耶は何か考えている様子だった。しかし、湊士が移動し始めたので慌てて尾行を続行する。
「やばっ、行くわよ!」
「まだ続けるんだ……」
その間、沙耶はずっとなにかを考えていた様子だったが、突然、「あ」と言って美白に提案してみる。
「ねえねえ、さっきのルーティーンの話で思ったんだけど」
「なに?」
「ていうかパブロフの犬の方が近いんだけど」
「だからなに?」
美白はなにか嫌な予感を感じていた。そしてその予想は的中する。
「毎日あいつの写真かなにかを毎朝見て、慣れるっていうのはどう?」
「はぁ……」
ほらやっぱり、と言わんばかりに美白は小さくため息をつく。
「なによー。いいアイデアでしょ?」
「そもそもどうやって写真を撮るの?」
「そりゃ盗撮」
「だから犯罪だって!」
「ごめんごめん。やっぱ無理かー」
「もう!」
そもそもほぼ毎日朝に出会っているにもかかわらず、会うたびに胸がドキドキするのに、そんなことしたら身が持たないと美白は思うのだった。
そうこうしていると湊士は花屋に入っていった。
「花屋? こんな時期に?」
「なんだろうね」
二人はうーんと悩んでいると、沙耶は何かに気付いたようにハッとする。
「これは……ズバリ彼女への誕生日プレゼントなんじゃ?」
「え? そ、そうなのかな……」
「そりゃそうでしょ。男が花に興味あるってなかなか聞かないし」
「やっぱり彼女さん、いるのかなあ……」
美白は見て取れるくらい、肩を落とした。相当ショックだったようで、今にも涙が零れそうになっている。
「まあ、しょうがないよ。でも安心して。みしろんにはあたしがいるじゃん」
「沙耶ちゃん……」
花屋の花が全て百合になりそうな雰囲気だったが、その空気を美白がバッサリ切り捨てる。
「まあ冗談は置いておいて、やっぱりバラとか買うのかなあ」
「えー。冗談じゃないのにー」
「はいはい」
美白に軽く流されたことに落ち込む沙耶だったが、美白はそんなことより湊士に注目する。
どうやら湊士が買ったのは、一輪のカーネーションのようだ。
「カーネーション……。あ、もしかして」
カーネーションで思いつくのは一つ、花屋のポスターにもあるとおり、母の日だった。
「なんだ、母の日のためにお花買ったんだ」
「なーんだ。つまんないなあ。……でも、あれ? なんかピンクのバラも買ってない?」
「え?」
確かに湊士の手にはカーネーションと共に、ピンクのバラが握られていた。
「これは……やっぱり彼女が関係してるのかな?」
「そ、そんなあ……」
お会計を済ませたようで、湊士は店から出てきた。
「さて、このまま彼女のところに行くのかな?」
沙耶が尾行を続行しようとしたことろで、美白が引き留める。
「さすがにもういいよ。これ以上はほんとに悪いって」
「ふーむ……。ま、いいでしょ」
沙耶も納得したようで、これ以上つきまとうことは終わりにする。
「あななたち、うちの店に用事?」
「はい?」
見ると、花屋の店員だった。二人の様子はかなり怪しかったのか、怪訝な顔をされる。
「あ、えーっと、そうじゃなくって……」
なんと答えようと思案していると、店員から質問される。
「もしかして、さっきの彼の知り合い?」
「え? あ、はい。そうです」
またも沙耶が適当なことを言って誤魔化す。そう言うと、店員は表情を明るくした。
「そうだったのね。じゃあ声をかけてあげればよかったのに」
「いや、まあ……恥ずかしくって」
「ふーん……。なるほどねえ」
店員は二人を見比べて、一言質問される。
「で、どっちが彼の彼女さん?」
「ぶっ!」
美白は思わず吹き出し、咳込んでしまう。
「あ、あなたの方なのね。ちゃんとバラをプレゼントされたら知らないフリしなさいよ?」
「あ、はい。そうします……」
美白も否定しづらくなり、誤魔化すことに。
「彼、いい子よね。まだ高校生で母の日のプレゼント買いに来たなんて」
「そ、そうですね」
「で、あなたたちは? 今ならサービスするけど」
「えっと、じゃあせっかくなんで……」
「はい、毎度ありがとうございます」
まるで店員に乗せられたようだったが、嘘がバレるよりマシだと思い、二人ともカーネーションを買うことに。
店を出て、二人は帰ることにした。
「あーあ、痛い出費だったなあ」
「もう! だから尾行なんてやめようって言ったのに」
「でも収穫も大きかったでしょ?」
「それは……まあ」
誰にでも優しいこと。名前。家族思いなこと。湊士のいろんな面が知れた一方で、一抹の不安が残った。
それは彼女がいるかもしれないということ。あのバラは誰の手に渡るのか。美白は気になって仕方なかった。
美白は家に帰った後も、湊士のシュートを決める横顔ににへへと笑ったり、顔も知らない女性にバラを渡している様子を妄想して落ち込んだりと、一人で百面相をしていた。
夕飯の時、親から大丈夫か聞かれたが、まさか尾行してましたとは言えず、口を濁すしかなかった。