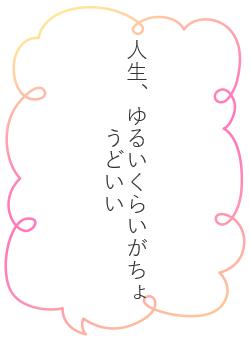4月 (美白パート)
真新しい高校生活。不安と期待が交じり合うこの時期に、白雪美白は生徒会に書記として抜擢されていた。というのも、入試でトップの成績を叩きだし、教師に推薦され押しに弱かった美白は流されるように生徒会へ入ったのだった。
「はあ……」
7時16分の1番ホーム。電車を待つ美白は思わずため息が漏れる。彩のない人生。退屈で窮屈な世界。でも自分からは変わろうとしない、そんな自分が一番嫌い。そんな負の感情が渦巻く。
電車がやってきて流されるように乗り込む。手すりを掴み、なるべく目立たないように佇む。
そこへ昨日までいなかった人物が駆け足で乗り込んできた。彼は少し息を切らせて、逆側の手すりにもたれかかる。そして、楽しそうに爽やかな笑顔をしていた彼の表情を見て、美白は胸がときめく。自信に満ちたその表情は、美白にはできないものだった。
単純に憧れた。どうすれば彼のような表情ができるんだろう?
世界に彩が塗られていく。体が軽くなったような錯覚を起こす。心臓の鼓動がうるさくて、咄嗟に目を反らす。ゆっくり深呼吸して心を落ち着けようとする。それでも緊張が解けなくて、まともに彼を見ることができない。変な子だって思われていないだろうか? またマイナスの感情が動き出す。しかし、同時に心底楽しそうにする彼の表情が忘れられなかった。ほんの少し彼の方を覗いてみる。彼は外を眺めているようだ。肩からはスポーツバッグをしょっている。恐らく運動部なのだろう。
(いいなあ。好きなことがある人って)
またため息をつきそうになって、慌てて口をふさぐ。
(ダメダメ! こんな姿、見られたくない!)
そこへOLと部下らしい男性の声が聞こえる。
「いい? 最初はミスもするだろうけど、私がフォローするからなんでも言いなさい。報連相は大事にね!」
「了解です!」
美白はいいなあ、と思わずOLの方を見る。彼女たちのように、なんでも言い合える関係になれたら――
(って、なに考えてるんだろ、私!)
顔を真っ赤にさせて、恥ずかしくて俯いてしまう。
これではまるで、恋する乙女みたいだ。
そうこうしていると彼はとある駅で降りていった。自分とは違う学校なのだから当たり前なのだが、美白は名残惜しそうにその男子を覗き込んでいた。
「明日も同じ時間の電車に乗れば会えるかな……?」
誰に言うでもない独り言を呟いて、電車は出発した。
私立宮ノ王高校。県内でも偏差値がかなり高い進学校。
白雪美白はそこでごく普通の学校生活を送っていた。少数とはいえ、仲のいい友人に囲まれ、敵らしい敵も作らない人格者。落ち着いた物腰は学校内の男子にもかなり好感度が高かった。
「え? 今なんて?」
「ちょ、そんな大きな声出さないでよ! 沙耶ちゃんだから言うんだからね?」
美白は友人の沙耶に、今朝電車で出会った男子のことを話す。
「ほえー。あの天下のみしろんが、よりにもよって学内じゃなくって他校の生徒、しかも年も名前も知らない相手に恋したと」
「ま、まだ恋と決まったわけじゃ……」
「いやいや、そんな反応しといて今更言い訳されても……」
沙耶もさすがに呆れていた。美白の奥手でにぶちんなところもかわいいと思いつつ、友人としてしっかりサポートせねばとやる気に満ちていた。
「とりあえずあたし、偵察にいこっか? ふざけたやつならぶっ飛ばしてくるけど」
「過激すぎだよ……。それに迷惑だって」
「いーや。みしろんはあたしたちが守らないと危なっかしいからね」
「そ、そんなことないもん……」
ぷくっと頬を膨らませて抗議する美白。しかし少し抜けたところがあるのは事実で、試験の日、消しゴムを忘れて慌てていたところ、沙耶が声をかけてくれて予備の消しゴムを貸してくれたのだ。それから仲良くなり、今に至る。
「ぶっちゃけ相手がいいやつなら告って全然いいと思うけどなあ。みしろんがフラれるなんて考えられないし」
「そ、そんなことないよ。私なんて別に普通だし……。それに、もし彼に彼女がいたら完全にお邪魔無視じゃん……」
「そん時は奪っちゃえば?」
「で、ででで、できないよそんなこと!」
勢いで大声を出してしまい、クラス中の視線を集めてしまう。我に返った美白はハッとして、しゅんと大人しくなる。
「と、とにかく! まだ何もしないし、する気もないよ。もうちょっとお近づきになれたら、考えるけど……」
「ほーん。で、そのお近づきっていうのはどうやって近づくの?」
「それは……」
美白は続く言葉が出てこなかった。完全にノープラン。
「はあ……。みしろん。恋は先手必勝だよ? ほっといたら向こうの学校で本当に彼女ができたりするんじゃない?」
「えぇ……。そんなこと言われても……」
美白はあたふたと困惑していた。そこには誰がどう見ても、恋する女の子の姿があった。
沙耶もそれがわかっているから応援したい、と思っている。だが、当の本人がその感情を恋と認めない限り、かえって脈無しと思われるかもしれなかった。だからまずは件の男子に告らせるより、恋してるんだという自覚を持たせようとした。
「ん、わかった。じゃあ一旦様子を見よう。みしろんにはみしろんのペースがあるんだし、急かしてごめんね」
「うん……。私こそごめんね。結局どうしたいか、自分でもわかんなくて……」
「いいって」
そう言って、沙耶は手をひらひらさせて、自分の席へ戻っていった。
美白はほっと胸を撫でおろす。彼の話をしていたからか、ずっと心臓がバクンバクン動いていた。
(胸が苦しい……。彼のことで頭がいっぱいになって他になにも考えられない。沙耶ちゃんのいうとおり、これが恋するってこと?)
こればかりは自分で気づくしかない。誰かに教えてもらえることではない。恋に落ちるとはよく言ったもので、美白は真っ暗な落とし穴に落ちて、不安だった。その穴が深ければ深いほど、地面に叩きつけられたときに大きなダメージを負うことになる。
傷つきたくなかった。痛いのは嫌だ。
ほんの少しだけ、彼に会ったことを後悔する。
会わなければ、こんな気持ちにならなかった。あの表情を見なければ、世界は灰色のままだったのに。それでも――
(やっぱり、また会いたいな)
その気持ちだけは本当だったと、自信を持って言える。
もっと一緒にいたい。できれば話したい。
どんな食べ物が好き? どういう時嬉しい? してほしいことってある? また会いたいって、あなたも思ってくれる?
一度爆発した気持ちはどんどん溢れて、妄想が止まらない。
(私、めんどくさい女なのかな……?)
口には出さない。だから、答える人もいない。
(ダメダメ! しっかりしなきゃ!)
そう言い聞かせて、自分を律する。
(とにかく! 今は何もできないんだから、真面目に授業を受けないとね!)
そしていつもの日常に戻る。
それでも、昼食はいつもより、喉を通らなかった。
その姿を見ていた沙耶も「重症だねこれは」と呆れていた。沙耶は気分転換のために、別の話題を振る。
「来週のゴールデンウィークさ。一緒にショッピングに行かない?」
「え? うん、わかった。予定空けとくね」
いつもの調子に戻った美白を見て、とりあえず安堵する沙耶。
その後、二人は雑談を始める。この時だけは美白も普段どおりに戻り、いつもの笑顔で沙耶を安心させる。
「ありがとね」
「ん? なにが?」
「いろいろだよ」
「なにそれ。まあ、嬉しいけど」
美白も内心わかっていた。自分が重すぎる気持ちに押しつぶされそうになっているのを見て、沙耶が気を使ってくれていることを。
だからお礼を言いたかった。自分はいい友人を持ったと、沙耶に感謝した。
真新しい高校生活。不安と期待が交じり合うこの時期に、白雪美白は生徒会に書記として抜擢されていた。というのも、入試でトップの成績を叩きだし、教師に推薦され押しに弱かった美白は流されるように生徒会へ入ったのだった。
「はあ……」
7時16分の1番ホーム。電車を待つ美白は思わずため息が漏れる。彩のない人生。退屈で窮屈な世界。でも自分からは変わろうとしない、そんな自分が一番嫌い。そんな負の感情が渦巻く。
電車がやってきて流されるように乗り込む。手すりを掴み、なるべく目立たないように佇む。
そこへ昨日までいなかった人物が駆け足で乗り込んできた。彼は少し息を切らせて、逆側の手すりにもたれかかる。そして、楽しそうに爽やかな笑顔をしていた彼の表情を見て、美白は胸がときめく。自信に満ちたその表情は、美白にはできないものだった。
単純に憧れた。どうすれば彼のような表情ができるんだろう?
世界に彩が塗られていく。体が軽くなったような錯覚を起こす。心臓の鼓動がうるさくて、咄嗟に目を反らす。ゆっくり深呼吸して心を落ち着けようとする。それでも緊張が解けなくて、まともに彼を見ることができない。変な子だって思われていないだろうか? またマイナスの感情が動き出す。しかし、同時に心底楽しそうにする彼の表情が忘れられなかった。ほんの少し彼の方を覗いてみる。彼は外を眺めているようだ。肩からはスポーツバッグをしょっている。恐らく運動部なのだろう。
(いいなあ。好きなことがある人って)
またため息をつきそうになって、慌てて口をふさぐ。
(ダメダメ! こんな姿、見られたくない!)
そこへOLと部下らしい男性の声が聞こえる。
「いい? 最初はミスもするだろうけど、私がフォローするからなんでも言いなさい。報連相は大事にね!」
「了解です!」
美白はいいなあ、と思わずOLの方を見る。彼女たちのように、なんでも言い合える関係になれたら――
(って、なに考えてるんだろ、私!)
顔を真っ赤にさせて、恥ずかしくて俯いてしまう。
これではまるで、恋する乙女みたいだ。
そうこうしていると彼はとある駅で降りていった。自分とは違う学校なのだから当たり前なのだが、美白は名残惜しそうにその男子を覗き込んでいた。
「明日も同じ時間の電車に乗れば会えるかな……?」
誰に言うでもない独り言を呟いて、電車は出発した。
私立宮ノ王高校。県内でも偏差値がかなり高い進学校。
白雪美白はそこでごく普通の学校生活を送っていた。少数とはいえ、仲のいい友人に囲まれ、敵らしい敵も作らない人格者。落ち着いた物腰は学校内の男子にもかなり好感度が高かった。
「え? 今なんて?」
「ちょ、そんな大きな声出さないでよ! 沙耶ちゃんだから言うんだからね?」
美白は友人の沙耶に、今朝電車で出会った男子のことを話す。
「ほえー。あの天下のみしろんが、よりにもよって学内じゃなくって他校の生徒、しかも年も名前も知らない相手に恋したと」
「ま、まだ恋と決まったわけじゃ……」
「いやいや、そんな反応しといて今更言い訳されても……」
沙耶もさすがに呆れていた。美白の奥手でにぶちんなところもかわいいと思いつつ、友人としてしっかりサポートせねばとやる気に満ちていた。
「とりあえずあたし、偵察にいこっか? ふざけたやつならぶっ飛ばしてくるけど」
「過激すぎだよ……。それに迷惑だって」
「いーや。みしろんはあたしたちが守らないと危なっかしいからね」
「そ、そんなことないもん……」
ぷくっと頬を膨らませて抗議する美白。しかし少し抜けたところがあるのは事実で、試験の日、消しゴムを忘れて慌てていたところ、沙耶が声をかけてくれて予備の消しゴムを貸してくれたのだ。それから仲良くなり、今に至る。
「ぶっちゃけ相手がいいやつなら告って全然いいと思うけどなあ。みしろんがフラれるなんて考えられないし」
「そ、そんなことないよ。私なんて別に普通だし……。それに、もし彼に彼女がいたら完全にお邪魔無視じゃん……」
「そん時は奪っちゃえば?」
「で、ででで、できないよそんなこと!」
勢いで大声を出してしまい、クラス中の視線を集めてしまう。我に返った美白はハッとして、しゅんと大人しくなる。
「と、とにかく! まだ何もしないし、する気もないよ。もうちょっとお近づきになれたら、考えるけど……」
「ほーん。で、そのお近づきっていうのはどうやって近づくの?」
「それは……」
美白は続く言葉が出てこなかった。完全にノープラン。
「はあ……。みしろん。恋は先手必勝だよ? ほっといたら向こうの学校で本当に彼女ができたりするんじゃない?」
「えぇ……。そんなこと言われても……」
美白はあたふたと困惑していた。そこには誰がどう見ても、恋する女の子の姿があった。
沙耶もそれがわかっているから応援したい、と思っている。だが、当の本人がその感情を恋と認めない限り、かえって脈無しと思われるかもしれなかった。だからまずは件の男子に告らせるより、恋してるんだという自覚を持たせようとした。
「ん、わかった。じゃあ一旦様子を見よう。みしろんにはみしろんのペースがあるんだし、急かしてごめんね」
「うん……。私こそごめんね。結局どうしたいか、自分でもわかんなくて……」
「いいって」
そう言って、沙耶は手をひらひらさせて、自分の席へ戻っていった。
美白はほっと胸を撫でおろす。彼の話をしていたからか、ずっと心臓がバクンバクン動いていた。
(胸が苦しい……。彼のことで頭がいっぱいになって他になにも考えられない。沙耶ちゃんのいうとおり、これが恋するってこと?)
こればかりは自分で気づくしかない。誰かに教えてもらえることではない。恋に落ちるとはよく言ったもので、美白は真っ暗な落とし穴に落ちて、不安だった。その穴が深ければ深いほど、地面に叩きつけられたときに大きなダメージを負うことになる。
傷つきたくなかった。痛いのは嫌だ。
ほんの少しだけ、彼に会ったことを後悔する。
会わなければ、こんな気持ちにならなかった。あの表情を見なければ、世界は灰色のままだったのに。それでも――
(やっぱり、また会いたいな)
その気持ちだけは本当だったと、自信を持って言える。
もっと一緒にいたい。できれば話したい。
どんな食べ物が好き? どういう時嬉しい? してほしいことってある? また会いたいって、あなたも思ってくれる?
一度爆発した気持ちはどんどん溢れて、妄想が止まらない。
(私、めんどくさい女なのかな……?)
口には出さない。だから、答える人もいない。
(ダメダメ! しっかりしなきゃ!)
そう言い聞かせて、自分を律する。
(とにかく! 今は何もできないんだから、真面目に授業を受けないとね!)
そしていつもの日常に戻る。
それでも、昼食はいつもより、喉を通らなかった。
その姿を見ていた沙耶も「重症だねこれは」と呆れていた。沙耶は気分転換のために、別の話題を振る。
「来週のゴールデンウィークさ。一緒にショッピングに行かない?」
「え? うん、わかった。予定空けとくね」
いつもの調子に戻った美白を見て、とりあえず安堵する沙耶。
その後、二人は雑談を始める。この時だけは美白も普段どおりに戻り、いつもの笑顔で沙耶を安心させる。
「ありがとね」
「ん? なにが?」
「いろいろだよ」
「なにそれ。まあ、嬉しいけど」
美白も内心わかっていた。自分が重すぎる気持ちに押しつぶされそうになっているのを見て、沙耶が気を使ってくれていることを。
だからお礼を言いたかった。自分はいい友人を持ったと、沙耶に感謝した。