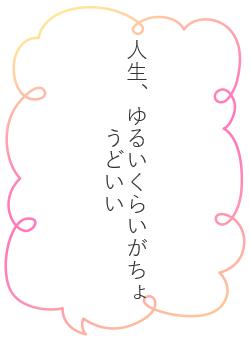3月(湊士パート)
ついにホワイトデー当日。
湊士は電車に乗り込むと、やはりというか、美白の姿はなかった。
「はいこれ、ホワイトデーのお返しです」
「お、気が利くじゃなーい。ちゃんと3倍返しなんでしょうね?」
「か、勘弁してくださいよ~」
いつものOLとその部下の会話が聞こえてくる。
そのいつもの空間に、湊士は立っている。
頭は妙に冴えている。覚悟が決まったからだろうか。
周りのどこを見てもホワイトデー一色に染まっている。湊士のポケットの中にはあるものが入っていた。それをぎゅっと握りしめる。
そして電車を降りて、学校を目指す。しかし、目指した場所は、湊士の学校ではなく、宮ノ王高校。彼女の通う高校だった。
というか、そもそも今日、電車で美白に会えないことはわかっていた。なぜなら湊士が乗った電車の時刻は7時58分だったからだ。校門までたどり着くと1限を知らせるチャイムが鳴ったところだった。
湊士はスタスタと校門から学校に入っていく。目的はもちろん、美白に会うためだが、どこの教室にいるのかわからなかった。だから、彼女の方から来てもらう事にした。
広いグラウンド。ちょうどその真ん中に仁王立ちし、大きく息を吸い込む。そして、
「白雪美白さぁぁぁぁぁぁん! 出てきてくださぁぁぁぁぁぁぁぁい!」
大声で、美白を呼びつけた。
当然ながら窓側に何事かと生徒が障子に注目する。湊士はきょろきょろと見回したが、彼女を見つけることはできなかった。
しばらくすると、教師が数名、湊士の元にやってきた。
「こらぁぁぁぁぁ! 何年何組の誰だぁぁぁぁぁ!」
「俺は昼ヶ丘高校一年、平賀湊士と言います!」
「昼ヶ丘ぁ? って他校生じゃんえか! なにやってんだこんなところで!」
「白雪美白さんに会いに来ました!」
「はあ? バカも休み休み言え! そんなこと言ってほいほい案内するわけないだろうが!」
教師は湊士を組み伏せて、職員室へ運ぼうとした。
「くそっ! 離せよ!」
「こいつ! 無駄な抵抗はよせ!」
しばらく取っ組み合いをしていると、聞き覚えのある声がした。
「まあまあ、そう邪険にしなくてもよろしいかと」
「ご、後藤くん……」
「ここはわたしの顔を立ててください。お願いします」
後藤と呼ばれた人物は、生徒会長だった。
「来なさい。生徒会室まで案内してあげよう」
「え、あ、はい……」
どうして教師がただの生徒会長の言葉に耳を傾けるのか不思議だった。その謎は、歩きながら話してくれた。
「来るならもっとスマートなやり方で来て欲しいものだね」
「す、すみません……」
「まあいい。君は理事長のお気に入りだからね」
「理事長……?」
誰のことかわからず、首をかしげる湊士。
「クフフ。見ればわかりますよ」
そう言って生徒会室の扉をノックする。
「どうぞ」
中からまたも、聞き覚えがある声がした。まさか、と湊士は思い、そのまさかだった。
「この前ぶりね。平賀湊士くん」
「え? お、お婆さん?」
そこには車椅子に乗り、かつて湊士と美白で病院まで案内し、この前電車で不安を吐露した相手だった。
「ご苦労様。お勉強、頑張ってね」
「はい、では」
そういって後藤は部屋から出て行った。
「あの、これはどういう……」
理解が追い付かな湊士に、丁寧に説明してくれた。
「まずはごめんなさいね。身分を黙ってて」
「い、いえ、それはいいんですけど」
「ほっほっほ。おかげで君という人物がわかって、あたしゃ大変満足だけどね」
そう言って笑いだすお婆さん、もとい理事長。
「さて、坊やには話さないといけないことがあるが……」
一度言葉を区切り、ドアの方を向く。
「当事者に話させるのがいいじゃろて」
「当事者……?」
「まあまあ。それまで老人の雑談に付き合っておくれ」
「は,はい」
「そうさねえ。まずは一応立場上叱っておこうかね」
「え?」
一瞬、何のことかわからない湊士。
「他校生が勝手に他の学校をうろついたり、さらには叫んだり。そういうことは、もうよしなさい」
「あっ、はい! どうも、すみませんでした!」
「ほっほっほ。まあお叱りはこの辺でいいじゃろ。坊や、いや湊士はちゃんと優しい子だって、他でもないあたしが知ってんだ。だから、必要以上に自分を責めるのも、よしなさい」
「はい……」
湊士は終始、頭が上がらなかった。
「そうそう、探していたお嬢ちゃんなんだけどね」
「白雪さんは、今ここにいるのでしょうか?」
「いるよ。もうすぐ来るじゃろ」
それを聞いてぱあっと表情が明るくなる湊士。
「じゃが約束しておくれ。あの子を決して責めないと」
「もちろんです」
即答だった。湊士は、どんな事情があろうとも、美白を責める気など毛頭なかった。
「よかった」
理事長も安心したようで、話を続ける。
「実はね、湊士の後数日後にお嬢ちゃん、美白と出くわしてねえ」
「え? そうなんですか?」
「おおよその話は聞いたし、学校にも届け出が出たから、悩みはこれかと知ったんじゃよ」
湊士は身を乗り出し、理事長に聞いてみた。
「教えてください。白雪さんに、なにがあったんですか?」
「それを当事者から説明させようと思ってねえ」
理事長がそういうと、ドアがコンコンっと控えめにノックされた。
「どうぞ」
理事長が促すと、「失礼します」という言葉と共に、美白が入ってきた。
久しぶりに会う美白に、湊士は感極まって泣き出してしまう。
「おやおや、最近の男子は泣き虫だねえ」
「あの……」
「まあ座りなさい。そして説明してあげなさい。一連の事情を」
「はい……」
そう言って美白は湊士の対面に座った。
「えっと、どこから話せばいいのか……」
美白も少し、困った様子だった。
「じゃあ、まずは俺のこと、嫌いになったのか教えてください」
「それは!」
「それは?」
それだけ言って、美白は理事長に視線を向ける。
「あたしのことは気にしなさんな」
そう言われて、美白は「はあ」と短くため息をついた。
「も、もちろん好きです。去年の4月、出合ったときから好きでした」
「お、俺と同じだ!」
嬉しそうにする湊士とは反対に、恥ずかしそうに赤面する美白。
とりあえず、そのまま湊士が質問を続けた。
「じゃあ、なんでバレンタインで告白してくれたのに会ってくれなかったの?」
決して責めるような口調ではなく、単純に真相を知りたいという願いから、自然と言葉に出ていた。
「それは……」
湊士は待つ。急かさない。焦らさない。怒鳴らない。
美白がはなしてくれるまで、じっとその場で彼女を見つめていた。
「……自分から告白しておいて、断らないといけなくなったからです」
「告白を断る?」
どういうことか、まだわからなかったので、再度美白の言葉を待つことにした。
「バレンタインの日。平賀くんにチョコを渡した日。家に帰ったら、父に言われたんです」
「……なにを?」
「……私、来月には海外にいるんです」
「……へ?」
海外という言葉に、湊士は言葉を噛み締めなかった。
「父が海外に転勤になって、母もそれについていかなくちゃいけなくて……。それで、まだ高校生の私を独り暮らしさせられないって。そう、言われて……」
美白の言葉で、湊士は全て合点がいった。
避けていたのは告白を断ると、俺が怒ると思ったから。
確かに、自分で告白して、次の日になかったことに、なんていうことになったら普通はそりゃないぜってなるだろう。
「ごめんなさい……。ずっと黙ってて……」
美白は肩を震わせ、泣き出してしまった。
そんな美白に、湊士は何も言わなかった。
「っと、いうことじゃったんじゃよ」
「ええ、把握できました。そっかあ。海外かあ……」
湊士はしばらくうーんと唸っていた。
「すみません……。勝ってばかり言って……」
「…………」
湊士は黙って何かを思案していた。
怒っているのだろうと思い、理事長が口を挟む。
「湊士。約束どおり、怒るのはなしじゃぞ?」
「え? あ、はい。そうじゃなくって……」
湊士が考えをまとめていると、美白は不思議そうに湊士を見た。
「あの? 平賀くん?」
「問題なのはさ。まだ高校生で放っておけないってことでしょ?」
「え? は、はい、そうです」
「たぶん、白雪さんのことだから、友人とかに頼って、それでも親がオッケーしなかった。違いますか?」
「いえ、そのとおりです」
「なら話は簡単だ」
「え?」
湊士は立ち上がり、バンッと机を叩く。
「大学生になったら、こっちに戻ってこれないんですか? 大学生の一人暮らしなんて、ありふれてると思いますけど」
「…………」
「あ、あれ? やっぱ無理ですか?」
はやり無理なことなのだろうかと思ったら、美白からポツリと言葉が漏れた。
「すごい……」
「え? なにが?」
どこにすごい要素があったのかわからず、ポカンとしていると、理事長が笑った。
「ほっほっほ。まさにその条件を、美白は父親に突きつけたんじゃよ」
「え? それって……」
「つまりじゃ。湊士の考えと同じく、美白も高校生だからダメということなら、大学生になったら日本に単身戻るという条件を出したのじゃ」
「それじゃあ……」
「うむ。美白の成績は事前に調べておる。この調子ならうちの大学も余裕じゃろうて」
「ってことは、宮ノ王大学に行けるかは俺の努力次第ってこと!?」
「まあ、そういうことになるな」
いつの間にか、後藤が湊士の後ろに立っていた。
「だから言っただろ。進路は大切。見学も無駄じゃなかったという訳だ」
「こりゃ勘九郎! 部屋を開けるときはノックくらいせい!」
「はいはい。お小言は家で十分だというのに……」
「家?」
やれやれと首を横に振る後藤。そんな後藤の正体を、理事長が明かした。
「勘九郎はわしの孫じゃよ」
「孫……。ってまごぉぉぉぉぉぉ!?」
「ふん。再三言ったはずだが? わたしはこの学校の利益になるならなんでも利用すると」
「それってつまり……」
「時期理事長の座を奪い、わたしは必ず上り詰めて見せる! それが野望だ」
「こりゃ! わしはまだまだ現役じゃわい!」
「そうは言いますがね。もうその足、治らないんでしょう?」
「え?」
驚きの連続だった。知り合いのほとんどが今回の件に絡んでいる。
湊士は一旦そういう面倒なことは置いておいて、理事長に大丈夫なのか尋ねる。
「治らないって、本当ですか?」
「んん……。まあ、あっとる。わしも年だからの。もう治る見込みはないそうじゃ」
「そんな……」
「そんな顔するでない」
理事長は、湊士の横まで移動する。
「おぬしは優しい子じゃ。その優しさを忘れず、若い世代でこの世を支えておくれ」
「理事長……」
「お婆さんでええよ」
そう言うと、ニッコリ笑う理事長。湊士もつられて、笑顔になる。
「つまりわたしにその座を譲っていただけると?」
「やかましいのお。少なくとも大学を卒業したら継がせてやるから、しっかり勉学に励みんしゃい!」
「まったく……。わたしより、平賀湊士くんの心配をなさっては?」
「どういうことじゃ?」
「風のうわさで聞きました。なんでもバスケの腕前は結構ですが、勉学の方は……」
後藤がわざと最後の方を濁しながら湊士を見つめる。
それを見て、やっぱりこいつとは仲良くできないなと、湊士は思った。
「ならお前が勉強を教えてららんか!」
「そうしたいのですが、学校が違うので理事長のおっしゃるとおり、他の学生は他の学校へ易々と踏み入るべきではないかと」
「ぐぬぬ……。ああ言えばこう言うな。……ん? ちょっと待て。その言葉を言ったのは湊士と二人きりの時じゃ!」
「おっと、これは失言」
「貴様! サボっておったな!」
「おお怖い。わたしはそろそろ退散するとしましょう」
「こりゃ! 帰ったら説教じゃからな!」
怒る狂う理事長と湊士たちを残して、後藤は去っていった。
「まったく……。呆れた孫じゃわい。湊士と美白の爪の垢を煎じて飲ませたいくらいじゃ」
「ははは……。でも生徒会長なんですよね? 頭いいんじゃ?」
「ふん。勉強はできても道徳を母親の腹の中に置いてきたようなやつじゃて。まったく誰に似たんじゃか……」
はあ、とため息を零す理事長。
「えっと、それでね?」
「え? ああ、ごめん!」
美白の存在をすっかり忘れていた湊士。それを見て、美白はちょっとご立腹だった。
「平賀くん? ほんとに私のこと、好き?」
「も、もちろん!」
「本当かなあ……」
湊士はまずいと思っていた。美白のためにここまで来たのに、その美白をほったらかしにしてしまった。
怒りを下げるため、湊士はあるのもを取り出す。
「これは?」
「バラの花びらで作ったアクリルキーだよ」
湊士の手には、例のピンク色のバラの花びらが押される形で作られたハンドメイドのアクリルキーが乗せられていた。
「気に入るかわからなかったけど、母さんがこういうのは彼女が出来たら渡しなさいって言って作り方教えてもらったんだ」
「わあ……」
キラキラした透明の板に、輝くピンクの花びら。美白は一瞬で心奪われてしまった。
「こういうの苦手で……。どう? 感想は?」
美白は、湊士の言葉も構わずそのアクリルキーをぎゅッと握りしめる。
「嬉しい……。大切にする」
「そうしてくれるとありがたいかな」
美白の機嫌が直って本当に良かったと思う湊士だった。
「さあ、湊士はもう自分の学校に帰りなさい」
「あ、はい。そうします」
「美白、校門まで送ってあげなさい」
「わかりました」
それから「失礼しました」と言って生徒会室を後にする。
「…………もうすぐ引っ越すの?」
「うん……19日には家を出る予定」
「そっか……」
それから沈黙してしまう。
そうしていると、校門までやってきてしまう。
(どうしよう……なにか、伝えたいことは――)
考えがぐちゃぐちゃしていると、湊士のほっぺに柔らかい感触が。
「――え?」
それが美白のキスだと理解するのに、時間がかかった。
「絶対、大学生になったら帰ってくるから」
「う、うん」
「勉強、サボっちゃダメだよ?」
「うん」
「…………ほっぺじゃないちゅーは、私が帰ってきてからね」
「え?」
それだけ言い残すと、美白は学校に戻っていった。
「絶対! 絶対俺も合格するから! 俺、頑張るから!」
聞こえたかどうかわからなかったが、きっと想いは届いているはず。そう、思った。
これで終わればどれだけよかったことか。
そんな終わりを迎えるのは小説の中だけである。
湊士は、勝手に宮ノ王に行ったことを、教師一同からこってり怒られた。
少しは向こうの理事長を見習ってくれ、と念じまくった。
教室に戻ると、まるでヒーロー扱いだった。
「恋のために他校に乗り込んだって? 勇者だな、お前!」
「かっくいー! で、彼女の写真とかないの?」
クラスメイトから質問攻めされて、グロッキーになる湊士。結局、
「うるせえぇぇぇぇぇぇぇ! 秘密だっ!」
この言葉で鎮圧できた。
「よお、ヒーロー」
「お前までからかうなって……」
「いいじゃねえか。俺らは、そういう関係だっただろ?」
「まあ、そうだけどさ……」
「で、上手くいったんだろ?」
「うーん、どうかな?」
「あれ? やけにすっきりした表情してるから、結局付き合ったのかなって思ったんだが」
「それがな?」
湊士は事の顛末を話した。
「マジか。海外ねえ。じゃあお前、勉強頑張らないとじゃねえか」
「そうなんだよ。だからさ?」
「……嫌な予感しかしねえ」
湊士は凌悟にすり寄り、甘い言葉を発した。
「勉強、教えてね。凌悟センセー?」
「はあ……。やっぱりこうなる」
「またまたー。俺とつるんで嬉しいくせにー」
「うっぜ。くたばれ」
「はいツンデレいただきましたー」
「おい! 誰がツンデレだごらぁ!」
湊士たちの人生は、青春は始まったばかり。高校生活も2年を残している。
湊士は、どんな人生が待っているか、ワクワクが止まらなかった。
ついにホワイトデー当日。
湊士は電車に乗り込むと、やはりというか、美白の姿はなかった。
「はいこれ、ホワイトデーのお返しです」
「お、気が利くじゃなーい。ちゃんと3倍返しなんでしょうね?」
「か、勘弁してくださいよ~」
いつものOLとその部下の会話が聞こえてくる。
そのいつもの空間に、湊士は立っている。
頭は妙に冴えている。覚悟が決まったからだろうか。
周りのどこを見てもホワイトデー一色に染まっている。湊士のポケットの中にはあるものが入っていた。それをぎゅっと握りしめる。
そして電車を降りて、学校を目指す。しかし、目指した場所は、湊士の学校ではなく、宮ノ王高校。彼女の通う高校だった。
というか、そもそも今日、電車で美白に会えないことはわかっていた。なぜなら湊士が乗った電車の時刻は7時58分だったからだ。校門までたどり着くと1限を知らせるチャイムが鳴ったところだった。
湊士はスタスタと校門から学校に入っていく。目的はもちろん、美白に会うためだが、どこの教室にいるのかわからなかった。だから、彼女の方から来てもらう事にした。
広いグラウンド。ちょうどその真ん中に仁王立ちし、大きく息を吸い込む。そして、
「白雪美白さぁぁぁぁぁぁん! 出てきてくださぁぁぁぁぁぁぁぁい!」
大声で、美白を呼びつけた。
当然ながら窓側に何事かと生徒が障子に注目する。湊士はきょろきょろと見回したが、彼女を見つけることはできなかった。
しばらくすると、教師が数名、湊士の元にやってきた。
「こらぁぁぁぁぁ! 何年何組の誰だぁぁぁぁぁ!」
「俺は昼ヶ丘高校一年、平賀湊士と言います!」
「昼ヶ丘ぁ? って他校生じゃんえか! なにやってんだこんなところで!」
「白雪美白さんに会いに来ました!」
「はあ? バカも休み休み言え! そんなこと言ってほいほい案内するわけないだろうが!」
教師は湊士を組み伏せて、職員室へ運ぼうとした。
「くそっ! 離せよ!」
「こいつ! 無駄な抵抗はよせ!」
しばらく取っ組み合いをしていると、聞き覚えのある声がした。
「まあまあ、そう邪険にしなくてもよろしいかと」
「ご、後藤くん……」
「ここはわたしの顔を立ててください。お願いします」
後藤と呼ばれた人物は、生徒会長だった。
「来なさい。生徒会室まで案内してあげよう」
「え、あ、はい……」
どうして教師がただの生徒会長の言葉に耳を傾けるのか不思議だった。その謎は、歩きながら話してくれた。
「来るならもっとスマートなやり方で来て欲しいものだね」
「す、すみません……」
「まあいい。君は理事長のお気に入りだからね」
「理事長……?」
誰のことかわからず、首をかしげる湊士。
「クフフ。見ればわかりますよ」
そう言って生徒会室の扉をノックする。
「どうぞ」
中からまたも、聞き覚えがある声がした。まさか、と湊士は思い、そのまさかだった。
「この前ぶりね。平賀湊士くん」
「え? お、お婆さん?」
そこには車椅子に乗り、かつて湊士と美白で病院まで案内し、この前電車で不安を吐露した相手だった。
「ご苦労様。お勉強、頑張ってね」
「はい、では」
そういって後藤は部屋から出て行った。
「あの、これはどういう……」
理解が追い付かな湊士に、丁寧に説明してくれた。
「まずはごめんなさいね。身分を黙ってて」
「い、いえ、それはいいんですけど」
「ほっほっほ。おかげで君という人物がわかって、あたしゃ大変満足だけどね」
そう言って笑いだすお婆さん、もとい理事長。
「さて、坊やには話さないといけないことがあるが……」
一度言葉を区切り、ドアの方を向く。
「当事者に話させるのがいいじゃろて」
「当事者……?」
「まあまあ。それまで老人の雑談に付き合っておくれ」
「は,はい」
「そうさねえ。まずは一応立場上叱っておこうかね」
「え?」
一瞬、何のことかわからない湊士。
「他校生が勝手に他の学校をうろついたり、さらには叫んだり。そういうことは、もうよしなさい」
「あっ、はい! どうも、すみませんでした!」
「ほっほっほ。まあお叱りはこの辺でいいじゃろ。坊や、いや湊士はちゃんと優しい子だって、他でもないあたしが知ってんだ。だから、必要以上に自分を責めるのも、よしなさい」
「はい……」
湊士は終始、頭が上がらなかった。
「そうそう、探していたお嬢ちゃんなんだけどね」
「白雪さんは、今ここにいるのでしょうか?」
「いるよ。もうすぐ来るじゃろ」
それを聞いてぱあっと表情が明るくなる湊士。
「じゃが約束しておくれ。あの子を決して責めないと」
「もちろんです」
即答だった。湊士は、どんな事情があろうとも、美白を責める気など毛頭なかった。
「よかった」
理事長も安心したようで、話を続ける。
「実はね、湊士の後数日後にお嬢ちゃん、美白と出くわしてねえ」
「え? そうなんですか?」
「おおよその話は聞いたし、学校にも届け出が出たから、悩みはこれかと知ったんじゃよ」
湊士は身を乗り出し、理事長に聞いてみた。
「教えてください。白雪さんに、なにがあったんですか?」
「それを当事者から説明させようと思ってねえ」
理事長がそういうと、ドアがコンコンっと控えめにノックされた。
「どうぞ」
理事長が促すと、「失礼します」という言葉と共に、美白が入ってきた。
久しぶりに会う美白に、湊士は感極まって泣き出してしまう。
「おやおや、最近の男子は泣き虫だねえ」
「あの……」
「まあ座りなさい。そして説明してあげなさい。一連の事情を」
「はい……」
そう言って美白は湊士の対面に座った。
「えっと、どこから話せばいいのか……」
美白も少し、困った様子だった。
「じゃあ、まずは俺のこと、嫌いになったのか教えてください」
「それは!」
「それは?」
それだけ言って、美白は理事長に視線を向ける。
「あたしのことは気にしなさんな」
そう言われて、美白は「はあ」と短くため息をついた。
「も、もちろん好きです。去年の4月、出合ったときから好きでした」
「お、俺と同じだ!」
嬉しそうにする湊士とは反対に、恥ずかしそうに赤面する美白。
とりあえず、そのまま湊士が質問を続けた。
「じゃあ、なんでバレンタインで告白してくれたのに会ってくれなかったの?」
決して責めるような口調ではなく、単純に真相を知りたいという願いから、自然と言葉に出ていた。
「それは……」
湊士は待つ。急かさない。焦らさない。怒鳴らない。
美白がはなしてくれるまで、じっとその場で彼女を見つめていた。
「……自分から告白しておいて、断らないといけなくなったからです」
「告白を断る?」
どういうことか、まだわからなかったので、再度美白の言葉を待つことにした。
「バレンタインの日。平賀くんにチョコを渡した日。家に帰ったら、父に言われたんです」
「……なにを?」
「……私、来月には海外にいるんです」
「……へ?」
海外という言葉に、湊士は言葉を噛み締めなかった。
「父が海外に転勤になって、母もそれについていかなくちゃいけなくて……。それで、まだ高校生の私を独り暮らしさせられないって。そう、言われて……」
美白の言葉で、湊士は全て合点がいった。
避けていたのは告白を断ると、俺が怒ると思ったから。
確かに、自分で告白して、次の日になかったことに、なんていうことになったら普通はそりゃないぜってなるだろう。
「ごめんなさい……。ずっと黙ってて……」
美白は肩を震わせ、泣き出してしまった。
そんな美白に、湊士は何も言わなかった。
「っと、いうことじゃったんじゃよ」
「ええ、把握できました。そっかあ。海外かあ……」
湊士はしばらくうーんと唸っていた。
「すみません……。勝ってばかり言って……」
「…………」
湊士は黙って何かを思案していた。
怒っているのだろうと思い、理事長が口を挟む。
「湊士。約束どおり、怒るのはなしじゃぞ?」
「え? あ、はい。そうじゃなくって……」
湊士が考えをまとめていると、美白は不思議そうに湊士を見た。
「あの? 平賀くん?」
「問題なのはさ。まだ高校生で放っておけないってことでしょ?」
「え? は、はい、そうです」
「たぶん、白雪さんのことだから、友人とかに頼って、それでも親がオッケーしなかった。違いますか?」
「いえ、そのとおりです」
「なら話は簡単だ」
「え?」
湊士は立ち上がり、バンッと机を叩く。
「大学生になったら、こっちに戻ってこれないんですか? 大学生の一人暮らしなんて、ありふれてると思いますけど」
「…………」
「あ、あれ? やっぱ無理ですか?」
はやり無理なことなのだろうかと思ったら、美白からポツリと言葉が漏れた。
「すごい……」
「え? なにが?」
どこにすごい要素があったのかわからず、ポカンとしていると、理事長が笑った。
「ほっほっほ。まさにその条件を、美白は父親に突きつけたんじゃよ」
「え? それって……」
「つまりじゃ。湊士の考えと同じく、美白も高校生だからダメということなら、大学生になったら日本に単身戻るという条件を出したのじゃ」
「それじゃあ……」
「うむ。美白の成績は事前に調べておる。この調子ならうちの大学も余裕じゃろうて」
「ってことは、宮ノ王大学に行けるかは俺の努力次第ってこと!?」
「まあ、そういうことになるな」
いつの間にか、後藤が湊士の後ろに立っていた。
「だから言っただろ。進路は大切。見学も無駄じゃなかったという訳だ」
「こりゃ勘九郎! 部屋を開けるときはノックくらいせい!」
「はいはい。お小言は家で十分だというのに……」
「家?」
やれやれと首を横に振る後藤。そんな後藤の正体を、理事長が明かした。
「勘九郎はわしの孫じゃよ」
「孫……。ってまごぉぉぉぉぉぉ!?」
「ふん。再三言ったはずだが? わたしはこの学校の利益になるならなんでも利用すると」
「それってつまり……」
「時期理事長の座を奪い、わたしは必ず上り詰めて見せる! それが野望だ」
「こりゃ! わしはまだまだ現役じゃわい!」
「そうは言いますがね。もうその足、治らないんでしょう?」
「え?」
驚きの連続だった。知り合いのほとんどが今回の件に絡んでいる。
湊士は一旦そういう面倒なことは置いておいて、理事長に大丈夫なのか尋ねる。
「治らないって、本当ですか?」
「んん……。まあ、あっとる。わしも年だからの。もう治る見込みはないそうじゃ」
「そんな……」
「そんな顔するでない」
理事長は、湊士の横まで移動する。
「おぬしは優しい子じゃ。その優しさを忘れず、若い世代でこの世を支えておくれ」
「理事長……」
「お婆さんでええよ」
そう言うと、ニッコリ笑う理事長。湊士もつられて、笑顔になる。
「つまりわたしにその座を譲っていただけると?」
「やかましいのお。少なくとも大学を卒業したら継がせてやるから、しっかり勉学に励みんしゃい!」
「まったく……。わたしより、平賀湊士くんの心配をなさっては?」
「どういうことじゃ?」
「風のうわさで聞きました。なんでもバスケの腕前は結構ですが、勉学の方は……」
後藤がわざと最後の方を濁しながら湊士を見つめる。
それを見て、やっぱりこいつとは仲良くできないなと、湊士は思った。
「ならお前が勉強を教えてららんか!」
「そうしたいのですが、学校が違うので理事長のおっしゃるとおり、他の学生は他の学校へ易々と踏み入るべきではないかと」
「ぐぬぬ……。ああ言えばこう言うな。……ん? ちょっと待て。その言葉を言ったのは湊士と二人きりの時じゃ!」
「おっと、これは失言」
「貴様! サボっておったな!」
「おお怖い。わたしはそろそろ退散するとしましょう」
「こりゃ! 帰ったら説教じゃからな!」
怒る狂う理事長と湊士たちを残して、後藤は去っていった。
「まったく……。呆れた孫じゃわい。湊士と美白の爪の垢を煎じて飲ませたいくらいじゃ」
「ははは……。でも生徒会長なんですよね? 頭いいんじゃ?」
「ふん。勉強はできても道徳を母親の腹の中に置いてきたようなやつじゃて。まったく誰に似たんじゃか……」
はあ、とため息を零す理事長。
「えっと、それでね?」
「え? ああ、ごめん!」
美白の存在をすっかり忘れていた湊士。それを見て、美白はちょっとご立腹だった。
「平賀くん? ほんとに私のこと、好き?」
「も、もちろん!」
「本当かなあ……」
湊士はまずいと思っていた。美白のためにここまで来たのに、その美白をほったらかしにしてしまった。
怒りを下げるため、湊士はあるのもを取り出す。
「これは?」
「バラの花びらで作ったアクリルキーだよ」
湊士の手には、例のピンク色のバラの花びらが押される形で作られたハンドメイドのアクリルキーが乗せられていた。
「気に入るかわからなかったけど、母さんがこういうのは彼女が出来たら渡しなさいって言って作り方教えてもらったんだ」
「わあ……」
キラキラした透明の板に、輝くピンクの花びら。美白は一瞬で心奪われてしまった。
「こういうの苦手で……。どう? 感想は?」
美白は、湊士の言葉も構わずそのアクリルキーをぎゅッと握りしめる。
「嬉しい……。大切にする」
「そうしてくれるとありがたいかな」
美白の機嫌が直って本当に良かったと思う湊士だった。
「さあ、湊士はもう自分の学校に帰りなさい」
「あ、はい。そうします」
「美白、校門まで送ってあげなさい」
「わかりました」
それから「失礼しました」と言って生徒会室を後にする。
「…………もうすぐ引っ越すの?」
「うん……19日には家を出る予定」
「そっか……」
それから沈黙してしまう。
そうしていると、校門までやってきてしまう。
(どうしよう……なにか、伝えたいことは――)
考えがぐちゃぐちゃしていると、湊士のほっぺに柔らかい感触が。
「――え?」
それが美白のキスだと理解するのに、時間がかかった。
「絶対、大学生になったら帰ってくるから」
「う、うん」
「勉強、サボっちゃダメだよ?」
「うん」
「…………ほっぺじゃないちゅーは、私が帰ってきてからね」
「え?」
それだけ言い残すと、美白は学校に戻っていった。
「絶対! 絶対俺も合格するから! 俺、頑張るから!」
聞こえたかどうかわからなかったが、きっと想いは届いているはず。そう、思った。
これで終わればどれだけよかったことか。
そんな終わりを迎えるのは小説の中だけである。
湊士は、勝手に宮ノ王に行ったことを、教師一同からこってり怒られた。
少しは向こうの理事長を見習ってくれ、と念じまくった。
教室に戻ると、まるでヒーロー扱いだった。
「恋のために他校に乗り込んだって? 勇者だな、お前!」
「かっくいー! で、彼女の写真とかないの?」
クラスメイトから質問攻めされて、グロッキーになる湊士。結局、
「うるせえぇぇぇぇぇぇぇ! 秘密だっ!」
この言葉で鎮圧できた。
「よお、ヒーロー」
「お前までからかうなって……」
「いいじゃねえか。俺らは、そういう関係だっただろ?」
「まあ、そうだけどさ……」
「で、上手くいったんだろ?」
「うーん、どうかな?」
「あれ? やけにすっきりした表情してるから、結局付き合ったのかなって思ったんだが」
「それがな?」
湊士は事の顛末を話した。
「マジか。海外ねえ。じゃあお前、勉強頑張らないとじゃねえか」
「そうなんだよ。だからさ?」
「……嫌な予感しかしねえ」
湊士は凌悟にすり寄り、甘い言葉を発した。
「勉強、教えてね。凌悟センセー?」
「はあ……。やっぱりこうなる」
「またまたー。俺とつるんで嬉しいくせにー」
「うっぜ。くたばれ」
「はいツンデレいただきましたー」
「おい! 誰がツンデレだごらぁ!」
湊士たちの人生は、青春は始まったばかり。高校生活も2年を残している。
湊士は、どんな人生が待っているか、ワクワクが止まらなかった。