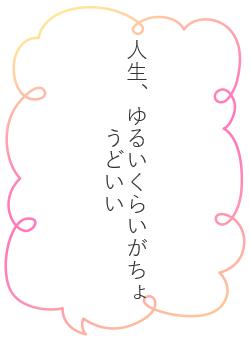4月 (湊士パート)
7時38分、草ヶ原駅の1番ホーム。
4月も終盤になり、湊士はバスケ部に所属し、初々しい高校生活をスタートさせていた。
朝練のため少しだけ早めに駅へ行くことにした。
時間ギリギリに電車に飛び込む。少し息を切らせて手すりの部分にもたれかかる。そこで彼女、白雪美白と出会った。
美白への第一印象は、とても儚い、というものだった。吹けば飛んでしまいそうな華奢な体。それでいて放っておくと消えてしまいそうな透明な瞳。そんな彼女が隣の手すりに摑まり、外を眺めていた。
一瞬だった。目を奪われるとはこのことで、理屈なんてなかった。かわいいとか、一緒にいると楽しそうとか、そういうなにかではなく、本能が湊士の心を動かしていた。整ってきた心臓が、またドクンと暴れ出す。湊士がじっと彼女を見つめていると、美白も湊士の方をチラっと見返してくる。
(やべっ!)
不審に思われたくなくて、咄嗟に視線を窓の外へ向ける。気持ち悪がられていないか不安だった。しかし、彼女の方を向くこともできず、電車から降りるまで視線を向けることができなかった。
一緒に乗っていたOLとその部下らしい男性の声が聞こえてくる。
「いい? 最初はミスもするだろうけど、私がフォローするからなんでも言いなさい。報連相は大事にね!」
「了解です!」
湊士はその様子を見て、羨ましいと思っていた。彼女ともそんなにフランクに話させる関係だったらいいのに、と。
そして湊士は電車を降りる。彼女はまだ残ったままだった。しばらく過ぎ去った電車を見つめる湊士。
「明日から、また会えるかな……」
そう呟いて、湊士は学校へ向かった。
場所は体育館。そこで湊士は朝練に励んでいる最中だった。
「なあ、聞いてくれよ! 俺、恋したかもしれねえ!」
「…………朝っぱらからなんだよ」
「おいおい凌悟さんよ。親友が恋に落ちたって言ってるんだぜ? ここは相談に乗るべきじゃあないかね?」
「うっぜ」
湊士は中学の頃からの友人である畠山凌悟に今朝のことを話した。
「てか、『かも』とか言っといて落ちてんじゃねえか。どっちなんだよ」
「そりゃもう落ちたね! 大絶賛落下中だ!」
「そうか。そりゃよかったな。つぶれてくたばれ」
「冷たいなあ。そんなだからモテないんだぞ♪」
「ぶっ殺す」
こんな会話も、お互い信頼し合ってるからこそだ。湊士にはわかっていた。なんだかんだ言いつつ、凌悟はいいやつで、相談に乗ってくれるということに。
「で、どうしたいんだよ?」
やっぱりなんだかんだ言いつつ相談に乗ってくれる親友を、湊士はふへへと笑顔を作り鍛えられた胸板にすり寄る。
「キモい。相談したかったんじゃないのか?」
「するするー! いやー、凌悟のそういうところ、マジで好きだわ」
「告白する相手、間違ってるぞ」
「当然あの子も好きだけど、凌悟のことだってずっと好きなんだぜ?」
「はいはい。あざーっす」
湊士は、にひひと笑いボールをダムッっと叩きつける。
「まあ、相談はしたいけど後でな。今は部活に集中しようぜ」
「お前から話題を振ってきたんだろうが……」
ぼやきながらも湊士と凌悟は朝練に戻った。湊士は凌悟と1体1をすることに。さっきまでの浮かれた様子はなく、その表情は真剣そのもの。そういうところが、凌悟も気に入っていた。
コートにバッシュの焼ける音がこだまする。
身長は湊士より凌悟の方が頭一つ高い。バスケは基本的に、背の高い方が有利とされている。それでも湊士は持ち前の切り返しやドリブルテクで凌悟を抜き去り、シュートを放つ。ボールはザシュっという気持ちのいい音をさせてゴールをくぐる。
「一手の差だけど、俺の勝ちだな」
「チッ!」
湊士の頭には、すでにさっきの恋うんぬんのことはきれいにすっぽ抜けていた。ただそこにいるのは純粋にバスケが好きな、ただの高校生の姿があった。
「ったく。ほんとそういうことろは尊敬するわ」
「ん? なんか言った?」
「なんも」
そうしてあっという間に朝練の時間は終わった。
それから着替えて、授業を受ける。しかし、湊士は完全に上の空で授業どころでがなかった。電車での出来事を思い出しては思い出し笑いをする。その度に、教師から注意されたが、湊士の頭は美白のことでいっぱいだった。
「ふーん。だから今日ずっとキモかったのね」
「ひどいな。藤宮にも見せてやりたいぜ。一目見て心奪われるなんて思いもしなかったからな」
「はー……。まあ、よかったわね」
昼休みの教室。湊士は高校で仲良くなった藤宮昴と親友の凌悟を交えて昼飯を食べながら相談に乗ってもらっていた。
「それで? ここの学校じゃないんでしょ? どこの学校かわかるの?」
「いや、わからん。とりあえず紺のブレザーと白いチェック柄のスカートが印象的だったな」
「ああ、なら2駅先の宮ノ王高校じゃない? あそこ、制服がかわいいから女子に人気なのよね」
「へえ、そうだったのか」
大きな情報を得て、湊士は満足げだった。
「…………わかってると思うけど、ストーカーにだけはならないでね。そんなことしたら、即絶交よ」
「わ、わかってるって……。さすがにそんなことしねーよ」
「ま、そうよね」
さすがに湊士はそんなことしないと思ってくれているらしい。昴からさらに突っ込んだ質問をされる。
「で、具体的にどうしたいの? 告白したいの?」
「いや、いきなり告白しても相手に迷惑だろ。なんかアイデアないか?」
「うーん……」
そこで二人とも頭を抱える。無理もない。なんせ学校が別なので情報が入ってこないのだ。加えて容姿や仕草、何が好きそうなどの印象も、会ったことのない二人には具体案が出てこない。
「とりあえず、様子見だな。今なにか行動しようとしても裏目る可能性の方が高いだろ」
「そうねえ……。そうかも。とりあえず今は耐えるべきね」
しょうがないとはいえ、湊士のテンションは目に見えて下がっていた。
「そんな顔すんなよ。例えば夏に弱そうならスポドリでも渡せばどうだ? そこから話題を広げるとか」
「えー。どうかしらね。見知らぬ男性からいきなり飲み物渡されたらキモって思うけど」
「え、マジか……」
「頼むぜ凌悟。お前までポンコツでどうする」
「うるせえポンコツ日本代表」
「はいはいケンカしないのポンコツども。平賀くんはとりあえず何もしない。ただ、それとなく様子を見て困っていそうな雰囲気があったらそれとなく声をかけて、助けがいりそうならお手伝いするって感じでいいんじゃない?」
「困っている時か。どういう時だろ?」
「わからん!」
「おい」
思わずツッコミを入れるが、確かにそんなことはわからない。昴の言うとおり、持久戦でいくしかないだろう。
「はあ……。前途多難だな」
「それはしょうがないんじゃない? あ、相談料は貰うからね。明日の昼食代よろ~」
「げぇ! マジかよ!?」
「当然。世の中ギブアンドテイクよ」
「あ、なら俺も」
「はぁ!? ~~あー、もう! わかったよ! いくらでも出してやらあ!」
「お、さすが。それじゃ遠慮なく」
湊士は肩を落とすが、お金で解決できるなら安いものだと割り切る。
それに正直、ありがたかった。対価を差し出すことで、一方的に相談に乗ってもらって申し訳ないという気持ちを少なくしてくれる友人の配慮があったからだ。この辺はさすが、友達付き合いの上手い昴だなと感心する。そして口には出さないが、湊士は心の中で二人に「ありがとう」と呟くのだった。
7時38分、草ヶ原駅の1番ホーム。
4月も終盤になり、湊士はバスケ部に所属し、初々しい高校生活をスタートさせていた。
朝練のため少しだけ早めに駅へ行くことにした。
時間ギリギリに電車に飛び込む。少し息を切らせて手すりの部分にもたれかかる。そこで彼女、白雪美白と出会った。
美白への第一印象は、とても儚い、というものだった。吹けば飛んでしまいそうな華奢な体。それでいて放っておくと消えてしまいそうな透明な瞳。そんな彼女が隣の手すりに摑まり、外を眺めていた。
一瞬だった。目を奪われるとはこのことで、理屈なんてなかった。かわいいとか、一緒にいると楽しそうとか、そういうなにかではなく、本能が湊士の心を動かしていた。整ってきた心臓が、またドクンと暴れ出す。湊士がじっと彼女を見つめていると、美白も湊士の方をチラっと見返してくる。
(やべっ!)
不審に思われたくなくて、咄嗟に視線を窓の外へ向ける。気持ち悪がられていないか不安だった。しかし、彼女の方を向くこともできず、電車から降りるまで視線を向けることができなかった。
一緒に乗っていたOLとその部下らしい男性の声が聞こえてくる。
「いい? 最初はミスもするだろうけど、私がフォローするからなんでも言いなさい。報連相は大事にね!」
「了解です!」
湊士はその様子を見て、羨ましいと思っていた。彼女ともそんなにフランクに話させる関係だったらいいのに、と。
そして湊士は電車を降りる。彼女はまだ残ったままだった。しばらく過ぎ去った電車を見つめる湊士。
「明日から、また会えるかな……」
そう呟いて、湊士は学校へ向かった。
場所は体育館。そこで湊士は朝練に励んでいる最中だった。
「なあ、聞いてくれよ! 俺、恋したかもしれねえ!」
「…………朝っぱらからなんだよ」
「おいおい凌悟さんよ。親友が恋に落ちたって言ってるんだぜ? ここは相談に乗るべきじゃあないかね?」
「うっぜ」
湊士は中学の頃からの友人である畠山凌悟に今朝のことを話した。
「てか、『かも』とか言っといて落ちてんじゃねえか。どっちなんだよ」
「そりゃもう落ちたね! 大絶賛落下中だ!」
「そうか。そりゃよかったな。つぶれてくたばれ」
「冷たいなあ。そんなだからモテないんだぞ♪」
「ぶっ殺す」
こんな会話も、お互い信頼し合ってるからこそだ。湊士にはわかっていた。なんだかんだ言いつつ、凌悟はいいやつで、相談に乗ってくれるということに。
「で、どうしたいんだよ?」
やっぱりなんだかんだ言いつつ相談に乗ってくれる親友を、湊士はふへへと笑顔を作り鍛えられた胸板にすり寄る。
「キモい。相談したかったんじゃないのか?」
「するするー! いやー、凌悟のそういうところ、マジで好きだわ」
「告白する相手、間違ってるぞ」
「当然あの子も好きだけど、凌悟のことだってずっと好きなんだぜ?」
「はいはい。あざーっす」
湊士は、にひひと笑いボールをダムッっと叩きつける。
「まあ、相談はしたいけど後でな。今は部活に集中しようぜ」
「お前から話題を振ってきたんだろうが……」
ぼやきながらも湊士と凌悟は朝練に戻った。湊士は凌悟と1体1をすることに。さっきまでの浮かれた様子はなく、その表情は真剣そのもの。そういうところが、凌悟も気に入っていた。
コートにバッシュの焼ける音がこだまする。
身長は湊士より凌悟の方が頭一つ高い。バスケは基本的に、背の高い方が有利とされている。それでも湊士は持ち前の切り返しやドリブルテクで凌悟を抜き去り、シュートを放つ。ボールはザシュっという気持ちのいい音をさせてゴールをくぐる。
「一手の差だけど、俺の勝ちだな」
「チッ!」
湊士の頭には、すでにさっきの恋うんぬんのことはきれいにすっぽ抜けていた。ただそこにいるのは純粋にバスケが好きな、ただの高校生の姿があった。
「ったく。ほんとそういうことろは尊敬するわ」
「ん? なんか言った?」
「なんも」
そうしてあっという間に朝練の時間は終わった。
それから着替えて、授業を受ける。しかし、湊士は完全に上の空で授業どころでがなかった。電車での出来事を思い出しては思い出し笑いをする。その度に、教師から注意されたが、湊士の頭は美白のことでいっぱいだった。
「ふーん。だから今日ずっとキモかったのね」
「ひどいな。藤宮にも見せてやりたいぜ。一目見て心奪われるなんて思いもしなかったからな」
「はー……。まあ、よかったわね」
昼休みの教室。湊士は高校で仲良くなった藤宮昴と親友の凌悟を交えて昼飯を食べながら相談に乗ってもらっていた。
「それで? ここの学校じゃないんでしょ? どこの学校かわかるの?」
「いや、わからん。とりあえず紺のブレザーと白いチェック柄のスカートが印象的だったな」
「ああ、なら2駅先の宮ノ王高校じゃない? あそこ、制服がかわいいから女子に人気なのよね」
「へえ、そうだったのか」
大きな情報を得て、湊士は満足げだった。
「…………わかってると思うけど、ストーカーにだけはならないでね。そんなことしたら、即絶交よ」
「わ、わかってるって……。さすがにそんなことしねーよ」
「ま、そうよね」
さすがに湊士はそんなことしないと思ってくれているらしい。昴からさらに突っ込んだ質問をされる。
「で、具体的にどうしたいの? 告白したいの?」
「いや、いきなり告白しても相手に迷惑だろ。なんかアイデアないか?」
「うーん……」
そこで二人とも頭を抱える。無理もない。なんせ学校が別なので情報が入ってこないのだ。加えて容姿や仕草、何が好きそうなどの印象も、会ったことのない二人には具体案が出てこない。
「とりあえず、様子見だな。今なにか行動しようとしても裏目る可能性の方が高いだろ」
「そうねえ……。そうかも。とりあえず今は耐えるべきね」
しょうがないとはいえ、湊士のテンションは目に見えて下がっていた。
「そんな顔すんなよ。例えば夏に弱そうならスポドリでも渡せばどうだ? そこから話題を広げるとか」
「えー。どうかしらね。見知らぬ男性からいきなり飲み物渡されたらキモって思うけど」
「え、マジか……」
「頼むぜ凌悟。お前までポンコツでどうする」
「うるせえポンコツ日本代表」
「はいはいケンカしないのポンコツども。平賀くんはとりあえず何もしない。ただ、それとなく様子を見て困っていそうな雰囲気があったらそれとなく声をかけて、助けがいりそうならお手伝いするって感じでいいんじゃない?」
「困っている時か。どういう時だろ?」
「わからん!」
「おい」
思わずツッコミを入れるが、確かにそんなことはわからない。昴の言うとおり、持久戦でいくしかないだろう。
「はあ……。前途多難だな」
「それはしょうがないんじゃない? あ、相談料は貰うからね。明日の昼食代よろ~」
「げぇ! マジかよ!?」
「当然。世の中ギブアンドテイクよ」
「あ、なら俺も」
「はぁ!? ~~あー、もう! わかったよ! いくらでも出してやらあ!」
「お、さすが。それじゃ遠慮なく」
湊士は肩を落とすが、お金で解決できるなら安いものだと割り切る。
それに正直、ありがたかった。対価を差し出すことで、一方的に相談に乗ってもらって申し訳ないという気持ちを少なくしてくれる友人の配慮があったからだ。この辺はさすが、友達付き合いの上手い昴だなと感心する。そして口には出さないが、湊士は心の中で二人に「ありがとう」と呟くのだった。