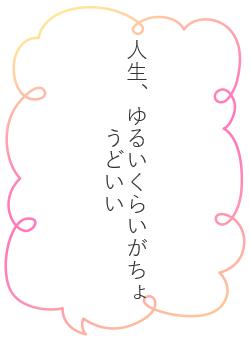12月(昴パート)
やはりおかしい。
約1か月。湊士と距離を置いたが、いつだって心の中には湊士がいた。
こんなこと初めてで混乱する昴。
「もうすぐクリスマス、か」
クリスマスと言えど、運動部は普通に部活がある。体育館に行けばそこには湊士がいるだろう。
どうしようと考えて、ベッドで横になる。
「……やっぱ改善しないな」
湊士と離れて、むしろ悪化したようにさえ思える。
「はあ……。とりあえず、相談に乗ってもらったお返しくらいはするか……」
そうと決めると、心が若干スッとした。
「クリスマスプレゼント、になるよね。湊士には好きな人がいるんだし、重くないものがいいかな」
そう言って何を渡そうか考える昴。
スマホでプレゼント候補を検索する。
「あっ、これ……」
そこには可愛らしいクッキーの画像が映っていた。
「……これくらいならいい、よね」
そして昴はクッキーを作ることにした。
昴は湊士に渡したときのことを想像する。
「これ、この前の相談料」
「お、サンキュー」
そう言って美味しそうにクッキーを食べる湊士の姿。その光景を想像すると、昴は顔を真っ赤にした。
「え!? なんで赤くなってんのあたし!?」
もう寝ようと布団にくるまる。それでも、なかなか寝付けず、結局その日は一睡もできなかった。
クリスマス当日。
昴は体育館でバスケの練習をしていた。カバンの中には手作りクッキー。男子も練習中だったので、終わったら渡そうと決めていた。
「ラスト1本!」
部長の声が体育館にこだまする。そして今日の練習は終わった。
「お疲れさまー」
各自ダウンをして更衣室へ向かう。男子はまだ続けているようで、先に着替えることにした。
着替えていても、頭がボーっとする昴。
もぞもぞと着替えていたせいで、ロッカーに押し込んでいたカバンがドサッと落ちてしまう。その拍子に可愛くラッピングされたクッキーが飛び出す。
「ん? なにこれ?」
先に拾ったのは先輩だった。
「もしかして、クリスマスプレゼント!? え、誰に渡すの?」
「え? あ、えーっと……」
湊士に、とはいえずに困り果てる昴。そうして咄嗟に出た言葉に、自分で後悔することになる。
「お、お世話になっている先輩にどうかなーって思いまして」
「え? じゃああたしたちに?」
「え、ええ」
「ホントに? 好きな人に渡すんじゃないの?」
「好きな……人?」
「違うの?」
そう言われて初めて、しっくりきた。いつも恋したと言って相談に乗っていた湊士のことを思い出す。
(ああ、そうか)
そこでようやく、湊士の気持ちがわかった。確かにこれは、言葉にできないものだ。
「ねえ、大丈夫?」
「あ、はい」
「ホントに食べていいの?」
「はい。どうぞ」
「じゃあ遠慮なく受け取っておくね」
そう言って先輩は去っていった。一人更衣室に残った昴は湊士を始めて尊敬した。
なぜ、こんな気持ちを恥ずかしげもなく話せるのか。
とてもじゃないが、自分には無理だった。昴は自分の気持ちにようやく気付いた。だが、その気持ちにふたをする。
「……ははっ。なにが相談に乗るよ」
昴の目から涙が零れる。
「あたしが寝とっちゃったら、サイテーじゃん……」
この気持ちをそうしていいかわからず、昴は一人、すすり泣いた。
やはりおかしい。
約1か月。湊士と距離を置いたが、いつだって心の中には湊士がいた。
こんなこと初めてで混乱する昴。
「もうすぐクリスマス、か」
クリスマスと言えど、運動部は普通に部活がある。体育館に行けばそこには湊士がいるだろう。
どうしようと考えて、ベッドで横になる。
「……やっぱ改善しないな」
湊士と離れて、むしろ悪化したようにさえ思える。
「はあ……。とりあえず、相談に乗ってもらったお返しくらいはするか……」
そうと決めると、心が若干スッとした。
「クリスマスプレゼント、になるよね。湊士には好きな人がいるんだし、重くないものがいいかな」
そう言って何を渡そうか考える昴。
スマホでプレゼント候補を検索する。
「あっ、これ……」
そこには可愛らしいクッキーの画像が映っていた。
「……これくらいならいい、よね」
そして昴はクッキーを作ることにした。
昴は湊士に渡したときのことを想像する。
「これ、この前の相談料」
「お、サンキュー」
そう言って美味しそうにクッキーを食べる湊士の姿。その光景を想像すると、昴は顔を真っ赤にした。
「え!? なんで赤くなってんのあたし!?」
もう寝ようと布団にくるまる。それでも、なかなか寝付けず、結局その日は一睡もできなかった。
クリスマス当日。
昴は体育館でバスケの練習をしていた。カバンの中には手作りクッキー。男子も練習中だったので、終わったら渡そうと決めていた。
「ラスト1本!」
部長の声が体育館にこだまする。そして今日の練習は終わった。
「お疲れさまー」
各自ダウンをして更衣室へ向かう。男子はまだ続けているようで、先に着替えることにした。
着替えていても、頭がボーっとする昴。
もぞもぞと着替えていたせいで、ロッカーに押し込んでいたカバンがドサッと落ちてしまう。その拍子に可愛くラッピングされたクッキーが飛び出す。
「ん? なにこれ?」
先に拾ったのは先輩だった。
「もしかして、クリスマスプレゼント!? え、誰に渡すの?」
「え? あ、えーっと……」
湊士に、とはいえずに困り果てる昴。そうして咄嗟に出た言葉に、自分で後悔することになる。
「お、お世話になっている先輩にどうかなーって思いまして」
「え? じゃああたしたちに?」
「え、ええ」
「ホントに? 好きな人に渡すんじゃないの?」
「好きな……人?」
「違うの?」
そう言われて初めて、しっくりきた。いつも恋したと言って相談に乗っていた湊士のことを思い出す。
(ああ、そうか)
そこでようやく、湊士の気持ちがわかった。確かにこれは、言葉にできないものだ。
「ねえ、大丈夫?」
「あ、はい」
「ホントに食べていいの?」
「はい。どうぞ」
「じゃあ遠慮なく受け取っておくね」
そう言って先輩は去っていった。一人更衣室に残った昴は湊士を始めて尊敬した。
なぜ、こんな気持ちを恥ずかしげもなく話せるのか。
とてもじゃないが、自分には無理だった。昴は自分の気持ちにようやく気付いた。だが、その気持ちにふたをする。
「……ははっ。なにが相談に乗るよ」
昴の目から涙が零れる。
「あたしが寝とっちゃったら、サイテーじゃん……」
この気持ちをそうしていいかわからず、昴は一人、すすり泣いた。