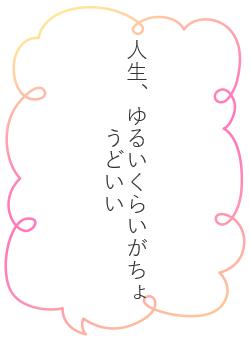11月(美白パート)
文化祭前日。
美白は例の花を受け取りに花屋に来ていた。
「いらっしゃいませー」
「こんにちは」
「はいこんにちは。花よね? 用意できてるわよ」
そう言って渡されたのは、彩とりどりの花束。しかもその中に見覚えのあるピンクのバラがあった。
「これ……」
「懐かしいでしょ? 彼に渡してあげたら?」
「む、無理ですよ。それにあの人とは学校が違うので文化祭には来ませんよ」
「そうなの? 残念」
世間話もそこそこに、美白は支払いを済ませ、店を出た。
帰りの電車で、ピンクのバラを眺めていたが、顔をブンブン振って文化祭に集中することにした。
戻った美白を、生徒会の先輩が労ってくれた。
「お使い、ありがとな。おお、いい花じゃないか!」
「ですよね。花瓶に水入れてきます」
そう言って花瓶を持って水道までやってくる。そこへ会長が現れた。
「白雪君。ご苦労様」
「あ、会長。お疲れ様です」
「明日の文化祭なのだが、君はそうするのかね?」
「もちろんお手伝いしますよ」
「……ふむ」
「……? どうしました?」
美白は首をかしげて、会長の顔を覗き込む。
「白雪君は自分のクラスの出し物に精を出しなさい」
「え? でも……」
「君は十分貢献してくれた。後は我々に任せたまえ」
そう言われて「わかりました」という性格を、美白はしていない。
「大丈夫です。頑張りますよ。私」
「その気持ちは嬉しいが、ここは先輩を立ててくれないか?」
「どういうことです?」
美白が尋ねると、会長はスラスラとすでに考えてあったかのように言葉が溢れてくる。
「いやなに。生徒会メンバーで何かするというのは今回が初めてだろう? 君たちは来年もあるが、我々は今年が最初で最後なのだよ。だから何かしたという爪痕を残したくてね」
そう言われて、美白は納得した。会長の言うとおり、生徒会で文化祭の一役を買うのは今年が初めてだ。ならばここは自分が身を引くべきだと考えた。
「わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます」
「うむ」
「それでは、失礼します」
そう言って美白は生徒会室へ戻っていった。
「……悪いね白雪君。これも君のためだ」
会長はクフフと笑い、その場を去った。
「お待たせしましたー」
「おー、おかえりー」
美白が生徒会室へ戻り、早速花を活けていく。その中でやはり気になるのはピンクのバラだった。
「お、きれいだねえ」
「そ、そうですよね」
先輩が花束を覗き込んでくる。
「これ、一輪しかないの? だったら一番前にしておこう」
「あ、はい。そうしましょう」
言われるがままに、美白はピンクのバラを手前にセットする。
「うん。見栄えいいね」
「そうですね」
こうして準備は完了した。そして各々の思惑が交差する文化祭が始まる。
美白のクラスはメイド喫茶をすることになっていた。注目はもちろん、美白のメイド姿だった。
「は、恥ずかしい……」
「いやー、みしろんが生徒会に取られなくってよかったよ。これで売り上げは2倍、いや3倍だね!」
「もう、沙耶ちゃんってば……」
よくある白と黒のメイド姿。だというのにいつの世の男性も、この姿に悶えるのだった。
「だーいじょうぶ。変なのいたら、またあたしがぶっ飛ばすから」
「ほどほどにね」
その日は大盛況だった。長蛇の列ができ、待ち時間はなんと1時間となっていた。
ようやく落ち着きを見せたのは、ジュースの在庫がなくなった夕方だった。
「め、目が回る~」
「お疲れ様。はいこれ」
沙耶に渡されたのは冷たいスポドリだった。
「水分補給はしっかりね」
「うん。ありがと」
よほど喉が渇いていたのか、美白は一気に飲み干してしまう。
「ほへー」
「明日は自由行動にしてもらったら? さすがにきついでしょ?」
しかし美白は首を横に振った。
「ううん。みんな頑張ってるし、私もできること、やりたいなって」
「みしろん……」
沙耶は美白を抱きしめる。
「無理、してないよね?」
「うん。大丈夫だよ」
「そう」
その言葉に嘘はなく、普段の状態にまで落ち着いていた。沙耶の頭をそっと撫でて、よしよしする。
「あーん。もうみしろんはあたし専属のメイドさんなのだー」
「はいはい。今だけはいいよ」
沙耶はこれでもかと美白に甘える。こういう風に沙耶と接するのも久しぶりだなと美白は思った。
そして考えるのはやはり湊士のことだった。
(来年こそは誘おう。今はまだ勇気が持てないけど、次こそは――)
実は昼時に、湊士は生徒会室で会長と会っていたなどとは毛ほども考えていない美白であった。
今のことろ、全ては会長の手のひらの上で事が運んでいた。当事者で美白だけが唯一蚊帳の外で、一人心穏やかに過ごしていた。
文化祭前日。
美白は例の花を受け取りに花屋に来ていた。
「いらっしゃいませー」
「こんにちは」
「はいこんにちは。花よね? 用意できてるわよ」
そう言って渡されたのは、彩とりどりの花束。しかもその中に見覚えのあるピンクのバラがあった。
「これ……」
「懐かしいでしょ? 彼に渡してあげたら?」
「む、無理ですよ。それにあの人とは学校が違うので文化祭には来ませんよ」
「そうなの? 残念」
世間話もそこそこに、美白は支払いを済ませ、店を出た。
帰りの電車で、ピンクのバラを眺めていたが、顔をブンブン振って文化祭に集中することにした。
戻った美白を、生徒会の先輩が労ってくれた。
「お使い、ありがとな。おお、いい花じゃないか!」
「ですよね。花瓶に水入れてきます」
そう言って花瓶を持って水道までやってくる。そこへ会長が現れた。
「白雪君。ご苦労様」
「あ、会長。お疲れ様です」
「明日の文化祭なのだが、君はそうするのかね?」
「もちろんお手伝いしますよ」
「……ふむ」
「……? どうしました?」
美白は首をかしげて、会長の顔を覗き込む。
「白雪君は自分のクラスの出し物に精を出しなさい」
「え? でも……」
「君は十分貢献してくれた。後は我々に任せたまえ」
そう言われて「わかりました」という性格を、美白はしていない。
「大丈夫です。頑張りますよ。私」
「その気持ちは嬉しいが、ここは先輩を立ててくれないか?」
「どういうことです?」
美白が尋ねると、会長はスラスラとすでに考えてあったかのように言葉が溢れてくる。
「いやなに。生徒会メンバーで何かするというのは今回が初めてだろう? 君たちは来年もあるが、我々は今年が最初で最後なのだよ。だから何かしたという爪痕を残したくてね」
そう言われて、美白は納得した。会長の言うとおり、生徒会で文化祭の一役を買うのは今年が初めてだ。ならばここは自分が身を引くべきだと考えた。
「わかりました。ではお言葉に甘えさせていただきます」
「うむ」
「それでは、失礼します」
そう言って美白は生徒会室へ戻っていった。
「……悪いね白雪君。これも君のためだ」
会長はクフフと笑い、その場を去った。
「お待たせしましたー」
「おー、おかえりー」
美白が生徒会室へ戻り、早速花を活けていく。その中でやはり気になるのはピンクのバラだった。
「お、きれいだねえ」
「そ、そうですよね」
先輩が花束を覗き込んでくる。
「これ、一輪しかないの? だったら一番前にしておこう」
「あ、はい。そうしましょう」
言われるがままに、美白はピンクのバラを手前にセットする。
「うん。見栄えいいね」
「そうですね」
こうして準備は完了した。そして各々の思惑が交差する文化祭が始まる。
美白のクラスはメイド喫茶をすることになっていた。注目はもちろん、美白のメイド姿だった。
「は、恥ずかしい……」
「いやー、みしろんが生徒会に取られなくってよかったよ。これで売り上げは2倍、いや3倍だね!」
「もう、沙耶ちゃんってば……」
よくある白と黒のメイド姿。だというのにいつの世の男性も、この姿に悶えるのだった。
「だーいじょうぶ。変なのいたら、またあたしがぶっ飛ばすから」
「ほどほどにね」
その日は大盛況だった。長蛇の列ができ、待ち時間はなんと1時間となっていた。
ようやく落ち着きを見せたのは、ジュースの在庫がなくなった夕方だった。
「め、目が回る~」
「お疲れ様。はいこれ」
沙耶に渡されたのは冷たいスポドリだった。
「水分補給はしっかりね」
「うん。ありがと」
よほど喉が渇いていたのか、美白は一気に飲み干してしまう。
「ほへー」
「明日は自由行動にしてもらったら? さすがにきついでしょ?」
しかし美白は首を横に振った。
「ううん。みんな頑張ってるし、私もできること、やりたいなって」
「みしろん……」
沙耶は美白を抱きしめる。
「無理、してないよね?」
「うん。大丈夫だよ」
「そう」
その言葉に嘘はなく、普段の状態にまで落ち着いていた。沙耶の頭をそっと撫でて、よしよしする。
「あーん。もうみしろんはあたし専属のメイドさんなのだー」
「はいはい。今だけはいいよ」
沙耶はこれでもかと美白に甘える。こういう風に沙耶と接するのも久しぶりだなと美白は思った。
そして考えるのはやはり湊士のことだった。
(来年こそは誘おう。今はまだ勇気が持てないけど、次こそは――)
実は昼時に、湊士は生徒会室で会長と会っていたなどとは毛ほども考えていない美白であった。
今のことろ、全ては会長の手のひらの上で事が運んでいた。当事者で美白だけが唯一蚊帳の外で、一人心穏やかに過ごしていた。