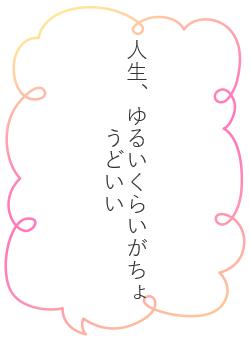11月(湊士パート)
文化祭当日。
湊士の喫茶店は、大繁盛とまでは言わないまでもそれなりに客がきてくれた。
湊士の担当は、指定のジュースを紙コップに入れる係だった。
それなりに忙しかったが、昼時を過ぎると客足も少なくなっていた。
「平賀くん、ご苦労様。あとはあたしたちでやっておくわ」
「お、やったぜ」
クラスメートの好意に甘え、湊士は文化祭を堪能することに。そしてぶらつこうとすると、昴から声をかけられた。
「ね、ねえ。一緒に回らない?」
「あー、うん。いいよ」
本当は凌悟に譲ってあげたかった。しかし、凌悟は午後から、湊士は午前からの担当でちょうど入れ替わりだった。そして昴も午後から休憩である。
ここで「1人がいい」と言っても不自然なのでここは了承しておく。
「どっか行きたいとこ、ある?」
「えっと、じゃあ体育館のライブ見に行きたいな」
「オッケー。じゃあ行こうか」
湊士が歩き出すと、昴が横を歩いたり、かと思えば後ろに下がったりしていた。
(あー、完全に意識してるよなー。凌悟の言ったとおりか)
湊士はいつもの調子で声をかける。
「なにやってんの? 新しい遊びか?」
「あ、いや、そういうわけじゃ……」
もじもじしている昴を見て、確かに恋してる女の子の姿がそこにはあった。
しかし、湊士からは決して手を出さない。手をつなぐことも、歩調を合わせることも、しない。
あくまで今までどおりの友人の距離を保つ。
そうして体育館にやって来た。
ちょうどライブが始まるようで、タイミングがよかった。
「よかったな。間に合って」
「あ、うん。そう、だね」
ライブが始まり、会場は湧きたつ。湊士も、場の空気にあてられ、少しテンションが上がる。
しかし、ライブに行きたいといった昴は、全然楽しんではいなかった。
ライブも終わり、どこかで休憩しようという流れになり、座れる場所を探す。そして、自販機で買ったジュースに口を付ける。
「ふぅ。楽しかったな」
「う、うん」
はやり湊士を意識してるのか、歯切れが悪い。
「ね、ねえ……」
「うん?」
「ちょっと聞きたいんだけど……」
「なに?」
何を聞かれるのかと思っていると、昴から予想の斜め上の質問が飛び出した。
「なんかさ。前から湊士のこと考えると頭がボーっとするんだけど、風邪でも引いたのかな?」
「は?」
いやいや、恋って言葉知らんのかと湊士は思ったが、たぶん本当に知らないのだろうと考えた。だとしたら初恋。どう答えたもんかと思い、うーんと唸る。
「だったら少し距離置いてみるか? そしたら治るかも」
「そう、なのかな」
「いや、知らんけど。やってみてダメならまた考えればいいんじゃね?」
「そう、だね。うん、そうする」
そう言うと昴は立ち上がった。
「あたし、喫茶店に戻るわ。なにか手伝えるかも」
「おう」
そう言って昴は去っていった。
「……なんか騙してるみたいで嫌だなあ」
はあっ……、とため息を零し、残ったジュースを一気飲みしてゴミ箱に投げ捨てた。
特に行くあてもなく、しばらくフラフラしていると見知った顔と出くわした。
「ちょっといいかね?」
「え? あ、はい……あっ」
そこにいたのは、美白の学校の生徒会長だった。
「君に少し、話があってね」
「俺に、ですか?」
「ここではなんだ。どこか腰を下ろせる場所はないかね?」
そう言われて、湊士はさっきまで座っていた場所へ案内する。
「ほう、いい場所だ。ここはちょうど出店の死角になっているのだな」
「それで? 俺に何の用件です?」
湊士には心当たりがなかった。急かす湊士に、会長は手で湊士を制する。
「まあ落ち着きたまえ。実は来週の土日に我が校でも文化祭があってな」
「はあ……」
「その文化祭に来て欲しいのだよ」
「はあ……。はあ?」
湊士は思わず、素っ頓狂な声をあげる。
「な、なんで俺なんですか? 初対面ですよね?」
「いや? 先月顔を合わせたはずだが?」
「え? それだけ? ってかあれだけで顔合わせ?」
湊士は驚いていた。確かに見た顔だが、話したのは今が初めてだ。
「なに、他校の生徒にも我が校の良さを知ってもらい、大学に進学してもらえると教師からも印象がよくてね」
「えぇ……」
「それとも、君は進学しないのかな?」
「いや、そりゃたぶん進学はしますけど……」
「なにか問題が?」
「そちらの大学、結構難関だって聞いてますけど」
「そうだな。自分で言うのもなんだが、かなり名門と言える」
「いやー、俺じゃちょっときついっていうか……」
「ふむ。君は彼女と一緒の大学生活を送りたいとは思わないのかね?」
湊士はどきんとする。
「……彼女って誰のことです?」
「個人情報ゆえ、名前は伏せさせてもらうが、君にはわかるのではないかな?」
わかっている。会長が言いたいのは十中八九、美白のことだろう。
「そりゃ、行けたらいいなーとは思ってますけど、でも……」
湊士が表情を暗くしていると、会長は湊士の肩に手を置く。
「まあ、高校と大学では全然違うが、それでも視察ということで一度我が校を覗きに来るのは悪いことではないと思いうが?」
「それは……まあ」
「それに、さっきも言ったが別の学生を引っ張ってくるとわたしのためでもあるのだよ。どうかな? 私を助けるためだと思って、ここはひとつ」
湊士はしばし考えた。将来のことなんて全く考えたことはなかった。
今は確かに通学路がたまたま同じということで美白と会える。しかし、大学が違えば?
もう二度と会うことはないかもしれない。
それは嫌だ。そう強く思う。
もし、同じ大学に行けたなら、またあの電車で一緒に通学できるのだろうか。そう思うと、湊士の中で答えは決まった。
「……わかりました。お邪魔させていただきます」
「クフフ。いい返事だ。では、また来週」
そう言って会長は去っていった。この時湊士は、将来のことについて、少し考えるようになった。
「今のままじゃ、ダメってことか……」
一方、会長は不敵に笑いながら、独り言を呟く。
「まったく。後輩のためとはいえ、このわたしが慈善活動など……。らしくないな。最近の白雪君にあてられたかな?」
会長は面白そうに笑いながら学校を後にした。
そして1週間が経った。
湊士は会長との約束を果たすため、美白の通う学校に来ていた。
「ここか……。つーか広っ!」
広大な敷地に湊士の学校の倍はあろうかという模擬店の数。正直、規模が違いすぎて驚きでいっぱいだった。
「うーわ。これどこ行きゃいいんだよ……」
げんなりしていると、正門の脇から一人の生徒が駆け寄ってくる。
「お困りですか?」
「え? あ、えーっと、そうです。どこ回ろうかなって思って」
「じゃあこちらをどうぞ。パンフレットになります」
「あ、ありがとうございます」
「あと、生徒会室では模擬店の詳細が確認できますので、良かったら見に来てください」
「あ、はい。どうも」
よく見ると、その生徒の腕には『生徒会』の腕章があった。
その後、その生徒は他の客のところで同じように声をかけていた。
「生徒会って大変なんだなあ」
そう呟きながら、貰ったパンフレットで生徒会室を探す。
「まあ、挨拶くらいしとかないとな……」
そして場所を確信し、生徒会室へ向かうことにした。
「失礼します」
そう言って訪れた生徒会室には会長がいた。
「よく来てくれた」
「まあ、約束したんで」
「ふむ、律儀に約束を守ろとは、君はいい人だな」
自分で読んでおいてこの言い方である。帰ろうかと思ったが、会長はいきなり核心をついてくる。
「うちの後輩がね。君を気に入っているようなのだ」
「え?」
あまりに突然の言葉に、湊士は言葉を失う。会長はかまわず言葉を続ける。
「いやね。わたしはこれでも君たちを応援しているのだよ。もちろん、わたし自身のために」
「……どういうことです?」
「なに、簡単な話だ。君と彼女がくっついてくれれば彼女はより精を出して生徒会をよりよくするだろう。むしろ、傷心して生徒会を抜けられるとわたしとしても困るのだよ」
「……俺たちの事情に勝手に割り込まないでください」
会長は「クフフ」と笑うと、湊士に近寄ってくる。
「そのとおりだ。正論だしごもっともだ。だからわたしは嫌なやつなのだろうね」
自分で嫌なやつという人を始めて見た湊士。この人とはあまり仲良くなれない気がした。
「だから利用させてもらうのさ。わたしは情報を提供する。しかし、行動するかは君次第だ。どうかね?」
湊士は考える。ここは名門校。その大学に進学するというなら早めに準備したほうがいいに決まっている。だから湊士の存在を知ってすぐに行動したのだろう。実力的に本当に進学できなくなる前に。
(そこまで考えてるのかな。この人は)
たぶんそうなのだろう。そうでなければ、進学がどうのとほのめかしたりはしない。
まったく、自分で言うだけあって本当に嫌な人だ。選択肢があるように見えて、実質一択だった。しかし、
「お断りします」
湊士は申し出を断った。会長は表情を変えずに湊士に質問する。
「なぜかね?」
「俺の事情のために、彼女のことを知るのはフェアじゃないので」
その言葉に、またも会長は笑った。
「なるほどなるほど。そういえば君はスポーツマンだったね。フェアな条件がお望みか」
「もうフェアじゃないですけどね」
「ふむ? というと?」
「だってあの子は、俺に好意を持ってくれてるって、知っちゃいましたから」
「ふふっ、それは悪いことをしたね」
「いいですよ。もう済んだことですし」
会長は湊士の肩をポンっと叩く。
「ますます気に入った。我が校の生徒ならぜひ生徒会に入ってほしいものだな」
湊士は黙って生徒会室を出ようとする。
「行くのかね?」
「ええ」
「それで、どうするつもりなのかね?」
「貰った情報は活かさないともったいないんで。使わせてもらいますよ」
「ほう、なら――」
「勘違いしないでください」
湊士は振り返り、会長の目を見る。
「俺から告白するのは大学に受かったらです。それまでは今までどおりを貫きます」
会長は拍手しながら湊士を賛辞する。
「結構。同じ目標に向かうのならいい刺激になるだろう」
「……お邪魔しました」
そう言って湊士は帰宅することにした。
ハッキリとわかった両想い。しかし、湊士は心にもやがかかった用に悶々とするのだった。
文化祭当日。
湊士の喫茶店は、大繁盛とまでは言わないまでもそれなりに客がきてくれた。
湊士の担当は、指定のジュースを紙コップに入れる係だった。
それなりに忙しかったが、昼時を過ぎると客足も少なくなっていた。
「平賀くん、ご苦労様。あとはあたしたちでやっておくわ」
「お、やったぜ」
クラスメートの好意に甘え、湊士は文化祭を堪能することに。そしてぶらつこうとすると、昴から声をかけられた。
「ね、ねえ。一緒に回らない?」
「あー、うん。いいよ」
本当は凌悟に譲ってあげたかった。しかし、凌悟は午後から、湊士は午前からの担当でちょうど入れ替わりだった。そして昴も午後から休憩である。
ここで「1人がいい」と言っても不自然なのでここは了承しておく。
「どっか行きたいとこ、ある?」
「えっと、じゃあ体育館のライブ見に行きたいな」
「オッケー。じゃあ行こうか」
湊士が歩き出すと、昴が横を歩いたり、かと思えば後ろに下がったりしていた。
(あー、完全に意識してるよなー。凌悟の言ったとおりか)
湊士はいつもの調子で声をかける。
「なにやってんの? 新しい遊びか?」
「あ、いや、そういうわけじゃ……」
もじもじしている昴を見て、確かに恋してる女の子の姿がそこにはあった。
しかし、湊士からは決して手を出さない。手をつなぐことも、歩調を合わせることも、しない。
あくまで今までどおりの友人の距離を保つ。
そうして体育館にやって来た。
ちょうどライブが始まるようで、タイミングがよかった。
「よかったな。間に合って」
「あ、うん。そう、だね」
ライブが始まり、会場は湧きたつ。湊士も、場の空気にあてられ、少しテンションが上がる。
しかし、ライブに行きたいといった昴は、全然楽しんではいなかった。
ライブも終わり、どこかで休憩しようという流れになり、座れる場所を探す。そして、自販機で買ったジュースに口を付ける。
「ふぅ。楽しかったな」
「う、うん」
はやり湊士を意識してるのか、歯切れが悪い。
「ね、ねえ……」
「うん?」
「ちょっと聞きたいんだけど……」
「なに?」
何を聞かれるのかと思っていると、昴から予想の斜め上の質問が飛び出した。
「なんかさ。前から湊士のこと考えると頭がボーっとするんだけど、風邪でも引いたのかな?」
「は?」
いやいや、恋って言葉知らんのかと湊士は思ったが、たぶん本当に知らないのだろうと考えた。だとしたら初恋。どう答えたもんかと思い、うーんと唸る。
「だったら少し距離置いてみるか? そしたら治るかも」
「そう、なのかな」
「いや、知らんけど。やってみてダメならまた考えればいいんじゃね?」
「そう、だね。うん、そうする」
そう言うと昴は立ち上がった。
「あたし、喫茶店に戻るわ。なにか手伝えるかも」
「おう」
そう言って昴は去っていった。
「……なんか騙してるみたいで嫌だなあ」
はあっ……、とため息を零し、残ったジュースを一気飲みしてゴミ箱に投げ捨てた。
特に行くあてもなく、しばらくフラフラしていると見知った顔と出くわした。
「ちょっといいかね?」
「え? あ、はい……あっ」
そこにいたのは、美白の学校の生徒会長だった。
「君に少し、話があってね」
「俺に、ですか?」
「ここではなんだ。どこか腰を下ろせる場所はないかね?」
そう言われて、湊士はさっきまで座っていた場所へ案内する。
「ほう、いい場所だ。ここはちょうど出店の死角になっているのだな」
「それで? 俺に何の用件です?」
湊士には心当たりがなかった。急かす湊士に、会長は手で湊士を制する。
「まあ落ち着きたまえ。実は来週の土日に我が校でも文化祭があってな」
「はあ……」
「その文化祭に来て欲しいのだよ」
「はあ……。はあ?」
湊士は思わず、素っ頓狂な声をあげる。
「な、なんで俺なんですか? 初対面ですよね?」
「いや? 先月顔を合わせたはずだが?」
「え? それだけ? ってかあれだけで顔合わせ?」
湊士は驚いていた。確かに見た顔だが、話したのは今が初めてだ。
「なに、他校の生徒にも我が校の良さを知ってもらい、大学に進学してもらえると教師からも印象がよくてね」
「えぇ……」
「それとも、君は進学しないのかな?」
「いや、そりゃたぶん進学はしますけど……」
「なにか問題が?」
「そちらの大学、結構難関だって聞いてますけど」
「そうだな。自分で言うのもなんだが、かなり名門と言える」
「いやー、俺じゃちょっときついっていうか……」
「ふむ。君は彼女と一緒の大学生活を送りたいとは思わないのかね?」
湊士はどきんとする。
「……彼女って誰のことです?」
「個人情報ゆえ、名前は伏せさせてもらうが、君にはわかるのではないかな?」
わかっている。会長が言いたいのは十中八九、美白のことだろう。
「そりゃ、行けたらいいなーとは思ってますけど、でも……」
湊士が表情を暗くしていると、会長は湊士の肩に手を置く。
「まあ、高校と大学では全然違うが、それでも視察ということで一度我が校を覗きに来るのは悪いことではないと思いうが?」
「それは……まあ」
「それに、さっきも言ったが別の学生を引っ張ってくるとわたしのためでもあるのだよ。どうかな? 私を助けるためだと思って、ここはひとつ」
湊士はしばし考えた。将来のことなんて全く考えたことはなかった。
今は確かに通学路がたまたま同じということで美白と会える。しかし、大学が違えば?
もう二度と会うことはないかもしれない。
それは嫌だ。そう強く思う。
もし、同じ大学に行けたなら、またあの電車で一緒に通学できるのだろうか。そう思うと、湊士の中で答えは決まった。
「……わかりました。お邪魔させていただきます」
「クフフ。いい返事だ。では、また来週」
そう言って会長は去っていった。この時湊士は、将来のことについて、少し考えるようになった。
「今のままじゃ、ダメってことか……」
一方、会長は不敵に笑いながら、独り言を呟く。
「まったく。後輩のためとはいえ、このわたしが慈善活動など……。らしくないな。最近の白雪君にあてられたかな?」
会長は面白そうに笑いながら学校を後にした。
そして1週間が経った。
湊士は会長との約束を果たすため、美白の通う学校に来ていた。
「ここか……。つーか広っ!」
広大な敷地に湊士の学校の倍はあろうかという模擬店の数。正直、規模が違いすぎて驚きでいっぱいだった。
「うーわ。これどこ行きゃいいんだよ……」
げんなりしていると、正門の脇から一人の生徒が駆け寄ってくる。
「お困りですか?」
「え? あ、えーっと、そうです。どこ回ろうかなって思って」
「じゃあこちらをどうぞ。パンフレットになります」
「あ、ありがとうございます」
「あと、生徒会室では模擬店の詳細が確認できますので、良かったら見に来てください」
「あ、はい。どうも」
よく見ると、その生徒の腕には『生徒会』の腕章があった。
その後、その生徒は他の客のところで同じように声をかけていた。
「生徒会って大変なんだなあ」
そう呟きながら、貰ったパンフレットで生徒会室を探す。
「まあ、挨拶くらいしとかないとな……」
そして場所を確信し、生徒会室へ向かうことにした。
「失礼します」
そう言って訪れた生徒会室には会長がいた。
「よく来てくれた」
「まあ、約束したんで」
「ふむ、律儀に約束を守ろとは、君はいい人だな」
自分で読んでおいてこの言い方である。帰ろうかと思ったが、会長はいきなり核心をついてくる。
「うちの後輩がね。君を気に入っているようなのだ」
「え?」
あまりに突然の言葉に、湊士は言葉を失う。会長はかまわず言葉を続ける。
「いやね。わたしはこれでも君たちを応援しているのだよ。もちろん、わたし自身のために」
「……どういうことです?」
「なに、簡単な話だ。君と彼女がくっついてくれれば彼女はより精を出して生徒会をよりよくするだろう。むしろ、傷心して生徒会を抜けられるとわたしとしても困るのだよ」
「……俺たちの事情に勝手に割り込まないでください」
会長は「クフフ」と笑うと、湊士に近寄ってくる。
「そのとおりだ。正論だしごもっともだ。だからわたしは嫌なやつなのだろうね」
自分で嫌なやつという人を始めて見た湊士。この人とはあまり仲良くなれない気がした。
「だから利用させてもらうのさ。わたしは情報を提供する。しかし、行動するかは君次第だ。どうかね?」
湊士は考える。ここは名門校。その大学に進学するというなら早めに準備したほうがいいに決まっている。だから湊士の存在を知ってすぐに行動したのだろう。実力的に本当に進学できなくなる前に。
(そこまで考えてるのかな。この人は)
たぶんそうなのだろう。そうでなければ、進学がどうのとほのめかしたりはしない。
まったく、自分で言うだけあって本当に嫌な人だ。選択肢があるように見えて、実質一択だった。しかし、
「お断りします」
湊士は申し出を断った。会長は表情を変えずに湊士に質問する。
「なぜかね?」
「俺の事情のために、彼女のことを知るのはフェアじゃないので」
その言葉に、またも会長は笑った。
「なるほどなるほど。そういえば君はスポーツマンだったね。フェアな条件がお望みか」
「もうフェアじゃないですけどね」
「ふむ? というと?」
「だってあの子は、俺に好意を持ってくれてるって、知っちゃいましたから」
「ふふっ、それは悪いことをしたね」
「いいですよ。もう済んだことですし」
会長は湊士の肩をポンっと叩く。
「ますます気に入った。我が校の生徒ならぜひ生徒会に入ってほしいものだな」
湊士は黙って生徒会室を出ようとする。
「行くのかね?」
「ええ」
「それで、どうするつもりなのかね?」
「貰った情報は活かさないともったいないんで。使わせてもらいますよ」
「ほう、なら――」
「勘違いしないでください」
湊士は振り返り、会長の目を見る。
「俺から告白するのは大学に受かったらです。それまでは今までどおりを貫きます」
会長は拍手しながら湊士を賛辞する。
「結構。同じ目標に向かうのならいい刺激になるだろう」
「……お邪魔しました」
そう言って湊士は帰宅することにした。
ハッキリとわかった両想い。しかし、湊士は心にもやがかかった用に悶々とするのだった。