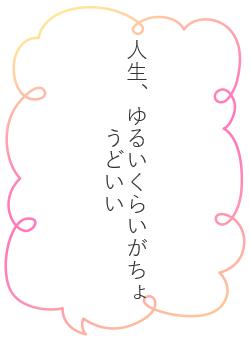10月(湊士パート)
来月は文化祭がある。
湊士のクラスでは喫茶店をすることに。
そのため、いろいろ買い出しが必要だった。買い出しは男手の方がいいだろうということで、男子でくじを引いた際運悪く湊士と凌悟で行くことに。他のクラスメートは内装を折り紙等で作ることになった。
「めんどくせー。しかも追加で必要になった分は連絡来るんだろ? ぜってー最初より多くなるって」
「わめいてもしょうがないだろ。あきらめろ」
とりあえず二人は、前に湊士がカーネーションを買いに行ったデパートへ向かうことに。
駅に向かい、電車を待つ。5分ほど待ってきた電車に乗り込む。
流石に通勤ラッシュを抜けた現在、座れる程度には乗客が少なかった。
だからそこに乗っていた美白の存在に、湊士はすぐに気が付いた。
「なに固まってんだ?」
「……彼女だよ」
「ん?」
「だから、あそこに座ってるの。俺が好きだって言ってる女の子」
凌悟はガラガラの車両を見渡し、二人で座っている男女を見つける。
「あの、男女で座っていて髪の長い?」
凌悟の指摘に湊士はコクンと頷く。
なにやら話し込んでいるようだった。向こうはこっちに気が付いていない。
「とりあえず座ろうぜ」
凌悟はそう言うと、一番近い席に座る。湊士もとりあえず腰を下ろすが、内心気が気でなかった。
「な、なあ。やっぱりあれって……」
「彼氏、と見るのが自然じゃないか?」
凌悟の容赦ないストーレート発言に、ダメージを受ける湊士。
「や、やっぱり?」
「なるほどな。確かにかわいいっていうのも頷ける。彼氏がいたってなんの違和感ねーレベルじゃん」
「男の方さ、めっちゃ頭いいですって感じで、しかも爽やかだな……」
「あー、湊士とじゃ天と地……は言い過ぎにしても、超えられない壁がある程度には格が違うな」
「……凌悟くん。それ死体蹴りっていうんだよ?」
「悪かったって。俺も、お前には諦めてほしくねえし」
「えっ?」
まさかそんなに応援してくれていたとは知らず、体が震える湊士。
「凌悟……。一生ついていきます」
「くんな。邪魔だ」
一蹴された。あまり大切には思ってくれていないのかもしれない。
「はあ、なに話してるんだろうな?」
「こらこら、余計なことすんなよ?」
「わかってらい。でも気になるのもしょうがないじゃん?」
「とりあえず男の方を視線で殺そうとするのはやめろ」
「だってー」
「だってじゃない……。っと」
少し騒がしくしてしまったか、向こうがこちらに気付く。一瞬だが視線が交差する。
「気付かれたかな?」
「たぶんな」
余計なことは言わずに大人しくしておくことに。
そこで凌悟がある違和感に気付いた。
「なあ、彼女って大人しいのか?」
「ん? まあ、電車内じゃしゃべったこと、ないかも」
「そうか……」
凌悟は手を顎に当ててなにか考えていた。
「どったの?」
「いや、彼氏彼女の関係にしては、浮ついてる様子もないし、俺らと違って全然しゃべってる感じもないから本当に彼氏なのかなって」
「うーん。確かに」
湊士たちが乗り込んできたとから、ぽつぽつしゃべることはあっても談笑という感じではなく、真剣そのものという感じだった。さらにしゃべっていないときは視線は真正面を向いており、どうも様子がおかしい。
そして次は湊士たちが降りる駅となる。電車がゆっくりとスピードを落とす。湊士たちはまだ座っていたが、美白だけおもむろに立ち上がる。
「あれ? 降りる駅同じじゃね?」
「え? ほんとだ」
どうやら美白たちも降りるらしく、早くも美白はドアの前で立っていた。そして
「会長! 降りますよ!」
という言葉が湊士たちまで聞こえてくる。
「会長、って……。もしかして生徒会長とか?」
「生徒会……。あっ!」
湊士はお婆さんを病院へ送ったときのことを思い出す。
確か自分は生徒会メンバーだと言っていた。
「彼女、生徒会メンバーだよ。前にそう言ってた!」
「なんだ。じゃあやっぱり生徒会でなにか買い物だろ。こんな時間だし、下校時のランデブーってより、俺らと同じ文化祭がらみじゃね?」
「そうだな! よかったー……。彼氏じゃなかったのか」
安堵していると、ドアが開く。
「おっと、俺らも降りるぞ」
「あいよー」
そして湊士は電車を降りる。しかし、美白の姿はなく、もう一人の男性がトイレの前で立っていた。
トイレか、と視線を男性に向けると、ニヤリと不敵に笑われる。
なんだ? と思ったが、凌悟が早くしろというので、湊士はその場から離れた。
「とりあえず余計な追加注文来る前に買い物済ませるぞ」
「確かに……。追加分は別のやつに行かせよーぜ」
そうと決まれば早速買い出しを始める。
ハサミやセロハンテープは各自持っているもので使えるが、看板に使う板などはこういう場所でしか入手できない。
そして、湊士たちは隅っこにあるホームセンターの一角を目指す。
「どれくらいの大きさがいいかな?」
「俺の身長の半分でいいだろ。でかすぎてもめんどくせー」
「確かに」
そう言って大小様々な板を買うことに。
「これくらいでいいか」
「そうだな。帰ろうぜ」
美白たちがなにを買いに来たのか結局わからなかったが、今考えても仕方ないと頭を切り替える。
そして帰りに見知った花屋が視界に入る。
湊士は少し考えたが、結局寄ることにした。
「悪い。もう1軒寄っていいか?」
「早めにな」
そう言って湊士は花屋に入っていく。
「いらっしゃいませー」
この前とは違う花が彩とりどりに飾られている。
「あら、今度は逆なのね」
「え? 逆?」
「なんでもないわ。気にしないで」
店員の言葉に何のことだろうと考えていると、「ねえ」と尋ねられる。
「あのバラ、どうしたの? 彼女にあげたりした?」
驚く湊士は、慌てて否定する。
「お、俺に彼女なんていないっすよ!」
「そうなの? ふーん……。あー、なるほどね」
店員は湊士を見つめる。というか視線が湊士の顔ではなく、どうも胸元やズボンを見ているように感じた。
「……なにか?」
「ああ、ごめんなさいね。それで? なにかご所望でしょうか?」
「えーっと、文化祭で喫茶店やるんですけど、いい花ないかなーって思って。だから買うのは今日じゃなくって来月になるんですけど」
「なるほど、じゃあ予約なんてどうですか? 指定の花を確実に取り置きできますよ」
「あ、いいですね! じゃあ花は……」
そう言って店内を見渡す湊士。ぶっちゃけどの花がいいかなんて、湊士にはよくわからなかった。
「あの、店員さんの選んだ花でいいですか?」
「わたしが選んでもいいんですか?」
「はい。あのバラ、とても好評だったので。店員さんを信じます」
「かしこまりました」
そう言って湊士は予約表に名前などを書いていく。
「ところでやっぱりあのバラ、誰かにあげたんですね」
「ええ、まあ。と言っても母にですよ? カーネーションのついでに」
「そうですか」
店員はなにやらニヤニヤしていたが、湊士は営業スマイルだろうと思うことにした。
「ありがとうございましたー」
予約を済ませ、凌悟と合流する。
「花なんか買ったのか?」
「今じゃないけど買ったよ。花飾ってあった方が、なんかオシャレじゃん?」
「まあ、そうかもな」
「じゃあ帰りますか」
そう言って学校に戻ることにした湊士たち。
帰りの電車では、美白たちはいなかった。
「まあ、そりゃそうだよね」
「帰りまで一緒とかタイミング良すぎだろ。ないない」
荷物を手すりスペースに置かせてもらい、湊士たちは席に座ることに。
「あー、結構おもてーな。肩だるいわ」
「だよなー」
他愛ない会話をしていると、凌悟から話題転換のように切り出してくる。
「最近、昴の様子、おかしくないか?」
「あー、おかしいよな。新学期始まった時くらいからか」
「明らかにお前を意識してるよな」
「そうかあ? 俺ってかなんかいつもボーっとしてるようにしか見えないけど」
「……鈍い野郎め」
「ん?」
「なんでもねー」
しばらく沈黙が続く。ここから流れる景色は久しぶりに見たので、新鮮な気分になる。
客も前より少なく、落ち着いて窓の向こうを眺めていた。
「…………なあ」
「なに?」
凌悟がソワソワしながら湊士に声をかける。
「お前、さっきの彼女のことが好きなんだよな?」
「もちろん。それがどったの?」
「…………絶対に内緒にしてくれよ」
凌悟は湊士の目を見つめて、そう前置きした。
「ああ、まあ内容聞かないとなんもわからんけど……」
湊士は凌悟が口を開くのを待つ。そして、
「俺、昴のことが好きなんだよ」
「…………は?」
「だから! 俺は前から昴が好きだったんだって!」
突然のカミングアウトに、湊士は何も言えないでいた。
「…………いつから?」
ようやく絞り出した言葉は、他愛ないものだった。
「初めて会ったときから、かな」
そう言って、出合ったときの頃を思い出していた。
4月のあの日、湊士たちと昴がまだただのクラスメートだった時――
「やったぜ。凌悟の後ろの席だ」
「どうやら50音順っぽいな」
「あー、『は』の次が俺の『ひ』ってことか」
そう言うと湊士は後ろの席の女子に声をかける。
「ねえねえ。きみって苗字『ふ』とかで始まるの?」
「……はい?」
今にして思えばいきなりな質問だったと思う。しかし、昴は嫌な顔せず答えてくれる。
「そうよあたし、藤宮昴」
「俺、平賀湊士。で、こっちが畠山凌悟。俺のツレ」
「ど、どうも」
「よろしくね」
「藤宮さんって電車通い?」
「いえ、家がこの近くなの」
「へー、いいなあ徒歩圏内かあ」
「じゃあさ、なんか部活に入ったりしないの?」
「うーん。ちょっと悩んでる」
「じゃあバスケ部とかどう? 面白いよ」
「バスケ? やったことないなあ……」
「俺ら、中学からバスケやってるから暇なとき練習に付き合うよ?」
「そこまで言うなら、やってみようかな」
「やったぜ! 教えるの、上手いんだぜ。主に凌悟が」
「っぷ! 平賀くんじゃないんだ?」
「俺は感覚派だから。な、凌悟」
「……あ、ああ。そうだな」
「てわけで何かあったら凌悟に聞くといいよ」
「よろしくね。畠山くん」
「あ、ああ、よろしく」
こうして凌悟は最初こそ昴を熱心に教育していた。しかし、女子と男子では戦略が大きく変わるため、基礎を教えたら後は女子バスの先輩が昴を教えるようになった。
「懐かしいな。俺が恋愛相談する前から恋に落ちてたんじゃん」
「恥ずかしながら、そうなるな」
「なんで恥ずかしいの?」
「えっ」
湊士の恥ずかしいの部分を否定した。
「そりゃ好きな人の前では緊張するし、上手く話せないけどさ。それと恥ずかしいっていうことは別じゃね?」
「別……?」
凌悟は湊士の言い分を聞こうとじっと湊士を見つめる。
「人が人を好きになるのって当たり前のことじゃん? そうやって俺らもこうして生まれた訳だし。だから、好きって気持ちを恥ずかしがる必要はないだろ」
「――」
凌悟は湊士の言ったことが、スッと胸にしみこんでいく。
「……そうだよな。好きが恥ずかしいわけじゃない。好きを隠す方が恥ずかしいのか」
「少なくとも俺はそうだよ。隠しててもなんにも起きないし、自分の理想には近づけないだろ?」
「……そうだな。俺も打ち明けてよかった」
「そっか」
そして少し満足そうにする凌悟。しかし、まだもやっとしているらしく、やや暗い表情だ。
「…………でもな。湊士」
「なに?」
「たぶん、昴はお前のこと、好きだと思う」
湊士は返事できなかった。
3人はいつだって一緒だった。むしろ練習に付き合った凌悟の方が一緒にいた時間は多かったはずだ。
「きっかけは、おそらくだが夏祭り、だろうな」
「夏祭り……?」
そう言われて夏祭りを思い出す。そして引っ張り出した記憶は、湊士がお姫様抱っこしたものだった。
「……あれか。なんかごめん」
「気にすんなよ。知らなかったんだ。怪我を心配するのは友人として当然だろ?」
「でもさ、先に事情を知ってたら俺は――」
「だからさ。隠してた俺が悪いのさ。恥ずかしいなんてくだらねえ理由で気持ちを隠してた。そりゃ誰も気付かないさ。気付かなければ、お前の言うとおり何も起きないんだよ」
「凌悟……」
「だからさ。情けねえ話だが、お前はあの子を好きでいてくれ。その間は、俺は頑張れる気がするから」
凌悟のこんな真剣な目を、湊士は見たことがなかった。だから誠意をもって返事する。
「俺の気持ちは動かねえ。あの子のところに置いてきた」
「……それを聞いて、安心できた」
「そっか」
そして電車は停車する。
二人は電車を降りて歩き出す。天気は二人の行く末を照らすような快晴だった。
来月は文化祭がある。
湊士のクラスでは喫茶店をすることに。
そのため、いろいろ買い出しが必要だった。買い出しは男手の方がいいだろうということで、男子でくじを引いた際運悪く湊士と凌悟で行くことに。他のクラスメートは内装を折り紙等で作ることになった。
「めんどくせー。しかも追加で必要になった分は連絡来るんだろ? ぜってー最初より多くなるって」
「わめいてもしょうがないだろ。あきらめろ」
とりあえず二人は、前に湊士がカーネーションを買いに行ったデパートへ向かうことに。
駅に向かい、電車を待つ。5分ほど待ってきた電車に乗り込む。
流石に通勤ラッシュを抜けた現在、座れる程度には乗客が少なかった。
だからそこに乗っていた美白の存在に、湊士はすぐに気が付いた。
「なに固まってんだ?」
「……彼女だよ」
「ん?」
「だから、あそこに座ってるの。俺が好きだって言ってる女の子」
凌悟はガラガラの車両を見渡し、二人で座っている男女を見つける。
「あの、男女で座っていて髪の長い?」
凌悟の指摘に湊士はコクンと頷く。
なにやら話し込んでいるようだった。向こうはこっちに気が付いていない。
「とりあえず座ろうぜ」
凌悟はそう言うと、一番近い席に座る。湊士もとりあえず腰を下ろすが、内心気が気でなかった。
「な、なあ。やっぱりあれって……」
「彼氏、と見るのが自然じゃないか?」
凌悟の容赦ないストーレート発言に、ダメージを受ける湊士。
「や、やっぱり?」
「なるほどな。確かにかわいいっていうのも頷ける。彼氏がいたってなんの違和感ねーレベルじゃん」
「男の方さ、めっちゃ頭いいですって感じで、しかも爽やかだな……」
「あー、湊士とじゃ天と地……は言い過ぎにしても、超えられない壁がある程度には格が違うな」
「……凌悟くん。それ死体蹴りっていうんだよ?」
「悪かったって。俺も、お前には諦めてほしくねえし」
「えっ?」
まさかそんなに応援してくれていたとは知らず、体が震える湊士。
「凌悟……。一生ついていきます」
「くんな。邪魔だ」
一蹴された。あまり大切には思ってくれていないのかもしれない。
「はあ、なに話してるんだろうな?」
「こらこら、余計なことすんなよ?」
「わかってらい。でも気になるのもしょうがないじゃん?」
「とりあえず男の方を視線で殺そうとするのはやめろ」
「だってー」
「だってじゃない……。っと」
少し騒がしくしてしまったか、向こうがこちらに気付く。一瞬だが視線が交差する。
「気付かれたかな?」
「たぶんな」
余計なことは言わずに大人しくしておくことに。
そこで凌悟がある違和感に気付いた。
「なあ、彼女って大人しいのか?」
「ん? まあ、電車内じゃしゃべったこと、ないかも」
「そうか……」
凌悟は手を顎に当ててなにか考えていた。
「どったの?」
「いや、彼氏彼女の関係にしては、浮ついてる様子もないし、俺らと違って全然しゃべってる感じもないから本当に彼氏なのかなって」
「うーん。確かに」
湊士たちが乗り込んできたとから、ぽつぽつしゃべることはあっても談笑という感じではなく、真剣そのものという感じだった。さらにしゃべっていないときは視線は真正面を向いており、どうも様子がおかしい。
そして次は湊士たちが降りる駅となる。電車がゆっくりとスピードを落とす。湊士たちはまだ座っていたが、美白だけおもむろに立ち上がる。
「あれ? 降りる駅同じじゃね?」
「え? ほんとだ」
どうやら美白たちも降りるらしく、早くも美白はドアの前で立っていた。そして
「会長! 降りますよ!」
という言葉が湊士たちまで聞こえてくる。
「会長、って……。もしかして生徒会長とか?」
「生徒会……。あっ!」
湊士はお婆さんを病院へ送ったときのことを思い出す。
確か自分は生徒会メンバーだと言っていた。
「彼女、生徒会メンバーだよ。前にそう言ってた!」
「なんだ。じゃあやっぱり生徒会でなにか買い物だろ。こんな時間だし、下校時のランデブーってより、俺らと同じ文化祭がらみじゃね?」
「そうだな! よかったー……。彼氏じゃなかったのか」
安堵していると、ドアが開く。
「おっと、俺らも降りるぞ」
「あいよー」
そして湊士は電車を降りる。しかし、美白の姿はなく、もう一人の男性がトイレの前で立っていた。
トイレか、と視線を男性に向けると、ニヤリと不敵に笑われる。
なんだ? と思ったが、凌悟が早くしろというので、湊士はその場から離れた。
「とりあえず余計な追加注文来る前に買い物済ませるぞ」
「確かに……。追加分は別のやつに行かせよーぜ」
そうと決まれば早速買い出しを始める。
ハサミやセロハンテープは各自持っているもので使えるが、看板に使う板などはこういう場所でしか入手できない。
そして、湊士たちは隅っこにあるホームセンターの一角を目指す。
「どれくらいの大きさがいいかな?」
「俺の身長の半分でいいだろ。でかすぎてもめんどくせー」
「確かに」
そう言って大小様々な板を買うことに。
「これくらいでいいか」
「そうだな。帰ろうぜ」
美白たちがなにを買いに来たのか結局わからなかったが、今考えても仕方ないと頭を切り替える。
そして帰りに見知った花屋が視界に入る。
湊士は少し考えたが、結局寄ることにした。
「悪い。もう1軒寄っていいか?」
「早めにな」
そう言って湊士は花屋に入っていく。
「いらっしゃいませー」
この前とは違う花が彩とりどりに飾られている。
「あら、今度は逆なのね」
「え? 逆?」
「なんでもないわ。気にしないで」
店員の言葉に何のことだろうと考えていると、「ねえ」と尋ねられる。
「あのバラ、どうしたの? 彼女にあげたりした?」
驚く湊士は、慌てて否定する。
「お、俺に彼女なんていないっすよ!」
「そうなの? ふーん……。あー、なるほどね」
店員は湊士を見つめる。というか視線が湊士の顔ではなく、どうも胸元やズボンを見ているように感じた。
「……なにか?」
「ああ、ごめんなさいね。それで? なにかご所望でしょうか?」
「えーっと、文化祭で喫茶店やるんですけど、いい花ないかなーって思って。だから買うのは今日じゃなくって来月になるんですけど」
「なるほど、じゃあ予約なんてどうですか? 指定の花を確実に取り置きできますよ」
「あ、いいですね! じゃあ花は……」
そう言って店内を見渡す湊士。ぶっちゃけどの花がいいかなんて、湊士にはよくわからなかった。
「あの、店員さんの選んだ花でいいですか?」
「わたしが選んでもいいんですか?」
「はい。あのバラ、とても好評だったので。店員さんを信じます」
「かしこまりました」
そう言って湊士は予約表に名前などを書いていく。
「ところでやっぱりあのバラ、誰かにあげたんですね」
「ええ、まあ。と言っても母にですよ? カーネーションのついでに」
「そうですか」
店員はなにやらニヤニヤしていたが、湊士は営業スマイルだろうと思うことにした。
「ありがとうございましたー」
予約を済ませ、凌悟と合流する。
「花なんか買ったのか?」
「今じゃないけど買ったよ。花飾ってあった方が、なんかオシャレじゃん?」
「まあ、そうかもな」
「じゃあ帰りますか」
そう言って学校に戻ることにした湊士たち。
帰りの電車では、美白たちはいなかった。
「まあ、そりゃそうだよね」
「帰りまで一緒とかタイミング良すぎだろ。ないない」
荷物を手すりスペースに置かせてもらい、湊士たちは席に座ることに。
「あー、結構おもてーな。肩だるいわ」
「だよなー」
他愛ない会話をしていると、凌悟から話題転換のように切り出してくる。
「最近、昴の様子、おかしくないか?」
「あー、おかしいよな。新学期始まった時くらいからか」
「明らかにお前を意識してるよな」
「そうかあ? 俺ってかなんかいつもボーっとしてるようにしか見えないけど」
「……鈍い野郎め」
「ん?」
「なんでもねー」
しばらく沈黙が続く。ここから流れる景色は久しぶりに見たので、新鮮な気分になる。
客も前より少なく、落ち着いて窓の向こうを眺めていた。
「…………なあ」
「なに?」
凌悟がソワソワしながら湊士に声をかける。
「お前、さっきの彼女のことが好きなんだよな?」
「もちろん。それがどったの?」
「…………絶対に内緒にしてくれよ」
凌悟は湊士の目を見つめて、そう前置きした。
「ああ、まあ内容聞かないとなんもわからんけど……」
湊士は凌悟が口を開くのを待つ。そして、
「俺、昴のことが好きなんだよ」
「…………は?」
「だから! 俺は前から昴が好きだったんだって!」
突然のカミングアウトに、湊士は何も言えないでいた。
「…………いつから?」
ようやく絞り出した言葉は、他愛ないものだった。
「初めて会ったときから、かな」
そう言って、出合ったときの頃を思い出していた。
4月のあの日、湊士たちと昴がまだただのクラスメートだった時――
「やったぜ。凌悟の後ろの席だ」
「どうやら50音順っぽいな」
「あー、『は』の次が俺の『ひ』ってことか」
そう言うと湊士は後ろの席の女子に声をかける。
「ねえねえ。きみって苗字『ふ』とかで始まるの?」
「……はい?」
今にして思えばいきなりな質問だったと思う。しかし、昴は嫌な顔せず答えてくれる。
「そうよあたし、藤宮昴」
「俺、平賀湊士。で、こっちが畠山凌悟。俺のツレ」
「ど、どうも」
「よろしくね」
「藤宮さんって電車通い?」
「いえ、家がこの近くなの」
「へー、いいなあ徒歩圏内かあ」
「じゃあさ、なんか部活に入ったりしないの?」
「うーん。ちょっと悩んでる」
「じゃあバスケ部とかどう? 面白いよ」
「バスケ? やったことないなあ……」
「俺ら、中学からバスケやってるから暇なとき練習に付き合うよ?」
「そこまで言うなら、やってみようかな」
「やったぜ! 教えるの、上手いんだぜ。主に凌悟が」
「っぷ! 平賀くんじゃないんだ?」
「俺は感覚派だから。な、凌悟」
「……あ、ああ。そうだな」
「てわけで何かあったら凌悟に聞くといいよ」
「よろしくね。畠山くん」
「あ、ああ、よろしく」
こうして凌悟は最初こそ昴を熱心に教育していた。しかし、女子と男子では戦略が大きく変わるため、基礎を教えたら後は女子バスの先輩が昴を教えるようになった。
「懐かしいな。俺が恋愛相談する前から恋に落ちてたんじゃん」
「恥ずかしながら、そうなるな」
「なんで恥ずかしいの?」
「えっ」
湊士の恥ずかしいの部分を否定した。
「そりゃ好きな人の前では緊張するし、上手く話せないけどさ。それと恥ずかしいっていうことは別じゃね?」
「別……?」
凌悟は湊士の言い分を聞こうとじっと湊士を見つめる。
「人が人を好きになるのって当たり前のことじゃん? そうやって俺らもこうして生まれた訳だし。だから、好きって気持ちを恥ずかしがる必要はないだろ」
「――」
凌悟は湊士の言ったことが、スッと胸にしみこんでいく。
「……そうだよな。好きが恥ずかしいわけじゃない。好きを隠す方が恥ずかしいのか」
「少なくとも俺はそうだよ。隠しててもなんにも起きないし、自分の理想には近づけないだろ?」
「……そうだな。俺も打ち明けてよかった」
「そっか」
そして少し満足そうにする凌悟。しかし、まだもやっとしているらしく、やや暗い表情だ。
「…………でもな。湊士」
「なに?」
「たぶん、昴はお前のこと、好きだと思う」
湊士は返事できなかった。
3人はいつだって一緒だった。むしろ練習に付き合った凌悟の方が一緒にいた時間は多かったはずだ。
「きっかけは、おそらくだが夏祭り、だろうな」
「夏祭り……?」
そう言われて夏祭りを思い出す。そして引っ張り出した記憶は、湊士がお姫様抱っこしたものだった。
「……あれか。なんかごめん」
「気にすんなよ。知らなかったんだ。怪我を心配するのは友人として当然だろ?」
「でもさ、先に事情を知ってたら俺は――」
「だからさ。隠してた俺が悪いのさ。恥ずかしいなんてくだらねえ理由で気持ちを隠してた。そりゃ誰も気付かないさ。気付かなければ、お前の言うとおり何も起きないんだよ」
「凌悟……」
「だからさ。情けねえ話だが、お前はあの子を好きでいてくれ。その間は、俺は頑張れる気がするから」
凌悟のこんな真剣な目を、湊士は見たことがなかった。だから誠意をもって返事する。
「俺の気持ちは動かねえ。あの子のところに置いてきた」
「……それを聞いて、安心できた」
「そっか」
そして電車は停車する。
二人は電車を降りて歩き出す。天気は二人の行く末を照らすような快晴だった。