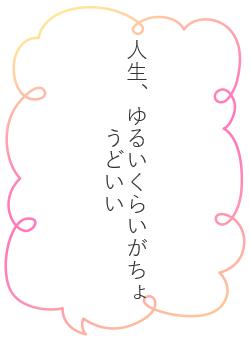8月(美白パート)
夏祭り当日。
美白は沙耶と一緒に着付けをしていた。
親に無理を言って新しい浴衣を買ってもらい、気分は絶好調だった。
「やっぱみしろんはかわいいなー」
「そんなことないよ。沙耶ちゃんだってかわいいよ」
「いやー、みしろんには負けますぜい」
「なにそのキャラ」
女子二人がキャッキャッと談笑していた。
沙耶は赤を基調した金色の金魚が目立つ派手な衣装。一方美白は、白を基調としてひまわりがアクセントになった衣装だった。
「じゃ、行きますか」
「うん」
今いるのは美白の家だった。美白の母親に着付けてもらい、その足でお祭りまで行く予定だ。
電車はかなり混んでいた。女性は半数が浴衣を着ていて、目的地は同じだとわかる。
電車内でこれだと、湊士に会うのは絶望的だろう。
そんな考えを見通されたのか、沙耶が美白の肩を叩く。
「ほら、せっかくのお祭りなんだし、楽しも?」
「う、うん。ごめんね」
「いいよ」
こうして祭りの最寄り駅で降車する。
駅の前ですら、すでに人混みでいっぱいだ。
「ほら、手掴んで。はぐれちゃうよ」
「ありがと、沙耶ちゃん」
美白はもちろんのこと、沙耶もかなりかわいい、というより美人であり、かつおめかししていることもあって周りの注目を集めていた。
「さすがみしろん。めっちゃ見られてるよ」
「そ、そうだね……。ちょっと怖いかな……」
美白の不安を感じ取ったのか、沙耶は美白の手をぎゅっと握る。
「大丈夫! あたしが守るから」
「沙耶ちゃん……。ありがと」
美白に笑顔が戻り、沙耶も一安心する。
「なんならあたしに惚れてもいいよ。あいつからあたしに乗り換えない?」
「もー、冗談ばっかり言って」
「半分本気だよー。みしろんにあいつはもったいないんだよなー」
「そんなことないよ。平賀くん、優しいよ?」
「あたしは?」
「沙耶ちゃんも優しい」
にへへと笑う美白に、沙耶は強く言えなかった。
「まあ、あたしは名前呼びだし、許す!」
「名前かー。確か湊士くん、だっけ」
「よく覚えてんね」
「まあ、うん」
「はあ……。それだけ好きってことか」
「もう! 茶化さないで!」
「ごめんて」
女子二人、姦しくしているとガラの悪そうな男性3人が美白たちの前に立ちふさがった。
「よお彼女。俺らと遊ばねえ?」
「お呼びじゃないんで。行くよ、みしろん」
「う、うん」
そう言って通り過ぎようとしても、壁のように邪魔してくる。
「まあそう言うなって」
「うっざ。早く消えてくんない?」
「おー、怖え怖え」
男は口では怖いと言いながらも、表情はニヤニヤと笑っていた。こういう時、他人というのは非情で確実に見えているのに誰も助けてくれない。みんな視線を外し、関係ないとばかりに去って行ってしまう。
「なあ、いいだろ? 遊ぼうぜ」
そう言って男の手は美白に伸びていく。そして――
次の瞬間には男は宙を舞っていた。
「ぐへっ!」
地面に叩きつけられて気絶したようだ。
「な、なにしやがるテメエ!」
他の二人も沙耶に襲い掛かる。しかし、
「遅いって」
沙耶は軽々と他二人も同じようにあしらってしまう。
「な、なんだ……。こいつ……」
「さすが沙耶ちゃんだね」
「だから言ったでしょ? ここにいないあいつよりあたしの方がみしろんを守れるよ」
「そ、それとこれとは話が違うから……」
「そんなー。かっこいいところ見せれたんだけどなー」
何とか意識のある男がフラフラになりながら怒鳴り散らしてくる。
「な、なにもんだ?」
「見てのとおり、ただの女子高生よ。ちょーっと合気道かじってるけど」
「あ、合気道、だと?」
「そ、これ以上痛い目見たくなきゃ消えたほうが身のためだよ? あたしまだ本気出してないし」
沙耶は余裕の笑みを見せると、男は捨て台詞を吐いて逃げていった。
「大したことないわね」
その瞬間、周りから歓声が上がる。
「大丈夫かい? ごめんな。怖くって助けられなくて」
「いえいえ~。大丈夫ですよ~」
見知らぬ人から謝られるが、沙耶はまったく気にしていなかった。
「ほら、行こ?」
「う、うん」
沙耶は再び美白の手を取り、祭り会場を目指す。
「ほんと、口ばっかりのやつしかいなくて反吐が出るわ」
「沙耶ちゃん……。そんな言い方しなくても……」
「だってそうでしょ? 結局誰も助けてくれない。自分を守るのは自分自身だよ。どうせあいつがいたってみしろんを守れたりしないんだ」
「そんなことないよ」
「どうしてそう言い切れるの!?」
沙耶の言葉が、つい強くなる。
悪いと思ったのか、しゅんと大人しくなり、謝ってくる。
「…………ごめん」
「いいよ。沙耶ちゃんも昔、大変だったもんね」
沙耶は小学生のころ、いじめられていた。男勝りな性格で、男子から男女と呼ばれ上履きやノートなど隠されたりしていた。同じ女子も、自分がターゲットにされたくないからか、誰も手を差し伸べる者はいなかった。
だから強くなろうと考えた。誰にも頼らず、自分だけで全て解決できるように。
そうして中学生になり、美白と出会った。
最初は美白のことも避けていた。どうせ裏切られる。自分は一人でいいと思っていた。
小学生高学年の時には、男子相手に返り討ちにするほど強くなっていたせいで、中学でも嫌な噂が一人歩きした。曰く、暴力的で素行に問題があると。
美白への評価が変わったのは家庭科の授業だった。
グループで浮いていた沙耶に、美白は手を差し伸べた。当然、その手を取らなかった。
周りも美白に、沙耶には関わるなと忠告した。しかし、
「沙耶ちゃん、別に何もしてないのに悪く言うのは良くないよ」
初めてだった。誰もが貼られたレッテルを鵜呑みにして距離を置いていたのに、美白だけがレッテルではなく、沙耶本人と向き合ったのだ。それから沙耶は考えが変わった。世の中は腐っているが、そんな中でも輝いているものはあるのだと。それを守るのが、自分の役目だと、いつしか美白に心を許した。
だからこそ許せない。肝心な時にいないあいつが。だったら自分が守ろう。今までも。これからも。
それでも、自分が心を許した人は、大丈夫だといってあいつを庇う。
ぶっちゃけただの嫉妬だってことはわかってる。わかってても、心がどうしようもなく受け入れられないことが、世の中にはあるのだ。
「どうして平賀くんのことが気になったのか、最近分かった気がするんだ」
「…………なんでなの?」
美白は笑顔で沙耶を指さした。
「だってあの人、沙耶ちゃんと同じ優しい目をしてたから」
「――」
そんなこと言われたら、あいつを否定したら美白が見てる自分も否定することになる。それは嫌だ。
「……はあ。あたしの負け」
「なにに?」
「美白の人を見る目が間違ってないって、あたしは信じたい。だから、あいつについて先入観でものを言うの、やめるよ」
「うん。ありがと」
「でも、ちょっとでもふさわしくないって思ったら絶対あいつを許さないから」
「それでいいよ」
美白は苦笑いしながら、今度は沙耶の手を引く。
「行こ? せっかくのお祭り、楽しまなくちゃ」
「そうだね。行こう」
こうして二人は祭りに繰り出した。
その後はさっきのことを忘れる勢いで遊び倒した。
花火まで少し時間がある。その間、クレープを食べたりヨーヨーすくいなどして楽しんだ。
そろそろ花火の時間になろうとしていた。後は花火を見て楽しい思い出になるはず、だった。
「あれ? あそこにいるのって、あいつじゃない?」
「え?」
まさか本当に会えるとは思っておらず、驚きながらも沙耶が指さす先を見つめる。そこには昴をお姫様抱っこしている湊士の姿があった。
「…………」
美白はなにも声を発せずに、息を飲み込んだ。
わざわざあんなことをするのだから、きっと訳がある。そう自分に言い聞かせるが、女性の少し嬉しそうな表情を見て、思考が停止する。
「みしろん? 大丈夫?」
「…………え? あ、うん。大丈夫……。大丈夫……」
全然大丈夫ではなかった。完全にパニックになり、その場から動けない。
「あれって……やっぱ彼女さん、なのかな」
沙耶の『彼女』という言葉に胸がズキンと痛む。
多少は覚悟していた。
湊士は人柄がいいため、彼女がいても不思議ではないと。しかし、実際に見せつけられると、心がぐちゃぐちゃになる。
「ちょっとみしろん! 顔真っ青だよ!?」
沙耶に肩を掴まれるが、意識が朦朧とする。
「帰ろ? 帰ってゆっくりしたほうがいいよ」
「…………うん。そう、する」
沙耶は肩を貸して美白を家まで送り届けた。
沙耶も家に帰ると、スマホのメッセージアプリで『大丈夫?』と聞いた。しかし、その返信がくることはなかった。
夏祭り当日。
美白は沙耶と一緒に着付けをしていた。
親に無理を言って新しい浴衣を買ってもらい、気分は絶好調だった。
「やっぱみしろんはかわいいなー」
「そんなことないよ。沙耶ちゃんだってかわいいよ」
「いやー、みしろんには負けますぜい」
「なにそのキャラ」
女子二人がキャッキャッと談笑していた。
沙耶は赤を基調した金色の金魚が目立つ派手な衣装。一方美白は、白を基調としてひまわりがアクセントになった衣装だった。
「じゃ、行きますか」
「うん」
今いるのは美白の家だった。美白の母親に着付けてもらい、その足でお祭りまで行く予定だ。
電車はかなり混んでいた。女性は半数が浴衣を着ていて、目的地は同じだとわかる。
電車内でこれだと、湊士に会うのは絶望的だろう。
そんな考えを見通されたのか、沙耶が美白の肩を叩く。
「ほら、せっかくのお祭りなんだし、楽しも?」
「う、うん。ごめんね」
「いいよ」
こうして祭りの最寄り駅で降車する。
駅の前ですら、すでに人混みでいっぱいだ。
「ほら、手掴んで。はぐれちゃうよ」
「ありがと、沙耶ちゃん」
美白はもちろんのこと、沙耶もかなりかわいい、というより美人であり、かつおめかししていることもあって周りの注目を集めていた。
「さすがみしろん。めっちゃ見られてるよ」
「そ、そうだね……。ちょっと怖いかな……」
美白の不安を感じ取ったのか、沙耶は美白の手をぎゅっと握る。
「大丈夫! あたしが守るから」
「沙耶ちゃん……。ありがと」
美白に笑顔が戻り、沙耶も一安心する。
「なんならあたしに惚れてもいいよ。あいつからあたしに乗り換えない?」
「もー、冗談ばっかり言って」
「半分本気だよー。みしろんにあいつはもったいないんだよなー」
「そんなことないよ。平賀くん、優しいよ?」
「あたしは?」
「沙耶ちゃんも優しい」
にへへと笑う美白に、沙耶は強く言えなかった。
「まあ、あたしは名前呼びだし、許す!」
「名前かー。確か湊士くん、だっけ」
「よく覚えてんね」
「まあ、うん」
「はあ……。それだけ好きってことか」
「もう! 茶化さないで!」
「ごめんて」
女子二人、姦しくしているとガラの悪そうな男性3人が美白たちの前に立ちふさがった。
「よお彼女。俺らと遊ばねえ?」
「お呼びじゃないんで。行くよ、みしろん」
「う、うん」
そう言って通り過ぎようとしても、壁のように邪魔してくる。
「まあそう言うなって」
「うっざ。早く消えてくんない?」
「おー、怖え怖え」
男は口では怖いと言いながらも、表情はニヤニヤと笑っていた。こういう時、他人というのは非情で確実に見えているのに誰も助けてくれない。みんな視線を外し、関係ないとばかりに去って行ってしまう。
「なあ、いいだろ? 遊ぼうぜ」
そう言って男の手は美白に伸びていく。そして――
次の瞬間には男は宙を舞っていた。
「ぐへっ!」
地面に叩きつけられて気絶したようだ。
「な、なにしやがるテメエ!」
他の二人も沙耶に襲い掛かる。しかし、
「遅いって」
沙耶は軽々と他二人も同じようにあしらってしまう。
「な、なんだ……。こいつ……」
「さすが沙耶ちゃんだね」
「だから言ったでしょ? ここにいないあいつよりあたしの方がみしろんを守れるよ」
「そ、それとこれとは話が違うから……」
「そんなー。かっこいいところ見せれたんだけどなー」
何とか意識のある男がフラフラになりながら怒鳴り散らしてくる。
「な、なにもんだ?」
「見てのとおり、ただの女子高生よ。ちょーっと合気道かじってるけど」
「あ、合気道、だと?」
「そ、これ以上痛い目見たくなきゃ消えたほうが身のためだよ? あたしまだ本気出してないし」
沙耶は余裕の笑みを見せると、男は捨て台詞を吐いて逃げていった。
「大したことないわね」
その瞬間、周りから歓声が上がる。
「大丈夫かい? ごめんな。怖くって助けられなくて」
「いえいえ~。大丈夫ですよ~」
見知らぬ人から謝られるが、沙耶はまったく気にしていなかった。
「ほら、行こ?」
「う、うん」
沙耶は再び美白の手を取り、祭り会場を目指す。
「ほんと、口ばっかりのやつしかいなくて反吐が出るわ」
「沙耶ちゃん……。そんな言い方しなくても……」
「だってそうでしょ? 結局誰も助けてくれない。自分を守るのは自分自身だよ。どうせあいつがいたってみしろんを守れたりしないんだ」
「そんなことないよ」
「どうしてそう言い切れるの!?」
沙耶の言葉が、つい強くなる。
悪いと思ったのか、しゅんと大人しくなり、謝ってくる。
「…………ごめん」
「いいよ。沙耶ちゃんも昔、大変だったもんね」
沙耶は小学生のころ、いじめられていた。男勝りな性格で、男子から男女と呼ばれ上履きやノートなど隠されたりしていた。同じ女子も、自分がターゲットにされたくないからか、誰も手を差し伸べる者はいなかった。
だから強くなろうと考えた。誰にも頼らず、自分だけで全て解決できるように。
そうして中学生になり、美白と出会った。
最初は美白のことも避けていた。どうせ裏切られる。自分は一人でいいと思っていた。
小学生高学年の時には、男子相手に返り討ちにするほど強くなっていたせいで、中学でも嫌な噂が一人歩きした。曰く、暴力的で素行に問題があると。
美白への評価が変わったのは家庭科の授業だった。
グループで浮いていた沙耶に、美白は手を差し伸べた。当然、その手を取らなかった。
周りも美白に、沙耶には関わるなと忠告した。しかし、
「沙耶ちゃん、別に何もしてないのに悪く言うのは良くないよ」
初めてだった。誰もが貼られたレッテルを鵜呑みにして距離を置いていたのに、美白だけがレッテルではなく、沙耶本人と向き合ったのだ。それから沙耶は考えが変わった。世の中は腐っているが、そんな中でも輝いているものはあるのだと。それを守るのが、自分の役目だと、いつしか美白に心を許した。
だからこそ許せない。肝心な時にいないあいつが。だったら自分が守ろう。今までも。これからも。
それでも、自分が心を許した人は、大丈夫だといってあいつを庇う。
ぶっちゃけただの嫉妬だってことはわかってる。わかってても、心がどうしようもなく受け入れられないことが、世の中にはあるのだ。
「どうして平賀くんのことが気になったのか、最近分かった気がするんだ」
「…………なんでなの?」
美白は笑顔で沙耶を指さした。
「だってあの人、沙耶ちゃんと同じ優しい目をしてたから」
「――」
そんなこと言われたら、あいつを否定したら美白が見てる自分も否定することになる。それは嫌だ。
「……はあ。あたしの負け」
「なにに?」
「美白の人を見る目が間違ってないって、あたしは信じたい。だから、あいつについて先入観でものを言うの、やめるよ」
「うん。ありがと」
「でも、ちょっとでもふさわしくないって思ったら絶対あいつを許さないから」
「それでいいよ」
美白は苦笑いしながら、今度は沙耶の手を引く。
「行こ? せっかくのお祭り、楽しまなくちゃ」
「そうだね。行こう」
こうして二人は祭りに繰り出した。
その後はさっきのことを忘れる勢いで遊び倒した。
花火まで少し時間がある。その間、クレープを食べたりヨーヨーすくいなどして楽しんだ。
そろそろ花火の時間になろうとしていた。後は花火を見て楽しい思い出になるはず、だった。
「あれ? あそこにいるのって、あいつじゃない?」
「え?」
まさか本当に会えるとは思っておらず、驚きながらも沙耶が指さす先を見つめる。そこには昴をお姫様抱っこしている湊士の姿があった。
「…………」
美白はなにも声を発せずに、息を飲み込んだ。
わざわざあんなことをするのだから、きっと訳がある。そう自分に言い聞かせるが、女性の少し嬉しそうな表情を見て、思考が停止する。
「みしろん? 大丈夫?」
「…………え? あ、うん。大丈夫……。大丈夫……」
全然大丈夫ではなかった。完全にパニックになり、その場から動けない。
「あれって……やっぱ彼女さん、なのかな」
沙耶の『彼女』という言葉に胸がズキンと痛む。
多少は覚悟していた。
湊士は人柄がいいため、彼女がいても不思議ではないと。しかし、実際に見せつけられると、心がぐちゃぐちゃになる。
「ちょっとみしろん! 顔真っ青だよ!?」
沙耶に肩を掴まれるが、意識が朦朧とする。
「帰ろ? 帰ってゆっくりしたほうがいいよ」
「…………うん。そう、する」
沙耶は肩を貸して美白を家まで送り届けた。
沙耶も家に帰ると、スマホのメッセージアプリで『大丈夫?』と聞いた。しかし、その返信がくることはなかった。