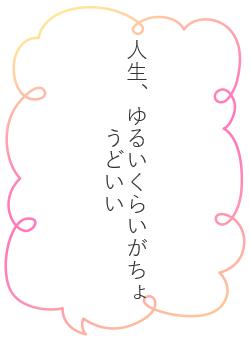雪がちらつく曇り空。
平賀湊士はいつもの通学のために、7時16分の電車に乗り込む。
指定席のように手すりの部分にもたれかかり、外を覗き込む。向こう側のホームの人たちも寒そうに肩を震わせている。久しぶりの雪だからだろうか。今日は特に冷える。
手はかじかみ、指先が冷たかったが電車内の熱気により、段々と感覚を取り戻していく。
いつものOLとその部下らしい男性もどこかそわそわしている。かく言う湊士も隣の手すりをちらっと見る。そこにはかわいい女の子が佇んでいた。ちょこんと佇んでいるが、姿勢がよく育ちがいいことが窺える。
名前は知らない。なぜなら学校が違うからだ。湊士が通っている高校とは違う制服。冬服がよく似合っており、紺のブレザーに赤いリボン。そしてチェック柄の少し短いスカートに長めのニーソックス。首にはリボンと同じ赤いマフラーが巻かれていた。
思うのだが、女子というのはそんなにスカートを短くして寒くないのだろうか? そう思わずにはいられないのが思春期の男子の思考、つまり湊士である。彼女は寒そうに手を息で温めていた。そこから見える細い指先。思わずゴクリと生唾を飲む。
(おっとっと)
あまりじろじろ見ては変に思われると考え、また外を覗く。相変わらず外は雪がちらほら舞っていた。
さっき彼女を見たとき、心なしか周りと同様そわそわしていたように思える。
それもそのはず、今日はバレンタインデーだ。
きっとあっちのOLも、男性にチョコを渡すタイミングを計っているのだろう。だとすると、彼女もだれかにチョコを渡すのだろうか。そう思うと、湊士の胸はキュッと締め付けられるように痛みを感じる。
なぜなら湊士は、名前も知らない彼女に約1年もの間片思いをしているからだ。
初めて彼女と出会ったときのことを今でも鮮明に思い出せる。
それくらい好きならいっそ告白しようとも思ったが、知らない男性からいきなり告白されても怖がらせるだけだろうと思い、実行には至っていない。
いや、それも湊士の言い訳だろう。好きなら行動すべきなのだ。相手に嫌われたら電車の時間を変えればいいだけ。それだけでもう関わることなど無いのだから。
そんな臆病な自分に腹が立っていた。同時に嫉妬した。名前もわからない、おそらく彼氏相手だろう。にチョコを渡す。彼女は嬉しそうに笑うだろう。その彼氏も。
そんな妄想を繰り返しては、湊士は悶々と心を痛めていた。
そんなことを考えていると、もうすぐ自分の降りる駅に到着しようとする。彼女はもう少し先の駅で降りるらしく、ここでお別れだ。そう、思っていた。
「あの、すみません……」
溶けそうな雪のように儚い声が聞こえた。
この声を、湊士は知っている。過去に少しだけ聞いたことのある声。それは他ならぬ、彼女の声だった。
彼女は顔を真っ赤にして顔を反らして、しかし体はしっかりと湊士の方へ向けていた。その手にはかわいらしいラッピングされた小袋。
まさか、と湊士は思った。そして、それはそのまさかだった。
「これ、受け取ってください……」
差し出された小袋。今日がなんの日かを考えると、答えは一つしかなかった。
「お、俺に?」
信じられない、という表情で尋ねる湊士。彼女はただ、コクンと頷いた。
「あ、ありがとう……」
もっと言いたいことは山ほどあった。でも、上手く言語化できない。
「あの……。電車、出ちゃいますよ?」
言われて湊士は我に返る。いつの間にか自分の降りる駅に到着し、出発する電子音が鳴り響いていた。慌てて降りようとする湊士。電車から降りると、ドアが閉まる。湊士は振り返って彼女を見る。そして、
「返事、絶対するから!」
ドア越しで湊士の声が聞こえたかわからないまま、電車はゆっくりと動き出し、やがて速度を上げてホームから去っていった。
湊士は小袋に貼りつけられた手紙に気が付く。中を読むと、
『ずっと気になっていました。好きです。付き合ってください。お返事はホワイトデーに。――白雪美白』
そう綴られていた。
「白雪……美白、さん。それが彼女の名前か……」
初めて知った名前。ずっと気になっていた相手。その彼女から、同じく気になっていたと言ってくれた。
「っしゃああああああ!」
湊士は他に人がいるにもかかわらず、手を振り上げガッツポーズする。
周りが何事かと湊士を見るが、当の本人はまったく気にしていなかった。
そして湊士は思い出に耽っていた。それは去年の4月。美白と出会ったばかりのあの頃を――。
平賀湊士はいつもの通学のために、7時16分の電車に乗り込む。
指定席のように手すりの部分にもたれかかり、外を覗き込む。向こう側のホームの人たちも寒そうに肩を震わせている。久しぶりの雪だからだろうか。今日は特に冷える。
手はかじかみ、指先が冷たかったが電車内の熱気により、段々と感覚を取り戻していく。
いつものOLとその部下らしい男性もどこかそわそわしている。かく言う湊士も隣の手すりをちらっと見る。そこにはかわいい女の子が佇んでいた。ちょこんと佇んでいるが、姿勢がよく育ちがいいことが窺える。
名前は知らない。なぜなら学校が違うからだ。湊士が通っている高校とは違う制服。冬服がよく似合っており、紺のブレザーに赤いリボン。そしてチェック柄の少し短いスカートに長めのニーソックス。首にはリボンと同じ赤いマフラーが巻かれていた。
思うのだが、女子というのはそんなにスカートを短くして寒くないのだろうか? そう思わずにはいられないのが思春期の男子の思考、つまり湊士である。彼女は寒そうに手を息で温めていた。そこから見える細い指先。思わずゴクリと生唾を飲む。
(おっとっと)
あまりじろじろ見ては変に思われると考え、また外を覗く。相変わらず外は雪がちらほら舞っていた。
さっき彼女を見たとき、心なしか周りと同様そわそわしていたように思える。
それもそのはず、今日はバレンタインデーだ。
きっとあっちのOLも、男性にチョコを渡すタイミングを計っているのだろう。だとすると、彼女もだれかにチョコを渡すのだろうか。そう思うと、湊士の胸はキュッと締め付けられるように痛みを感じる。
なぜなら湊士は、名前も知らない彼女に約1年もの間片思いをしているからだ。
初めて彼女と出会ったときのことを今でも鮮明に思い出せる。
それくらい好きならいっそ告白しようとも思ったが、知らない男性からいきなり告白されても怖がらせるだけだろうと思い、実行には至っていない。
いや、それも湊士の言い訳だろう。好きなら行動すべきなのだ。相手に嫌われたら電車の時間を変えればいいだけ。それだけでもう関わることなど無いのだから。
そんな臆病な自分に腹が立っていた。同時に嫉妬した。名前もわからない、おそらく彼氏相手だろう。にチョコを渡す。彼女は嬉しそうに笑うだろう。その彼氏も。
そんな妄想を繰り返しては、湊士は悶々と心を痛めていた。
そんなことを考えていると、もうすぐ自分の降りる駅に到着しようとする。彼女はもう少し先の駅で降りるらしく、ここでお別れだ。そう、思っていた。
「あの、すみません……」
溶けそうな雪のように儚い声が聞こえた。
この声を、湊士は知っている。過去に少しだけ聞いたことのある声。それは他ならぬ、彼女の声だった。
彼女は顔を真っ赤にして顔を反らして、しかし体はしっかりと湊士の方へ向けていた。その手にはかわいらしいラッピングされた小袋。
まさか、と湊士は思った。そして、それはそのまさかだった。
「これ、受け取ってください……」
差し出された小袋。今日がなんの日かを考えると、答えは一つしかなかった。
「お、俺に?」
信じられない、という表情で尋ねる湊士。彼女はただ、コクンと頷いた。
「あ、ありがとう……」
もっと言いたいことは山ほどあった。でも、上手く言語化できない。
「あの……。電車、出ちゃいますよ?」
言われて湊士は我に返る。いつの間にか自分の降りる駅に到着し、出発する電子音が鳴り響いていた。慌てて降りようとする湊士。電車から降りると、ドアが閉まる。湊士は振り返って彼女を見る。そして、
「返事、絶対するから!」
ドア越しで湊士の声が聞こえたかわからないまま、電車はゆっくりと動き出し、やがて速度を上げてホームから去っていった。
湊士は小袋に貼りつけられた手紙に気が付く。中を読むと、
『ずっと気になっていました。好きです。付き合ってください。お返事はホワイトデーに。――白雪美白』
そう綴られていた。
「白雪……美白、さん。それが彼女の名前か……」
初めて知った名前。ずっと気になっていた相手。その彼女から、同じく気になっていたと言ってくれた。
「っしゃああああああ!」
湊士は他に人がいるにもかかわらず、手を振り上げガッツポーズする。
周りが何事かと湊士を見るが、当の本人はまったく気にしていなかった。
そして湊士は思い出に耽っていた。それは去年の4月。美白と出会ったばかりのあの頃を――。