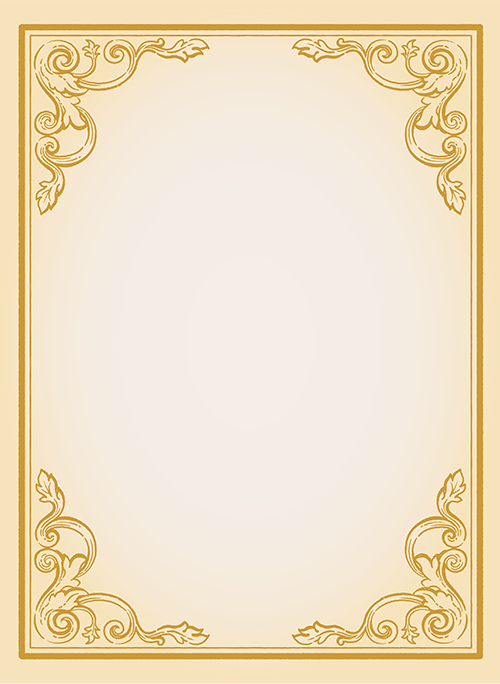祭り会場は人で溢れかえっていた。真っ直ぐ歩くなんて到底不可能で、蛇行しながら進む。隣を歩く栞は、はぐれないように僕の手を握っている。まだ照れくさい。顔が熱くなる。火照るのは、夏のせいではないだろう。
栞を唯一視認できる人物に僕が選ばれたのは、偶然ではなかった。繋がりはしっかりあった。
「栞の未練って、彼氏を作る以外に何かあったの?」
「そりゃあ、もちろん。一番はそれかなーって思ってたけど、他にも美味しいもの食べたいとか、旅行行きたいとか。いっぱいあったよ。生きてるうちに何もできなかったからね」
その中に、僕への感謝も含まれていて、それら全てを叶えてあげられる人物を選んだのだろう。誰が選んだのかはわからないけれど。神様かな?
「あれ食べてみたい」
彼女が指差したのは、りんご飴。祭りの代名詞とも言える。
「二つください」
屋台のおじさんにお金を渡し、りんご飴を受け取る。一つを彼女に渡す。
「甘いねぇ。でも、美味しい」
「気に入った?」
「うん」
屋台をいくつか回り、焼きそばを購入した。人が密集していない土手を見つけたので、そこに座って食べることにした。
「浴衣汚れそー」
言いながら、栞はお尻をつけて座った。
「言ってなかったけど、すごく似合ってるね。浴衣」
「おそっ。ありがとー」
「会ったときは、言える雰囲気じゃなかったでしょ。僕、どれだけ空気読めないやつなの」
「確かに」
栞は上品に笑った。いつもの彼女だ。
「焼きそば、美味しいね」
「うん。なんか祭りに出てるものってなんでも美味しく感じてしまう」
「祭りの雰囲気のせいだろうねぇ」
至福の表情をしている。焼きそばでこんな表情をできるのは、彼女くらいじゃないかと思う。
あのとき僕がスマホを渡していなかったら、こうして二人で祭りに来ることができなかったと思うと、過去の自分の選択に感謝する。一つ選択を誤れば、今の彼女の笑顔を見ることは叶わなかっただろう。
「ねえねえ、訊きたいことがあるんだけど」
「なに?」
「いつから私のこと意識してくれたの?」
僕はすすっていた焼きそばを吹き出してしまった。地面には落ちなかった。
「汚いよ?」
「誰のせいだ」
「別に変なことは訊いてないじゃん。いつからいつから?」
彼女はニヤニヤしてる。
僕が好きであることを認めたのだから、確かに変なことではないけれど、いきなり言われると焦る。本人を目の前にして言うほど恥ずかしいものはない。
「多分、二人で遊園地に行った帰りくらいかな」
「恋人だったのに、それまで好きじゃなかったんだー。ショックだよ」
と言いつつも、ショックを受けている様子は微塵も感じられなくて、付き合っているという関係上一応言っておいた、と言ったところだろう。
「それは栞だって、そうだろ?」
「私は会ったときから、好きだったけどね」
「本当のところは?」
「最初から好きだったのは間違ってないからね? でも、ショッピングモールに行ったあたりから、異性として意識しちゃうようになってきたかも。本屋で時間通りに君が来てくれなかったときは、本当に不安になっちゃったし、離れたくないっていう想いが強かったと思う」
「その節は、申し訳なかった......」
あのときの栞の表情は今でも鮮明に覚えている。あんな悲しげな表情は二度と見たくなかったし、そんな表情を絶対させたくないと思った。
「そのときから、徐々に好きになってしまいそうな気持ちが、秋太くんに向かないように自分の心を誤魔化してた。それでもホテルで秋太くんの初恋の話とか聞いてるとき、やばい! って思ったよ。さっき秋太くんに好きだって言われて、完全に認めちゃった。自分の気持ち」
よく考えれば、僕は初恋の相手に、初恋の話をしていたのか......。恥ずかしい。
「でも、僕に惚れる要素ってある?」
シンプルに疑問だ。彼女と違い、特段容姿が優れているわけでもない。どこに惹かれてくれたのだろう。
「え、いっぱいあるよ。それ本気で言ってる?」
「本気だけど......」
「まず優しいところでしょ。見ず知らずの私に数週間付きあってくれたんだよ? そんな人、めったにいないと思うよ」
「多分僕以外にもいると思うけど」
「なんで?」
「......可愛いし」
彼女の頬が急速に紅潮していくのが、わかった。
「君は破壊力抜群な発言をいきなりぶっこんでくるね? ずるいからやめてね......」
「言われ慣れてそうなのに意外と耐性ないんだね」
好きな人から言われるのって特別なんですー、と言いながら僕の言葉にむくれる彼女。そういう行動も僕にとっては効果抜群であることを彼女も自覚して欲しい。
僕は顔だけではなく、耳まで熱くなるのがわかった。
「なんか恥ずかしくなっちゃった。逆に秋太くんはどうして、好きになってくれたの? 初恋の相手だったから?」
「初恋の相手とかは関係ないよ。意識し始めたのは、初恋の相手だって知る前のことだし。高校生の君の全てを好きになった」
僕が言うと、彼女は「そっかー。嬉しいなぁ」と照れ隠しせずに言った。
焼きそばを食べ終わったので、ゴミ箱に容器を捨て、また屋台を回り始めることにした。
射的をしたいという栞の要望で、射的をすることになったが、当然対応してくれた屋台の人には僕が一人でするようにしか見えない。どうしようかと頭を捻って考えた。恥ずかしかったけれど、僕が彼女の後ろから手を添える形で、遊ぶことにした。周りからは、変な体勢で撃つんだな、と思われていたに違いない。密着していると、頭がおかしくなりそうだった。
冷静にいられなかったせいもあり、僕らが放ったコルクは商品と商品の間を抜けていった。
金魚すくいをするときは二回分支払い、ポイを二つ受け取った。そのうちの一つを彼女に渡した。裏から盗んでも最終的にお店側が損することはない。元通りになるから。けれど、彼女に盗みを提案するのはどうかと思ったので、律儀に二回分を払ったのだ。彼女は不器用なようで、すぐに穴を空けていた。彼女の反応に気を取られていると、僕のポイもすぐに破れた。
栞は、「まあ、掬えたとしても、私は飼えないしねー」と強がっていたが、悔しそうな表情をしているのを見逃さなかった。
「ラムネ飲みたい!」
と元気良く言ったので、僕は二本ラムネを買った。氷水につけられていたこともあり、とても冷えていた。彼女も、「つめたっ」と言った。
「ありがとー。ねえ、どうやって開けるの?」
僕が手本として、開けてみる。キャップを取り、ビー玉を押すための突起物をラムネ瓶の先端に当てる。少し力を入れて押すと、ビー玉は重力に従い、落ちた。溢れてくるラムネをこぼさないように、すぐに口元に運んだ。
カラン、という音も夏らしさを感じる。
「やってみる」
不器用だからか、単純に非力だからかはわからないけれど、苦戦していた。眉間にしわを寄せ、「うぅ」と言いながら、力を込めている。
「おお、開いたよ! わっ」
ラムネが溢れでて、彼女の手をつたっている。
「すごいね。よくできたね。でも、こぼしちゃったから、次は気をつけようね」
「子ども扱いしないで欲しいんですけどー」
僕がハンカチを渡すと、手を拭いた。不服そうな顔もラムネを一口飲んだら、ぱっと笑顔に変わった。
ラムネの泡が消えていく様子を見ていると、彼女もあと数日で消えてしまう事実が頭をよぎる。考えないようにしても、頭から追い出すことはできなかった。彼女も泡のように、少しずつ消えていくのだろうか。それはきっと美しいものだろう。
「ラムネ飲んでると、夏だーって感じがするね」
手を洗うために、トイレを目指している最中に言った。下駄を履いてるし、ラムネをこぼさないか心配になる。
「ラムネ飲んだことあったの?」
「え、ないよ? でも、テレビで見たことあったの。これも憧れだった」
そう言って、また一口飲む。意外と飲みっぷりがいいな。
仮設トイレに着くと、数人並んでいた。近くのコンビニに行くのとどちらの方が早いだろう? 僕と同じ考えの人がいてもおかしくないので、そっちもきっと待つことになるか。
「順番抜かして入っちゃおうかなー」
「プライバシーの侵害」
「冗談だよ。ちゃんと並びますー」
そう言って、栞は最後尾に並び始めた。数分暇かもな、と思っていると、なぜかこちらへ戻ってきた。
「どうしたの?」
「私の番って一生来ないよね?」
一瞬、どういうことか理解できなかったけど、彼女が並んでいることを誰も見えていないのだから、順番を抜かされ続けることに気づいた。
「やっぱ、すり抜ける?」
僕は冗談で言った。
「すり抜けません! 一緒に並んでくれない?」
それ以外に方法はなさそうなので、頷いた。
「ねえ、初恋についてもっと知りたいんだけど」
並び始めて数秒後、僕の袖を持ち、見上げる形で栞は訊いてきた。
「何を話せばいいの?」
「何もできない私をどうして好きになったのか、聞きたい」
ずっと考えていたことだけど、明確に何に惹かれたのか覚えていない。目を見て、楽しそうに話を聞いてくれるところには惹かれたはずだけど、それが決定打となったのかはわからない。僕の恋愛に対する関心って、今までそんなものだったのだ。何かしら理由があったのだろうけど、それが不明。
かなりあいまいなので、僕はぼかすことにした。
「あんまり覚えてないんだよね」
「それって本当に初恋なの? 私の名前も忘れてるし」
「多分......」
僕の中では初恋として、処理されている。確かに名前も忘れてしまっていたし、話し相手として好きだっただけなのかな? あの頃は友達としてなのか、異性としてなのか、その判別をしっかりできていなかったと思う。それなら、僕の初恋は、十七の夏が初めてということになるのか?
「そういう栞は僕の名前覚えてた?」
「もちろんだよ。覚えていたからこそ、苗字が違うせいで、この人じゃないって思い込んじゃった」
「なるほどです......」
本当に僕のは初恋と呼べない気がしてきた。
「まあ、今は初恋とか関係なしに好きになってくれたんだよね」
「うん」
「即答で嬉しいなぁ。あと明日から数えて、五日しかないんだね。少ないなー」
「延長できないの?」
無理だとわかっているのに、離れたくない思いが一層強くなった僕は、そんなことを訊いてしまった。
「うん。多分、無理。九月になったら、成仏するって念を押されたし」
「誰に?」
「説明は難しいんだけど、私が死んだときに死後の案内をしてくれた生物に? かな。秋太くんにも見せてあげたいよ。全体が黒くて、赤い目みたいなのが二つついてて、口はなさそうなのに、ちゃんと説明は受けることができたんだぁ。もしかしたら、私の脳に直接話しかけてたのかも」
とても現実味のない話だけれど、僕は完全に信用している。彼女が言うのなら、そうなのだろう、と。
「そういう案内人さんはタキシード姿だったり、動物の姿だったりをイメージするけど、全然違うんだ」
「全然違うよ! それは完全にフィクションの世界の話だね。私が見たのは、愛嬌のかけらもない、おぞましいものだった......」
彼女はビクビクしながら、言った。ちょっと気になってしまう。僕もいつか会えるだろうか?
「あ、空いたよ」
扉が開き、中から人が出てきた。僕らの番となったので、彼女に入るように促す。
「え、一緒に入んないの?」
「いや、僕は入らなくてもいいだろ」
「多分、後ろの人に文句言われるよ?」
怪しまれない程度に後ろを振り向くと、三十代ぐらいの女性に訝しげな目で見られていた。当然か。全然中に入ろうとしないし、独り言をペラペラ喋り続けてるんだから。そろそろ声をかけられても、おかしくない。
僕は渋々、中に入った。二人で入るにはかなり狭い。故意ではないが、彼女と触れてしまうことがあり、気が気じゃなかった。
何だか出会った頃を思い出した。僕らの出会った本屋でもそんな感じだった気がする。痴漢と間違われたのではないか、という僕の勘違いで話しかけたことから始まった。
そういえば、彼女があの場にいたのは、偶然なのだろうか? 偶然、彼女が漫画を読んでいるときに、僕が本屋を訪れた。偶然ではないだろうな。
「おっわりー。ごめん。またハンカチ借りてもいい?」
僕は先ほどラムネを拭いたハンカチを渡す。染みてないかな?
「ありがと」
栞が手を洗う間、手に持っていたラムネと交換する形で、ハンカチを受け取る。
他にも待っている人がいたので、すぐにトイレから出た。
あと二十分ほどで花火が始まる時間になっていた。時間が経つのが、早すぎるな。もっと遅くても、いいのに。
「そろそろ花火を観る場所、確保しとく?」
「おお。もうこんな時間だったんだ。早いねえ。そうしよっか」
僕らは先ほど焼きそばを食べるときに座った土手で観ることにした。そんなに人はいなかったし、少し高さもあるため、よく見えると思う。向かう途中のゴミ箱で飲み終えたラムネ瓶は捨てた。
土手の下に着くと、生えている雑草の上に座る人がちらほらいた。まだまだスペースはあるので、僕らも人の少ない場所に座ることにした。
「気になったんだけど、僕らが出会った場所覚えてる?」
「病院?」
「じゃなくて、なんて言えばいいのかな。幽霊になった後?」
「えっ。私、今、幽霊なの?」
以前に自分でそんなことを言っていた気がするけど、いつだったかな。別に深く考えずに、彼女は言ったんだろうな。
「わからないけど、いい表現が見つからなかった」
「幽霊ってちょっと酷いと思いまーす」
「悪かった。じゃあ、彷徨う魂」
「魂だけじゃなくて、ちゃんとここに存在してるからね? しかも、彷徨ってないからね?」
栞は目を細め、唇を尖らせている。屋台から少し距離があるため、暗めだけれど、隣に座る彼女の顔くらいならよく見える。
「なんか話ずれてるね」
「誰のせいですか!」
彼女は頬を少し膨らませた。そんな表情も、やっぱり可愛かった。
「ごめんごめん。さっきの話だけど、本屋で出会ったこと覚えてる?」
「うん」
「そのとき僕らが出会ったのは、偶然?」
彼女はお怒りモードだった表情を崩し、口角を上げた。
「だと思う?」
「思わない」
確かに僕は本屋が好きだし、かなりの頻度で行く。けれど、栞が生き返った初日に、ちょうど出会う確率ってどれくらいなのだろう? 時間までぴったり合ってないといけない。僕らが出会ったのは必然だと考えるのが自然だろう。
「正解。よくわからない生物さんに言われたの。あの時間の本屋に行けば、私のことを見つけてくれる人がいるよ、って」
「もしかして、未来が見えるのかな? それとも、未来を思い通りに変えることができるのかな?」
「どうだろ? 私の未練を晴らす機会を作ることができるんだから、そんな能力持ってても不思議じゃないよね」
「うん。でも、僕らのこれまでのやりとりが初めから決まっていたことだと思うと、何だか釈然としないな」
神様のような存在の思い通りに動いていたとなると、まるで操り人形のようだ。まあ、彼女に出会わせてくれたと思えば、感謝すべきなんだろうけど。
「確かにねー。でもね、私は秋太くんと出会えたことが嬉しいし、出会わせてくれたことに感謝してるよ」
「同じこと考えてた」
「えっ。本当?」
彼女は目を大きく開き、驚いていた。僕も彼女と同じ考えを持っていたことに、自分自身に驚いている。
僕は同意を示すため、軽く頷いた。
「何だか思考も似てきたのかな。私たち」
「これだけ一緒にいれば、そうなってしまったのかもしれない。残念だけど」
「残念とか言わないで欲しいんですけどっ! そりゃあ、生まれ変わっても、秋太くんは私みたいになりたくないのかもしれないけどー」
栞は意味を取り違えた。彼女の方が僕に似てきてしまったことに対して、言った。僕はいい性格をしている方ではないと思っているので、彼女は僕のようにならないで欲しいな、と思う。
逆に、栞はいつも真っ直ぐ物事を見ていて、感じたことがすぐに顔に出てしまうような人間だ。いわば僕と正反対に位置する人種だ。僕は基本的に感情を押し殺して、表に出さないようにしている。なんだか自分の内側をさらけ出しているようで、気持ちの悪い感覚に陥ってしまうのだ。
栞はそんなことを平気でやってしまう。僕にない部分を持っているからこそ、彼女に惹かれたのかもしれない。
彼女の方を見て話していると、眩しい光と共に破裂音が聞こえた。どうやら花火が打ち上がり始めたようだ。僕の方を見ていた彼女も、視線を花火の方へ向けた。
「うわー」
色とりどりの花火があがる。とても綺麗で、迫力満点だった。
花火の光で栞の表情がよく見える。反応を見る限り、花火も初めてのことだったのだろう。満足してくれているのが、感想を直接聞かなくてもわかる。
気づけば栞を見ていた。今は花火を観るべきだ。それなのに、無意識のうちに、隣に座る彼女の方を見てしまう自分がいた。思わず、視線をそらすが、気になってしまい、すぐに視線は戻ってきてしまう。
僕は、栞に消えて欲しくない。そう強く思ってしまう気持ちは本当に大きくなってしまったようだ。
「綺麗だったね」
「うん、すごかった。来れて良かったよ」
全ての花火が打ち終わり、余韻に浸りながら、僕らは駅を目指していた。
駅へ向かう群衆の中に紛れて、歩いている。会場に着く前とはかなり心持ちが違う。数週間前と同じように、他愛ない会話をしている。この時間がずっと続けばいいのに。
電車に乗っても、会話が途切れることはなく色んな話をした。栞が生前に好きだった漫画の話とか。彼女も漫画を読み始めたきっかけは、入院生活が暇で仕方がなかったから。また一つ、彼女についての情報が増えて、嬉しくなる。
最寄駅に着き、電車から降りる。改札をくぐり抜け、駅前に出る。
「今日は楽しかった。誘ってくれて、ありがと」
「これは誘ったって言うのか?」
僕が一方的に日時を告げただけなので、あまり誘ったという感覚はない。
「誘ったってことでいいんじゃない?」
「そういうことにしとくか」
「うん。また明日も会ってくれる?」
「もちろん」
「やったね。じゃあまた明日行くね。ばいばい」
彼女は手を振って、歩き始める。僕も小さく手を振る。
このまま帰していいのだろうか。きっと栞は僕が知らないような場所で今日も寝るのだろう。考えてる時間はない。僕が迷っている間にも、彼女はどんどん遠くなる。もう少しで暗闇に消えてしまう。
僕は小走りで栞の元へ向かい、腕を握った。
「わっ。びっくりした。足音がどんどん近づいてくるから、ちょっと怖かったよ」
「ごめん」
「ううん。私が誘拐されることはないし、心配する必要なんてないんだけどねー」
彼女はおどけて言った。
「それで、どうしたの?」
「どこに帰るの?」
「まだ決めてないなー。これから探すつもり」
「栞さえ、嫌じゃなければ......うちに来ない?」
彼女の口元がぷるぷる震えている。まるで、喜びを隠しきれないように。
「いいの?」
「うん」
「じゃあ、お邪魔しちゃおうかなぁ」
僕たちの間に気まずい雰囲気はもうなかった。
栞を唯一視認できる人物に僕が選ばれたのは、偶然ではなかった。繋がりはしっかりあった。
「栞の未練って、彼氏を作る以外に何かあったの?」
「そりゃあ、もちろん。一番はそれかなーって思ってたけど、他にも美味しいもの食べたいとか、旅行行きたいとか。いっぱいあったよ。生きてるうちに何もできなかったからね」
その中に、僕への感謝も含まれていて、それら全てを叶えてあげられる人物を選んだのだろう。誰が選んだのかはわからないけれど。神様かな?
「あれ食べてみたい」
彼女が指差したのは、りんご飴。祭りの代名詞とも言える。
「二つください」
屋台のおじさんにお金を渡し、りんご飴を受け取る。一つを彼女に渡す。
「甘いねぇ。でも、美味しい」
「気に入った?」
「うん」
屋台をいくつか回り、焼きそばを購入した。人が密集していない土手を見つけたので、そこに座って食べることにした。
「浴衣汚れそー」
言いながら、栞はお尻をつけて座った。
「言ってなかったけど、すごく似合ってるね。浴衣」
「おそっ。ありがとー」
「会ったときは、言える雰囲気じゃなかったでしょ。僕、どれだけ空気読めないやつなの」
「確かに」
栞は上品に笑った。いつもの彼女だ。
「焼きそば、美味しいね」
「うん。なんか祭りに出てるものってなんでも美味しく感じてしまう」
「祭りの雰囲気のせいだろうねぇ」
至福の表情をしている。焼きそばでこんな表情をできるのは、彼女くらいじゃないかと思う。
あのとき僕がスマホを渡していなかったら、こうして二人で祭りに来ることができなかったと思うと、過去の自分の選択に感謝する。一つ選択を誤れば、今の彼女の笑顔を見ることは叶わなかっただろう。
「ねえねえ、訊きたいことがあるんだけど」
「なに?」
「いつから私のこと意識してくれたの?」
僕はすすっていた焼きそばを吹き出してしまった。地面には落ちなかった。
「汚いよ?」
「誰のせいだ」
「別に変なことは訊いてないじゃん。いつからいつから?」
彼女はニヤニヤしてる。
僕が好きであることを認めたのだから、確かに変なことではないけれど、いきなり言われると焦る。本人を目の前にして言うほど恥ずかしいものはない。
「多分、二人で遊園地に行った帰りくらいかな」
「恋人だったのに、それまで好きじゃなかったんだー。ショックだよ」
と言いつつも、ショックを受けている様子は微塵も感じられなくて、付き合っているという関係上一応言っておいた、と言ったところだろう。
「それは栞だって、そうだろ?」
「私は会ったときから、好きだったけどね」
「本当のところは?」
「最初から好きだったのは間違ってないからね? でも、ショッピングモールに行ったあたりから、異性として意識しちゃうようになってきたかも。本屋で時間通りに君が来てくれなかったときは、本当に不安になっちゃったし、離れたくないっていう想いが強かったと思う」
「その節は、申し訳なかった......」
あのときの栞の表情は今でも鮮明に覚えている。あんな悲しげな表情は二度と見たくなかったし、そんな表情を絶対させたくないと思った。
「そのときから、徐々に好きになってしまいそうな気持ちが、秋太くんに向かないように自分の心を誤魔化してた。それでもホテルで秋太くんの初恋の話とか聞いてるとき、やばい! って思ったよ。さっき秋太くんに好きだって言われて、完全に認めちゃった。自分の気持ち」
よく考えれば、僕は初恋の相手に、初恋の話をしていたのか......。恥ずかしい。
「でも、僕に惚れる要素ってある?」
シンプルに疑問だ。彼女と違い、特段容姿が優れているわけでもない。どこに惹かれてくれたのだろう。
「え、いっぱいあるよ。それ本気で言ってる?」
「本気だけど......」
「まず優しいところでしょ。見ず知らずの私に数週間付きあってくれたんだよ? そんな人、めったにいないと思うよ」
「多分僕以外にもいると思うけど」
「なんで?」
「......可愛いし」
彼女の頬が急速に紅潮していくのが、わかった。
「君は破壊力抜群な発言をいきなりぶっこんでくるね? ずるいからやめてね......」
「言われ慣れてそうなのに意外と耐性ないんだね」
好きな人から言われるのって特別なんですー、と言いながら僕の言葉にむくれる彼女。そういう行動も僕にとっては効果抜群であることを彼女も自覚して欲しい。
僕は顔だけではなく、耳まで熱くなるのがわかった。
「なんか恥ずかしくなっちゃった。逆に秋太くんはどうして、好きになってくれたの? 初恋の相手だったから?」
「初恋の相手とかは関係ないよ。意識し始めたのは、初恋の相手だって知る前のことだし。高校生の君の全てを好きになった」
僕が言うと、彼女は「そっかー。嬉しいなぁ」と照れ隠しせずに言った。
焼きそばを食べ終わったので、ゴミ箱に容器を捨て、また屋台を回り始めることにした。
射的をしたいという栞の要望で、射的をすることになったが、当然対応してくれた屋台の人には僕が一人でするようにしか見えない。どうしようかと頭を捻って考えた。恥ずかしかったけれど、僕が彼女の後ろから手を添える形で、遊ぶことにした。周りからは、変な体勢で撃つんだな、と思われていたに違いない。密着していると、頭がおかしくなりそうだった。
冷静にいられなかったせいもあり、僕らが放ったコルクは商品と商品の間を抜けていった。
金魚すくいをするときは二回分支払い、ポイを二つ受け取った。そのうちの一つを彼女に渡した。裏から盗んでも最終的にお店側が損することはない。元通りになるから。けれど、彼女に盗みを提案するのはどうかと思ったので、律儀に二回分を払ったのだ。彼女は不器用なようで、すぐに穴を空けていた。彼女の反応に気を取られていると、僕のポイもすぐに破れた。
栞は、「まあ、掬えたとしても、私は飼えないしねー」と強がっていたが、悔しそうな表情をしているのを見逃さなかった。
「ラムネ飲みたい!」
と元気良く言ったので、僕は二本ラムネを買った。氷水につけられていたこともあり、とても冷えていた。彼女も、「つめたっ」と言った。
「ありがとー。ねえ、どうやって開けるの?」
僕が手本として、開けてみる。キャップを取り、ビー玉を押すための突起物をラムネ瓶の先端に当てる。少し力を入れて押すと、ビー玉は重力に従い、落ちた。溢れてくるラムネをこぼさないように、すぐに口元に運んだ。
カラン、という音も夏らしさを感じる。
「やってみる」
不器用だからか、単純に非力だからかはわからないけれど、苦戦していた。眉間にしわを寄せ、「うぅ」と言いながら、力を込めている。
「おお、開いたよ! わっ」
ラムネが溢れでて、彼女の手をつたっている。
「すごいね。よくできたね。でも、こぼしちゃったから、次は気をつけようね」
「子ども扱いしないで欲しいんですけどー」
僕がハンカチを渡すと、手を拭いた。不服そうな顔もラムネを一口飲んだら、ぱっと笑顔に変わった。
ラムネの泡が消えていく様子を見ていると、彼女もあと数日で消えてしまう事実が頭をよぎる。考えないようにしても、頭から追い出すことはできなかった。彼女も泡のように、少しずつ消えていくのだろうか。それはきっと美しいものだろう。
「ラムネ飲んでると、夏だーって感じがするね」
手を洗うために、トイレを目指している最中に言った。下駄を履いてるし、ラムネをこぼさないか心配になる。
「ラムネ飲んだことあったの?」
「え、ないよ? でも、テレビで見たことあったの。これも憧れだった」
そう言って、また一口飲む。意外と飲みっぷりがいいな。
仮設トイレに着くと、数人並んでいた。近くのコンビニに行くのとどちらの方が早いだろう? 僕と同じ考えの人がいてもおかしくないので、そっちもきっと待つことになるか。
「順番抜かして入っちゃおうかなー」
「プライバシーの侵害」
「冗談だよ。ちゃんと並びますー」
そう言って、栞は最後尾に並び始めた。数分暇かもな、と思っていると、なぜかこちらへ戻ってきた。
「どうしたの?」
「私の番って一生来ないよね?」
一瞬、どういうことか理解できなかったけど、彼女が並んでいることを誰も見えていないのだから、順番を抜かされ続けることに気づいた。
「やっぱ、すり抜ける?」
僕は冗談で言った。
「すり抜けません! 一緒に並んでくれない?」
それ以外に方法はなさそうなので、頷いた。
「ねえ、初恋についてもっと知りたいんだけど」
並び始めて数秒後、僕の袖を持ち、見上げる形で栞は訊いてきた。
「何を話せばいいの?」
「何もできない私をどうして好きになったのか、聞きたい」
ずっと考えていたことだけど、明確に何に惹かれたのか覚えていない。目を見て、楽しそうに話を聞いてくれるところには惹かれたはずだけど、それが決定打となったのかはわからない。僕の恋愛に対する関心って、今までそんなものだったのだ。何かしら理由があったのだろうけど、それが不明。
かなりあいまいなので、僕はぼかすことにした。
「あんまり覚えてないんだよね」
「それって本当に初恋なの? 私の名前も忘れてるし」
「多分......」
僕の中では初恋として、処理されている。確かに名前も忘れてしまっていたし、話し相手として好きだっただけなのかな? あの頃は友達としてなのか、異性としてなのか、その判別をしっかりできていなかったと思う。それなら、僕の初恋は、十七の夏が初めてということになるのか?
「そういう栞は僕の名前覚えてた?」
「もちろんだよ。覚えていたからこそ、苗字が違うせいで、この人じゃないって思い込んじゃった」
「なるほどです......」
本当に僕のは初恋と呼べない気がしてきた。
「まあ、今は初恋とか関係なしに好きになってくれたんだよね」
「うん」
「即答で嬉しいなぁ。あと明日から数えて、五日しかないんだね。少ないなー」
「延長できないの?」
無理だとわかっているのに、離れたくない思いが一層強くなった僕は、そんなことを訊いてしまった。
「うん。多分、無理。九月になったら、成仏するって念を押されたし」
「誰に?」
「説明は難しいんだけど、私が死んだときに死後の案内をしてくれた生物に? かな。秋太くんにも見せてあげたいよ。全体が黒くて、赤い目みたいなのが二つついてて、口はなさそうなのに、ちゃんと説明は受けることができたんだぁ。もしかしたら、私の脳に直接話しかけてたのかも」
とても現実味のない話だけれど、僕は完全に信用している。彼女が言うのなら、そうなのだろう、と。
「そういう案内人さんはタキシード姿だったり、動物の姿だったりをイメージするけど、全然違うんだ」
「全然違うよ! それは完全にフィクションの世界の話だね。私が見たのは、愛嬌のかけらもない、おぞましいものだった......」
彼女はビクビクしながら、言った。ちょっと気になってしまう。僕もいつか会えるだろうか?
「あ、空いたよ」
扉が開き、中から人が出てきた。僕らの番となったので、彼女に入るように促す。
「え、一緒に入んないの?」
「いや、僕は入らなくてもいいだろ」
「多分、後ろの人に文句言われるよ?」
怪しまれない程度に後ろを振り向くと、三十代ぐらいの女性に訝しげな目で見られていた。当然か。全然中に入ろうとしないし、独り言をペラペラ喋り続けてるんだから。そろそろ声をかけられても、おかしくない。
僕は渋々、中に入った。二人で入るにはかなり狭い。故意ではないが、彼女と触れてしまうことがあり、気が気じゃなかった。
何だか出会った頃を思い出した。僕らの出会った本屋でもそんな感じだった気がする。痴漢と間違われたのではないか、という僕の勘違いで話しかけたことから始まった。
そういえば、彼女があの場にいたのは、偶然なのだろうか? 偶然、彼女が漫画を読んでいるときに、僕が本屋を訪れた。偶然ではないだろうな。
「おっわりー。ごめん。またハンカチ借りてもいい?」
僕は先ほどラムネを拭いたハンカチを渡す。染みてないかな?
「ありがと」
栞が手を洗う間、手に持っていたラムネと交換する形で、ハンカチを受け取る。
他にも待っている人がいたので、すぐにトイレから出た。
あと二十分ほどで花火が始まる時間になっていた。時間が経つのが、早すぎるな。もっと遅くても、いいのに。
「そろそろ花火を観る場所、確保しとく?」
「おお。もうこんな時間だったんだ。早いねえ。そうしよっか」
僕らは先ほど焼きそばを食べるときに座った土手で観ることにした。そんなに人はいなかったし、少し高さもあるため、よく見えると思う。向かう途中のゴミ箱で飲み終えたラムネ瓶は捨てた。
土手の下に着くと、生えている雑草の上に座る人がちらほらいた。まだまだスペースはあるので、僕らも人の少ない場所に座ることにした。
「気になったんだけど、僕らが出会った場所覚えてる?」
「病院?」
「じゃなくて、なんて言えばいいのかな。幽霊になった後?」
「えっ。私、今、幽霊なの?」
以前に自分でそんなことを言っていた気がするけど、いつだったかな。別に深く考えずに、彼女は言ったんだろうな。
「わからないけど、いい表現が見つからなかった」
「幽霊ってちょっと酷いと思いまーす」
「悪かった。じゃあ、彷徨う魂」
「魂だけじゃなくて、ちゃんとここに存在してるからね? しかも、彷徨ってないからね?」
栞は目を細め、唇を尖らせている。屋台から少し距離があるため、暗めだけれど、隣に座る彼女の顔くらいならよく見える。
「なんか話ずれてるね」
「誰のせいですか!」
彼女は頬を少し膨らませた。そんな表情も、やっぱり可愛かった。
「ごめんごめん。さっきの話だけど、本屋で出会ったこと覚えてる?」
「うん」
「そのとき僕らが出会ったのは、偶然?」
彼女はお怒りモードだった表情を崩し、口角を上げた。
「だと思う?」
「思わない」
確かに僕は本屋が好きだし、かなりの頻度で行く。けれど、栞が生き返った初日に、ちょうど出会う確率ってどれくらいなのだろう? 時間までぴったり合ってないといけない。僕らが出会ったのは必然だと考えるのが自然だろう。
「正解。よくわからない生物さんに言われたの。あの時間の本屋に行けば、私のことを見つけてくれる人がいるよ、って」
「もしかして、未来が見えるのかな? それとも、未来を思い通りに変えることができるのかな?」
「どうだろ? 私の未練を晴らす機会を作ることができるんだから、そんな能力持ってても不思議じゃないよね」
「うん。でも、僕らのこれまでのやりとりが初めから決まっていたことだと思うと、何だか釈然としないな」
神様のような存在の思い通りに動いていたとなると、まるで操り人形のようだ。まあ、彼女に出会わせてくれたと思えば、感謝すべきなんだろうけど。
「確かにねー。でもね、私は秋太くんと出会えたことが嬉しいし、出会わせてくれたことに感謝してるよ」
「同じこと考えてた」
「えっ。本当?」
彼女は目を大きく開き、驚いていた。僕も彼女と同じ考えを持っていたことに、自分自身に驚いている。
僕は同意を示すため、軽く頷いた。
「何だか思考も似てきたのかな。私たち」
「これだけ一緒にいれば、そうなってしまったのかもしれない。残念だけど」
「残念とか言わないで欲しいんですけどっ! そりゃあ、生まれ変わっても、秋太くんは私みたいになりたくないのかもしれないけどー」
栞は意味を取り違えた。彼女の方が僕に似てきてしまったことに対して、言った。僕はいい性格をしている方ではないと思っているので、彼女は僕のようにならないで欲しいな、と思う。
逆に、栞はいつも真っ直ぐ物事を見ていて、感じたことがすぐに顔に出てしまうような人間だ。いわば僕と正反対に位置する人種だ。僕は基本的に感情を押し殺して、表に出さないようにしている。なんだか自分の内側をさらけ出しているようで、気持ちの悪い感覚に陥ってしまうのだ。
栞はそんなことを平気でやってしまう。僕にない部分を持っているからこそ、彼女に惹かれたのかもしれない。
彼女の方を見て話していると、眩しい光と共に破裂音が聞こえた。どうやら花火が打ち上がり始めたようだ。僕の方を見ていた彼女も、視線を花火の方へ向けた。
「うわー」
色とりどりの花火があがる。とても綺麗で、迫力満点だった。
花火の光で栞の表情がよく見える。反応を見る限り、花火も初めてのことだったのだろう。満足してくれているのが、感想を直接聞かなくてもわかる。
気づけば栞を見ていた。今は花火を観るべきだ。それなのに、無意識のうちに、隣に座る彼女の方を見てしまう自分がいた。思わず、視線をそらすが、気になってしまい、すぐに視線は戻ってきてしまう。
僕は、栞に消えて欲しくない。そう強く思ってしまう気持ちは本当に大きくなってしまったようだ。
「綺麗だったね」
「うん、すごかった。来れて良かったよ」
全ての花火が打ち終わり、余韻に浸りながら、僕らは駅を目指していた。
駅へ向かう群衆の中に紛れて、歩いている。会場に着く前とはかなり心持ちが違う。数週間前と同じように、他愛ない会話をしている。この時間がずっと続けばいいのに。
電車に乗っても、会話が途切れることはなく色んな話をした。栞が生前に好きだった漫画の話とか。彼女も漫画を読み始めたきっかけは、入院生活が暇で仕方がなかったから。また一つ、彼女についての情報が増えて、嬉しくなる。
最寄駅に着き、電車から降りる。改札をくぐり抜け、駅前に出る。
「今日は楽しかった。誘ってくれて、ありがと」
「これは誘ったって言うのか?」
僕が一方的に日時を告げただけなので、あまり誘ったという感覚はない。
「誘ったってことでいいんじゃない?」
「そういうことにしとくか」
「うん。また明日も会ってくれる?」
「もちろん」
「やったね。じゃあまた明日行くね。ばいばい」
彼女は手を振って、歩き始める。僕も小さく手を振る。
このまま帰していいのだろうか。きっと栞は僕が知らないような場所で今日も寝るのだろう。考えてる時間はない。僕が迷っている間にも、彼女はどんどん遠くなる。もう少しで暗闇に消えてしまう。
僕は小走りで栞の元へ向かい、腕を握った。
「わっ。びっくりした。足音がどんどん近づいてくるから、ちょっと怖かったよ」
「ごめん」
「ううん。私が誘拐されることはないし、心配する必要なんてないんだけどねー」
彼女はおどけて言った。
「それで、どうしたの?」
「どこに帰るの?」
「まだ決めてないなー。これから探すつもり」
「栞さえ、嫌じゃなければ......うちに来ない?」
彼女の口元がぷるぷる震えている。まるで、喜びを隠しきれないように。
「いいの?」
「うん」
「じゃあ、お邪魔しちゃおうかなぁ」
僕たちの間に気まずい雰囲気はもうなかった。