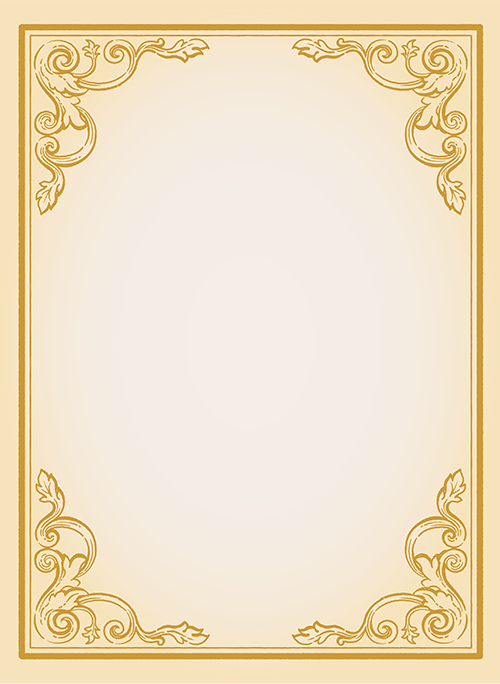目を覚ますと、見慣れぬ真っ白の天井が見えた。起き上がり、辺りを見渡すことで、状況を把握した。そうだ。栞と旅行に来ていたんだ。
隣のベッドを見ると、めくれ上がった掛け布団がそこにはあった。僕が寝ている間に彼女は、どこへ行ったのだろう。ベッドから降り、軽く捜索していると、浴室の方からシャワーの音が聞こえてきた。手違いで一ヶ月経たずして、彼女が消えてしまったのかと思い、少し焦った。
彼女がいることに安堵の息をつく。彼女に消えて欲しくないと思っていることに気づくのは容易なことだった。あと十日ほどで彼女のいない世界がくる。それに僕は耐えられるだろうか? まだ出会って三週間も経っていないというのに、濃い日常を送っているせいか、僕たちの関係は数ヶ月も前から続いているような錯覚を覚えた。
シャワーの音が止んだ。そろそろ栞が出てくるのだろう。暗い顔していたら、変な心配をかけてしまうかもしれない。一旦、思案することはやめて、残りの時間を楽しもうと思った。
歯磨きとか済ませたいけれど、まだ入ることはできない。というわけで、着替えだけ済ませて、彼女が出てくるのを待つことにした。
「起きてたんだ。おはよ」
「おはよう」
さっぱりした髪を揺らしながら、部屋を歩く。かなりラフな格好なので、目のやり場に困る。僕は彼女に意識が向かないように、洗面所の方へ移動した。
歯磨きをし終え、適当に髪を整えると、洗面所を出た。
「どう?」
彼女はすでに着替え終わっていた。いつもと髪型が違う。普段は長くて、黒い、艶のある髪を下ろしているのに、今日はポニーテールにしていた。どういった心境の変化だろう。
「似合ってると思うけど、急にどうしたの?」
「たまには気分を変えて、こういうのもありかなーって。ドキドキする?」
彼女はわざと後ろを向き、日焼けとは無縁の白いうなじを見せてくる。そんなことされなくとも、ドキドキしてしまう自分がいた。
「少しだけ、ね」
「彼女をちゃんと褒めて欲しいなー」
栞は少しむくれた。機嫌を損ねたようだけど、すぐに戻ってくれるだろう。
「朝ごはん何時からだっけ?」
「八時じゃなかった? えっ、もうこんな時間!?」
時計を見ると、七時五十五分だった。
彼女は俊敏な動きで、軽く荷物をまとめている。
「別に急がなくても、朝ごはんは逃げないよ」
「そうなんだけど。せっかくの一日を無駄にしたくはないじゃん?」
栞が言うと、とても説得力があるな。彼女にとって、一日一日はとても貴重で、一分一秒も無駄にしたくないんだろう。僕だって明日交通事故で死ぬかもしれないのに、そういう意識が薄い。もしかしたら、彼女よりも早くにこの世を去るかもしれないのに。
「よしっ! 食べに行こっか」
「うん」
朝食を食べ終わり、部屋に戻ってきたのは九時前。部屋を出る前に荷物をまとめてあったので、スムーズに部屋を出ることができた。
部屋の鍵を返し、ホテルを出ると、また嫌になる暑さが僕らを襲う。肌を焼くような陽の光を浴びながら、行動を開始した。
「暑いですねー」
彼女は平気そうな顔で、言った。本当に暑いと思っていれば、僕のように苦い顔になるはずだ。やっぱり、彼女は暑さ、寒さといった温度を感じないのではないか? 僕は試してみたくなった。
「ちょっと飲み物だけ買ってもいい?」
「うん」
「栞は何か飲む?」
「私は大丈夫だよ。ありがと」
彼女からの許可をもらったので、小走りでホテル前の自販機へ飲み物を買いに行く。冷たいお茶を一本購入した。
雲一つない、真っ青な空を彼女は見上げていた。遠くから見ると、絵になるな。
「お待たせ」
「いえいえ」
「あそこにパンダいない?」
「パンダ!?」
誰が聞いてもわかる嘘だけど、彼女なら騙せると思い、適当に言った。僕の予想通り彼女は見事に騙され、僕が指差した方角を見た。背を向けながら、いないよー、という彼女のほっぺにさっき買ったばかりのお茶を優しく当てた。
「ひゃっ。冷たい」
「なんだ、冷たいってやっぱり感じるんだ」
「私を何だと思ってるんですか!」
「人間?」
「確かに今の私は人間かどうか怪しいけど、一応人間だと思ってるから! どこにでもいる女子高生だから!」
彼女くらいの美貌を持ち合わせた女子高生がどこにでもいるわけない。そこを訂正するのは少し恥ずかしいので、僕の心の中だけで訂正しておこう。
「ごめんごめん。いつもこの暑さでも涼しい顔をしてるから、やっぱり温度感じないんじゃないかと思って」
「前にも言ったけど、ちゃんと感じます! 次やったら怒るからね」
「悪かったよ」
すでに少し怒り気味であることを指摘するのは、火に油を注ぐようなものなので、つっこまないでおこう。
遊園地以外に目的はなかったけれど、新幹線に乗るまで時間に余裕があったので、近くの商店街に向かった。色んなお店が立ち並んでいたけれど、僕の好奇心をそそるようなお店はなかった。
彼女は食べ物に目がないようで、コロッケや肉まんなどを注文した。僕の財布は時間が経つにつれて、軽くなっていった。本当にお金は返ってくるんだよな......。貯金も底をつきかけているし、戻ってこなかったら僕は漫画も買えない極貧生活が待っている。
お気楽な彼女を見ていると、少し不安だ。でも、彼女のために使ったお金であれば、嫌な気分はしないな。
手に持っていた串カツを食べ終えた彼女は、雑貨屋に入りたがった。まだ少し時間はあったので、寄っていくことにした。
南国を想起させるBGMがかかっており、せっかくの涼しい店内とミスマッチな気がした。
「ねえねえ、これ可愛くない?」
栞が手に持っていたのは小さなよくわからないキャラクターのキーホルダーだ。見たことないし、オリジナルだろうか。
「僕には可愛さがあんまりわからないんだけど」
「えー、感覚死んでるんじゃない?」
「栞に言われると、変な気分だな」
黄色い丸い球体に、目が二つ。髪の毛にも見えるし、手にも見えるような黒くて、細いものが目の上のあたりから二本飛び出ている。あと鼻か口か判別がつかないものもついてる。やっぱり、あんまり可愛くないな。
結局、僕はそのキーホルダーを買うこととなった。お揃いがいい、と彼女が言ったので、僕は仕方なく二つ購入した。彼女に対して、甘いな、と思う。あと、数週間で消えるわけだし、これくらいしてあげてもいいだろ、と自分に言い訳をする。
「そろそろ駅に向かう?」
「そうだね。満足!」
駅には迷うことなく、着いた。席についたら、彼女は早速キーホルダーを僕が昨日渡した端末につけていた。彼女は、「おお」と小さく声をあげ、感激しているようだった。感激し終えると、彼女は僕を見つめた。言葉を発しなくとも、僕は彼女が言いたいことがわかった。スマホにつけろ、ということだろう。
渋々スマホにつけてみたが、少し大きくて邪魔だ。せめて、もう少し可愛ければ良かったのだけれど。
「なんかやっとカップルっぽいことできたね」
彼女は言うと、無邪気に笑った。
「二人で旅行って時点で、めちゃくちゃカップルっぽいけどね」
「......確かに」
無駄話をしていると、時間はあっという間に過ぎた。新幹線から乗り換えたと思えば、いつのまにか地元に帰ってきていた。彼女といると、時間は一瞬だ。彼女がどう感じているかわからないけれど、もし僕と同じように感じているのであれば、それはあまり好ましいことではない気もする。
「明日はちょっと休憩しよっか。旅行で疲れたでしょ?」
「まあ、多少は」
「次は明後日に秋太くんのお家におじゃまさせてもらうね」
彼女なりの気遣いだろうか。彼女の方からそんなことを言ってくるとは予想していなかったので、ちょっとびっくりしている。明後日には会うわけだけれど。
「じゃあまたね」
「うん。また明後日」
僕たちは別れた。今日も彼女は僕の知らない場所で、寝るのだろう。同じ部屋で一度寝たわけだし、僕の家に招いても良かったのかもしれない。僕らの間には何もなかった。いたって健全だった。僕の部屋に泊めても、何も起こらないことはわかっている。それでも、理性がそれを拒んでいる。
彼女との距離をこれ以上縮めたくない。親密になりたくない。近くにいる期間が長くなればなるほど、認めたくない感情が表に出てきてしまう。いつかダムが決壊するように、一気に溢れてしまうんじゃないか、と思う。そうならないために、制御すべきだ。
最近の僕の生活は彼女中心に回っている。彼女が普通の人間とは違う環境にあるから、というのもある。でも、それ以上にあらゆる物事を彼女に結びつけて考えてしまう自分に気づいてしまったのだ。
それはつまり、そういうことになるのだろう。
一日の終わりを告げる茜色の空。日に日に日没が早くなっていることを感じる。夏がもう少しで終わる。夏の終わりは、彼女との別れを意味する。
僕はぐちゃぐちゃになった心が整理されないまま、帰路についた。
「大井はさ、好きなやつっている?」
「なんだよ、急に。そうだな。いるっちゃいるな」
「その曖昧な返答はどう受け取ればいいんだよ」
今日は栞と会わない。久しぶりにフリーの日ができたので、ダメ元で大井に連絡してみると、空いてるとのことだったので、二人でファミレスに行くことにした。おしゃべりが目的ではなくて、溜まりに溜まった宿題を終わらせるためだ。
八月に入ってから、彼女に付き合っていたこともあり、宿題の進みがかなり遅かった。成績は悪くないので、ペンが止まることはないが、書き続けてるせいもあり腕が疲れてきた。
休憩ということにして、僕は訊いてみたのだ。
「俺が好きなのは、鈴原ミナホちゃんだし~」
「ああ......」
そういや、大井はアイドルが好きなんだっけ。握手会とやらにも行くほどの熱烈なファンだと、本人の口から聞いたことがあった。鈴原ミナホさんはおそらく大井が好きなグループのメンバー。僕もテレビかなんかで名前くらいは聞いたことがあった。顔は思い出せないけど、多分あってる。
僕も漫画好きということで、オタク要素は持ち合わせているので、大井のアイドル趣味を軽蔑するといったことはない。けれど、大井がどこまで本気なのかはわからないけど、叶わぬ恋をするのって辛くないんだろうか。
「なんだ、その顔は。佐竹の妄想彼女よりはマシだと思うけどな」
フードコートでの一端を見られたせいで、まだ勘違いされ続けている。彼女の存在を説明するわけにいかないし、説明したとしても信じてはもらえないだろう。
僕は自分がヤバイ人間になったという設定を突き通そう。
「僕の話はいいよ。本気でその鈴原さんのことが好きなの? 大井は」
相手はアイドルなのに慎重に、手探り感を出しながら訊いた。
大井は考える間もなく、口を開いた。
「そうだけど」
そう言うと思った。当たり前だろ? みたいな顔をしている。少し憎たらしい。
「辛くないの?」
「なんで?」
「だって......」
さすがに躊躇う。本当に恋しているのなら、なおさら言いづらい。僕は口をつぐんでしまった。
「実らない恋だからか?」
僕が黙り込んでいると、大井から言われた。
「......うん」
「俺もわかってるよ。でもな、誰かのことを好きになるのって、よく言うことだけど、理屈じゃないんだよ。たとえ、相手がテレビの向こう側にいるような、手の届かない相手だとしても、一度好きだと自覚してしまったら、この気持ちは簡単に止まったりしないんだよな」
大井は謎にふんぞり返った。
「かっこいいこと言ってるようだけど、結構ヤバイな」
「うっせー。いつもは遠くからしか応援できないけど、数ヶ月に一度握手会が開催されるんだけどな。俺はあの一瞬のために生きてるし、次また会うために毎日頑張ろうって思えるんだよ。こんなにも一人の人間を強く想うなんて、恋と呼ばずしてなんと呼ぶ?」
大井は身振り手振りを使い、熱弁する。
「なんて言えばいいんだろう。大井って僕が思ってる以上に、ヤバイやつなのかな」
「は? お前、俺の言葉が胸に響かなかったのか?」
「ちゃんと聞いたよ。だから、同時にちょっとかっけえ、ってなった」
素直な感想だった。
僕だって誰かを好きになったことはある。初恋もそうだし、中学の頃に付きあった子のこともそうだ。好きだという気持ちが芽生えたから、それが恋だって自覚した。けれど、僕は彼女たちに対して、大井ほどの熱量を持っていたかと訊かれれば、自信をもって頷けない。
確かに好きだった。それは間違いないのだけど、それならどうして僕は初恋の彼女との別れを簡単に乗り越えることができたのか。まだ小学生だったから、深刻に捉えていなかっただけかもしれない。今では連絡先くらい知っていれば、良かったのにな、と思う。でもその程度なのだ。あの頃の『好き』というのは、今よりも漠然としていて、今の僕が考える、『好き』とはまた違っていたんじゃないかと思う。まだ本当に『好き』という気持ちをわかっていなかったのだろう。
中学の頃付きあった子もそうだ。最終的には僕がフられたわけだけど、「私にあんまり興味ないんじゃない?」そんなことを言われて、フられた気がする。そのときの僕はきっと否定したはずだ。ちゃんと好きだったから。けれど、別れた後、部屋で涙を濡らしたわけでもないし、すぐに普段通りの生活に戻ることができていた。申し訳ないけれど、僕は本気を装っていただけのように思える。
きっと『好き』には二種類あるんだ。一緒に遊びに行ったり、駄弁ったり、ご飯を食べたり、そういう関わりの中でも一定の距離感が保たれている人に感じる『好き』。友達なんかはこれに属するのだろう。もう一つは、四六時中と言っても大げさではないくらい、ある一人のことを考えてしまう。ただその人が笑ったり、泣いたり、怒ったり、そういう一つ一つの表情の変化にも心を動かされてしまう。そういう人に感じる『好き』。
僕が今まで好きだと言ってきたのは、前者ばかりだったのだと思う。後者は経験して、初めて気づく。
大井はシンプルに褒められたせいか、頭をかいて照れている。
「まあ、なんだ。妄想の中の彼女さんのことが好きなら、それはそれでいいんじゃねーの。俺と同じ叶わぬ恋同士、頑張ろうぜ。いつか別れは来ると思うから、そのときは早く別れた方がラーメン奢ってやることにしようぜ」
大井の言う別れとは、鈴原さんがいつかは卒業してしまうということだろう。きっと、僕の別れが先。
「いいよ」
僕は栞のことが好きだ。あと数日で消える人のことを好きになってしまった。これだけ密度の濃い日々を過ごしていれば、意識してしまう。最初は彼女が特異な存在であるから、僕の意識は彼女に向かっているのだと思った。違ったのだ。僕が彼女のことが好きだから、意識は向いていた。ただそれだけだったんだ。
テーブルの上のスマホが振動した。
『明日、二時ぐらいに行くの!』
とメッセージが届いていた。僕の心を読まれているんじゃないかと思うタイミングだったので、辺りを見渡したが、栞の姿はなかった。ほっと、息を漏らす。
よく見ると、語尾がちょっとおかしい。彼女はそんな喋り方をしたことがないし、イメージとは違う。きっと誤字だ。本当は『行くね!』と打ちたかったのではないだろうか。
思わず、笑みがこぼれる。
「彼女からか? お前も大概ヤバイな」
「うるさい」
僕は『待ってる』と返信しておいた。
僕は一度芽生えたこの気持ちをどう処理すべきか模索しながら、ワークに視線を落とした。
隣のベッドを見ると、めくれ上がった掛け布団がそこにはあった。僕が寝ている間に彼女は、どこへ行ったのだろう。ベッドから降り、軽く捜索していると、浴室の方からシャワーの音が聞こえてきた。手違いで一ヶ月経たずして、彼女が消えてしまったのかと思い、少し焦った。
彼女がいることに安堵の息をつく。彼女に消えて欲しくないと思っていることに気づくのは容易なことだった。あと十日ほどで彼女のいない世界がくる。それに僕は耐えられるだろうか? まだ出会って三週間も経っていないというのに、濃い日常を送っているせいか、僕たちの関係は数ヶ月も前から続いているような錯覚を覚えた。
シャワーの音が止んだ。そろそろ栞が出てくるのだろう。暗い顔していたら、変な心配をかけてしまうかもしれない。一旦、思案することはやめて、残りの時間を楽しもうと思った。
歯磨きとか済ませたいけれど、まだ入ることはできない。というわけで、着替えだけ済ませて、彼女が出てくるのを待つことにした。
「起きてたんだ。おはよ」
「おはよう」
さっぱりした髪を揺らしながら、部屋を歩く。かなりラフな格好なので、目のやり場に困る。僕は彼女に意識が向かないように、洗面所の方へ移動した。
歯磨きをし終え、適当に髪を整えると、洗面所を出た。
「どう?」
彼女はすでに着替え終わっていた。いつもと髪型が違う。普段は長くて、黒い、艶のある髪を下ろしているのに、今日はポニーテールにしていた。どういった心境の変化だろう。
「似合ってると思うけど、急にどうしたの?」
「たまには気分を変えて、こういうのもありかなーって。ドキドキする?」
彼女はわざと後ろを向き、日焼けとは無縁の白いうなじを見せてくる。そんなことされなくとも、ドキドキしてしまう自分がいた。
「少しだけ、ね」
「彼女をちゃんと褒めて欲しいなー」
栞は少しむくれた。機嫌を損ねたようだけど、すぐに戻ってくれるだろう。
「朝ごはん何時からだっけ?」
「八時じゃなかった? えっ、もうこんな時間!?」
時計を見ると、七時五十五分だった。
彼女は俊敏な動きで、軽く荷物をまとめている。
「別に急がなくても、朝ごはんは逃げないよ」
「そうなんだけど。せっかくの一日を無駄にしたくはないじゃん?」
栞が言うと、とても説得力があるな。彼女にとって、一日一日はとても貴重で、一分一秒も無駄にしたくないんだろう。僕だって明日交通事故で死ぬかもしれないのに、そういう意識が薄い。もしかしたら、彼女よりも早くにこの世を去るかもしれないのに。
「よしっ! 食べに行こっか」
「うん」
朝食を食べ終わり、部屋に戻ってきたのは九時前。部屋を出る前に荷物をまとめてあったので、スムーズに部屋を出ることができた。
部屋の鍵を返し、ホテルを出ると、また嫌になる暑さが僕らを襲う。肌を焼くような陽の光を浴びながら、行動を開始した。
「暑いですねー」
彼女は平気そうな顔で、言った。本当に暑いと思っていれば、僕のように苦い顔になるはずだ。やっぱり、彼女は暑さ、寒さといった温度を感じないのではないか? 僕は試してみたくなった。
「ちょっと飲み物だけ買ってもいい?」
「うん」
「栞は何か飲む?」
「私は大丈夫だよ。ありがと」
彼女からの許可をもらったので、小走りでホテル前の自販機へ飲み物を買いに行く。冷たいお茶を一本購入した。
雲一つない、真っ青な空を彼女は見上げていた。遠くから見ると、絵になるな。
「お待たせ」
「いえいえ」
「あそこにパンダいない?」
「パンダ!?」
誰が聞いてもわかる嘘だけど、彼女なら騙せると思い、適当に言った。僕の予想通り彼女は見事に騙され、僕が指差した方角を見た。背を向けながら、いないよー、という彼女のほっぺにさっき買ったばかりのお茶を優しく当てた。
「ひゃっ。冷たい」
「なんだ、冷たいってやっぱり感じるんだ」
「私を何だと思ってるんですか!」
「人間?」
「確かに今の私は人間かどうか怪しいけど、一応人間だと思ってるから! どこにでもいる女子高生だから!」
彼女くらいの美貌を持ち合わせた女子高生がどこにでもいるわけない。そこを訂正するのは少し恥ずかしいので、僕の心の中だけで訂正しておこう。
「ごめんごめん。いつもこの暑さでも涼しい顔をしてるから、やっぱり温度感じないんじゃないかと思って」
「前にも言ったけど、ちゃんと感じます! 次やったら怒るからね」
「悪かったよ」
すでに少し怒り気味であることを指摘するのは、火に油を注ぐようなものなので、つっこまないでおこう。
遊園地以外に目的はなかったけれど、新幹線に乗るまで時間に余裕があったので、近くの商店街に向かった。色んなお店が立ち並んでいたけれど、僕の好奇心をそそるようなお店はなかった。
彼女は食べ物に目がないようで、コロッケや肉まんなどを注文した。僕の財布は時間が経つにつれて、軽くなっていった。本当にお金は返ってくるんだよな......。貯金も底をつきかけているし、戻ってこなかったら僕は漫画も買えない極貧生活が待っている。
お気楽な彼女を見ていると、少し不安だ。でも、彼女のために使ったお金であれば、嫌な気分はしないな。
手に持っていた串カツを食べ終えた彼女は、雑貨屋に入りたがった。まだ少し時間はあったので、寄っていくことにした。
南国を想起させるBGMがかかっており、せっかくの涼しい店内とミスマッチな気がした。
「ねえねえ、これ可愛くない?」
栞が手に持っていたのは小さなよくわからないキャラクターのキーホルダーだ。見たことないし、オリジナルだろうか。
「僕には可愛さがあんまりわからないんだけど」
「えー、感覚死んでるんじゃない?」
「栞に言われると、変な気分だな」
黄色い丸い球体に、目が二つ。髪の毛にも見えるし、手にも見えるような黒くて、細いものが目の上のあたりから二本飛び出ている。あと鼻か口か判別がつかないものもついてる。やっぱり、あんまり可愛くないな。
結局、僕はそのキーホルダーを買うこととなった。お揃いがいい、と彼女が言ったので、僕は仕方なく二つ購入した。彼女に対して、甘いな、と思う。あと、数週間で消えるわけだし、これくらいしてあげてもいいだろ、と自分に言い訳をする。
「そろそろ駅に向かう?」
「そうだね。満足!」
駅には迷うことなく、着いた。席についたら、彼女は早速キーホルダーを僕が昨日渡した端末につけていた。彼女は、「おお」と小さく声をあげ、感激しているようだった。感激し終えると、彼女は僕を見つめた。言葉を発しなくとも、僕は彼女が言いたいことがわかった。スマホにつけろ、ということだろう。
渋々スマホにつけてみたが、少し大きくて邪魔だ。せめて、もう少し可愛ければ良かったのだけれど。
「なんかやっとカップルっぽいことできたね」
彼女は言うと、無邪気に笑った。
「二人で旅行って時点で、めちゃくちゃカップルっぽいけどね」
「......確かに」
無駄話をしていると、時間はあっという間に過ぎた。新幹線から乗り換えたと思えば、いつのまにか地元に帰ってきていた。彼女といると、時間は一瞬だ。彼女がどう感じているかわからないけれど、もし僕と同じように感じているのであれば、それはあまり好ましいことではない気もする。
「明日はちょっと休憩しよっか。旅行で疲れたでしょ?」
「まあ、多少は」
「次は明後日に秋太くんのお家におじゃまさせてもらうね」
彼女なりの気遣いだろうか。彼女の方からそんなことを言ってくるとは予想していなかったので、ちょっとびっくりしている。明後日には会うわけだけれど。
「じゃあまたね」
「うん。また明後日」
僕たちは別れた。今日も彼女は僕の知らない場所で、寝るのだろう。同じ部屋で一度寝たわけだし、僕の家に招いても良かったのかもしれない。僕らの間には何もなかった。いたって健全だった。僕の部屋に泊めても、何も起こらないことはわかっている。それでも、理性がそれを拒んでいる。
彼女との距離をこれ以上縮めたくない。親密になりたくない。近くにいる期間が長くなればなるほど、認めたくない感情が表に出てきてしまう。いつかダムが決壊するように、一気に溢れてしまうんじゃないか、と思う。そうならないために、制御すべきだ。
最近の僕の生活は彼女中心に回っている。彼女が普通の人間とは違う環境にあるから、というのもある。でも、それ以上にあらゆる物事を彼女に結びつけて考えてしまう自分に気づいてしまったのだ。
それはつまり、そういうことになるのだろう。
一日の終わりを告げる茜色の空。日に日に日没が早くなっていることを感じる。夏がもう少しで終わる。夏の終わりは、彼女との別れを意味する。
僕はぐちゃぐちゃになった心が整理されないまま、帰路についた。
「大井はさ、好きなやつっている?」
「なんだよ、急に。そうだな。いるっちゃいるな」
「その曖昧な返答はどう受け取ればいいんだよ」
今日は栞と会わない。久しぶりにフリーの日ができたので、ダメ元で大井に連絡してみると、空いてるとのことだったので、二人でファミレスに行くことにした。おしゃべりが目的ではなくて、溜まりに溜まった宿題を終わらせるためだ。
八月に入ってから、彼女に付き合っていたこともあり、宿題の進みがかなり遅かった。成績は悪くないので、ペンが止まることはないが、書き続けてるせいもあり腕が疲れてきた。
休憩ということにして、僕は訊いてみたのだ。
「俺が好きなのは、鈴原ミナホちゃんだし~」
「ああ......」
そういや、大井はアイドルが好きなんだっけ。握手会とやらにも行くほどの熱烈なファンだと、本人の口から聞いたことがあった。鈴原ミナホさんはおそらく大井が好きなグループのメンバー。僕もテレビかなんかで名前くらいは聞いたことがあった。顔は思い出せないけど、多分あってる。
僕も漫画好きということで、オタク要素は持ち合わせているので、大井のアイドル趣味を軽蔑するといったことはない。けれど、大井がどこまで本気なのかはわからないけど、叶わぬ恋をするのって辛くないんだろうか。
「なんだ、その顔は。佐竹の妄想彼女よりはマシだと思うけどな」
フードコートでの一端を見られたせいで、まだ勘違いされ続けている。彼女の存在を説明するわけにいかないし、説明したとしても信じてはもらえないだろう。
僕は自分がヤバイ人間になったという設定を突き通そう。
「僕の話はいいよ。本気でその鈴原さんのことが好きなの? 大井は」
相手はアイドルなのに慎重に、手探り感を出しながら訊いた。
大井は考える間もなく、口を開いた。
「そうだけど」
そう言うと思った。当たり前だろ? みたいな顔をしている。少し憎たらしい。
「辛くないの?」
「なんで?」
「だって......」
さすがに躊躇う。本当に恋しているのなら、なおさら言いづらい。僕は口をつぐんでしまった。
「実らない恋だからか?」
僕が黙り込んでいると、大井から言われた。
「......うん」
「俺もわかってるよ。でもな、誰かのことを好きになるのって、よく言うことだけど、理屈じゃないんだよ。たとえ、相手がテレビの向こう側にいるような、手の届かない相手だとしても、一度好きだと自覚してしまったら、この気持ちは簡単に止まったりしないんだよな」
大井は謎にふんぞり返った。
「かっこいいこと言ってるようだけど、結構ヤバイな」
「うっせー。いつもは遠くからしか応援できないけど、数ヶ月に一度握手会が開催されるんだけどな。俺はあの一瞬のために生きてるし、次また会うために毎日頑張ろうって思えるんだよ。こんなにも一人の人間を強く想うなんて、恋と呼ばずしてなんと呼ぶ?」
大井は身振り手振りを使い、熱弁する。
「なんて言えばいいんだろう。大井って僕が思ってる以上に、ヤバイやつなのかな」
「は? お前、俺の言葉が胸に響かなかったのか?」
「ちゃんと聞いたよ。だから、同時にちょっとかっけえ、ってなった」
素直な感想だった。
僕だって誰かを好きになったことはある。初恋もそうだし、中学の頃に付きあった子のこともそうだ。好きだという気持ちが芽生えたから、それが恋だって自覚した。けれど、僕は彼女たちに対して、大井ほどの熱量を持っていたかと訊かれれば、自信をもって頷けない。
確かに好きだった。それは間違いないのだけど、それならどうして僕は初恋の彼女との別れを簡単に乗り越えることができたのか。まだ小学生だったから、深刻に捉えていなかっただけかもしれない。今では連絡先くらい知っていれば、良かったのにな、と思う。でもその程度なのだ。あの頃の『好き』というのは、今よりも漠然としていて、今の僕が考える、『好き』とはまた違っていたんじゃないかと思う。まだ本当に『好き』という気持ちをわかっていなかったのだろう。
中学の頃付きあった子もそうだ。最終的には僕がフられたわけだけど、「私にあんまり興味ないんじゃない?」そんなことを言われて、フられた気がする。そのときの僕はきっと否定したはずだ。ちゃんと好きだったから。けれど、別れた後、部屋で涙を濡らしたわけでもないし、すぐに普段通りの生活に戻ることができていた。申し訳ないけれど、僕は本気を装っていただけのように思える。
きっと『好き』には二種類あるんだ。一緒に遊びに行ったり、駄弁ったり、ご飯を食べたり、そういう関わりの中でも一定の距離感が保たれている人に感じる『好き』。友達なんかはこれに属するのだろう。もう一つは、四六時中と言っても大げさではないくらい、ある一人のことを考えてしまう。ただその人が笑ったり、泣いたり、怒ったり、そういう一つ一つの表情の変化にも心を動かされてしまう。そういう人に感じる『好き』。
僕が今まで好きだと言ってきたのは、前者ばかりだったのだと思う。後者は経験して、初めて気づく。
大井はシンプルに褒められたせいか、頭をかいて照れている。
「まあ、なんだ。妄想の中の彼女さんのことが好きなら、それはそれでいいんじゃねーの。俺と同じ叶わぬ恋同士、頑張ろうぜ。いつか別れは来ると思うから、そのときは早く別れた方がラーメン奢ってやることにしようぜ」
大井の言う別れとは、鈴原さんがいつかは卒業してしまうということだろう。きっと、僕の別れが先。
「いいよ」
僕は栞のことが好きだ。あと数日で消える人のことを好きになってしまった。これだけ密度の濃い日々を過ごしていれば、意識してしまう。最初は彼女が特異な存在であるから、僕の意識は彼女に向かっているのだと思った。違ったのだ。僕が彼女のことが好きだから、意識は向いていた。ただそれだけだったんだ。
テーブルの上のスマホが振動した。
『明日、二時ぐらいに行くの!』
とメッセージが届いていた。僕の心を読まれているんじゃないかと思うタイミングだったので、辺りを見渡したが、栞の姿はなかった。ほっと、息を漏らす。
よく見ると、語尾がちょっとおかしい。彼女はそんな喋り方をしたことがないし、イメージとは違う。きっと誤字だ。本当は『行くね!』と打ちたかったのではないだろうか。
思わず、笑みがこぼれる。
「彼女からか? お前も大概ヤバイな」
「うるさい」
僕は『待ってる』と返信しておいた。
僕は一度芽生えたこの気持ちをどう処理すべきか模索しながら、ワークに視線を落とした。