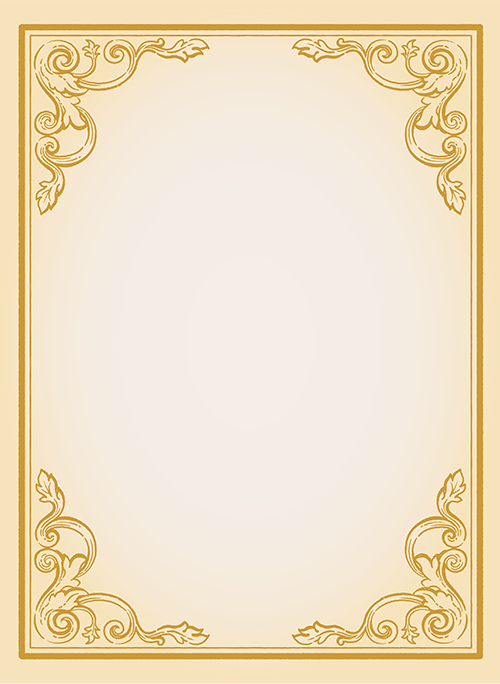「おっはよーっ!」
「おはよ。朝から元気だね」
「逆に旅行当日の朝にそのテンションでいられる秋太くんの頭の中を覗いてみたいよ」
朝はどうも気分が上がらない。理由は単純で朝が得意でないから。特に今日は夏休みに入ってから、一番早く起きた。もっと健康的な生活をすべきなんだろうけど、夏休みという期間だけは許して欲しい。また九月からは早寝早起きの毎日が待っているのだから。たった一ヶ月の間だけ、不健康でもいいじゃないか。そんな風に誰に言うともなく、心の中でつぶやく。
「もしかして、人の頭の中を見れる能力も備わっているのか......?」
僕は少し怯えながら、言った。
「さすがにないよ! 私が使えるのは壁をすり抜けるだけだって!」
栞は「ははっ」と笑いながら、言った。
朝から彼女のテンションは本当に高かった。終始話が途切れることはなく、ある話題が終わったと思えば、すぐに次の話題へ目紛しく変化した。最初の方は眠いせいもあり、相槌を打ち続けて終わった話もあったけれど、彼女のトークを聞いていると徐々に眠気は消えていき、新幹線に乗車した頃には完全に僕も目が冴え、笑い合っていた。
一応、新幹線は指定席で二席取っておいた。僕の分だけでも良かったのかもしれないけれど、栞が座ったシートがどういう扱いになるのかわからなかったので、念には念を、だ。
もしかしたら、見知らぬ人が栞の上に座る可能性だってある。僕にしか見えていないのだから、気づかなくて当然だ。きっとすり抜けて、その人は座るのだろうけど、僕が隣に向かって話しかけると、その人が反応するに決まっている。さすがに周りをあまり気にしない僕でも、隣に座る人に変な目を向けられながら、一時間以上新幹線に乗り続けるほどのメンタルは持ち合わせていなかった。というか、そんなことをしていれば、乗務員さんに通報されかねない。そういった事態は避けなければいけなかった。
窓側に彼女は座っている。基本的に僕の方を向いて喋っているのだけど、綺麗な景色が窓に映ると、無邪気な子どものように窓に張り付いていた。微笑ましかった。
「ねえねえ」
顔を窓から剥がした栞は、こちらを向いた。なぜかわからないけれど、少しだけ、むっ、としているような気がした。
「どうしたの?」
「私のことよく見て欲しいの」
栞が急に訳のわからないことを言い出したので、従って彼女ことを凝視することにした。今日も綺麗な顔をしている。見ているこっちが恥ずかしくなってきた。
見つめ合っている時間が長くなるにつれて、彼女の表情は曇っていった。
「違う! 顔以外も見てよ!」
「え、ああ、わかった」
しびれを切らしたように、栞が言ったので、僕は下から上へ彼女を見た。白いワンピースを着ていた。とてもよく似合っている。既視感があるな......。
「それって、この前買ってあげた服?」
「そう! 気づくの遅すぎるよ」
朝一で会ったときはまだ脳が正常に働いていなかったので仕方ない。似合っているな、とぼんやりと思っただけだ。しかし、今の今まで気づかなかったのは、どうかと思う。自責の念にかられる。
「ごめん。すごく似合ってるよ。直接言うのは恥ずかしいけど、綺麗だよ」
いつもなら心の中でつぶやくだけにするような柄にもないことを言ったのは、彼女に対して負い目があるからかもしれない。
「恥ずかしがりながらも言ってくれて、ありがとう。直接言われると、私も恥ずかしくなりました」
僕たちは小さく笑った。
もうあと十分ほどで到着するタイミングで、僕は彼女に渡しておきたいものがあったことを思い出した。
カバンの中からそれを取り出し、前の座席についているテーブルを出して、そこに置いた。
「なにこれ? プレゼント?」
「プレゼントっていうほどの物でもないんだけど、スマホ」
「え!」
「まあさすがに契約とかは僕一人じゃできなかったから、中古のやつなんだけどね」
「電話できるの?」
「契約はしてないから外では使えないんだけど、Wi-Fi環境が整ってるところだったら、僕らが離れていても連絡が取り合えるよ」
僕が言うと、彼女の表情はパッと明るくなった。
「どうして今まで思いつかなかったんだろ! 秋太くん天才!」
「今まで思いつかなかったことが申し訳ないくらいだよ。最近ならフリーWi-Fiスポットも増えてるし、使えるところ多いと思う」
「ありがと!」
そう言った栞は、カバンを探り始めた。そして、僕がさっきしたように、テーブルの上に取り出した物を置いた。
「イヤフォン?」
「正解! イヤフォンだよ」
僕が状況を理解できず、首を傾げていると彼女はピンク色のイヤフォンを手に取り、僕に手渡してきた。
「くれるの?」
「うん。アトラクションの待ち時間絶対喋るでしょ? でもさすがにずっと誰もいない場所を見ながら、話してたら周りの人を困惑させちゃうと思うの」
「確かに」
「だからイヤフォンで通話してるように見せかければ、いいんじゃないかと思って持ってきた!」
スマホを手に持って話すのもありだけど、何時間も腕を上げた状態をキープするのは疲れるだろう。その点、イヤフォンであれば耳につけておけばいいだけなので、疲労することはないはずだ。
「......盗んだやつ?」
「違う! これはちゃんと私が家から持ってきたやつです! あ、ちゃんと綺麗にしてあるので、ご心配なく!」
「ごめんごめん。ありがたく、使わせてもらうよ」
「どうぞどうぞ」
彼女の言う通り、何日も使っていないはずのイヤフォンらしかったが、新品かと思うくらい綺麗だった。昨日のうちに色々してくれたんだろうな。
そんな話をしているうちに駅に到着した。僕たちは忘れ物がないかを確認し、降車した。
新幹線が停まるくらいなのでそこそこ大きな駅で、一度離れれば再び会うことが叶わないようなそんな気がした。彼女は「うわぁー」と辺りを見渡している。突っ立ってても邪魔になるので、改札を目指して歩き始めた。
「迷子にならないように手でも繋いじゃう?」
彼女はいたって普通に、平然と言った。対照的に僕は心を乱されるわけだけど。
「いやそこまでしなくても大丈夫でしょ。多分」
動揺を隠すためいつもよりぶっきらぼうに言った。
「なんか断られた気分です」
彼女は前を向き、むすっとした。
「繋ぎたくないからそう言ったわけじゃなくて......なんていうか......」
「ふふっ。別にそんなことで怒ってないよ。まだ手を繋ぐのは早いかー。手繋ぎデートとか憧れるんだけどなぁ」
彼女は笑顔に戻り、さっきのは本気で怒っていたわけではなく、僕をからかっただけだとわかった。
「もう少しだけ待って欲しい」
「もう少しって?」
「今月中」
「わかった。待つね」
僕の前を歩く彼女は改札のドアをスッとすり抜けた。その後を切符を入れた僕は追った。
腕時計を確認すると、八時四十分になろうとしていた。僕たちが今日行く遊園地まで徒歩十分くらいで着くらしい。九時開園なのでちょうど良い時間に着きそうだ。
スマホの地図アプリで遊園地の名前を入れ、ルート案内を開始した。栞は「すごー」と言って、驚いていた。
初めての土地なので、どの方角を見ても、面白い。見たことも聞いたこともない名前のスーパーだったり、会社だったり、学校だったり、新鮮さがあって非日常を味わっている。たまに僕もよく知るコンビニなんかもあって、こんなところにもあるんだな、と感慨深くなる。
「何か買っておく物とかない?」
遊園地まであと五分くらい。入園する前に買う物はないか、訊いておいた。
「んー。飲み物だけ欲しいかなぁ」
「了解」
僕らが信号が変わるのを待っている大きな交差点を渡った先に、コンビニを発見した。横断歩道を渡り、入店すると冷気が僕の肌に触れる。心地いい。
僕も持ってきていたお茶が残りわずかとなっていたので、麦茶を買うことにした。彼女はサイダーを選んでいた。二本分の会計を済ませ、店を出ると、太陽の熱を全身で感じることとなり、まるで天国から地獄へ落とされたような気持ちになった。
結局九時過ぎに到着した。途中でコンビニ寄ったのと、土地鑑がないため少し予定よりも時間がかかってしまった。すでに入口付近には大勢の人がいた。僕は一枚分のチケットを買い、列の最後尾で番が来るのを待った。
「家族連れが多いね」
「夏休みだしね」
お盆は過ぎているけれど、夏休みに変わりはないので当然人は多い。アトラクションもすんなり乗ることはできないだろう。
「秋太くんも行ったことないんだよね?」
どこに行ったことないのかを詳しく栞は言わなかったけれど、遊園地のことだと解釈して言うことにした。
「うん。僕の記憶が正しければだけど」
「ジェットコースターってどんな感じなのかなっ」
「怖いんじゃない? 知らないけど」
「ふふっ。楽しみだね」
僕たちの番がやって来て、入園した。彼女はまたまたスッと通り抜けた。その能力、僕も欲しいな。
園内に入ると、一箇所に集まっていた人が一斉に散っていく。僕たちも例に漏れず、歩き始めた。
「何から乗る!?」
「僕はなんでもいいから、決めていいよ」
言うと、栞はパンフレットを見ながら考え始めた。こっちもいいとか、あっちもいいとか、そんなことを言いながら真剣に考えているようだった。もしかしたら、彼女と出会ってから一番と言ってもいいくらい真剣な眼差しで見ていた。
「決めた! まずはこれにしよ!」
彼女が指差したのはこの遊園地の目玉とも言えるジェットコースターだった。アトラクションの軽い説明文を読むと、高さ九十メートルから急降下するらしい。全長も二キロを超えており、読んだだけで寒気立つ。
園内マップを見なくとも、ジェットコースター乗り場の位置は大体把握できた。僕たちはすでに何十人も待っている列の最後尾に並ぶことにした。現在の待ち時間は十五分ほどらしい。これがお昼を過ぎたあたりになれば、もっと待ち時間が伸びるんだろうな。今は開園したばかりなので、マシな方だろう。
栞からさっき貰ったイヤフォンを片耳につけた。
「おっ、早速活用してくれてるね」
「せっかくだしね」
「なんかあげたものを身につけてくれてると嬉しいものだねぇ」
「僕も前に買ってあげた服を着てもらえて嬉しいよ」
「最初気づかなかったけどねー」
「それは、マジでごめん」
話していると、あっという間に時間が過ぎた。今走っているコースターが帰ってきたら、僕らの番になる。遊園地に来た思い出がないので、当然ジェットコースターに乗るのも初だ。ちょっと緊張してきた。彼女の方は怖がるそぶりを一切見せていなかった。本当に楽しみにしていることが感じ取れた。
「さっきはありがとう」
コースターが上っている最中に栞は言った。
「彼女扱いしてくれて、嬉しかったよ」
僕はチケットを二枚分スタッフの人に出した。一枚は僕の、もう一枚は彼女の。僕の隣は空けてもらう必要があったので、僕以外に見えていない彼女のことをどう説明しようか迷った。ただチケットを二枚用意するだけじゃ断れると思い、少しずるいが、亡くなった彼女と来ている気分を味わいたい、という半分嘘で半分本当のことを言い、感情に訴えかけた。何とか上手くいき、僕の隣は空けてもらえることになった。
「一応今は彼氏ってことになってるし」
僕が言うと、彼女は微笑んだ。
「じゃあ一つ、彼氏らしいことをお願いしてもいいかな?」
「何を?」
「私今、めちゃくちゃ怖いから手握ってて欲しい」
笑顔は消え、震え声で彼女は言った。僕はいつも彼女が見せるような笑みを浮かべ、優しく手を重ねた。こんなにも早く手をつなぐ機会が訪れてしまうとはな。これを手をつないだとして、カウントしていいものなのかわからないけれど。
彼女の悲鳴と共に、コースターは頂上から降下した。
「無理無理無理無理!」
ジェットコースターから降車した僕たちは、近くのベンチで休憩していた。どうやら栞は絶叫系が苦手なタイプのようだ。今まで遊園地に来たことがなかったので、それもわからなかったのだろう。
水を飲みながら、「うぇっ」と彼女はしかめっ面をしながら言う。
「僕は結構楽しかったけどな」
「なんで? ありえないんだけど!」
恐怖からか普段の彼女の口調よりフランクになっている気がした。
「次はフリーフォールにでも乗る?」
「怒るよ?」
傍から見れば、カップルのように見えるやりとりをしているのかもしれない。見られることはないけれど。
「冗談だよ」
「怒ったので、次も私が行きたいところに付きあってもらいます」
「全然構わないよ」
おそらく、コーヒーカップやメリーゴーランドだろう。どのアトラクションでも僕は全く恐怖心はないはずなので、彼女の後をスタスタついていく。
何気ない会話をしながら、少し歩くと、彼女がどこへ行くつもりなのか察した。
「ごめん。さっきのことは謝るから、別のアトラクションにしない?」
「なにぃ? 怖いのぉ?」
栞ついていくと、僕はお化け屋敷の前に立たされていた。お化け屋敷に入ったことはないけれど、僕は苦手な方だろう。ホラー映画が苦手なのだから、多分。
できれば、避けたい。避けたいが、彼女はニヤニヤ笑って、そうさせてくれそうにない。今だけ彼女のことが悪魔に見える。
「うん。怖い。だから、やめよう」
「そこは見栄を張ってでも、先導するところじゃないの? 彼氏なら」
「普通はそうかもしれない。でも、僕たちの関係は普通じゃないだろ? だから今回の彼氏らしい行動に関しても、僕たちの場合、普通っていう言葉は適用されないと思うんだ。例外だよ、例外」
「つべこべ言わずに行こ」
そう言って、栞は僕の手を掴んだ。渋々入ることになってしまった。絶叫しないように、頑張ろう......。
「楽しいねー」
暗い中を彼女は怖がるそぶりを一切見せずに、歩いていく。僕はその後をつける。情けないとは思うけれど、怖いものは怖いのだから、仕方ない。用心深く、辺りを見渡しながら、進む。今のところ、大丈夫だ。
目が一つしかないお化けや口から血を流した化け物が、僕らを驚かそうとしてくる。僕はびくっとしながらも、何とか進めている。あと少しで出口かな? こんなにも出口を待ち遠しく思ったのは、生まれて初めてかもしれない。
「ふふっ。かわいいー」
驚かしてきたろくろ首に対して彼女はそんなことを言った。さすがに、『かわいい』は理解できない。彼女の頭の中がどうなっているのか、僕が見たいくらいだ。
廊下の突き当たりに大きな扉が見える。そろそろ終わりかな、と思い、重量のある扉をゆっくりと開けた。
「ひぃっ」
非常に情けない声を出した。扉の上の方から生首がぶら下がっている。怖いというか、びっくりさせられた。こういう驚かし方はずるい。驚かないはずないじゃないか! 僕が心の中で文句を垂れていると、彼女が静かなことに気がついた。さっきまで余裕ぶっていたけれど、とうとう怖くなってしまったのかと思い、振り向くと、複雑そうな表情をしていた。
どうしてそんな顔をしているのかと思い、彼女の全身をよく見ると、彼女の腕が誰かに掴まれていた。僕は誰がそんなことを! と思い、辺りを見渡そうとしたところで、冷静になった。彼女のことを視認できるのは、この世に僕だけ。つまり、彼女の腕に触れている手は、僕の手。
「ご、ごめん。つい......」
とりあえず、僕は手を離した。怖くなって咄嗟に彼女の腕を掴んでしまったようだ。セクハラで訴えられてもおかしくない。後悔の念に駆られる。
「い、いや、私もいきなりだったんで、ちょっとびっくりしただけです。うん。大丈夫!」
大丈夫、そう言った彼女だったが、明らかに動揺しているのが目に見えてわかった。気まずい雰囲気の中お化け屋敷を出た。最後にも驚かされたけれど、僕の意識は完全に栞に向かっていたため、あまりびっくりせずに済んだ。
ジェットコースターを乗り終えた後と同じように、近くにあったベンチに座った。先ほどとは違い、言葉が上手く出てこなかった。
「さっきはその......ごめん」
謝って許してもらえるとは思っていないけれど、今の僕にできるのはこれくらいしかなかった。
「本当に大丈夫なんで......ただびっくりしただけです」
「それでも......君に悪いことをした」
「いやいや! 確かにいきなり掴まれたのはびっくりしたんですけど、嬉しくもあったんですよ、私」
どこから『嬉しい』という感情が生まれてくるのかわからなかったので、先を促すように僕は頷いた。
「ここ数週間の私って、秋太くんに頼ってばっかりだったじゃないですか?」
「そんなことはないと思うけど......」
たまに助けることはあったけれど、頼るというほどのことでもない気がする。誰だってできるような、簡単なことしか僕はしていない。だから、曖昧な反応になってしまった。
彼女はこちらを向き、僕と目を合わせた。
「そんなことあるから!」
彼女の語気は強かった。気圧され、僕は背後に手をついてしまった。
「今日だって私一人じゃ、来ることはできなかったし、この前のかき氷もそう。私一人じゃ、なーんにもできないの。秋太くんが不可能を可能にしてくれてるんだよ?」
「僕だって一人で遊園地には来ないよ。栞が行くから来ただけ」
「それは気持ちの問題でしょ? 私の場合はどう頑張っても、無理なの!」
栞はいつになく、真剣な表情をしていた。最近少しは彼女のことをわかったつもりになっていたが、まだまだわからないことの方が多いようだ。
「だから、私ができないことをさせてくれる、秋太くんには感謝してるよ。多分まだまだ頼ると思う。頼ってばっかりだった私が、初めて頼られたような気持ちになったから、嬉しかったの」
ああ、そういうことか。彼女はどこかで無力感みたいなものを抱いていたのかもしれない。つい先日まで会話すらしたことがなかった僕に、色々頼みごとをするのは、彼女も心苦しさを感じていたのだろう。感じながらも頼れる人は、彼女の世界に僕しかいないのだ。彼女からは見えるのに、誰も彼女のことを見ることはできない。マジックミラーを隔てているように。
そんな彼女が初めて頼られたとなれば、嬉しいものなのだろう。でも、僕が頼った原因がお化け屋敷でびびって腕を掴むって、自然と頬が緩んでしまう。
「え! 何笑ってるの?」
「いやあ、それって頼ったうちに入るのかな? って思ってさ」
「もしかして......入らない?」
彼女は不安そうな顔で見つめてきた。
「入ることにしとこうか。僕は君の腕を掴んだおかげで、お化け屋敷を全速力でかけて、出口に向かわずに済んだんだからね」
「良かったぁ」
ホッと安堵の息をついたようだ。
「じゃあそろそろ次の乗りに行く?」
「そうだね」
僕たちは立ち上がって、別のアトラクションを目指した。
一つ言い忘れていたことがあった。
「そういやさっき頼ってばっかりって言ってたけど、僕も頼らせてもらってるよ」
「え、嘘!?」
「本当だけど」
「いついつ?」
「いつか教えるよ、いつか」
栞は「ケチー」と言って膨れたが、不快感が全く表情から出ていなかった。
僕一人では絶対にできない体験をさせてもらってるという意味では、彼女と出会ってからずっと頼りっぱなしと捉えることもできる。
「おはよ。朝から元気だね」
「逆に旅行当日の朝にそのテンションでいられる秋太くんの頭の中を覗いてみたいよ」
朝はどうも気分が上がらない。理由は単純で朝が得意でないから。特に今日は夏休みに入ってから、一番早く起きた。もっと健康的な生活をすべきなんだろうけど、夏休みという期間だけは許して欲しい。また九月からは早寝早起きの毎日が待っているのだから。たった一ヶ月の間だけ、不健康でもいいじゃないか。そんな風に誰に言うともなく、心の中でつぶやく。
「もしかして、人の頭の中を見れる能力も備わっているのか......?」
僕は少し怯えながら、言った。
「さすがにないよ! 私が使えるのは壁をすり抜けるだけだって!」
栞は「ははっ」と笑いながら、言った。
朝から彼女のテンションは本当に高かった。終始話が途切れることはなく、ある話題が終わったと思えば、すぐに次の話題へ目紛しく変化した。最初の方は眠いせいもあり、相槌を打ち続けて終わった話もあったけれど、彼女のトークを聞いていると徐々に眠気は消えていき、新幹線に乗車した頃には完全に僕も目が冴え、笑い合っていた。
一応、新幹線は指定席で二席取っておいた。僕の分だけでも良かったのかもしれないけれど、栞が座ったシートがどういう扱いになるのかわからなかったので、念には念を、だ。
もしかしたら、見知らぬ人が栞の上に座る可能性だってある。僕にしか見えていないのだから、気づかなくて当然だ。きっとすり抜けて、その人は座るのだろうけど、僕が隣に向かって話しかけると、その人が反応するに決まっている。さすがに周りをあまり気にしない僕でも、隣に座る人に変な目を向けられながら、一時間以上新幹線に乗り続けるほどのメンタルは持ち合わせていなかった。というか、そんなことをしていれば、乗務員さんに通報されかねない。そういった事態は避けなければいけなかった。
窓側に彼女は座っている。基本的に僕の方を向いて喋っているのだけど、綺麗な景色が窓に映ると、無邪気な子どものように窓に張り付いていた。微笑ましかった。
「ねえねえ」
顔を窓から剥がした栞は、こちらを向いた。なぜかわからないけれど、少しだけ、むっ、としているような気がした。
「どうしたの?」
「私のことよく見て欲しいの」
栞が急に訳のわからないことを言い出したので、従って彼女ことを凝視することにした。今日も綺麗な顔をしている。見ているこっちが恥ずかしくなってきた。
見つめ合っている時間が長くなるにつれて、彼女の表情は曇っていった。
「違う! 顔以外も見てよ!」
「え、ああ、わかった」
しびれを切らしたように、栞が言ったので、僕は下から上へ彼女を見た。白いワンピースを着ていた。とてもよく似合っている。既視感があるな......。
「それって、この前買ってあげた服?」
「そう! 気づくの遅すぎるよ」
朝一で会ったときはまだ脳が正常に働いていなかったので仕方ない。似合っているな、とぼんやりと思っただけだ。しかし、今の今まで気づかなかったのは、どうかと思う。自責の念にかられる。
「ごめん。すごく似合ってるよ。直接言うのは恥ずかしいけど、綺麗だよ」
いつもなら心の中でつぶやくだけにするような柄にもないことを言ったのは、彼女に対して負い目があるからかもしれない。
「恥ずかしがりながらも言ってくれて、ありがとう。直接言われると、私も恥ずかしくなりました」
僕たちは小さく笑った。
もうあと十分ほどで到着するタイミングで、僕は彼女に渡しておきたいものがあったことを思い出した。
カバンの中からそれを取り出し、前の座席についているテーブルを出して、そこに置いた。
「なにこれ? プレゼント?」
「プレゼントっていうほどの物でもないんだけど、スマホ」
「え!」
「まあさすがに契約とかは僕一人じゃできなかったから、中古のやつなんだけどね」
「電話できるの?」
「契約はしてないから外では使えないんだけど、Wi-Fi環境が整ってるところだったら、僕らが離れていても連絡が取り合えるよ」
僕が言うと、彼女の表情はパッと明るくなった。
「どうして今まで思いつかなかったんだろ! 秋太くん天才!」
「今まで思いつかなかったことが申し訳ないくらいだよ。最近ならフリーWi-Fiスポットも増えてるし、使えるところ多いと思う」
「ありがと!」
そう言った栞は、カバンを探り始めた。そして、僕がさっきしたように、テーブルの上に取り出した物を置いた。
「イヤフォン?」
「正解! イヤフォンだよ」
僕が状況を理解できず、首を傾げていると彼女はピンク色のイヤフォンを手に取り、僕に手渡してきた。
「くれるの?」
「うん。アトラクションの待ち時間絶対喋るでしょ? でもさすがにずっと誰もいない場所を見ながら、話してたら周りの人を困惑させちゃうと思うの」
「確かに」
「だからイヤフォンで通話してるように見せかければ、いいんじゃないかと思って持ってきた!」
スマホを手に持って話すのもありだけど、何時間も腕を上げた状態をキープするのは疲れるだろう。その点、イヤフォンであれば耳につけておけばいいだけなので、疲労することはないはずだ。
「......盗んだやつ?」
「違う! これはちゃんと私が家から持ってきたやつです! あ、ちゃんと綺麗にしてあるので、ご心配なく!」
「ごめんごめん。ありがたく、使わせてもらうよ」
「どうぞどうぞ」
彼女の言う通り、何日も使っていないはずのイヤフォンらしかったが、新品かと思うくらい綺麗だった。昨日のうちに色々してくれたんだろうな。
そんな話をしているうちに駅に到着した。僕たちは忘れ物がないかを確認し、降車した。
新幹線が停まるくらいなのでそこそこ大きな駅で、一度離れれば再び会うことが叶わないようなそんな気がした。彼女は「うわぁー」と辺りを見渡している。突っ立ってても邪魔になるので、改札を目指して歩き始めた。
「迷子にならないように手でも繋いじゃう?」
彼女はいたって普通に、平然と言った。対照的に僕は心を乱されるわけだけど。
「いやそこまでしなくても大丈夫でしょ。多分」
動揺を隠すためいつもよりぶっきらぼうに言った。
「なんか断られた気分です」
彼女は前を向き、むすっとした。
「繋ぎたくないからそう言ったわけじゃなくて......なんていうか......」
「ふふっ。別にそんなことで怒ってないよ。まだ手を繋ぐのは早いかー。手繋ぎデートとか憧れるんだけどなぁ」
彼女は笑顔に戻り、さっきのは本気で怒っていたわけではなく、僕をからかっただけだとわかった。
「もう少しだけ待って欲しい」
「もう少しって?」
「今月中」
「わかった。待つね」
僕の前を歩く彼女は改札のドアをスッとすり抜けた。その後を切符を入れた僕は追った。
腕時計を確認すると、八時四十分になろうとしていた。僕たちが今日行く遊園地まで徒歩十分くらいで着くらしい。九時開園なのでちょうど良い時間に着きそうだ。
スマホの地図アプリで遊園地の名前を入れ、ルート案内を開始した。栞は「すごー」と言って、驚いていた。
初めての土地なので、どの方角を見ても、面白い。見たことも聞いたこともない名前のスーパーだったり、会社だったり、学校だったり、新鮮さがあって非日常を味わっている。たまに僕もよく知るコンビニなんかもあって、こんなところにもあるんだな、と感慨深くなる。
「何か買っておく物とかない?」
遊園地まであと五分くらい。入園する前に買う物はないか、訊いておいた。
「んー。飲み物だけ欲しいかなぁ」
「了解」
僕らが信号が変わるのを待っている大きな交差点を渡った先に、コンビニを発見した。横断歩道を渡り、入店すると冷気が僕の肌に触れる。心地いい。
僕も持ってきていたお茶が残りわずかとなっていたので、麦茶を買うことにした。彼女はサイダーを選んでいた。二本分の会計を済ませ、店を出ると、太陽の熱を全身で感じることとなり、まるで天国から地獄へ落とされたような気持ちになった。
結局九時過ぎに到着した。途中でコンビニ寄ったのと、土地鑑がないため少し予定よりも時間がかかってしまった。すでに入口付近には大勢の人がいた。僕は一枚分のチケットを買い、列の最後尾で番が来るのを待った。
「家族連れが多いね」
「夏休みだしね」
お盆は過ぎているけれど、夏休みに変わりはないので当然人は多い。アトラクションもすんなり乗ることはできないだろう。
「秋太くんも行ったことないんだよね?」
どこに行ったことないのかを詳しく栞は言わなかったけれど、遊園地のことだと解釈して言うことにした。
「うん。僕の記憶が正しければだけど」
「ジェットコースターってどんな感じなのかなっ」
「怖いんじゃない? 知らないけど」
「ふふっ。楽しみだね」
僕たちの番がやって来て、入園した。彼女はまたまたスッと通り抜けた。その能力、僕も欲しいな。
園内に入ると、一箇所に集まっていた人が一斉に散っていく。僕たちも例に漏れず、歩き始めた。
「何から乗る!?」
「僕はなんでもいいから、決めていいよ」
言うと、栞はパンフレットを見ながら考え始めた。こっちもいいとか、あっちもいいとか、そんなことを言いながら真剣に考えているようだった。もしかしたら、彼女と出会ってから一番と言ってもいいくらい真剣な眼差しで見ていた。
「決めた! まずはこれにしよ!」
彼女が指差したのはこの遊園地の目玉とも言えるジェットコースターだった。アトラクションの軽い説明文を読むと、高さ九十メートルから急降下するらしい。全長も二キロを超えており、読んだだけで寒気立つ。
園内マップを見なくとも、ジェットコースター乗り場の位置は大体把握できた。僕たちはすでに何十人も待っている列の最後尾に並ぶことにした。現在の待ち時間は十五分ほどらしい。これがお昼を過ぎたあたりになれば、もっと待ち時間が伸びるんだろうな。今は開園したばかりなので、マシな方だろう。
栞からさっき貰ったイヤフォンを片耳につけた。
「おっ、早速活用してくれてるね」
「せっかくだしね」
「なんかあげたものを身につけてくれてると嬉しいものだねぇ」
「僕も前に買ってあげた服を着てもらえて嬉しいよ」
「最初気づかなかったけどねー」
「それは、マジでごめん」
話していると、あっという間に時間が過ぎた。今走っているコースターが帰ってきたら、僕らの番になる。遊園地に来た思い出がないので、当然ジェットコースターに乗るのも初だ。ちょっと緊張してきた。彼女の方は怖がるそぶりを一切見せていなかった。本当に楽しみにしていることが感じ取れた。
「さっきはありがとう」
コースターが上っている最中に栞は言った。
「彼女扱いしてくれて、嬉しかったよ」
僕はチケットを二枚分スタッフの人に出した。一枚は僕の、もう一枚は彼女の。僕の隣は空けてもらう必要があったので、僕以外に見えていない彼女のことをどう説明しようか迷った。ただチケットを二枚用意するだけじゃ断れると思い、少しずるいが、亡くなった彼女と来ている気分を味わいたい、という半分嘘で半分本当のことを言い、感情に訴えかけた。何とか上手くいき、僕の隣は空けてもらえることになった。
「一応今は彼氏ってことになってるし」
僕が言うと、彼女は微笑んだ。
「じゃあ一つ、彼氏らしいことをお願いしてもいいかな?」
「何を?」
「私今、めちゃくちゃ怖いから手握ってて欲しい」
笑顔は消え、震え声で彼女は言った。僕はいつも彼女が見せるような笑みを浮かべ、優しく手を重ねた。こんなにも早く手をつなぐ機会が訪れてしまうとはな。これを手をつないだとして、カウントしていいものなのかわからないけれど。
彼女の悲鳴と共に、コースターは頂上から降下した。
「無理無理無理無理!」
ジェットコースターから降車した僕たちは、近くのベンチで休憩していた。どうやら栞は絶叫系が苦手なタイプのようだ。今まで遊園地に来たことがなかったので、それもわからなかったのだろう。
水を飲みながら、「うぇっ」と彼女はしかめっ面をしながら言う。
「僕は結構楽しかったけどな」
「なんで? ありえないんだけど!」
恐怖からか普段の彼女の口調よりフランクになっている気がした。
「次はフリーフォールにでも乗る?」
「怒るよ?」
傍から見れば、カップルのように見えるやりとりをしているのかもしれない。見られることはないけれど。
「冗談だよ」
「怒ったので、次も私が行きたいところに付きあってもらいます」
「全然構わないよ」
おそらく、コーヒーカップやメリーゴーランドだろう。どのアトラクションでも僕は全く恐怖心はないはずなので、彼女の後をスタスタついていく。
何気ない会話をしながら、少し歩くと、彼女がどこへ行くつもりなのか察した。
「ごめん。さっきのことは謝るから、別のアトラクションにしない?」
「なにぃ? 怖いのぉ?」
栞ついていくと、僕はお化け屋敷の前に立たされていた。お化け屋敷に入ったことはないけれど、僕は苦手な方だろう。ホラー映画が苦手なのだから、多分。
できれば、避けたい。避けたいが、彼女はニヤニヤ笑って、そうさせてくれそうにない。今だけ彼女のことが悪魔に見える。
「うん。怖い。だから、やめよう」
「そこは見栄を張ってでも、先導するところじゃないの? 彼氏なら」
「普通はそうかもしれない。でも、僕たちの関係は普通じゃないだろ? だから今回の彼氏らしい行動に関しても、僕たちの場合、普通っていう言葉は適用されないと思うんだ。例外だよ、例外」
「つべこべ言わずに行こ」
そう言って、栞は僕の手を掴んだ。渋々入ることになってしまった。絶叫しないように、頑張ろう......。
「楽しいねー」
暗い中を彼女は怖がるそぶりを一切見せずに、歩いていく。僕はその後をつける。情けないとは思うけれど、怖いものは怖いのだから、仕方ない。用心深く、辺りを見渡しながら、進む。今のところ、大丈夫だ。
目が一つしかないお化けや口から血を流した化け物が、僕らを驚かそうとしてくる。僕はびくっとしながらも、何とか進めている。あと少しで出口かな? こんなにも出口を待ち遠しく思ったのは、生まれて初めてかもしれない。
「ふふっ。かわいいー」
驚かしてきたろくろ首に対して彼女はそんなことを言った。さすがに、『かわいい』は理解できない。彼女の頭の中がどうなっているのか、僕が見たいくらいだ。
廊下の突き当たりに大きな扉が見える。そろそろ終わりかな、と思い、重量のある扉をゆっくりと開けた。
「ひぃっ」
非常に情けない声を出した。扉の上の方から生首がぶら下がっている。怖いというか、びっくりさせられた。こういう驚かし方はずるい。驚かないはずないじゃないか! 僕が心の中で文句を垂れていると、彼女が静かなことに気がついた。さっきまで余裕ぶっていたけれど、とうとう怖くなってしまったのかと思い、振り向くと、複雑そうな表情をしていた。
どうしてそんな顔をしているのかと思い、彼女の全身をよく見ると、彼女の腕が誰かに掴まれていた。僕は誰がそんなことを! と思い、辺りを見渡そうとしたところで、冷静になった。彼女のことを視認できるのは、この世に僕だけ。つまり、彼女の腕に触れている手は、僕の手。
「ご、ごめん。つい......」
とりあえず、僕は手を離した。怖くなって咄嗟に彼女の腕を掴んでしまったようだ。セクハラで訴えられてもおかしくない。後悔の念に駆られる。
「い、いや、私もいきなりだったんで、ちょっとびっくりしただけです。うん。大丈夫!」
大丈夫、そう言った彼女だったが、明らかに動揺しているのが目に見えてわかった。気まずい雰囲気の中お化け屋敷を出た。最後にも驚かされたけれど、僕の意識は完全に栞に向かっていたため、あまりびっくりせずに済んだ。
ジェットコースターを乗り終えた後と同じように、近くにあったベンチに座った。先ほどとは違い、言葉が上手く出てこなかった。
「さっきはその......ごめん」
謝って許してもらえるとは思っていないけれど、今の僕にできるのはこれくらいしかなかった。
「本当に大丈夫なんで......ただびっくりしただけです」
「それでも......君に悪いことをした」
「いやいや! 確かにいきなり掴まれたのはびっくりしたんですけど、嬉しくもあったんですよ、私」
どこから『嬉しい』という感情が生まれてくるのかわからなかったので、先を促すように僕は頷いた。
「ここ数週間の私って、秋太くんに頼ってばっかりだったじゃないですか?」
「そんなことはないと思うけど......」
たまに助けることはあったけれど、頼るというほどのことでもない気がする。誰だってできるような、簡単なことしか僕はしていない。だから、曖昧な反応になってしまった。
彼女はこちらを向き、僕と目を合わせた。
「そんなことあるから!」
彼女の語気は強かった。気圧され、僕は背後に手をついてしまった。
「今日だって私一人じゃ、来ることはできなかったし、この前のかき氷もそう。私一人じゃ、なーんにもできないの。秋太くんが不可能を可能にしてくれてるんだよ?」
「僕だって一人で遊園地には来ないよ。栞が行くから来ただけ」
「それは気持ちの問題でしょ? 私の場合はどう頑張っても、無理なの!」
栞はいつになく、真剣な表情をしていた。最近少しは彼女のことをわかったつもりになっていたが、まだまだわからないことの方が多いようだ。
「だから、私ができないことをさせてくれる、秋太くんには感謝してるよ。多分まだまだ頼ると思う。頼ってばっかりだった私が、初めて頼られたような気持ちになったから、嬉しかったの」
ああ、そういうことか。彼女はどこかで無力感みたいなものを抱いていたのかもしれない。つい先日まで会話すらしたことがなかった僕に、色々頼みごとをするのは、彼女も心苦しさを感じていたのだろう。感じながらも頼れる人は、彼女の世界に僕しかいないのだ。彼女からは見えるのに、誰も彼女のことを見ることはできない。マジックミラーを隔てているように。
そんな彼女が初めて頼られたとなれば、嬉しいものなのだろう。でも、僕が頼った原因がお化け屋敷でびびって腕を掴むって、自然と頬が緩んでしまう。
「え! 何笑ってるの?」
「いやあ、それって頼ったうちに入るのかな? って思ってさ」
「もしかして......入らない?」
彼女は不安そうな顔で見つめてきた。
「入ることにしとこうか。僕は君の腕を掴んだおかげで、お化け屋敷を全速力でかけて、出口に向かわずに済んだんだからね」
「良かったぁ」
ホッと安堵の息をついたようだ。
「じゃあそろそろ次の乗りに行く?」
「そうだね」
僕たちは立ち上がって、別のアトラクションを目指した。
一つ言い忘れていたことがあった。
「そういやさっき頼ってばっかりって言ってたけど、僕も頼らせてもらってるよ」
「え、嘘!?」
「本当だけど」
「いついつ?」
「いつか教えるよ、いつか」
栞は「ケチー」と言って膨れたが、不快感が全く表情から出ていなかった。
僕一人では絶対にできない体験をさせてもらってるという意味では、彼女と出会ってからずっと頼りっぱなしと捉えることもできる。