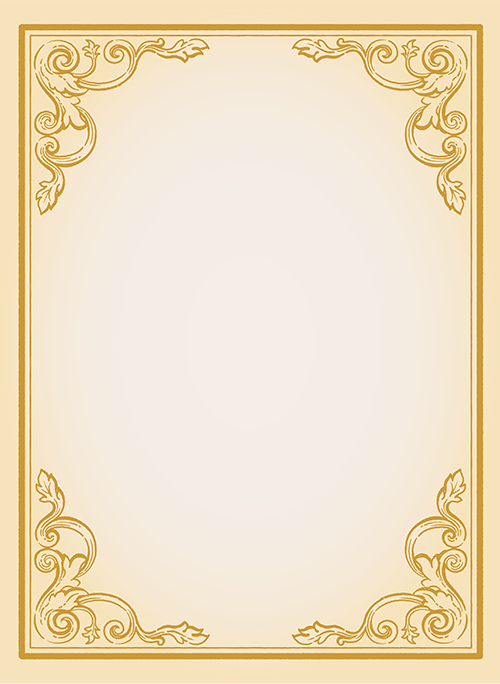八月二十六日。二十六日目にして初めて栞が家に泊まりに来ることになった。たった二十六日と捉えることもできるが、濃い日々を過ごす毎日からすれば、そんな風に捉えることはできなかった。やっと、という感覚の方が強い。
「あ、一回私の家に寄ってもいい? 部屋着取りに行きたい」
僕の服を貸すこともできたが、サイズの問題もあったので、一度彼女の実家に行くことにした。彼女に先導してもらうと、すぐに着いた。駅から徒歩十分もかからないところにあった。きちんと表札には、『柏木』と書かれている。
「じゃあ、ちょっと待っててね」
扉をすり抜け、部屋着を取りに彼女は中へ入っていった。数分後、浴衣から私服に変わった栞が出てきた。手さげを持っており、そこに部屋着を入れているのだろう。
「お待たせ。行こっか」
用が済んだので、彼女の家を後にする。
たまに走行音が聞こえるくらいで、とても静かだった。僕と栞の声だけが響く。人とすれ違うこともほとんどなかった。
僕はこの道を通るたびに、彼女のことを思い出すことになるのかもしれない。今まで彼女と一緒に訪れた場所へ行くと、彼女のことを想起してしまうに違いない。そのたびに、僕の中に形容しがたい感情が生まれるだろう。それを承知の上で、彼女と残り期間を過ごすことを僕は決めたのだ。自分の選択が間違いでなかったことを証明したい。
自宅につき、玄関に入ると、母さんがいた。
「おかえり」
「ただいま」
栞は「おじゃまします」と言って、お辞儀をした。彼女を歓迎するかのように、母さんが微笑んだように見えたのは、きっと気のせい。
とりあえず、僕の部屋に向かった。
「何回も来てるはずなのに、なんかちょっと緊張しちゃう」
言いながら栞は、手さげを床に置いた。
栞が来ることがわかっていれば、もう少し部屋を片付けておいたのになあ。
「お風呂先に入ってきなよ。母さんはもう入ってるようだったし、風呂場で遭遇する最悪の事態にはならないだろうし」
「それじゃあ、お言葉に甘えて」
「階段降りて、リビングの前を通り過ぎた突き当たりにあるから」
「わかった」
僕は一人になった。彼女が言う通り、いつもは何とも思わなかったのに、今日は栞がいることに変な緊張が走る。部屋に一人になったことで、肩の力が抜けたのか、自然とホッと一息ついた。変に力が入っていたようだ。ここ数日、ずっと気が張っていたこともあるからだろう。
栞が帰ってくる前に少しくらい片付けておこうと思い、軽くなった腰を上げた。
「何する?」
「寝ないの?」
「えー、せっかくだし、もう少しおしゃべりしようよ」
栞の調子もすっかり元通りだ。僕がお風呂から上がると、彼女は漫画を読んで待っていてくれた。
色々あって疲れたし、今日は寝るつもりだったが、彼女は寝かせてくれなそうだ。
「何について話すの?」
「やっぱりこういうときは、恋バナ?」
「そういうのは友達同士でやるもんじゃないの? 彼女とする話ではないと思うけど」
「改めて彼女って言われると、ドキドキしちゃうね」
「今までも言ってたと思うけど」
「今までとは意味が違うよ」
そう言った彼女の頬が少し赤い気がしたけど、それはお風呂上がりのせいだろうか。
「恋バナって言っても、僕の話は全てしたよ。初恋の話もしたんだから」
「そっかー」
「栞はないの? そういう話」
「私はないよ。男の子の家に入るのも死んじゃった後が初めてなんだから」
そういや、出会ったときそんなこと言ってたな。あのときは信じられなかったけれど、今は本当だろう、と思える。
「じゃあ恋バナはなしだね」
「そうっぽいねー。話題を探すと、出ないもんだねえ」
「確かに。なんか会話って自然と成り立ってるよね」
「うんうん」
栞は、ふわぁ、と大きな欠伸をした。
「眠いの?」
「ちょっとだけ」
「最近眠れてた?」
「あんまり、かな」
理由は訊かなかった。僕もここ数日は眠れても、快眠とはいかなかった。疲れがとれない、質の低い睡眠だった。栞も同じような感じだろう。
「やっぱり、布団に入らない? 入りながらでも喋れるんだし」
「そうだね」
僕は敷布団を部屋に持ってきて、敷いた。彼女は、一緒にベッドで寝ようよ、と提案してきたが、僕の理性がそれを拒んだのと、単純にシングルベッドを二人で使うのは狭すぎるという理由から遠慮しておいた。
彼女にはベッドで寝てもらうことにし、僕は床で寝る。
消灯すると、静寂が訪れた。
布団に入ると、眠気は一気に押し寄せてきた。わだかまりも解消されたことで、今夜はぐっすり眠れるはずだ。
「秋太くん、まだ起きてる?」
「起きてるよ。寝ちゃいそうだけど」
「私も布団に入ったら、すっごい眠くなってきちゃった」
冷房は数時間後に消えるように、設定してあるのでひんやりして気持ちがいい。寝るにはベストコンディションだ。
「寝た方がいいよ。明日、何するか考えといて」
「うん。おやすみ」
「おやすみ」
僕は目を瞑り、視界をシャットダウンする。彼女の寝息を聞く前に、眠りに落ちた。
目を覚ますと、一瞬自分がどこで寝ているのかわからなかった。普段目覚めたときに見える光景と少し違うからだ。徐々に意識が覚醒すると、昨夜の出来事が思い起こされ、状況を把握する。
夜の静けさと打って変わって、野鳥の元気な鳴き声が聞こえてくる。冷房はすでに切れており、少し汗ばんでいる。この不快感をシャワーで洗い流したい。
ベッドの上の彼女は、顔をこちらに向け、眠っている。寝顔も綺麗だった。
「......起こさない方がいいかな」
こんなに気持ち良さそうに寝ているのを邪魔するわけにいかないと思い、僕はそっと部屋の扉を開け、可能な限り音を立てないように一階へ降りた。母さんは出かけているようで、リビングにいなかった。
用を足し、洗面所で歯を磨く。僕が鏡を見て、歯を磨いていると、階段が軋む音が聞こえてきた。ここまで聞こえるということは、それなりの勢いがある。
洗面所の扉が勢いよく開かれた。そこには、息を切らした、栞が立っていた。
「おはよ」
「よかったぁ」
彼女は腰が抜けたように座り込んでしまった。
「朝から元気だね。どうしたの?」
歯ブラシを口から抜き、話しかけた。
「どうしたの? じゃないよ! 起きたら秋太くんいなかったから、私を残してどこかに行っちゃったのかと思った」
「ああ。ごめんごめん。気持ち良さそうに寝てたから、起こしたら悪いかと思って」
「えっ。そんなに気持ち良さそうだった?」
「うん。至福の表情してた」
「恥ずかしい......というか、私の寝顔見ないでください」
彼女は、ふんっ、と鼻を鳴らし腕組みをした。
「同じ部屋で寝てて、それは無理があると思うんだけど」
「それでもです!」
「無茶だなぁ。じゃあ、明日からは僕より早く起きたら?」
「その手があったか! 私より早く起きないでね、明日から」
それも無茶なお願いなんだけど。僕が起きる時間を調整するのではなく、彼女の方が調整して欲しいところ。
「私も歯磨きしたい」
僕は歯ブラシを口で咥え、洗面台の下にある収納スペースを探った。この辺に使い捨て歯ブラシがあった気がする。
「あった。これ」
「ありがと!」
歯磨き粉を貸し、彼女も鏡を見ながら歯を磨く。
「秋太くん、寝癖すごいね」
「ほっといてくれ。逆に栞はほとんど乱れてないな」
「寝相には自信があるので」
彼女は踏ん反り返った。そんなことで威張られても......。
「なんだかこうしてると、夫婦みたいだよね」
「ゴホッ」
僕は勢いよく吐き出した。ちゃんと洗面器の中に収まっている。セーフ。
「だ、大丈夫!?」
夫婦みたい、と言った栞の発言に自分が想像以上に動揺してしまった。
「大丈夫。ちょっとむせちゃっただけだから」
「気をつけてねー」
誰のせいでこうなったと思ってるんだ。昨日も祭り会場で似たようなことを感じたなぁ。別に彼女に非があるわけではないけれど、ナチュラルに僕を動揺させる発言をするから困る。
栞よりも早くから磨いていた僕が先に口をゆすいだ。顔を洗い、髪も濡らし、交代する。
長い髪を耳にかけ、口に水を含んだ後、口内に行き渡らせている姿につい見入ってしまった。一連の動作に一秒たりとも無駄はない。目が離せなかった。
「ねえ、私にもタオル取ってくれない?」
「あ、わかった」
話しかけられたことで、僕の意識は現実に戻ってきた。一枚タオルを取って、彼女に渡す。
「私の気のせいかもしれないけど、今、私のこと見てた?」
気のせいではなく、事実。しかし、そんなこと言えるはずもなく、やんわり否定する。
「気のせいだと思うよ」
「そうなのかなー」
言いながら拭く栞は、ニヤニヤしていた。きっとバレてるだろうな、と思った。
母さんがいないので、二人でリビングで朝食をとった。何気ない話をした。数週間前と変わらない、何気ない話だ。そんな話をしているうちに、一日が終わった。
彼女と出会って二十九日目。着々と別れのときが近づいてくる。意識しまいと期限のことを頭の隅に追いやろうとするが、上手くいかず、逆に強く意識してしまう。逆効果だった。
昨日は二人で映画を観にいった。僕の部屋で観たことはあったが、映画館で観るのは初めてだった。切ない恋愛映画を観たが、どうしてそのジャンルをチョイスをしてしまったのか、今になって悔やまれる。その映画では病気のヒロインが最後は亡くなってしまい、彼氏と別れることになってしまうものだった。別れ方は違うが、僕たちも似たような感じだ。
観終わった後、栞は、「秋太くんはあんな感じで号泣しないでね。私を笑顔で見送ってね」と言った。自信はなかったけれど、栞がそれを望むなら頷くしかなかった。
別れを経験したことがなかった僕でも、こんなにも好きになってしまった彼女と別れることが辛いことくらいもうわかっている。ただその程度がどれくらいのものなのかはまだわからない。僕がどれだけ引きずるかも定かではない。でも、そんな一週間やそこらで立ち直りたくはないな、と思う。もっと時間をかけて、何ヶ月、何年もかけて、彼女との別れを乗り越えたい。
「秋太!」
僕の部屋でトランプをしているとき、栞が言った。
普段と違う呼ばれ方をして、少し戸惑う。
「どうしたの、急に」
「昨日の映画観て、なんかいいなーって思ったの。ダメ?」
映画で出てきた二人は、互いのことを呼び捨てで呼んでいた。それに感化されたのだろう。
「全然。むしろ、そっちの方が嬉しい」
「やったー。これから、秋太って呼ぶね」
新しい呼び方にこれから先慣れることはない。そのことに寂しさを覚えながら、二十九日目が終了した。
「あ、一回私の家に寄ってもいい? 部屋着取りに行きたい」
僕の服を貸すこともできたが、サイズの問題もあったので、一度彼女の実家に行くことにした。彼女に先導してもらうと、すぐに着いた。駅から徒歩十分もかからないところにあった。きちんと表札には、『柏木』と書かれている。
「じゃあ、ちょっと待っててね」
扉をすり抜け、部屋着を取りに彼女は中へ入っていった。数分後、浴衣から私服に変わった栞が出てきた。手さげを持っており、そこに部屋着を入れているのだろう。
「お待たせ。行こっか」
用が済んだので、彼女の家を後にする。
たまに走行音が聞こえるくらいで、とても静かだった。僕と栞の声だけが響く。人とすれ違うこともほとんどなかった。
僕はこの道を通るたびに、彼女のことを思い出すことになるのかもしれない。今まで彼女と一緒に訪れた場所へ行くと、彼女のことを想起してしまうに違いない。そのたびに、僕の中に形容しがたい感情が生まれるだろう。それを承知の上で、彼女と残り期間を過ごすことを僕は決めたのだ。自分の選択が間違いでなかったことを証明したい。
自宅につき、玄関に入ると、母さんがいた。
「おかえり」
「ただいま」
栞は「おじゃまします」と言って、お辞儀をした。彼女を歓迎するかのように、母さんが微笑んだように見えたのは、きっと気のせい。
とりあえず、僕の部屋に向かった。
「何回も来てるはずなのに、なんかちょっと緊張しちゃう」
言いながら栞は、手さげを床に置いた。
栞が来ることがわかっていれば、もう少し部屋を片付けておいたのになあ。
「お風呂先に入ってきなよ。母さんはもう入ってるようだったし、風呂場で遭遇する最悪の事態にはならないだろうし」
「それじゃあ、お言葉に甘えて」
「階段降りて、リビングの前を通り過ぎた突き当たりにあるから」
「わかった」
僕は一人になった。彼女が言う通り、いつもは何とも思わなかったのに、今日は栞がいることに変な緊張が走る。部屋に一人になったことで、肩の力が抜けたのか、自然とホッと一息ついた。変に力が入っていたようだ。ここ数日、ずっと気が張っていたこともあるからだろう。
栞が帰ってくる前に少しくらい片付けておこうと思い、軽くなった腰を上げた。
「何する?」
「寝ないの?」
「えー、せっかくだし、もう少しおしゃべりしようよ」
栞の調子もすっかり元通りだ。僕がお風呂から上がると、彼女は漫画を読んで待っていてくれた。
色々あって疲れたし、今日は寝るつもりだったが、彼女は寝かせてくれなそうだ。
「何について話すの?」
「やっぱりこういうときは、恋バナ?」
「そういうのは友達同士でやるもんじゃないの? 彼女とする話ではないと思うけど」
「改めて彼女って言われると、ドキドキしちゃうね」
「今までも言ってたと思うけど」
「今までとは意味が違うよ」
そう言った彼女の頬が少し赤い気がしたけど、それはお風呂上がりのせいだろうか。
「恋バナって言っても、僕の話は全てしたよ。初恋の話もしたんだから」
「そっかー」
「栞はないの? そういう話」
「私はないよ。男の子の家に入るのも死んじゃった後が初めてなんだから」
そういや、出会ったときそんなこと言ってたな。あのときは信じられなかったけれど、今は本当だろう、と思える。
「じゃあ恋バナはなしだね」
「そうっぽいねー。話題を探すと、出ないもんだねえ」
「確かに。なんか会話って自然と成り立ってるよね」
「うんうん」
栞は、ふわぁ、と大きな欠伸をした。
「眠いの?」
「ちょっとだけ」
「最近眠れてた?」
「あんまり、かな」
理由は訊かなかった。僕もここ数日は眠れても、快眠とはいかなかった。疲れがとれない、質の低い睡眠だった。栞も同じような感じだろう。
「やっぱり、布団に入らない? 入りながらでも喋れるんだし」
「そうだね」
僕は敷布団を部屋に持ってきて、敷いた。彼女は、一緒にベッドで寝ようよ、と提案してきたが、僕の理性がそれを拒んだのと、単純にシングルベッドを二人で使うのは狭すぎるという理由から遠慮しておいた。
彼女にはベッドで寝てもらうことにし、僕は床で寝る。
消灯すると、静寂が訪れた。
布団に入ると、眠気は一気に押し寄せてきた。わだかまりも解消されたことで、今夜はぐっすり眠れるはずだ。
「秋太くん、まだ起きてる?」
「起きてるよ。寝ちゃいそうだけど」
「私も布団に入ったら、すっごい眠くなってきちゃった」
冷房は数時間後に消えるように、設定してあるのでひんやりして気持ちがいい。寝るにはベストコンディションだ。
「寝た方がいいよ。明日、何するか考えといて」
「うん。おやすみ」
「おやすみ」
僕は目を瞑り、視界をシャットダウンする。彼女の寝息を聞く前に、眠りに落ちた。
目を覚ますと、一瞬自分がどこで寝ているのかわからなかった。普段目覚めたときに見える光景と少し違うからだ。徐々に意識が覚醒すると、昨夜の出来事が思い起こされ、状況を把握する。
夜の静けさと打って変わって、野鳥の元気な鳴き声が聞こえてくる。冷房はすでに切れており、少し汗ばんでいる。この不快感をシャワーで洗い流したい。
ベッドの上の彼女は、顔をこちらに向け、眠っている。寝顔も綺麗だった。
「......起こさない方がいいかな」
こんなに気持ち良さそうに寝ているのを邪魔するわけにいかないと思い、僕はそっと部屋の扉を開け、可能な限り音を立てないように一階へ降りた。母さんは出かけているようで、リビングにいなかった。
用を足し、洗面所で歯を磨く。僕が鏡を見て、歯を磨いていると、階段が軋む音が聞こえてきた。ここまで聞こえるということは、それなりの勢いがある。
洗面所の扉が勢いよく開かれた。そこには、息を切らした、栞が立っていた。
「おはよ」
「よかったぁ」
彼女は腰が抜けたように座り込んでしまった。
「朝から元気だね。どうしたの?」
歯ブラシを口から抜き、話しかけた。
「どうしたの? じゃないよ! 起きたら秋太くんいなかったから、私を残してどこかに行っちゃったのかと思った」
「ああ。ごめんごめん。気持ち良さそうに寝てたから、起こしたら悪いかと思って」
「えっ。そんなに気持ち良さそうだった?」
「うん。至福の表情してた」
「恥ずかしい......というか、私の寝顔見ないでください」
彼女は、ふんっ、と鼻を鳴らし腕組みをした。
「同じ部屋で寝てて、それは無理があると思うんだけど」
「それでもです!」
「無茶だなぁ。じゃあ、明日からは僕より早く起きたら?」
「その手があったか! 私より早く起きないでね、明日から」
それも無茶なお願いなんだけど。僕が起きる時間を調整するのではなく、彼女の方が調整して欲しいところ。
「私も歯磨きしたい」
僕は歯ブラシを口で咥え、洗面台の下にある収納スペースを探った。この辺に使い捨て歯ブラシがあった気がする。
「あった。これ」
「ありがと!」
歯磨き粉を貸し、彼女も鏡を見ながら歯を磨く。
「秋太くん、寝癖すごいね」
「ほっといてくれ。逆に栞はほとんど乱れてないな」
「寝相には自信があるので」
彼女は踏ん反り返った。そんなことで威張られても......。
「なんだかこうしてると、夫婦みたいだよね」
「ゴホッ」
僕は勢いよく吐き出した。ちゃんと洗面器の中に収まっている。セーフ。
「だ、大丈夫!?」
夫婦みたい、と言った栞の発言に自分が想像以上に動揺してしまった。
「大丈夫。ちょっとむせちゃっただけだから」
「気をつけてねー」
誰のせいでこうなったと思ってるんだ。昨日も祭り会場で似たようなことを感じたなぁ。別に彼女に非があるわけではないけれど、ナチュラルに僕を動揺させる発言をするから困る。
栞よりも早くから磨いていた僕が先に口をゆすいだ。顔を洗い、髪も濡らし、交代する。
長い髪を耳にかけ、口に水を含んだ後、口内に行き渡らせている姿につい見入ってしまった。一連の動作に一秒たりとも無駄はない。目が離せなかった。
「ねえ、私にもタオル取ってくれない?」
「あ、わかった」
話しかけられたことで、僕の意識は現実に戻ってきた。一枚タオルを取って、彼女に渡す。
「私の気のせいかもしれないけど、今、私のこと見てた?」
気のせいではなく、事実。しかし、そんなこと言えるはずもなく、やんわり否定する。
「気のせいだと思うよ」
「そうなのかなー」
言いながら拭く栞は、ニヤニヤしていた。きっとバレてるだろうな、と思った。
母さんがいないので、二人でリビングで朝食をとった。何気ない話をした。数週間前と変わらない、何気ない話だ。そんな話をしているうちに、一日が終わった。
彼女と出会って二十九日目。着々と別れのときが近づいてくる。意識しまいと期限のことを頭の隅に追いやろうとするが、上手くいかず、逆に強く意識してしまう。逆効果だった。
昨日は二人で映画を観にいった。僕の部屋で観たことはあったが、映画館で観るのは初めてだった。切ない恋愛映画を観たが、どうしてそのジャンルをチョイスをしてしまったのか、今になって悔やまれる。その映画では病気のヒロインが最後は亡くなってしまい、彼氏と別れることになってしまうものだった。別れ方は違うが、僕たちも似たような感じだ。
観終わった後、栞は、「秋太くんはあんな感じで号泣しないでね。私を笑顔で見送ってね」と言った。自信はなかったけれど、栞がそれを望むなら頷くしかなかった。
別れを経験したことがなかった僕でも、こんなにも好きになってしまった彼女と別れることが辛いことくらいもうわかっている。ただその程度がどれくらいのものなのかはまだわからない。僕がどれだけ引きずるかも定かではない。でも、そんな一週間やそこらで立ち直りたくはないな、と思う。もっと時間をかけて、何ヶ月、何年もかけて、彼女との別れを乗り越えたい。
「秋太!」
僕の部屋でトランプをしているとき、栞が言った。
普段と違う呼ばれ方をして、少し戸惑う。
「どうしたの、急に」
「昨日の映画観て、なんかいいなーって思ったの。ダメ?」
映画で出てきた二人は、互いのことを呼び捨てで呼んでいた。それに感化されたのだろう。
「全然。むしろ、そっちの方が嬉しい」
「やったー。これから、秋太って呼ぶね」
新しい呼び方にこれから先慣れることはない。そのことに寂しさを覚えながら、二十九日目が終了した。