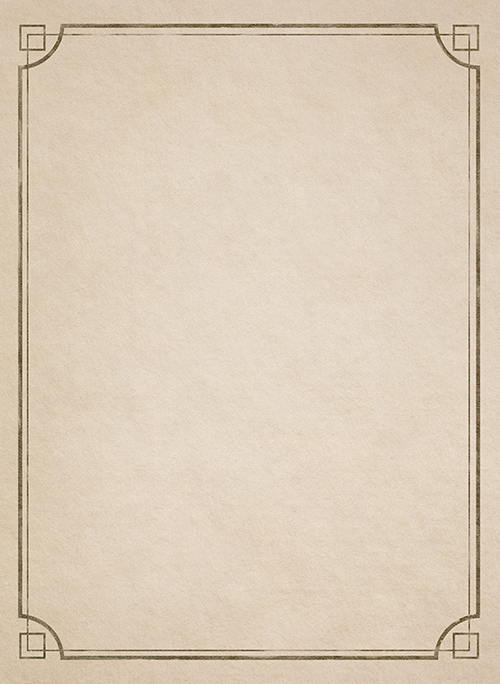私は足の感覚が一切なく、歩いているのか止まっているのかも分からなくなっていた。なんなら足の裏にキャタピラーでもついていて私は直立不動のまま前に進んでいるのではないだろうか。
ぐにゃりと捻じ曲がった視界は貧血の時より何倍もの不快感を募らせる。壁に手をついて深いため息をついた。これほどにまで私はしんどいアピールを全開で放っているというのに、すれ違うスーツ姿の紳士方は私には目もくれずまっすぐ街道を進んでいく。いや、目もくれずというのは嘘だ。私を一瞥した後、何もなかったかのようにすぐ目を逸らしているのだ。
それなら私だってアンタたちから目を背けてやる。道路とは反対方向を見ると、そこには真っ白なマネキンが派手なファッションを着ているショーウィンドウが目に留まる。赤や白い華々しい服装に身を包み、顔のないマネキンは堂々と胸を張ってポーズをとっている。
そしてそのショーウィンドウには真っ黒な服に身を包んだ、情けない顔をした女性が映っていた。というか、私だった。。
救いを求めるようにショーウィンドウに近づき、窓にガラスに手を付けた。近づきすぎたせいで私の姿は真っ黒な影になり、私の姿は反射しなくなる。不意に店の中から私を覗き見る店員と目が合った。店員もマネキンのようにオシャレで可愛らしい服装をしていた。
私を見つめる瞳はやがて疑問から不快に変わり、私は耐えられずにショーウィンドウから離れるように逃げる。だがどこに行っても人の目はしつこく私の見た目を嘗め回し、ある人は忌避をしてある人は無関心を示す。
「そんな目で、私を見ないでよ……」
気が付けば私は走り出していた。あれほど感覚がマヒしていた足は名馬のごとく大地を力強く踏みしめ、脱兎のごとく一心不乱に突き進んでいた。
無差別に地面に突き立てられたビル群の隙間を縫って進み、私を認めようとしない有象無象の大衆たちを押しのけて猛進し、大都会を後にした。
どこかもわからずに私は走り続ける。両足が攣りそうになりながらも万里の長城を駆け抜け、名もなき街道を走り抜け、とにかく今から逃げたかった。
気が付けば私の地元についていて、そこには私を見下ろすようなコンクリートの建物も鬱蒼とした人間の大群もいない。私は汗も全く掻いておらず、息も全く荒れていない。だから家に帰ることはせず、まっすぐ私の通っていた高校まで足を運んだ。
「制服着てくるの忘れた……」
そう思って自分の服を見下ろすと、私は紺色のセーラー服に真っ黒なローファーを履いていた。気分は清々しく、花壇に植えられたバンジーの花を少女漫画のごとく私の背景に溶け込んでいく。カラーにすればバンジーは十人十色の花言葉が生まれ、冒頭カラーなら赤バンジーで確定。アバンギャルドなコマ割りで初心な少年を惑わし、ウィスパーボイスで語る心理描写は男子禁制の乙女心。分かってほしいけど裸の心は見せたくない、単純な男には氷山の一角だけを見て乙女心を理解してほしいという無理難題。でも仕方ないでしょ、女の子なんだモン。略してノコモンが登場したところで校舎を駆け上がる。
壁ドン、顎クイ、間接キス、バックハグ、ポケット繋ぎ、不意パシャ、何でもござれの胸キュン仕草。妄想乙の痛々しい女、妄想乙女と蔑まれようとも私がいるのは華の高校生活。モラトリアムの海で浮かんでピンク色の夢を見てもまだ許される歳ではないか。
ルンルンスキップで階段を上って教室へと向かう。元気よく教室の扉を開けて挨拶をしようとした瞬間、教室の中にいる一人の女性に気が付いた。彼女はスカート丈を上げて胸元のリボンは解いて肌が露出している。ナチュラルメイクで肌をきれいに見せ、エクステに淡いピンク色の口紅までつけている。私の記憶にはこんなばっちりメイクを決めてクラスの中心になっていた女の子はいなかったはずだ。だが、どういうわけかその女の子の顔には見覚えがあった。というか、私だった。
頭から理解という概念そのものが欠落した。最速で建築したモンサンミッシェルは事も無げにアトランティスの遺物になり果て、枯れ尾花が擬態した悪魔の手だと分かった際には魑魅も魍魎も恐怖へと帰納する。
「なんで私がここにいるか分かる?」
気が付けば綺麗な私は私の目の前で小賢しく笑っていた。
「もしかして変わると思った? 残念でした。過去に戻ろうとも妄想の中だろうとも、あなたに華のある人生は送れない。だってあなたにお花は似合わないでしょ」
綺麗な私は私の背景から満開に咲いたパンジーの花を払いのけた。
「ふざけないでよ……」
激情に委ねたままはだけた胸元に掴みかかる。
「やぁん、怖い!」
なんとも甲高くふにゃふにゃな声で綺麗な私は私の手から逃れる。刹那に獲物を狙う虎のように私の睨みつけ唸るような低い声を出す。
「どう? あなたにはこんな可愛い素振りができないでしょ?」
「そんなぶりっ子みたいなマネ、出来るわけないでしょ」
「でもぉ、バカな男はぁ、こんな風にネコを被った女の子の方が好きなんだにゃ?」
にゃ?にゃ?と手をネコの手のように曲げて小突いてくる。その手をうざったく払いのけて同じように睨みつけた。
「そんな演技で騙されるような男の人と付き合いたくなんてないもの。もっと私が恋愛したいのは――」
「真面目でイケメンで浮気をしない男でどこか奥手そうだけどいざというときは強引に抱きしめてほしくてちゃんと自分を愛してくれている人、かにゃ?」
真っ黒な猫耳と優雅に揺れるしっぽを付けて、鈴をチャリンと鳴らした。
「馬鹿じゃないの。真面目なだけだとつまらないし、髪型と服装を変えればある程度は格好良くなる。浮気の一つも出来ないような競争率の低い男と付き合っても仕方ない。奥手な男は一生奥手だし、その年になってもまだ『愛』なんて身体がむず痒くなることいってるの? いい加減に恋愛は打算と性欲で成り立っていることに気づきなさいよ」
ぬるぬると背後に忍び寄り、私の耳元で香水のにおいをまき散らしながら甘く囁く。
「大事なのは虚勢を張ることなのよ。だから私たちは化粧をするの。『美しさ』という虚勢を張り、その虚勢がバレる『恐れ』を隠すために化粧という道具はピッタリなの。でもあなたは化粧ではなく、ネットで隠したのよ。数ミリの液晶と目に見えないWi-Fiは化粧の代替品」
ポケットからスマホを取り出す。画面に映る私は大学のカフェテリアに座っており、隣には黒田くんが爽やかに笑っている。
「変わるチャンスはいくらでもあったはずよ。でも、あなたは一度も変わらなかった」
スマホをスクロールすると、高校受験をしている私の姿があった。さらにスクロールをすると高校に入学したの時の私。高校の学園祭の時の私。大学入学時の私。去年の私、先月の私、昨日の私、そしてカフェテリアに座る私がいた。
「それを妄想の中だけでも高校に戻って華の高校生をやり直す? 随分と頭の中がお花畑のようだけど、その花はそろそろすべて刈り取った方がいいわよ。あなたにはそのお花畑を維持できるほどの経済力も人材もそろえられないでしょ」
蒙きを啓くは天啓の如く、狂気を孕むも私を形容したのは事実。愛は資格の問題。公衆の面前で晒した天秤にて測るは比重ではなく価値の差分。不義を犯した円卓の騎士に酷似した、などとは雄獅子の傲慢、所持を許されるのは彼の騎士を束ねた獅子の魂を持つ騎士王だけだろう。なんてことはない、私は姫君ではなく白馬に乗った精悍な騎士に憧れを抱く村娘Dだったのだ。
「さあ、そろそろ夢は醒める時間よ。自分の行いを顧みてみるといいわ。一応仮名の市岡芽依ちゃん」
私は私に押し倒され、昏い闇に飲まれていくかのように深い淵の中へと落ちていった。
ぐにゃりと捻じ曲がった視界は貧血の時より何倍もの不快感を募らせる。壁に手をついて深いため息をついた。これほどにまで私はしんどいアピールを全開で放っているというのに、すれ違うスーツ姿の紳士方は私には目もくれずまっすぐ街道を進んでいく。いや、目もくれずというのは嘘だ。私を一瞥した後、何もなかったかのようにすぐ目を逸らしているのだ。
それなら私だってアンタたちから目を背けてやる。道路とは反対方向を見ると、そこには真っ白なマネキンが派手なファッションを着ているショーウィンドウが目に留まる。赤や白い華々しい服装に身を包み、顔のないマネキンは堂々と胸を張ってポーズをとっている。
そしてそのショーウィンドウには真っ黒な服に身を包んだ、情けない顔をした女性が映っていた。というか、私だった。。
救いを求めるようにショーウィンドウに近づき、窓にガラスに手を付けた。近づきすぎたせいで私の姿は真っ黒な影になり、私の姿は反射しなくなる。不意に店の中から私を覗き見る店員と目が合った。店員もマネキンのようにオシャレで可愛らしい服装をしていた。
私を見つめる瞳はやがて疑問から不快に変わり、私は耐えられずにショーウィンドウから離れるように逃げる。だがどこに行っても人の目はしつこく私の見た目を嘗め回し、ある人は忌避をしてある人は無関心を示す。
「そんな目で、私を見ないでよ……」
気が付けば私は走り出していた。あれほど感覚がマヒしていた足は名馬のごとく大地を力強く踏みしめ、脱兎のごとく一心不乱に突き進んでいた。
無差別に地面に突き立てられたビル群の隙間を縫って進み、私を認めようとしない有象無象の大衆たちを押しのけて猛進し、大都会を後にした。
どこかもわからずに私は走り続ける。両足が攣りそうになりながらも万里の長城を駆け抜け、名もなき街道を走り抜け、とにかく今から逃げたかった。
気が付けば私の地元についていて、そこには私を見下ろすようなコンクリートの建物も鬱蒼とした人間の大群もいない。私は汗も全く掻いておらず、息も全く荒れていない。だから家に帰ることはせず、まっすぐ私の通っていた高校まで足を運んだ。
「制服着てくるの忘れた……」
そう思って自分の服を見下ろすと、私は紺色のセーラー服に真っ黒なローファーを履いていた。気分は清々しく、花壇に植えられたバンジーの花を少女漫画のごとく私の背景に溶け込んでいく。カラーにすればバンジーは十人十色の花言葉が生まれ、冒頭カラーなら赤バンジーで確定。アバンギャルドなコマ割りで初心な少年を惑わし、ウィスパーボイスで語る心理描写は男子禁制の乙女心。分かってほしいけど裸の心は見せたくない、単純な男には氷山の一角だけを見て乙女心を理解してほしいという無理難題。でも仕方ないでしょ、女の子なんだモン。略してノコモンが登場したところで校舎を駆け上がる。
壁ドン、顎クイ、間接キス、バックハグ、ポケット繋ぎ、不意パシャ、何でもござれの胸キュン仕草。妄想乙の痛々しい女、妄想乙女と蔑まれようとも私がいるのは華の高校生活。モラトリアムの海で浮かんでピンク色の夢を見てもまだ許される歳ではないか。
ルンルンスキップで階段を上って教室へと向かう。元気よく教室の扉を開けて挨拶をしようとした瞬間、教室の中にいる一人の女性に気が付いた。彼女はスカート丈を上げて胸元のリボンは解いて肌が露出している。ナチュラルメイクで肌をきれいに見せ、エクステに淡いピンク色の口紅までつけている。私の記憶にはこんなばっちりメイクを決めてクラスの中心になっていた女の子はいなかったはずだ。だが、どういうわけかその女の子の顔には見覚えがあった。というか、私だった。
頭から理解という概念そのものが欠落した。最速で建築したモンサンミッシェルは事も無げにアトランティスの遺物になり果て、枯れ尾花が擬態した悪魔の手だと分かった際には魑魅も魍魎も恐怖へと帰納する。
「なんで私がここにいるか分かる?」
気が付けば綺麗な私は私の目の前で小賢しく笑っていた。
「もしかして変わると思った? 残念でした。過去に戻ろうとも妄想の中だろうとも、あなたに華のある人生は送れない。だってあなたにお花は似合わないでしょ」
綺麗な私は私の背景から満開に咲いたパンジーの花を払いのけた。
「ふざけないでよ……」
激情に委ねたままはだけた胸元に掴みかかる。
「やぁん、怖い!」
なんとも甲高くふにゃふにゃな声で綺麗な私は私の手から逃れる。刹那に獲物を狙う虎のように私の睨みつけ唸るような低い声を出す。
「どう? あなたにはこんな可愛い素振りができないでしょ?」
「そんなぶりっ子みたいなマネ、出来るわけないでしょ」
「でもぉ、バカな男はぁ、こんな風にネコを被った女の子の方が好きなんだにゃ?」
にゃ?にゃ?と手をネコの手のように曲げて小突いてくる。その手をうざったく払いのけて同じように睨みつけた。
「そんな演技で騙されるような男の人と付き合いたくなんてないもの。もっと私が恋愛したいのは――」
「真面目でイケメンで浮気をしない男でどこか奥手そうだけどいざというときは強引に抱きしめてほしくてちゃんと自分を愛してくれている人、かにゃ?」
真っ黒な猫耳と優雅に揺れるしっぽを付けて、鈴をチャリンと鳴らした。
「馬鹿じゃないの。真面目なだけだとつまらないし、髪型と服装を変えればある程度は格好良くなる。浮気の一つも出来ないような競争率の低い男と付き合っても仕方ない。奥手な男は一生奥手だし、その年になってもまだ『愛』なんて身体がむず痒くなることいってるの? いい加減に恋愛は打算と性欲で成り立っていることに気づきなさいよ」
ぬるぬると背後に忍び寄り、私の耳元で香水のにおいをまき散らしながら甘く囁く。
「大事なのは虚勢を張ることなのよ。だから私たちは化粧をするの。『美しさ』という虚勢を張り、その虚勢がバレる『恐れ』を隠すために化粧という道具はピッタリなの。でもあなたは化粧ではなく、ネットで隠したのよ。数ミリの液晶と目に見えないWi-Fiは化粧の代替品」
ポケットからスマホを取り出す。画面に映る私は大学のカフェテリアに座っており、隣には黒田くんが爽やかに笑っている。
「変わるチャンスはいくらでもあったはずよ。でも、あなたは一度も変わらなかった」
スマホをスクロールすると、高校受験をしている私の姿があった。さらにスクロールをすると高校に入学したの時の私。高校の学園祭の時の私。大学入学時の私。去年の私、先月の私、昨日の私、そしてカフェテリアに座る私がいた。
「それを妄想の中だけでも高校に戻って華の高校生をやり直す? 随分と頭の中がお花畑のようだけど、その花はそろそろすべて刈り取った方がいいわよ。あなたにはそのお花畑を維持できるほどの経済力も人材もそろえられないでしょ」
蒙きを啓くは天啓の如く、狂気を孕むも私を形容したのは事実。愛は資格の問題。公衆の面前で晒した天秤にて測るは比重ではなく価値の差分。不義を犯した円卓の騎士に酷似した、などとは雄獅子の傲慢、所持を許されるのは彼の騎士を束ねた獅子の魂を持つ騎士王だけだろう。なんてことはない、私は姫君ではなく白馬に乗った精悍な騎士に憧れを抱く村娘Dだったのだ。
「さあ、そろそろ夢は醒める時間よ。自分の行いを顧みてみるといいわ。一応仮名の市岡芽依ちゃん」
私は私に押し倒され、昏い闇に飲まれていくかのように深い淵の中へと落ちていった。