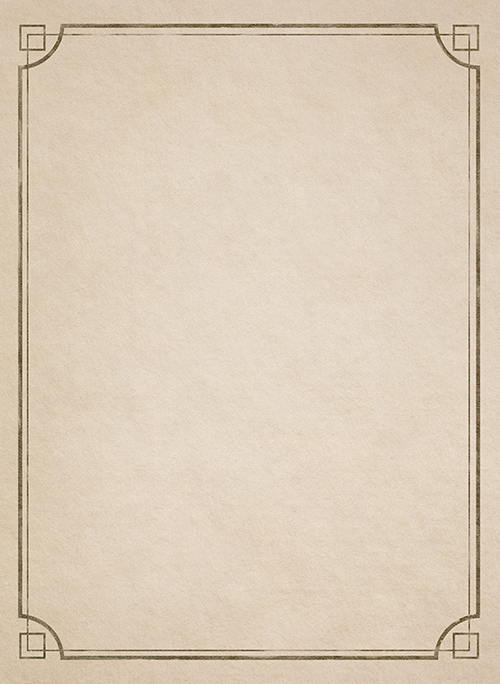翌日。私は生者を探すゾンビか、はたまた彷徨い続けるキョンシーの如く大学のキャンパスを右往左往、縦横無尽で歩き続けた。昨日の夜はなかなか寝付けず、寝不足で視界も曖昧だが体力の続く限り私は大学内の散策をかれこれ三時間以上行っていた。
私の目的はただ一つ、ナイト様がこの大学に通っているのかを確かめるということだ。
そのためなら手段と時間は問わない。あらかじめナイト様に関する身バレ記事をネットで漁り、証拠になりそうなものはすべて把握している。
そもそも私はVtuberの中身に関しては一線を引いており、身バレ記事までには手を出すことはなかった。ある種の訓戒として私の心にとどめていたのだが、こんな形でそれを破ることになるのは誠に遺憾でしかない。
言い訳をしながらも、私は内なる真理追及欲求という名の好奇心に逆らうことはできなかったことは事実だ。別に会ってどうこうしたいというわけではなく、これはただの好奇心だ。そう、ただの好奇心でしかない。
とはいえ闇雲に探してもやはり成果はなかなか得られない。
調べ上げた情報によるとナイト様は一年ほど前からときどき飲酒配信をしており、それ以前はお酒に関することは一切話していなかったのでナイト様は21歳の可能性が高い。ナイト様が学生だと思われる発言は過去にも何度がしており、「高校のリア友には話したけど今の友達にはまだVtuberをやっていると話していない」や、リスナーに学歴を聞かれて「学歴についてはまだ免許未皆伝ですね(笑)」と言っていたことがあり、直接的な言い回しではないものの大学生で間違いないのではないかと言われている。
ナイト様は他にも自分が一人っ子であることも公開していたため、あのカードがナイト様ではなく家族の誰かがこの大学の学生であるということもない。
いくつものサイトをネットサーフィンしたが、さすがに素顔に関する情報はなかった。そのため、私は幾度となく聞き続けたナイト様の声を頼りに本人を探すしかないのだ。
私は聴覚を研ぎ澄ませながらキャンパスを進むが、誰もが声を発しながら歩いているわけではないためすれ違う男性すべてを確認することはできない。一人で音楽を聴きながら歩いている学生や、グループ内の後ろの方で一言も喋っていない人を見ると、こっそり後を追いかけて喋るタイミングを見計らうしかなかった。
だが当然、こんな方法では効率が悪すぎる。何しろナイト様が浪人で大学に入ったことも考慮すると、一年生から三年生までの男子学生を合わせたおよそ1500人以上の中から見つけ出すしかないのだ。そもそも今日、この大学に来ているとも限らない。
「疲れた……」
寝不足と歩きすぎたことでもう身体は悲鳴を上げていた。
「そうだ……!」
どこかで休憩しようとしたとき、ちょうど名案が思い浮かぶ。
私は大学に併設されているカフェテリアにまで移動した。最大で300人を収容できる大きさで、まだ昼前にもかかわらず半分近くの席に学生が座っている。そして学園祭のとき、ティッシュが配られた場所もこのカフェテリアだった。
もしナイト様がここの学生ならこのカフェテリアを利用するはずだ。休憩がてらナイト様を探すことができるため、一石二鳥である。
たとえ何日何ヶ月かかろうともここでナイト様を見つけるという決意のもと、カフェテリアの真ん中の席に腰を下ろした。そして例の如く耳を澄ましてナイト様の声を聴き分ける。
「でもあのドラマってさあ……」
「いや今年のマンチェスターは無理だよ」
「俺のインターン意識高い系ばっか……」
「明日の合コンのことだけど」
あちらこちらの席で雑談やら文句やら愚痴やら、人目を憚らず猥談までする輩もいる。雑多なノイズは耳に入れないように努めるが、一度会話を聞いてしまえばその後まで聞こうとしてしまう。
うるさい!ちょっと静かにして!
と人目もはばからずに叫びたい。私が聴きたいのはナイト様のお声だけなのだからと片っ端から文句を言って怒りたいが、そこは”私”。
椅子に座って体を小さくしたまま、じっとナイト様の声が聞こえるまで待つことしかできなかった。だが不思議なもので、その瞬間は唐突にやって来る。
真っ暗闇を照らす一筋の光のように、幾度となく鼓膜と私の心を震わせた、逞しさと優しさ、剛と柔。相反するものをすべてを受け入れるかのような寛大さすら感じさせるその声が、ネット越しではないリアルの空気を振動して私の耳へと届いた。話している内容までは聞こえなかったが、声は間違いなくナイト様のものだ。
顔を上げると、カフェテリアの入り口から四人組の男子学生が入ってきているところだった。あの学生たちの中にナイト様がいるはずなのだが、口元まで見ることができずに四人のうち誰かが分からない。
「テラスの方開いてっかな」
学生の一人がそう言って、私の近くの席にカバンを置いた。
「どうだろうな。俺が見にいこうか?」
「そうだな。じゃあ黒田はひとまずこの席とっといてくれよ」
三人の学生はそう言って席から離れていった。三人とも喋ったが、その声はナイト様とは似ても似つかない。
となると……。
私は席に一人残された男子学生を横目で盗み見る。長い足を組み、綺麗な黒髪には一部メッシュが入っている。スマホを触りながら頬杖を突くその様子は優雅さを醸し出していた。
正直、心の中ではナイト様の本人の姿がイケメンだということに期待は持っていなかった。そもそも私が恋しているのはナイト様という理想であって、現実にナイト様を動かして喋っている人ではないからだ。だがしかし、目の前にいるこの男子学生はまるでナイト様の立ち絵をそのまま実写化したようなイケメンである。
私が本当に好きなのはVtuberとしての黒岸ナイトのはずなのに、こうして近くにナイト様が近くにいると鼓動は胸を突き破るほど高鳴っている。
いやいや、まだこの人がナイト様だと決まったわけではない。どうにかしてこの人の声を確認しなければ……!
モヤモヤした感情を抱えつつも隣をチラリと横目で確認すると、ナイト様が私の方を向いていた。慌てて顔を逸らす。
心臓がずっとバクバクと鳴り続け、気を紛らわすようにカバンの中を探る素振りをした。
「すみません、それって……」
男子学生が席を立ち、誰かに話しかける。その声は紛れもない、ナイト様本人だった。
あまりの衝撃にナイト様が話しかけている相手が私だということに気づくのに時間がかかってしまった。
「あ、は、ひゃい!」
声が裏返って変な声が出てしまう。頭に血が上って耳まで熱くなっている感覚がより恥ずかしくなる。変な声を出して勝手に照れているような女にもナイト様は微笑んで気にせず話を続けてくれた。
「そのキーホルダー、ひょっとしてピンクタイガー?」
ナイト様が指さしているのは私のカバンについているピンクタイガーのキーホルダーだった。昨日もアイシングで作っていた通り、ナイト様はピンクタイガーの大ファンである。私はしばらくカバンにつけったぱなしだったため、ついつい外してくることを忘れていた。もしかしたら私がナイト様のリスナーだとバレてしまうかもしれない。そんな不安で私はキーホルダーを掴んで隠した。
「ごめんね。ちょっと聞きたいんだけど、それってどこで買ったの?」
食いつくように尋ねるナイト様。私は目を合わせないように小さく答えた。
「えっと……。海外の方のサイトで買いました」
「海外、その手があったか……!」
ナイト様は膝を打ってやられた、という顔をした。
「いや、俺も公式サイトはくまなくチェックしているんだけどさ、このキャラってなかなかグッズがないじゃん。だから見覚えのないキーホルダー付けててビックリしたんだよ」
「ほとんどが他のキャラと一緒に写ってるものばかりですからね……」
「そうそう。単体となるとやっぱり人気がないからなぁ」
こうして話してみると、やはり目の前の彼が黒岸ナイトだと確信を持った。声質はもちろん、口調からでもナイト様独特の母音の伸ばし方がある。
「ところでさ」
ナイト様の身体が近づき、私の心臓はより一層跳ね上がる。
「その海外のサイトっていうの教えてくれない? 俺もそのキーホルダー欲しいからさ」
「は……はい、大丈夫ですよ」
震える手でカバンの中からスマホを取り出した。
スマホを付けるといきなり画面にナイト様の中身について調べたサイトが開いてしまった。ナイト様に話しかけられたときとはまた別の心臓の高鳴りが響き、私は慌ててタスクを切った。だがナイト様の方は私の画面には全く見ておらず、私のカバンに付いたキーホルダーを子供のようにキラキラした目で触っていた。
ナイト様は私の視線に気づいたのか、すぐにキーホルダーから手を離す。
「あ、すみません! 勝手に触っちゃって」
「いえ、……大丈夫ですよ」
平静を装うが、絶対にこのキーホルダーは家宝にしようと心に決めた。
検索エンジンに英語でポチポチと打ち込むと、海外の公式サイトまでたどり着く。そのサイトを開いてナイト様に見せた。
「これです。海外だからキーホルダーより送料の方が高くなっちゃうんですけどね」
「へえ。ちょっと、いいですか?」
ナイト様は私のスマホに触れて角度を調整すると、自分のスマホに手打ちでURLを打ち込んでいく。その際にナイト様の暖かい指が私の手の甲に少しだけ触れ、そのたびにドギマギと胸が高鳴る。
もうここまでくるとさっきまでの焦りや照れよりも高揚感の方が勝り、はっきりと目の前の男性の顔を見ることができた。肌は女の子のように白くきめ細かいが、肩幅は広く服の上から見ても筋肉質だと分かる。質の良い革のジャケットを着てジーパンを履いているためスタイルの良さが際立っているのだ。
軽くワックスで整えた黒い髪。立ち絵のナイト様のように艶やかな長い髪ではないが、ツーブロックで爽やかな見た目はまた違った格好良さだった。だが鼻筋の高さや唇の薄さ、睫毛の長い大きな瞳からは立ち絵と同じ中性的な甘美さを感じ取れた。
「ホントだ。送料かなり高いな……」
そう呟くと喉ぼとけが艶めかしく動き、細くも凹凸のある首筋に見惚れてしまう。
「なるほど、こうするのか……。ありがとう、助かったよ! えっと……」
「あ、市岡です」
「市岡さんね。俺は黒田です」
「黒田さん……」
下の名前も聞いてみたいが、それはさすがにおこがましいだろうか。変に聞いて引かれてしまっても困るし、ここでがめつくすれば私が黒岸ナイトのリスナーだとバレてしまうかもしれない。いや、でもナイト様の本名も気になるし……。
心の中で葛藤している間に、話は次の話題へと流れた。
「海外のサイトにも詳しいみたいだけど、ひょっとして国際学部?」
「文学部です。でも英語は専門で取っているのである程度得意なんですよ」
「そうなんだ。俺は経済学部なんだけど、英語なんて高校以来まったく触ってないよ。さっきのサイトでも書いてあること一切分からなかったから」
「でもさっきなるほどって……」
「あれは……なんか癖みたいなものかな。ホラ、たまにあるじゃん。よくわからないけど『なるほど!』って言っちゃうみたいな」
「そんなのないですよ」
思わず笑ってしまう。日々の配信のコメントで鍛えあげた相槌で会話も弾み、黒田くんも楽しそうに白い歯を見せて笑っていた。
和やかにカフェテリアの一席で話している男女。これはもう周りから見れば付き合っていると思われてもいいのではないだろうか。いくら人付き合いが乏しい私でも今の私と黒田くんとの距離感が縮まっていることには気づいていた。
今なら言えるかもしれない。『もっとピンクタイガーについて話したいので、連絡先交換しませんか?』と尋ねるだけでいい。確かにいきなりかもしれないが、それでもチャンスはあるはずだ。
言うぞ言うぞ、とスマホを強く握りしめる。
「あれ? 何やってんだよ、黒田」
そのとき、食べ物を持ってきた黒田くんの友人たちが席に戻って来た。髪の毛を金色に染めた遊び人風な学生が私と黒田くんを交互に見つめる。
私の方を見つめる目にはどこか覚えがあった。何でお前が、というような疑問と不満を混ぜたような色をしてる。その湿った瞳で見られると、私は古傷が痛むかのように何も言えなくなる。
「テラスの方開いてたからそっちの方行こうぜ」
もう一人のの派手な格好をした学生がやってきて、黒田くんと金髪の学生を催促した。
「おう。じゃあ行こうぜ、黒田」
「うん。ごめんね、市岡さん。サイト教えてくれてありがとう」
そう言って黒田くんが私から離れていく。
「あ……いえ」
私は呼び止めることもできず、ただスマホを握りしめたまま黒田くんの背中を見つめた。
「え? なに、黒田って意外とああいうのがタイプだったりすんの?」
遠くの方で黒田くんに金髪の友人が話しかける声が聞こえる。本人は小声で話しているつもりなのだろうが、本人が思っている以上に声は大きく耳を澄まさなくてもはっきりと会話の内容が聞こえてきてしまう。
”ああいうの”?
ゲシュタルト崩壊でも起こしたかのように頭の中でアとイとウとノが散り散りになって飛び交う。
「別にそんなんじゃないよ。俺はただ――」
黒田くんがその質問に答え終わる前に、私は荷物をまとめて逃げるようにカフェテリアを後にした。
私の目的はただ一つ、ナイト様がこの大学に通っているのかを確かめるということだ。
そのためなら手段と時間は問わない。あらかじめナイト様に関する身バレ記事をネットで漁り、証拠になりそうなものはすべて把握している。
そもそも私はVtuberの中身に関しては一線を引いており、身バレ記事までには手を出すことはなかった。ある種の訓戒として私の心にとどめていたのだが、こんな形でそれを破ることになるのは誠に遺憾でしかない。
言い訳をしながらも、私は内なる真理追及欲求という名の好奇心に逆らうことはできなかったことは事実だ。別に会ってどうこうしたいというわけではなく、これはただの好奇心だ。そう、ただの好奇心でしかない。
とはいえ闇雲に探してもやはり成果はなかなか得られない。
調べ上げた情報によるとナイト様は一年ほど前からときどき飲酒配信をしており、それ以前はお酒に関することは一切話していなかったのでナイト様は21歳の可能性が高い。ナイト様が学生だと思われる発言は過去にも何度がしており、「高校のリア友には話したけど今の友達にはまだVtuberをやっていると話していない」や、リスナーに学歴を聞かれて「学歴についてはまだ免許未皆伝ですね(笑)」と言っていたことがあり、直接的な言い回しではないものの大学生で間違いないのではないかと言われている。
ナイト様は他にも自分が一人っ子であることも公開していたため、あのカードがナイト様ではなく家族の誰かがこの大学の学生であるということもない。
いくつものサイトをネットサーフィンしたが、さすがに素顔に関する情報はなかった。そのため、私は幾度となく聞き続けたナイト様の声を頼りに本人を探すしかないのだ。
私は聴覚を研ぎ澄ませながらキャンパスを進むが、誰もが声を発しながら歩いているわけではないためすれ違う男性すべてを確認することはできない。一人で音楽を聴きながら歩いている学生や、グループ内の後ろの方で一言も喋っていない人を見ると、こっそり後を追いかけて喋るタイミングを見計らうしかなかった。
だが当然、こんな方法では効率が悪すぎる。何しろナイト様が浪人で大学に入ったことも考慮すると、一年生から三年生までの男子学生を合わせたおよそ1500人以上の中から見つけ出すしかないのだ。そもそも今日、この大学に来ているとも限らない。
「疲れた……」
寝不足と歩きすぎたことでもう身体は悲鳴を上げていた。
「そうだ……!」
どこかで休憩しようとしたとき、ちょうど名案が思い浮かぶ。
私は大学に併設されているカフェテリアにまで移動した。最大で300人を収容できる大きさで、まだ昼前にもかかわらず半分近くの席に学生が座っている。そして学園祭のとき、ティッシュが配られた場所もこのカフェテリアだった。
もしナイト様がここの学生ならこのカフェテリアを利用するはずだ。休憩がてらナイト様を探すことができるため、一石二鳥である。
たとえ何日何ヶ月かかろうともここでナイト様を見つけるという決意のもと、カフェテリアの真ん中の席に腰を下ろした。そして例の如く耳を澄ましてナイト様の声を聴き分ける。
「でもあのドラマってさあ……」
「いや今年のマンチェスターは無理だよ」
「俺のインターン意識高い系ばっか……」
「明日の合コンのことだけど」
あちらこちらの席で雑談やら文句やら愚痴やら、人目を憚らず猥談までする輩もいる。雑多なノイズは耳に入れないように努めるが、一度会話を聞いてしまえばその後まで聞こうとしてしまう。
うるさい!ちょっと静かにして!
と人目もはばからずに叫びたい。私が聴きたいのはナイト様のお声だけなのだからと片っ端から文句を言って怒りたいが、そこは”私”。
椅子に座って体を小さくしたまま、じっとナイト様の声が聞こえるまで待つことしかできなかった。だが不思議なもので、その瞬間は唐突にやって来る。
真っ暗闇を照らす一筋の光のように、幾度となく鼓膜と私の心を震わせた、逞しさと優しさ、剛と柔。相反するものをすべてを受け入れるかのような寛大さすら感じさせるその声が、ネット越しではないリアルの空気を振動して私の耳へと届いた。話している内容までは聞こえなかったが、声は間違いなくナイト様のものだ。
顔を上げると、カフェテリアの入り口から四人組の男子学生が入ってきているところだった。あの学生たちの中にナイト様がいるはずなのだが、口元まで見ることができずに四人のうち誰かが分からない。
「テラスの方開いてっかな」
学生の一人がそう言って、私の近くの席にカバンを置いた。
「どうだろうな。俺が見にいこうか?」
「そうだな。じゃあ黒田はひとまずこの席とっといてくれよ」
三人の学生はそう言って席から離れていった。三人とも喋ったが、その声はナイト様とは似ても似つかない。
となると……。
私は席に一人残された男子学生を横目で盗み見る。長い足を組み、綺麗な黒髪には一部メッシュが入っている。スマホを触りながら頬杖を突くその様子は優雅さを醸し出していた。
正直、心の中ではナイト様の本人の姿がイケメンだということに期待は持っていなかった。そもそも私が恋しているのはナイト様という理想であって、現実にナイト様を動かして喋っている人ではないからだ。だがしかし、目の前にいるこの男子学生はまるでナイト様の立ち絵をそのまま実写化したようなイケメンである。
私が本当に好きなのはVtuberとしての黒岸ナイトのはずなのに、こうして近くにナイト様が近くにいると鼓動は胸を突き破るほど高鳴っている。
いやいや、まだこの人がナイト様だと決まったわけではない。どうにかしてこの人の声を確認しなければ……!
モヤモヤした感情を抱えつつも隣をチラリと横目で確認すると、ナイト様が私の方を向いていた。慌てて顔を逸らす。
心臓がずっとバクバクと鳴り続け、気を紛らわすようにカバンの中を探る素振りをした。
「すみません、それって……」
男子学生が席を立ち、誰かに話しかける。その声は紛れもない、ナイト様本人だった。
あまりの衝撃にナイト様が話しかけている相手が私だということに気づくのに時間がかかってしまった。
「あ、は、ひゃい!」
声が裏返って変な声が出てしまう。頭に血が上って耳まで熱くなっている感覚がより恥ずかしくなる。変な声を出して勝手に照れているような女にもナイト様は微笑んで気にせず話を続けてくれた。
「そのキーホルダー、ひょっとしてピンクタイガー?」
ナイト様が指さしているのは私のカバンについているピンクタイガーのキーホルダーだった。昨日もアイシングで作っていた通り、ナイト様はピンクタイガーの大ファンである。私はしばらくカバンにつけったぱなしだったため、ついつい外してくることを忘れていた。もしかしたら私がナイト様のリスナーだとバレてしまうかもしれない。そんな不安で私はキーホルダーを掴んで隠した。
「ごめんね。ちょっと聞きたいんだけど、それってどこで買ったの?」
食いつくように尋ねるナイト様。私は目を合わせないように小さく答えた。
「えっと……。海外の方のサイトで買いました」
「海外、その手があったか……!」
ナイト様は膝を打ってやられた、という顔をした。
「いや、俺も公式サイトはくまなくチェックしているんだけどさ、このキャラってなかなかグッズがないじゃん。だから見覚えのないキーホルダー付けててビックリしたんだよ」
「ほとんどが他のキャラと一緒に写ってるものばかりですからね……」
「そうそう。単体となるとやっぱり人気がないからなぁ」
こうして話してみると、やはり目の前の彼が黒岸ナイトだと確信を持った。声質はもちろん、口調からでもナイト様独特の母音の伸ばし方がある。
「ところでさ」
ナイト様の身体が近づき、私の心臓はより一層跳ね上がる。
「その海外のサイトっていうの教えてくれない? 俺もそのキーホルダー欲しいからさ」
「は……はい、大丈夫ですよ」
震える手でカバンの中からスマホを取り出した。
スマホを付けるといきなり画面にナイト様の中身について調べたサイトが開いてしまった。ナイト様に話しかけられたときとはまた別の心臓の高鳴りが響き、私は慌ててタスクを切った。だがナイト様の方は私の画面には全く見ておらず、私のカバンに付いたキーホルダーを子供のようにキラキラした目で触っていた。
ナイト様は私の視線に気づいたのか、すぐにキーホルダーから手を離す。
「あ、すみません! 勝手に触っちゃって」
「いえ、……大丈夫ですよ」
平静を装うが、絶対にこのキーホルダーは家宝にしようと心に決めた。
検索エンジンに英語でポチポチと打ち込むと、海外の公式サイトまでたどり着く。そのサイトを開いてナイト様に見せた。
「これです。海外だからキーホルダーより送料の方が高くなっちゃうんですけどね」
「へえ。ちょっと、いいですか?」
ナイト様は私のスマホに触れて角度を調整すると、自分のスマホに手打ちでURLを打ち込んでいく。その際にナイト様の暖かい指が私の手の甲に少しだけ触れ、そのたびにドギマギと胸が高鳴る。
もうここまでくるとさっきまでの焦りや照れよりも高揚感の方が勝り、はっきりと目の前の男性の顔を見ることができた。肌は女の子のように白くきめ細かいが、肩幅は広く服の上から見ても筋肉質だと分かる。質の良い革のジャケットを着てジーパンを履いているためスタイルの良さが際立っているのだ。
軽くワックスで整えた黒い髪。立ち絵のナイト様のように艶やかな長い髪ではないが、ツーブロックで爽やかな見た目はまた違った格好良さだった。だが鼻筋の高さや唇の薄さ、睫毛の長い大きな瞳からは立ち絵と同じ中性的な甘美さを感じ取れた。
「ホントだ。送料かなり高いな……」
そう呟くと喉ぼとけが艶めかしく動き、細くも凹凸のある首筋に見惚れてしまう。
「なるほど、こうするのか……。ありがとう、助かったよ! えっと……」
「あ、市岡です」
「市岡さんね。俺は黒田です」
「黒田さん……」
下の名前も聞いてみたいが、それはさすがにおこがましいだろうか。変に聞いて引かれてしまっても困るし、ここでがめつくすれば私が黒岸ナイトのリスナーだとバレてしまうかもしれない。いや、でもナイト様の本名も気になるし……。
心の中で葛藤している間に、話は次の話題へと流れた。
「海外のサイトにも詳しいみたいだけど、ひょっとして国際学部?」
「文学部です。でも英語は専門で取っているのである程度得意なんですよ」
「そうなんだ。俺は経済学部なんだけど、英語なんて高校以来まったく触ってないよ。さっきのサイトでも書いてあること一切分からなかったから」
「でもさっきなるほどって……」
「あれは……なんか癖みたいなものかな。ホラ、たまにあるじゃん。よくわからないけど『なるほど!』って言っちゃうみたいな」
「そんなのないですよ」
思わず笑ってしまう。日々の配信のコメントで鍛えあげた相槌で会話も弾み、黒田くんも楽しそうに白い歯を見せて笑っていた。
和やかにカフェテリアの一席で話している男女。これはもう周りから見れば付き合っていると思われてもいいのではないだろうか。いくら人付き合いが乏しい私でも今の私と黒田くんとの距離感が縮まっていることには気づいていた。
今なら言えるかもしれない。『もっとピンクタイガーについて話したいので、連絡先交換しませんか?』と尋ねるだけでいい。確かにいきなりかもしれないが、それでもチャンスはあるはずだ。
言うぞ言うぞ、とスマホを強く握りしめる。
「あれ? 何やってんだよ、黒田」
そのとき、食べ物を持ってきた黒田くんの友人たちが席に戻って来た。髪の毛を金色に染めた遊び人風な学生が私と黒田くんを交互に見つめる。
私の方を見つめる目にはどこか覚えがあった。何でお前が、というような疑問と不満を混ぜたような色をしてる。その湿った瞳で見られると、私は古傷が痛むかのように何も言えなくなる。
「テラスの方開いてたからそっちの方行こうぜ」
もう一人のの派手な格好をした学生がやってきて、黒田くんと金髪の学生を催促した。
「おう。じゃあ行こうぜ、黒田」
「うん。ごめんね、市岡さん。サイト教えてくれてありがとう」
そう言って黒田くんが私から離れていく。
「あ……いえ」
私は呼び止めることもできず、ただスマホを握りしめたまま黒田くんの背中を見つめた。
「え? なに、黒田って意外とああいうのがタイプだったりすんの?」
遠くの方で黒田くんに金髪の友人が話しかける声が聞こえる。本人は小声で話しているつもりなのだろうが、本人が思っている以上に声は大きく耳を澄まさなくてもはっきりと会話の内容が聞こえてきてしまう。
”ああいうの”?
ゲシュタルト崩壊でも起こしたかのように頭の中でアとイとウとノが散り散りになって飛び交う。
「別にそんなんじゃないよ。俺はただ――」
黒田くんがその質問に答え終わる前に、私は荷物をまとめて逃げるようにカフェテリアを後にした。