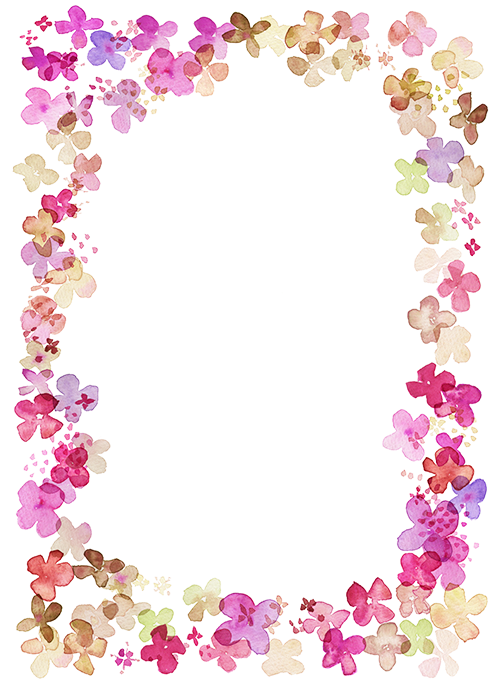二度とないと思ったから、行為の最中の麻衣子はとても素直だった。
もっと来て、離れちゃいやとしがみついて、まるで娼婦のようだったから、たぶん彼も欲望をぶつけられたのだと思う。
彼の大事な人は壊れやすい細工物のような少女だから。自分はちょうどいいはけ口になれると、うぬぼれていられた。
「痛かったか」
けれど行為の後、包むように後ろから抱きしめられて、麻衣子はもう出ないと思っていた涙が流れた。
「全然」
「嘘ばかりつくな」
唇を寄せて涙をなめられて、麻衣子は憮然とした。
彼の言う通りだった。処女の血を流した体が、麻衣子の強がりを暴いていた。
「なんで初めてだって言わなかった」
晃はまた怒ったように言う。
「振り向きもしない男は誰なんだ」
私、初めてを晃にあげられたんだ。麻衣子はぼんやりとそれに気づいて、思わず笑った。
「麻衣子。答えろ」
苛立たしげに名前を呼ばれるのも、晃だとこんなにうれしくて、哀しい。
麻衣子は体を丸めて泣いた。晃は腕をほどかなかったから、息苦しいくらいだった。
「……忘れさせるか」
振り向かせられて、荒々しく口づけられた。足を開かされて、麻衣子の中に入ってくる。
晃が何に苛立っているのかはわからなかったけれど、その行為の行きつく先はわかっていた。
……だめ、そんなに奥まで入ってきたら。繰り返し欲望をぶつけられた体は、麻衣子ではどうにもできない形を結んでいるかもしれなかった。
嵐に翻弄される木の葉のように、昇っては落ちる。食い入るようにみつめる晃のまなざしだけが見えていた。
晃が麻衣子を離したのは、明け方のことだった。
抱き上げてシャワー室に連れて行かれて、体を洗われた。その頃には麻衣子は強がりも言えなくて、晃のなすがままだった。
体から流れていく晃の残滓を惜しいと思いながら、これで終わりなのだとうつろな目で虚空を眺めていた。
晃は麻衣子の体を拭き終わると、ガウンを着せてベッドに寝かせた。
「少しだけ夢を見ていろ」
晃は屈んで、麻衣子の唇にキスを落とした。それは昨晩の嵐の中のキスとは違って、存外に優しいキスだった。
「……起きたら、現実しかないと気づくから」
子どものように頭をなでられて、麻衣子はその心地よさに目を閉じた。
もっと来て、離れちゃいやとしがみついて、まるで娼婦のようだったから、たぶん彼も欲望をぶつけられたのだと思う。
彼の大事な人は壊れやすい細工物のような少女だから。自分はちょうどいいはけ口になれると、うぬぼれていられた。
「痛かったか」
けれど行為の後、包むように後ろから抱きしめられて、麻衣子はもう出ないと思っていた涙が流れた。
「全然」
「嘘ばかりつくな」
唇を寄せて涙をなめられて、麻衣子は憮然とした。
彼の言う通りだった。処女の血を流した体が、麻衣子の強がりを暴いていた。
「なんで初めてだって言わなかった」
晃はまた怒ったように言う。
「振り向きもしない男は誰なんだ」
私、初めてを晃にあげられたんだ。麻衣子はぼんやりとそれに気づいて、思わず笑った。
「麻衣子。答えろ」
苛立たしげに名前を呼ばれるのも、晃だとこんなにうれしくて、哀しい。
麻衣子は体を丸めて泣いた。晃は腕をほどかなかったから、息苦しいくらいだった。
「……忘れさせるか」
振り向かせられて、荒々しく口づけられた。足を開かされて、麻衣子の中に入ってくる。
晃が何に苛立っているのかはわからなかったけれど、その行為の行きつく先はわかっていた。
……だめ、そんなに奥まで入ってきたら。繰り返し欲望をぶつけられた体は、麻衣子ではどうにもできない形を結んでいるかもしれなかった。
嵐に翻弄される木の葉のように、昇っては落ちる。食い入るようにみつめる晃のまなざしだけが見えていた。
晃が麻衣子を離したのは、明け方のことだった。
抱き上げてシャワー室に連れて行かれて、体を洗われた。その頃には麻衣子は強がりも言えなくて、晃のなすがままだった。
体から流れていく晃の残滓を惜しいと思いながら、これで終わりなのだとうつろな目で虚空を眺めていた。
晃は麻衣子の体を拭き終わると、ガウンを着せてベッドに寝かせた。
「少しだけ夢を見ていろ」
晃は屈んで、麻衣子の唇にキスを落とした。それは昨晩の嵐の中のキスとは違って、存外に優しいキスだった。
「……起きたら、現実しかないと気づくから」
子どものように頭をなでられて、麻衣子はその心地よさに目を閉じた。