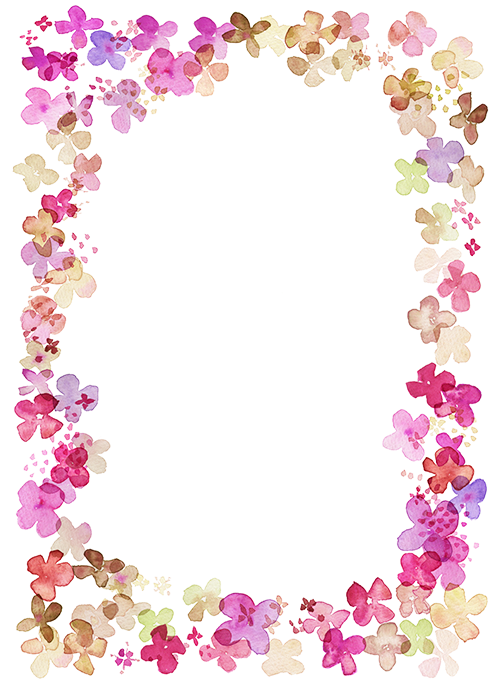眠れない夜に使う強い酒を口移しで流し込んで、麻衣子は晃を見上げた。
「相、原……なに」
「馬鹿。なんで来たの」
晃は酒に弱いのを知っている。麻衣子はふふっと笑うと、よろめいた晃を部屋に引き入れて扉を閉める。
ベッドに向かう時間も惜しくて、床でのしかかって晃の着衣を解く。抵抗しようと晃が伸ばした手を、裸の胸に当てた。
「触ってみて。どきどきしてるでしょう?」
心は泣いているのに、まるで悪役のように笑うのを止められない。
実際悪役そのものなのだろう。こんな風に璃子を裏切って、きっと二度と会えなくなるのがわかっている。
でも止められない。ばらばらになった心が、もっと壊してしまえと麻衣子を責め立てる。
ネクタイをほどいて、吸い付くように喉にキスをする。晃が息を呑む感覚さえ、触れているのが心地よかった。
「相原、やめろ!」
それでも晃は男性で、麻衣子より力が強かった。ふいに体を起こして、麻衣子をひきはがす。
一瞬流れる沈黙、ぜえぜえと荒い呼吸。麻衣子は耐えられなくなって頭を押さえていた。
「わぁぁぁ!」
麻衣子は子どものように顔を上げて、わんわんと泣き出した。
「嫌なの! もう嫌ぁ……! 全部忘れたいの!」
ひぐっ、ぐすっと、情けなくしゃくりあげて泣く。
「私でいいって言って! まちがいでいいから。二度と邪魔しないって誓うから……!」
晃が呆然としている。こんな訳の分からないことを言われて、迷惑してる。
私の馬鹿。いっそ消えてしまいたいのに、晃の目に映ってるのが私だけの今が少しだけ、うれしいと思ってる。
ふいに呼吸が詰まる。引き寄せられて、強く抱きしめられたから。
「……ずっと前から好きな奴がいるって知ってる」
私、晃の腕の中にいる? そう思った途端、また涙があふれた。
「いいのか、まちがって。後悔しないか」
体を離して、晃はぐしゃぐしゃになった麻衣子の顔をみつめた。
入社したその日、怒ったように麻衣子を見たまなざしと同じだった。懐かしくて、麻衣子はすがるように腕を回していた。
「晃……」
名前を呼んだとき、少しだけ彼の体が震えた。
抱き上げられて、ベッドに運ばれた。まるでお姫様と、舞い上がりそうだった。
これは幸せな夢。明日になったら消えてなくなってしまう。
でも、これでいい。十年間、宝物のように胸に抱いていた夢だから、まちがいじゃない。
唇を合わせながらからめた体が、彼の熱だけを追っていた。
「相、原……なに」
「馬鹿。なんで来たの」
晃は酒に弱いのを知っている。麻衣子はふふっと笑うと、よろめいた晃を部屋に引き入れて扉を閉める。
ベッドに向かう時間も惜しくて、床でのしかかって晃の着衣を解く。抵抗しようと晃が伸ばした手を、裸の胸に当てた。
「触ってみて。どきどきしてるでしょう?」
心は泣いているのに、まるで悪役のように笑うのを止められない。
実際悪役そのものなのだろう。こんな風に璃子を裏切って、きっと二度と会えなくなるのがわかっている。
でも止められない。ばらばらになった心が、もっと壊してしまえと麻衣子を責め立てる。
ネクタイをほどいて、吸い付くように喉にキスをする。晃が息を呑む感覚さえ、触れているのが心地よかった。
「相原、やめろ!」
それでも晃は男性で、麻衣子より力が強かった。ふいに体を起こして、麻衣子をひきはがす。
一瞬流れる沈黙、ぜえぜえと荒い呼吸。麻衣子は耐えられなくなって頭を押さえていた。
「わぁぁぁ!」
麻衣子は子どものように顔を上げて、わんわんと泣き出した。
「嫌なの! もう嫌ぁ……! 全部忘れたいの!」
ひぐっ、ぐすっと、情けなくしゃくりあげて泣く。
「私でいいって言って! まちがいでいいから。二度と邪魔しないって誓うから……!」
晃が呆然としている。こんな訳の分からないことを言われて、迷惑してる。
私の馬鹿。いっそ消えてしまいたいのに、晃の目に映ってるのが私だけの今が少しだけ、うれしいと思ってる。
ふいに呼吸が詰まる。引き寄せられて、強く抱きしめられたから。
「……ずっと前から好きな奴がいるって知ってる」
私、晃の腕の中にいる? そう思った途端、また涙があふれた。
「いいのか、まちがって。後悔しないか」
体を離して、晃はぐしゃぐしゃになった麻衣子の顔をみつめた。
入社したその日、怒ったように麻衣子を見たまなざしと同じだった。懐かしくて、麻衣子はすがるように腕を回していた。
「晃……」
名前を呼んだとき、少しだけ彼の体が震えた。
抱き上げられて、ベッドに運ばれた。まるでお姫様と、舞い上がりそうだった。
これは幸せな夢。明日になったら消えてなくなってしまう。
でも、これでいい。十年間、宝物のように胸に抱いていた夢だから、まちがいじゃない。
唇を合わせながらからめた体が、彼の熱だけを追っていた。