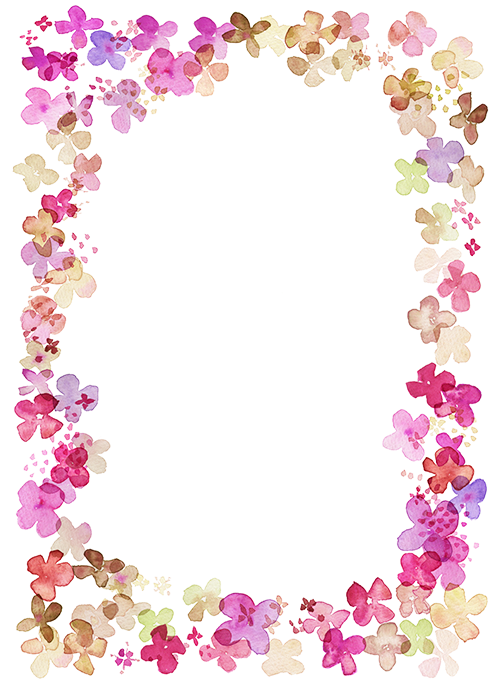大事な話がある。今夜、少し会えないか。
電車の中で晃からのメールを見たとき、麻衣子は熱と寒気が同時に来たように震えた。
入社したときに交換して、一度もやりとりしたことがない連絡先をずっと大事に保管していたのを、彼は知っていただろうか。
すぐに飛んでいきたい自分と、悪い予感に怯える自分がせめぎあう。メールを返そうとして手が震えて、うまく文字が打てなかった。
無理よ、先約があるもの。やっとのことで馬鹿な返信をして、電車を降りた。
璃子の紹介とはいえ、他の男性との約束などすぐに断ればいいと思ったのに、麻衣子は待ち合わせの店に向かっていた。
逃げなさい。たぶんこれは、悪い知らせだから。麻衣子をそう思わせたのは、十年という時間だった。
出会ったその日に好きになった。それなのに意地っ張りな自分が邪魔をして、そっけない態度を取り続けた。
こんな私、好きになるはずないじゃない。想いは十年分も積もっているのに、自信はもうとっくに底をついていた。
たぶん迷子のような足取りで歩いて、麻衣子は街角を曲がった。
日本に来るたび璃子と食事をするいつもの洋食店は、クリスマス仕様なのか、緑の看板に赤いペンでデコレーションがされていた。
赤茶色の明かりが店内を照らしていて、窓辺に座る二人を映していた。
一人はふんわりとした淡いピンクのニットが似合う璃子だった。もう一人は引き締まった体躯を一分の隙もなくスーツで包んだ、晃だった。
どうして二人が? 麻衣子が混乱したのは一瞬だけで、次の瞬間には心が凍り付いていた。
――璃子には敵わないな。
晃が麻衣子には見せないような柔らかい表情で、苦笑しながら言ったのが見えた。
……ああ、そうだったのと、麻衣子は急にいろいろなことが見えた気がした。
言い寄る女性が絶えなかった晃が今まで結婚しなかった理由。引っ込み思案な璃子がいつになく積極的に、晃を紹介したいと言った理由。
大事な話……大事な人を紹介したいと、二人は麻衣子に言おうとしたのだ。
麻衣子は踵を返して走り出していた。雪が降りだしていた。
しゃくりあげて泣いていた。涙が流れた頬に雪がかすめて、痛かった。
ホテルに戻ってからもシーツをかぶって泣いた。世界は真っ暗で、なんにも見えなかった。
どれくらい時間が経ったのか。携帯の着信音がして、麻衣子はシーツの隙間からそれを見た。
「反田君」。入社したときの登録名のまま表示されていて、もう尽きたと思っていた涙がまたあふれた。
きっと泣きすぎてまともな考えなどできなくなっていた。麻衣子はうつろな目で携帯に手を伸ばした。
気が変わった。来てくれるなら、話を聞くわよ。
ホテル名と部屋番号を打ち込んで、麻衣子は携帯を枕元に投げた。
大事な彼女を置いてこんな女のところになんて来ないで。……嫌、それでも来て。
来て、来ないで、来て……。自分でも気持ちの境目がわからなくなった頃、ノックの音が麻衣子の耳に届いた。
日付が変わる時刻、切ったはずの暖房の駆動音がどこかで聞こえる。
シーツだけを体に巻いて戸口に立つ。扉のノブに手をかけて、開いた。
驚いた表情の晃がいた。それだけ確認しただけだった。
「相……」
切望するように聞きたかった声を閉じ込めるようにして、麻衣子は彼にキスをした。
電車の中で晃からのメールを見たとき、麻衣子は熱と寒気が同時に来たように震えた。
入社したときに交換して、一度もやりとりしたことがない連絡先をずっと大事に保管していたのを、彼は知っていただろうか。
すぐに飛んでいきたい自分と、悪い予感に怯える自分がせめぎあう。メールを返そうとして手が震えて、うまく文字が打てなかった。
無理よ、先約があるもの。やっとのことで馬鹿な返信をして、電車を降りた。
璃子の紹介とはいえ、他の男性との約束などすぐに断ればいいと思ったのに、麻衣子は待ち合わせの店に向かっていた。
逃げなさい。たぶんこれは、悪い知らせだから。麻衣子をそう思わせたのは、十年という時間だった。
出会ったその日に好きになった。それなのに意地っ張りな自分が邪魔をして、そっけない態度を取り続けた。
こんな私、好きになるはずないじゃない。想いは十年分も積もっているのに、自信はもうとっくに底をついていた。
たぶん迷子のような足取りで歩いて、麻衣子は街角を曲がった。
日本に来るたび璃子と食事をするいつもの洋食店は、クリスマス仕様なのか、緑の看板に赤いペンでデコレーションがされていた。
赤茶色の明かりが店内を照らしていて、窓辺に座る二人を映していた。
一人はふんわりとした淡いピンクのニットが似合う璃子だった。もう一人は引き締まった体躯を一分の隙もなくスーツで包んだ、晃だった。
どうして二人が? 麻衣子が混乱したのは一瞬だけで、次の瞬間には心が凍り付いていた。
――璃子には敵わないな。
晃が麻衣子には見せないような柔らかい表情で、苦笑しながら言ったのが見えた。
……ああ、そうだったのと、麻衣子は急にいろいろなことが見えた気がした。
言い寄る女性が絶えなかった晃が今まで結婚しなかった理由。引っ込み思案な璃子がいつになく積極的に、晃を紹介したいと言った理由。
大事な話……大事な人を紹介したいと、二人は麻衣子に言おうとしたのだ。
麻衣子は踵を返して走り出していた。雪が降りだしていた。
しゃくりあげて泣いていた。涙が流れた頬に雪がかすめて、痛かった。
ホテルに戻ってからもシーツをかぶって泣いた。世界は真っ暗で、なんにも見えなかった。
どれくらい時間が経ったのか。携帯の着信音がして、麻衣子はシーツの隙間からそれを見た。
「反田君」。入社したときの登録名のまま表示されていて、もう尽きたと思っていた涙がまたあふれた。
きっと泣きすぎてまともな考えなどできなくなっていた。麻衣子はうつろな目で携帯に手を伸ばした。
気が変わった。来てくれるなら、話を聞くわよ。
ホテル名と部屋番号を打ち込んで、麻衣子は携帯を枕元に投げた。
大事な彼女を置いてこんな女のところになんて来ないで。……嫌、それでも来て。
来て、来ないで、来て……。自分でも気持ちの境目がわからなくなった頃、ノックの音が麻衣子の耳に届いた。
日付が変わる時刻、切ったはずの暖房の駆動音がどこかで聞こえる。
シーツだけを体に巻いて戸口に立つ。扉のノブに手をかけて、開いた。
驚いた表情の晃がいた。それだけ確認しただけだった。
「相……」
切望するように聞きたかった声を閉じ込めるようにして、麻衣子は彼にキスをした。