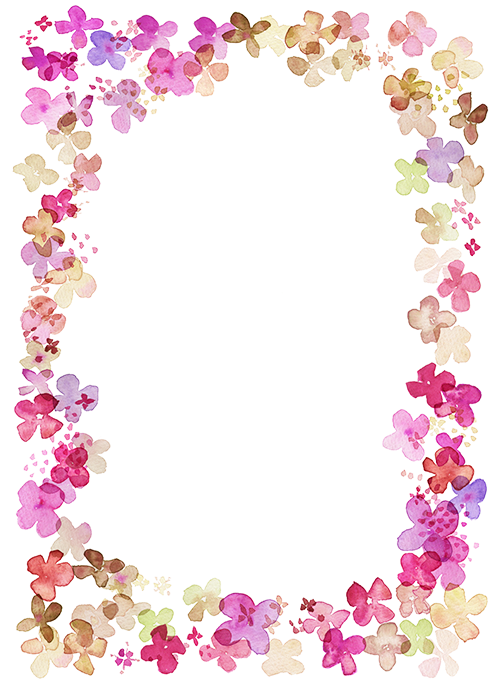麻衣子の療養生活は、箱の中で暮らしているようだった。
帰国してすぐに晃に連れてこられた大病院で、食事から睡眠まで何もかも人の助けを借りながら生活する。
意識が頻繁に途切れて、一日が細切れで過ぎていく。免疫も低下しているから、ささいな風邪でもひどい熱が出た。
熱に浮かされながらコウキの名前を呼んだ。コウキに会わせて、あの子のところに帰してと、自由にならない体をひきずって病室を抜け出した。
「麻衣子、今は駄目だ。さ、温かくして……よくおやすみ」
きっと毎日訪れて麻衣子を抱きしめた晃がいなければ、心ごと病に連れていかれたに違いない。
晃は仕事人間だったはずなのに、夕方になると必ず麻衣子のところにやって来た。
「今日はいまひとつだったよ」
麻衣子に食事を取らせて、体を拭いて、言葉少なく話をする。
「俺はいつも言葉が足らないな」
こんな生活になってから、麻衣子は初めて晃の弱音を聞いた。
晃は厳しい副社長氏だったが、自分にも厳しいことを知った。愚痴というよりため息のような反省をつぶやいて、しっかりしないとなと自分を奮い立たせていた。
「よかった。それ、気に入ったんだな」
それで麻衣子の顔色が良くてたくさん食べたときは、自分のことのように喜んだ。
「免疫を強くしてくれるらしい。あんまり日本では流通してないらしいから、また食事に出せないか頼んでおくよ」
晃が柔らかく笑うのも見慣れなくて、麻衣子は不思議な思いで彼を見上げた。
不思議というなら、晃がどこかに帰っている様子もほとんどないことだった。
晃は、麻衣子が入院している病院のすぐ近くのホテルにロングステイしていると話していた。
麻衣子が就寝するまで病院で過ごして、麻衣子の調子が悪いときは真夜中でも駆けつけた。そのまま病院で朝を迎えることも多くて、とても新婚の妻がいるようには思えなかった。
時々、本当に時々、麻衣子は馬鹿なことを考えた。コウキが元気に過ごしていることさえ確かなら、自分はこの箱の中で一生を終えてもいいかもしれないと。
だって麻衣子は、今の生活に幸せを感じていた。毎日好きな人が自分に会いに来てくれる。心配して、時には笑ってくれる。
私は何を恐れていたのかな。
そう思い至ったとき、麻衣子の心は小さく動いた。
明日終わったっていい。それなら、私はもうちょっと勇気を持つことだってできないかな。
傷つくことが怖くて晃に思いを伝えられなかった。小さな箱に閉じこもるようにして、私なんてと自ら高い壁を作った。
入社したあの日に戻ることは二度とできないけど、思いは今もまだ出会ったあの日と変わらない。
伝えてみようか。晃を困らせるだけ? もしかしたらいつかのクリスマスイブのように、一晩だけ抱いてくれる?
それでもいいと思った。そして、そのときはやって来る。
「麻衣子、大事な話がある」
その日、晃は花束を持って病室を訪れた。
「明日は四月一日だ。何の日か覚えてるか?」
晃が怒ったように自分を見る、そのまなざしは覚えがあった。
「入社の初日で」
そしてあなたと出会った日だと、あの日と同じまなざしをみつめながら麻衣子は答えた。
晃はうなずいて言った。
「明日、退院できる」
晃は麻衣子を見据えて切り出した。
「会社が間に入ってパスポートを作ってくれた。コウキを日本に呼べる」
「こ、コウキを?」
麻衣子は胸に迫った喜びがあまりに大きくて、ほとんど泣いている声で言う。
「何て言えばいいかわからない。……あ、ありがとう! どうしよう、私、私」
言っているうちに涙があふれてきた。
箱の外に出たら、晃と離れなければいけない。でも彼は何よりの幸せを麻衣子に贈ってくれた。それが彼の愛情だと、今なら信じられる。
「元気になったら必ずお返しをするわ。なんでも言って」
「「はい」と、一言言ってほしい」
まばたきをしたとき、麻衣子の目からはらっと涙が落ちた。
晃はあの瑠璃石のように、唐突に花束を押し付けて言った。
「……結婚してくれ、麻衣子」
瞬間、麻衣子はまた夢を見ているのだと思った。
晃を見上げて、震える声で問う。
「でもあなたはもう、璃子と……」
「璃子?」
晃は怪訝そうに問い返す。
「知らなかったのか。璃子はとっくに出海と結婚した」
「え……」
「あと、璃子は養子に入っているから苗字は違うが」
晃は苦笑しながら言った。
「俺の実の妹だ。何か誤解していたな?」
気を取り直すように、晃は真剣な目に戻る。
「返事は?」
その一言は、今まで経験したことがない大きな勇気が必要だった。
でも麻衣子は腕を回して、できる限りの力で晃を抱きしめた。
はいとうなずく。出会ってから心にこめていた思いを、その一言にこめて繰り返す。
もうわかったからと言ってほしくて何度も言ったのに、晃はやめさせようとしなかった。
「もっと言ってくれ。十三年、待ったんだからな」
代わりに麻衣子をきつく抱き寄せて、泣き笑いのような声で言った。
帰国してすぐに晃に連れてこられた大病院で、食事から睡眠まで何もかも人の助けを借りながら生活する。
意識が頻繁に途切れて、一日が細切れで過ぎていく。免疫も低下しているから、ささいな風邪でもひどい熱が出た。
熱に浮かされながらコウキの名前を呼んだ。コウキに会わせて、あの子のところに帰してと、自由にならない体をひきずって病室を抜け出した。
「麻衣子、今は駄目だ。さ、温かくして……よくおやすみ」
きっと毎日訪れて麻衣子を抱きしめた晃がいなければ、心ごと病に連れていかれたに違いない。
晃は仕事人間だったはずなのに、夕方になると必ず麻衣子のところにやって来た。
「今日はいまひとつだったよ」
麻衣子に食事を取らせて、体を拭いて、言葉少なく話をする。
「俺はいつも言葉が足らないな」
こんな生活になってから、麻衣子は初めて晃の弱音を聞いた。
晃は厳しい副社長氏だったが、自分にも厳しいことを知った。愚痴というよりため息のような反省をつぶやいて、しっかりしないとなと自分を奮い立たせていた。
「よかった。それ、気に入ったんだな」
それで麻衣子の顔色が良くてたくさん食べたときは、自分のことのように喜んだ。
「免疫を強くしてくれるらしい。あんまり日本では流通してないらしいから、また食事に出せないか頼んでおくよ」
晃が柔らかく笑うのも見慣れなくて、麻衣子は不思議な思いで彼を見上げた。
不思議というなら、晃がどこかに帰っている様子もほとんどないことだった。
晃は、麻衣子が入院している病院のすぐ近くのホテルにロングステイしていると話していた。
麻衣子が就寝するまで病院で過ごして、麻衣子の調子が悪いときは真夜中でも駆けつけた。そのまま病院で朝を迎えることも多くて、とても新婚の妻がいるようには思えなかった。
時々、本当に時々、麻衣子は馬鹿なことを考えた。コウキが元気に過ごしていることさえ確かなら、自分はこの箱の中で一生を終えてもいいかもしれないと。
だって麻衣子は、今の生活に幸せを感じていた。毎日好きな人が自分に会いに来てくれる。心配して、時には笑ってくれる。
私は何を恐れていたのかな。
そう思い至ったとき、麻衣子の心は小さく動いた。
明日終わったっていい。それなら、私はもうちょっと勇気を持つことだってできないかな。
傷つくことが怖くて晃に思いを伝えられなかった。小さな箱に閉じこもるようにして、私なんてと自ら高い壁を作った。
入社したあの日に戻ることは二度とできないけど、思いは今もまだ出会ったあの日と変わらない。
伝えてみようか。晃を困らせるだけ? もしかしたらいつかのクリスマスイブのように、一晩だけ抱いてくれる?
それでもいいと思った。そして、そのときはやって来る。
「麻衣子、大事な話がある」
その日、晃は花束を持って病室を訪れた。
「明日は四月一日だ。何の日か覚えてるか?」
晃が怒ったように自分を見る、そのまなざしは覚えがあった。
「入社の初日で」
そしてあなたと出会った日だと、あの日と同じまなざしをみつめながら麻衣子は答えた。
晃はうなずいて言った。
「明日、退院できる」
晃は麻衣子を見据えて切り出した。
「会社が間に入ってパスポートを作ってくれた。コウキを日本に呼べる」
「こ、コウキを?」
麻衣子は胸に迫った喜びがあまりに大きくて、ほとんど泣いている声で言う。
「何て言えばいいかわからない。……あ、ありがとう! どうしよう、私、私」
言っているうちに涙があふれてきた。
箱の外に出たら、晃と離れなければいけない。でも彼は何よりの幸せを麻衣子に贈ってくれた。それが彼の愛情だと、今なら信じられる。
「元気になったら必ずお返しをするわ。なんでも言って」
「「はい」と、一言言ってほしい」
まばたきをしたとき、麻衣子の目からはらっと涙が落ちた。
晃はあの瑠璃石のように、唐突に花束を押し付けて言った。
「……結婚してくれ、麻衣子」
瞬間、麻衣子はまた夢を見ているのだと思った。
晃を見上げて、震える声で問う。
「でもあなたはもう、璃子と……」
「璃子?」
晃は怪訝そうに問い返す。
「知らなかったのか。璃子はとっくに出海と結婚した」
「え……」
「あと、璃子は養子に入っているから苗字は違うが」
晃は苦笑しながら言った。
「俺の実の妹だ。何か誤解していたな?」
気を取り直すように、晃は真剣な目に戻る。
「返事は?」
その一言は、今まで経験したことがない大きな勇気が必要だった。
でも麻衣子は腕を回して、できる限りの力で晃を抱きしめた。
はいとうなずく。出会ってから心にこめていた思いを、その一言にこめて繰り返す。
もうわかったからと言ってほしくて何度も言ったのに、晃はやめさせようとしなかった。
「もっと言ってくれ。十三年、待ったんだからな」
代わりに麻衣子をきつく抱き寄せて、泣き笑いのような声で言った。