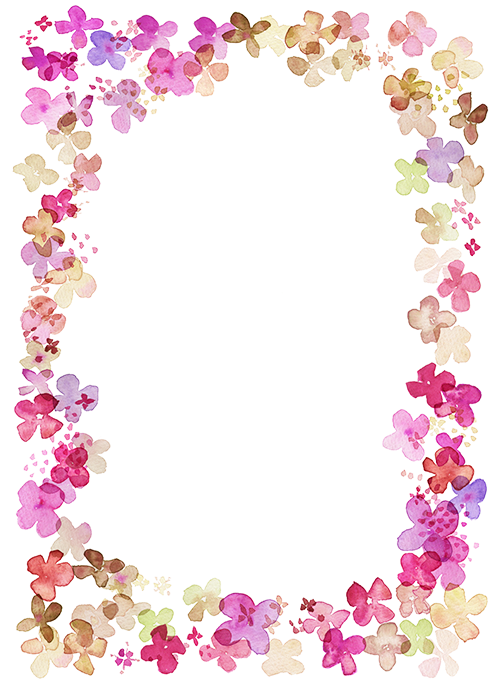麻衣子は深い意識の底で、何度も古い記憶を見ていた。
これは走馬燈だろうかと思いながら、たまらなく懐かしい記憶をみつめていられるのがうれしかった。
それは麻衣子が新城商事に入社したときの、歓迎パーティのときのことだった。
食品輸入を生業とする新城商事は、四月一日に新商品のビュッフェ会を開く。それに合わせて新入社員の歓迎会が行われていた。
そこで、麻衣子は晃と出会った。
「相原です。よろしく」
「反田だ」
隣の席だからあいさつをしたのに、晃は不愛想に苗字だけ言い捨てて、例の怒ったような目で麻衣子を見た。
仕事でいろいろな顧客に営業をしなければいけないのに、こんな態度で仕事ができるのだろうか。
麻衣子の晃に対する初印象は、最悪に近かった。
でも麻衣子は人のことを言えないほど、自分が冷たく見えるのを承知していた。
可愛い、愛想のいい女の子になって気に入られるなんて、お断りだと言ってはばからなかった。本当はちょっとうらやましいなんて、内緒だった。
そんな麻衣子と違って、他の同期の女の子たちは明るくておしゃべりが上手で、すぐに場になじんでいく。
その頃、麻衣子は淡くあこがれている人がいた。
「相原さんが入社試験でレクをした商品も、今日置いてあるんだよ」
「あ……覚えていてくださったんですか」
それが初老の新城社長だった。紳士で、名札をしていなくても新入社員の名前を全員覚えていて、あまり上手とは言えなかった麻衣子のレクのこともちゃんと見ていてくれた人だった。
「もちろん。おいしいジャムだ。ファンになっちゃったよ」
お茶目に笑う社長に、麻衣子は顔を赤くしながらうつむいていた。
そんなときだった。社長が輸入した果物の缶を開けるときに少し指を切ってしまった。
麻衣子はすぐに、鞄に入れていた傷テープを思い出した。
「どうぞ、社長」
「ありがとう」
けど、気の利く女の子たちは当然そういうものを持っている子も多くて、麻衣子の傷テープなどに出番はなかった。
あんな地味で味気ない傷テープ、見せなくてよかった。社長だって可愛い子に巻いてもらった方がうれしいのだから。
そんな卑屈さで淡いあこがれさえ苦い思いにしてしまう自分が情けなくて、麻衣子はポーチを持って化粧室にこもろうとしていた。
「あ、反田君も指切っちゃったの?」
あの一言も会話らしいことをしなかった同期に、先輩の女性が声をかけた。
「巻いてあげるよ。指出して」
晃は目つきは悪いが顔立ちは整っていて、先輩の声は弾んでいた。
あらよかったわね、綺麗なお姉さんに巻いてもらえば。麻衣子がむすっとして顔を背けようとしたら、なぜか晃はこちらをじっと見ていた。
「いいです。俺、べたべたしたの嫌いなんで」
晃はそっけなく断って、さっさと洗面所に向かった。
手を洗ってきたらしい晃は、今度はまっすぐ麻衣子の前にやってきて手を差し出す。
「傷テープ、持ってるだろ。一枚くれるか」
ポーチからのぞいていたのを見られたのだと気まずい思いがしながら、目を逸らして答える。
「ボロいテープよ」
「それでいい」
変な男。麻衣子は少し晃の印象を修正して、しぶしぶというように傷テープを渡す。
晃は自分で傷テープを巻く。でも横目で見ていると、片手だからあまりうまくいっていない。
「貸して」
麻衣子は気が付けば手を出して、晃の指にテープを巻いていた。
近くなる距離に晃も息を詰めている気配がして、麻衣子はなんだか落ち着かなかった。
テープを巻き終わると、麻衣子は憮然として言った。
「悪かったわよ。余計なことして」
じろっと晃はにらむように麻衣子を見て、別にとぼやいた。
そのまま会話なんて続くとは思っていなかったのに、意外にも口を開いたのは晃の方だった。
「初レク、自信あったか」
入社試験のときのことを訊いた彼に、麻衣子は即答した。
「全然」
「俺は全然なかった」
声が重なって、麻衣子ははっと顔を上げる。
「反田君はトップで入社したのに」
「苦手なんだよ。人に思いを話すのは」
麻衣子が思わず晃の顔をみつめると、彼は目を逸らす。
気まずい沈黙があって、麻衣子も晃と目を合わせられなかった。
春の陽気の中、会社のテラスはにぎやかで明るかった。
ふいにビュッフェのテーブルできらっと光るものがあって、麻衣子の口をついて出た言葉があった。
「反田君がレクをした、妻に贈る宝石っていう発想、素敵だった」
テーブルに置いてあるのは瑠璃石の原石だ。晃はそれを染料して使った食花のレクで、見事トップ入社を果たしたのだった。
麻衣子も初めて見たときは信じられなかった。鮮やかな紫の花は、宝石を原料にしながら一般家庭でも買うことができる値段だった。
「王子様しかそんなこと考えないと思った」
きっと一輪食卓に飾ってあっただけで忘れられないディナーになる。こんなことを考えるのは、どんな王子様だろうと思った。
実際会ってみたら、とても不愛想な王子様だったけど。
晃は麻衣子の言葉に、眉間のしわを濃くした。気を悪くするようなことを言ったかと麻衣子がその顔をのぞきこむと、晃は身を引く。
「悪い魔法使いがいいところだ」
苦虫をかみつぶしたように言うので、麻衣子は思わず少し笑った。
新入社員とは思えないほどスーツが似合って、もう気迫みたいなものをまとった人なのに。彼も自分と同期なんだとあらためて気づく。
「やるよ」
「え?」
ふいに麻衣子の前に差し出されたのは、小さな星の浮いたしずく形の瑠璃石だった。
晃のレクをきっかけに新城商事が食花を輸入し始めたので、輸入元の農家が晃に贈ったものだと聞く。
「渡す相手もいないしな」
晃はそっけなく言ったが、麻衣子は耳が熱くなるのを感じた。
馬鹿、こんなのただの気まぐれよ。そう思うのに、麻衣子の心臓はせわしなく音を立てる。
麻衣子は隠すように、さっとそれを手の中に包んだ。晃もすぐに目を逸らした。
「仕事、がんばろうな」
今度こそ社交辞令だったに違いないのに、麻衣子にとっては二度と忘れられない一言だった。
がんばるよ、当たり前でしょ。
……そうじゃないと、あなたと一緒にいられなくなるんでしょう?
そうしてタイの下に瑠璃石を隠したまま、麻衣子の甘くて苦い毎日が始まったのだった。
これは走馬燈だろうかと思いながら、たまらなく懐かしい記憶をみつめていられるのがうれしかった。
それは麻衣子が新城商事に入社したときの、歓迎パーティのときのことだった。
食品輸入を生業とする新城商事は、四月一日に新商品のビュッフェ会を開く。それに合わせて新入社員の歓迎会が行われていた。
そこで、麻衣子は晃と出会った。
「相原です。よろしく」
「反田だ」
隣の席だからあいさつをしたのに、晃は不愛想に苗字だけ言い捨てて、例の怒ったような目で麻衣子を見た。
仕事でいろいろな顧客に営業をしなければいけないのに、こんな態度で仕事ができるのだろうか。
麻衣子の晃に対する初印象は、最悪に近かった。
でも麻衣子は人のことを言えないほど、自分が冷たく見えるのを承知していた。
可愛い、愛想のいい女の子になって気に入られるなんて、お断りだと言ってはばからなかった。本当はちょっとうらやましいなんて、内緒だった。
そんな麻衣子と違って、他の同期の女の子たちは明るくておしゃべりが上手で、すぐに場になじんでいく。
その頃、麻衣子は淡くあこがれている人がいた。
「相原さんが入社試験でレクをした商品も、今日置いてあるんだよ」
「あ……覚えていてくださったんですか」
それが初老の新城社長だった。紳士で、名札をしていなくても新入社員の名前を全員覚えていて、あまり上手とは言えなかった麻衣子のレクのこともちゃんと見ていてくれた人だった。
「もちろん。おいしいジャムだ。ファンになっちゃったよ」
お茶目に笑う社長に、麻衣子は顔を赤くしながらうつむいていた。
そんなときだった。社長が輸入した果物の缶を開けるときに少し指を切ってしまった。
麻衣子はすぐに、鞄に入れていた傷テープを思い出した。
「どうぞ、社長」
「ありがとう」
けど、気の利く女の子たちは当然そういうものを持っている子も多くて、麻衣子の傷テープなどに出番はなかった。
あんな地味で味気ない傷テープ、見せなくてよかった。社長だって可愛い子に巻いてもらった方がうれしいのだから。
そんな卑屈さで淡いあこがれさえ苦い思いにしてしまう自分が情けなくて、麻衣子はポーチを持って化粧室にこもろうとしていた。
「あ、反田君も指切っちゃったの?」
あの一言も会話らしいことをしなかった同期に、先輩の女性が声をかけた。
「巻いてあげるよ。指出して」
晃は目つきは悪いが顔立ちは整っていて、先輩の声は弾んでいた。
あらよかったわね、綺麗なお姉さんに巻いてもらえば。麻衣子がむすっとして顔を背けようとしたら、なぜか晃はこちらをじっと見ていた。
「いいです。俺、べたべたしたの嫌いなんで」
晃はそっけなく断って、さっさと洗面所に向かった。
手を洗ってきたらしい晃は、今度はまっすぐ麻衣子の前にやってきて手を差し出す。
「傷テープ、持ってるだろ。一枚くれるか」
ポーチからのぞいていたのを見られたのだと気まずい思いがしながら、目を逸らして答える。
「ボロいテープよ」
「それでいい」
変な男。麻衣子は少し晃の印象を修正して、しぶしぶというように傷テープを渡す。
晃は自分で傷テープを巻く。でも横目で見ていると、片手だからあまりうまくいっていない。
「貸して」
麻衣子は気が付けば手を出して、晃の指にテープを巻いていた。
近くなる距離に晃も息を詰めている気配がして、麻衣子はなんだか落ち着かなかった。
テープを巻き終わると、麻衣子は憮然として言った。
「悪かったわよ。余計なことして」
じろっと晃はにらむように麻衣子を見て、別にとぼやいた。
そのまま会話なんて続くとは思っていなかったのに、意外にも口を開いたのは晃の方だった。
「初レク、自信あったか」
入社試験のときのことを訊いた彼に、麻衣子は即答した。
「全然」
「俺は全然なかった」
声が重なって、麻衣子ははっと顔を上げる。
「反田君はトップで入社したのに」
「苦手なんだよ。人に思いを話すのは」
麻衣子が思わず晃の顔をみつめると、彼は目を逸らす。
気まずい沈黙があって、麻衣子も晃と目を合わせられなかった。
春の陽気の中、会社のテラスはにぎやかで明るかった。
ふいにビュッフェのテーブルできらっと光るものがあって、麻衣子の口をついて出た言葉があった。
「反田君がレクをした、妻に贈る宝石っていう発想、素敵だった」
テーブルに置いてあるのは瑠璃石の原石だ。晃はそれを染料して使った食花のレクで、見事トップ入社を果たしたのだった。
麻衣子も初めて見たときは信じられなかった。鮮やかな紫の花は、宝石を原料にしながら一般家庭でも買うことができる値段だった。
「王子様しかそんなこと考えないと思った」
きっと一輪食卓に飾ってあっただけで忘れられないディナーになる。こんなことを考えるのは、どんな王子様だろうと思った。
実際会ってみたら、とても不愛想な王子様だったけど。
晃は麻衣子の言葉に、眉間のしわを濃くした。気を悪くするようなことを言ったかと麻衣子がその顔をのぞきこむと、晃は身を引く。
「悪い魔法使いがいいところだ」
苦虫をかみつぶしたように言うので、麻衣子は思わず少し笑った。
新入社員とは思えないほどスーツが似合って、もう気迫みたいなものをまとった人なのに。彼も自分と同期なんだとあらためて気づく。
「やるよ」
「え?」
ふいに麻衣子の前に差し出されたのは、小さな星の浮いたしずく形の瑠璃石だった。
晃のレクをきっかけに新城商事が食花を輸入し始めたので、輸入元の農家が晃に贈ったものだと聞く。
「渡す相手もいないしな」
晃はそっけなく言ったが、麻衣子は耳が熱くなるのを感じた。
馬鹿、こんなのただの気まぐれよ。そう思うのに、麻衣子の心臓はせわしなく音を立てる。
麻衣子は隠すように、さっとそれを手の中に包んだ。晃もすぐに目を逸らした。
「仕事、がんばろうな」
今度こそ社交辞令だったに違いないのに、麻衣子にとっては二度と忘れられない一言だった。
がんばるよ、当たり前でしょ。
……そうじゃないと、あなたと一緒にいられなくなるんでしょう?
そうしてタイの下に瑠璃石を隠したまま、麻衣子の甘くて苦い毎日が始まったのだった。