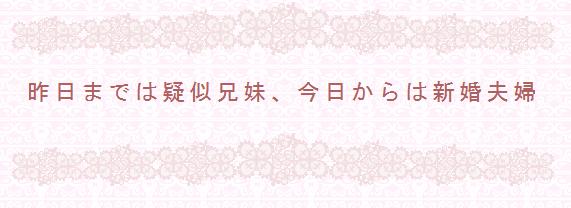
いつか、こうなることは、分かっていたはずだった。
なのに、何となく、見ないフリをしてきた気がする。
物心ついた時からずっと、いずれはこの人と結婚するのだと、言い聞かせられて育ったのに。
この人が、あまりにも何の遠慮も無く、まるで“兄妹”か“友人”のように、私に接してきたから。
私もいつの間にか、許嫁に対する緊張感のようなものを失ってしまっていた。
まだ二人とも幼いうちから、同じ屋根の下に暮らしてきたことも、問題があったような気がする。
両親を一度に事故で喪って、既に婚約の決まっていた私は、両親の遺した財産とともに、予定よりもだいぶ早くこの家に入ることとなった。
もちろん、正式な結婚は、それなりの年齢になってからと決められていたけれど。
義父母は、まるで本当の娘のように私を可愛がってくれた。
この人は、初めのうちは戸惑っていたようだけど、すぐに私を妹のように……いいえ、時には“弟”のように“悪友”のように、遊びにつき合わせるようになった。
昔はおとなしかったはずの私が、すっかりお転婆で、言いたいことをズケズケ言う性格に育ってしまったのは、私の体力や能力を一切考えず無茶な遊びに連れ回した、この人のせいだと思っている。
この人にとっては、きっと『新しい遊び相手ができた』くらいの感覚だったのだろう。
そして、それは私も同じことだった。
出逢った頃は、あまりにも幼過ぎて、“結婚”というものをちゃんと理解できていなかったし、“許嫁”という実感も湧いていなかった。
この家に入ったその時から、私はこの人の“家族”で、きっとそれが大人になっても、ずっとずっと続いていくのだろうと、そんな感覚だった。
だけど、その認識が間違いであったことに、やがて私も気がついた。
家族は家族でも、それは親子やきょうだいとは、まるで違う種類の関係性だ。そのことに、戸惑いを覚えた。
性の知識は増えていっても、この人とそうなることの想像がつかなかった。
この人との関係は、相変わらず兄妹のようで、友達のようで……その状態が心地良過ぎて、いずれこの関係が変わってしまうことなんて、考えられなかった。
心のどこかで、考えることを拒否していたのかも知れない。
だけど、私たちは結局、兄妹でも、ただの友人でもないのだ。
時が来てしまえば当然のように結婚式が行われ、その関係性が“夫婦”へと書き換えられる。
そして今日からは、二人一緒の部屋で寝起きするようになる。
その“寝る”とはもちろん、ただ同じ部屋で睡眠をとるというだけの意味ではない。
新しく調えられた寝室に、二人きりで取り残され、私は極度の緊張と、激しい動悸に震えていた。
いずれこうなることは分かっていたはずなのに。
心の準備ができていないなどと口が裂けても言えないほど、長い長い時間を、共に過ごしてきたのに……。
どうして今さら、こんなにうろたえているのだろう。
「嫌なのか?」
ふいに訊かれて、心臓が跳ねる。
「ち……違っ……嫌じゃない……嫌じゃ……ない……けど……だけど……っ」
この人のことが嫌いなわけはない。
むしろ実の家族を喪った私にとっては、世界の誰よりも身近で、大切な人だ。
だから、嫌なわけではない……はずだ。なのに……
「……上手く、言えない……けど……」
この気持ちを、どう伝えたら良いのか分からない。
自分の心のはずなのに、自分自身でさえ上手く理解できなくて、言葉にならない。
ふいに手を伸ばされて、ビクリと身体が震える。
けれど優しいその指は、無意識ににじんでいた涙を拭ってくれただけだった。
「泣くなよ。怒ってるわけじゃない」
彷徨っていた視線を戻して真っ直ぐに見つめると、彼は困ったように微笑んでいた。
「戸惑うよな、そりゃ。いきなり『今日から夫婦です』って言われても、急には気持ちを切り換えられないよな」
その言葉に、そう感じていたのが私だけではなかったのだと、今頃になって気づかされる。
私たちはきっと、近くにい過ぎたのだ。
肉体を結ばなくても居心地の良い完璧な関係を、既に築き過ぎていた。
「気持ちがついて行かないのに、焦って無理にするようなことでもないだろ。急には変われないなら、ゆっくり“夫婦”になっていけばいい。俺たちは、これからもずっと一緒にいるんだから」
「でも……いいの……?」
おそるおそる見上げると、彼はただ苦笑していた。
「無理をさせて、お前の俺を見る目が変わることの方がキツいからな」
そう言って彼は、いつものように、私の頭を優しく叩く。
「ただ……あんまり長くは待たせないでくれよな。俺の方は割と早く、その気になりそうな気がするんでな」
「え……」
思わず問うような声が出ていた。
彼は私の目を避けるように、あわてて横を向く。
その耳朶は、心なしか、ほのかに赤く染まっているようだった。
「……問い返すなよ。恥ずかしいだろ」
本当に恥ずかしそうに、わざとぶっきらぼうに呟かれた声に、何だか私まで恥ずかしくなる。頬が熱くなり、胸の辺りがむずがゆくなる。
これは、昨日までには感じたことのなかったものだ。
ただの兄妹や友人なら、たぶん、感じるはずのない気持ち……。
けれど、決して不快なものではない。むしろ、どこか甘くて、ざわざわと胸が湧き立つような……。
「……では、お言葉に甘えて。今宵はもうお休みしましょう。……旦那様」
昨日までとは違う呼び名を、初めて口にしてみる。
彼は、はっとしたように私を見た後、微かに笑った。
「そうだな。おやすみ」
ほんの少し手を触れただけで、その日は二人、早々に床に入った。
けれど、物思うことが多くて、すぐには眠れる気がしなかった。
明日からもきっと、少しだけ触れ合ってみたり、少しだけ今までと違う言葉を交わしてみたり、そうしてそのことに照れて、互いに頬を赤らめたりしながら、私たちは少しずつ、関係の形を変えていくのだろう。
想像するだけでどきどきするし、未知への恐怖もあるけれど、決して嫌なことではない。
贈り物のリボンを解いて、包みを剥がして、少しずつ少しずつ開けていくような……そんな幸せな期待感が胸にある。
私たちは、ゆっくりと少しずつ、夫婦になっていく。
明日からも、きっとずっと、共に人生を歩いていくのだ。

