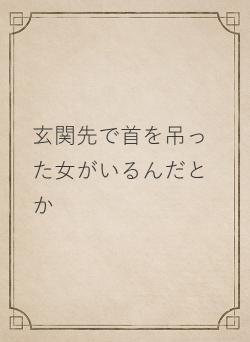頭からガブリとやられたのかすでに顔はない。
しかし灰色の体と長いシッポがネズミであったことを物語っていた。
「い、いっ……」
これは須賀君にとって大切な食事なんだ。
果物だけじゃ偏ってしまうから、咄嗟に狩をしてしまったんだ。
頭でそう理解しようとしても難しかった。
サッと血の気が引いていき、気持ちが悪いという気持ちがわいてきてしまう。
そして悲鳴を上げそうになったとき「お前、なに食べてんの?」という声が聞こえてきたので、悲鳴は喉の奥に引っ込んでしまった。
ショックを受けた状態のまま顔を上げると、いつの間にかバドミントンをしていた3人組みが近くに立っていた。
あたしたちと同じ1年生だけど、あまりいい噂を聞かない3人組みだ。
騒いで授業を中断させたり、外でよくない友人と会ったりしていると聞いたことがあった。
あたしは咄嗟に身構えて3人をにらみつけた。
「もしかしてお前ネズミ食ってんのか?」
「う~わ、キモッ!」
3人の言葉に嫌な雰囲気が広がっていくのがわかった。
「す、須賀君はスカンクだからだよ!」
咄嗟に須賀君をかばうように前に出た。
だけどあたしのことなんて視界に入っていないようで、3人は須賀君の腕をつかんで取り囲んでしまった。
「ちょ、ちょっと!」
3人ともどんなトレーニングをしているのか知らないが、高校1年生とは思えないほど筋肉がついている。
背も高くて、小さな須賀君にとってはひとたまりもない存在だ。
しかし灰色の体と長いシッポがネズミであったことを物語っていた。
「い、いっ……」
これは須賀君にとって大切な食事なんだ。
果物だけじゃ偏ってしまうから、咄嗟に狩をしてしまったんだ。
頭でそう理解しようとしても難しかった。
サッと血の気が引いていき、気持ちが悪いという気持ちがわいてきてしまう。
そして悲鳴を上げそうになったとき「お前、なに食べてんの?」という声が聞こえてきたので、悲鳴は喉の奥に引っ込んでしまった。
ショックを受けた状態のまま顔を上げると、いつの間にかバドミントンをしていた3人組みが近くに立っていた。
あたしたちと同じ1年生だけど、あまりいい噂を聞かない3人組みだ。
騒いで授業を中断させたり、外でよくない友人と会ったりしていると聞いたことがあった。
あたしは咄嗟に身構えて3人をにらみつけた。
「もしかしてお前ネズミ食ってんのか?」
「う~わ、キモッ!」
3人の言葉に嫌な雰囲気が広がっていくのがわかった。
「す、須賀君はスカンクだからだよ!」
咄嗟に須賀君をかばうように前に出た。
だけどあたしのことなんて視界に入っていないようで、3人は須賀君の腕をつかんで取り囲んでしまった。
「ちょ、ちょっと!」
3人ともどんなトレーニングをしているのか知らないが、高校1年生とは思えないほど筋肉がついている。
背も高くて、小さな須賀君にとってはひとたまりもない存在だ。