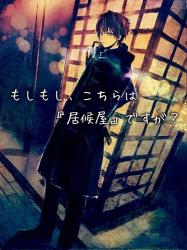長月のはじめ、深緑に金糸雀色や鶏冠石、銀朱が宿りはじめたモミジは、枯れ落ちた葉で寂しくなりつつある木々を温かく包み込む。
一宮 悟は、この日は午前六時と早起きであった。土曜日の休日であるにも関わらず。
それもそのはず、悟はため込んだ小遣いを母の誕生日プレゼントに使うため、都会に出る予定だったのだ。
もはや悟にとって毎年恒例の行事になりつつある。悟はあまり遠出をするのが好きではない。確かにここはど田舎で何もない不便な場所であるが、電車や新幹線を乗り継いで苦労してまで遊びに行きたいとは思わない。要は面倒なのである。それを同学年の友人に言えば「変わり者」「時代遅れ」「考えがジジ臭い」と言われる始末。それを毎度毎度いわれるたびに悟は放っておいてほしいとうんざりするのである。都会に憧れる気持ちはわからないわけではないのだが、悟の場合は面倒臭さが圧倒的に上回るのだ。
その甲斐あって、小遣いはほとんど使わず仕舞いで溜まっていく一方であり、使い道が日頃から世話になっている両親への誕生日プレゼントになるのだ。
誕生日プレゼントといっても、何を渡せば良いのかさっぱりなので毎年バースデーケーキを一個購入するだけになる。いらない物を押しつけられても使い道に困るだけだろうというのが悟の考えだ。ただその考えの中にプレゼントを考えるのが面倒臭いというのも含まれている。
母の誕生日がたまたま土曜日であったが、平日が誕生日だった場合には悟は小学校の放課後にそのまま都会へ出て予約したケーキ屋に取りに行っていた。
買いに行くケーキ屋は毎年異なる。インターネットの特集で取り上げられていたものや評価の高いものから選択する。膨大な情報量からたった一つの店を選択するのは集中力のいる作業である。これが自分用であるならば適当に選んでさっさと済ませてしまうところだがそうもいかない。せっかく食べてもらうのだから、美味しいものを食べてほしいと悟は思う。
面倒臭がりで都会に出たがらない悟の性格をよく知っている悟の両親は、にんまりと嬉しそうな顔をして悟を遠目でこっそりと見送りをする。悟は両親が寝ているうちに黙って抜き足差し足と忍者のように音を立てないようにして家を出たつもりだったが、ほとんど意味をなさなかった。しかもその事実を悟は知る由もない。
予約したケーキ屋は『パティスリー・カ・ルーラ』というところだ。都内で有名なケーキ屋なだけに行列を見せている。
悟は携帯電話で時間を確認する。現在時刻十時十六分であった。予約の客は別の列であり、並んで受け取るまでそう時間はかからなかった。
バースデーケーキは五八五〇円だった。蝋燭はいるかと店員に言われたが悟は首を横に振って断る。父の誕生日で蝋燭を刺した時は特に問題はなかったのだが、母の誕生日でそれを実行するのは躊躇われた。女性という生き物は年齢に大層敏感らしく、歳をとったのだと自覚したくないのだそうだ。それを蝋燭という目に見えるかたちにされると非常に辛いらしい。
形が崩れないように両手で大事に抱え込んで悟はケーキ屋をあとにする。
信号機が青に切り替わったことを確認して横断歩道をわたる。中央に差し掛かったところで、自動車のクラクションの大きな音が悟の耳をつんざく。合間に人々の悲鳴が混ざって聞こえた。進む足を止めて音のした方に顔を向けば、大型トラックが数センチ前までに迫っていたことに気がつく。
思考が働く間も無く、身体が少し浮きいつのまにかコンクリートにうつ伏せになる。二度瞬きして見えたのは一羽の黒い烏。
「おまえ、死ぬの?」
人間の言葉を喋るはずもないのに、その烏は首を傾げながらそう話したように見えた。「喋ったの?」そう問うために悟は口を開こうにも上手く動かないし身体も動きやしない。
そこではじめて悟は理解する。自分がトラックに跳ねられたことに──。
人々の悲鳴を聞きながら痛みを感じる間も無く悟は意識を飛ばした。
一宮 悟は、この日は午前六時と早起きであった。土曜日の休日であるにも関わらず。
それもそのはず、悟はため込んだ小遣いを母の誕生日プレゼントに使うため、都会に出る予定だったのだ。
もはや悟にとって毎年恒例の行事になりつつある。悟はあまり遠出をするのが好きではない。確かにここはど田舎で何もない不便な場所であるが、電車や新幹線を乗り継いで苦労してまで遊びに行きたいとは思わない。要は面倒なのである。それを同学年の友人に言えば「変わり者」「時代遅れ」「考えがジジ臭い」と言われる始末。それを毎度毎度いわれるたびに悟は放っておいてほしいとうんざりするのである。都会に憧れる気持ちはわからないわけではないのだが、悟の場合は面倒臭さが圧倒的に上回るのだ。
その甲斐あって、小遣いはほとんど使わず仕舞いで溜まっていく一方であり、使い道が日頃から世話になっている両親への誕生日プレゼントになるのだ。
誕生日プレゼントといっても、何を渡せば良いのかさっぱりなので毎年バースデーケーキを一個購入するだけになる。いらない物を押しつけられても使い道に困るだけだろうというのが悟の考えだ。ただその考えの中にプレゼントを考えるのが面倒臭いというのも含まれている。
母の誕生日がたまたま土曜日であったが、平日が誕生日だった場合には悟は小学校の放課後にそのまま都会へ出て予約したケーキ屋に取りに行っていた。
買いに行くケーキ屋は毎年異なる。インターネットの特集で取り上げられていたものや評価の高いものから選択する。膨大な情報量からたった一つの店を選択するのは集中力のいる作業である。これが自分用であるならば適当に選んでさっさと済ませてしまうところだがそうもいかない。せっかく食べてもらうのだから、美味しいものを食べてほしいと悟は思う。
面倒臭がりで都会に出たがらない悟の性格をよく知っている悟の両親は、にんまりと嬉しそうな顔をして悟を遠目でこっそりと見送りをする。悟は両親が寝ているうちに黙って抜き足差し足と忍者のように音を立てないようにして家を出たつもりだったが、ほとんど意味をなさなかった。しかもその事実を悟は知る由もない。
予約したケーキ屋は『パティスリー・カ・ルーラ』というところだ。都内で有名なケーキ屋なだけに行列を見せている。
悟は携帯電話で時間を確認する。現在時刻十時十六分であった。予約の客は別の列であり、並んで受け取るまでそう時間はかからなかった。
バースデーケーキは五八五〇円だった。蝋燭はいるかと店員に言われたが悟は首を横に振って断る。父の誕生日で蝋燭を刺した時は特に問題はなかったのだが、母の誕生日でそれを実行するのは躊躇われた。女性という生き物は年齢に大層敏感らしく、歳をとったのだと自覚したくないのだそうだ。それを蝋燭という目に見えるかたちにされると非常に辛いらしい。
形が崩れないように両手で大事に抱え込んで悟はケーキ屋をあとにする。
信号機が青に切り替わったことを確認して横断歩道をわたる。中央に差し掛かったところで、自動車のクラクションの大きな音が悟の耳をつんざく。合間に人々の悲鳴が混ざって聞こえた。進む足を止めて音のした方に顔を向けば、大型トラックが数センチ前までに迫っていたことに気がつく。
思考が働く間も無く、身体が少し浮きいつのまにかコンクリートにうつ伏せになる。二度瞬きして見えたのは一羽の黒い烏。
「おまえ、死ぬの?」
人間の言葉を喋るはずもないのに、その烏は首を傾げながらそう話したように見えた。「喋ったの?」そう問うために悟は口を開こうにも上手く動かないし身体も動きやしない。
そこではじめて悟は理解する。自分がトラックに跳ねられたことに──。
人々の悲鳴を聞きながら痛みを感じる間も無く悟は意識を飛ばした。