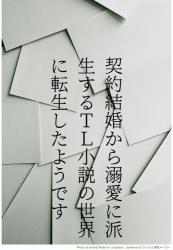***
行ってみると、貫一お宮之像の前は別れ話をするには向いていなかった。
音声解説が延々流れているし、特段道が広い訳でもないので長いこと立ち止まっていることもできない。
「なんか、よくあるがっかり名所だな」
「タケルさん、一応芸能人なんだからそういうこと言っちゃダメだよ」
「でもお前もちょっと思っただろう」
「黙秘します」
半ば認めたも同然だが、一応そう言った。
その後向かった秘宝館も今日は休館で、結局私達は早々にホテルへとやってきた。
早めのチェックインができそうだったので部屋に入ると、私はちょっと驚いてしまう。
「ねえ、予約した部屋とちがくない? 露天風呂とかついてるし広いよ?」
「広いにこしたことねぇだろ」
「でも広すぎるし、自動でアップグレードしてくれたのかな。お客さんあんまりいなさそうだし」
「……さあな」
素っ気なく言いながら浴衣に着替え始めるタケルさんに、私は思わず見惚れた。
昔はだらしのない身体だったのに、ライブやらイベントやらで歌ったり踊ったりするようになってから、タケルさんの身体はかなり引き締まった。
元々運動はできるようだが、私と出会った頃は売れないせいでかなり腐っていたらしく、色々と残念だったのだ。
「タケルさん、最近良い男になったね」
思わずこぼすと、タケルさんが得意げな顔をする。
こういうときに謙遜せず、調子に乗るところが私は好きだ。
「気づくのが遅すぎだ」
「うん、そうだね」
もっと早くに気づいていれば、こんなに好きにならなかったのになと思う。
タケルさんは、私にとっては無理めな男の人だ。
人気者で、容姿もそこそこ良くて、身体も逞しくて、無駄に声が良い。
そんな彼をつなぎ止めておくのは、ほどほどの私にはかなり無理がある。
「タケルさん」
「何だ?」
「別れようか」
貫一お宮之像の前で言えなかった言葉を口にすると、得意げだった顔がもの凄く間の抜けた物になる。
お陰で、言葉と一緒にこぼれそうになった涙が引っ込んだ。
「何の冗談だ」
「冗談じゃなくて」
「部屋に入って10分もたたずにそういうこと言うか普通!」
「ああそっか、せめてお風呂入れば良かったね」
「風呂の後でも言うなよ」
「じゃあご飯の後?」
いつが良いタイミングだったのだろうかと考えていると、私の前にタケルさんがどっかりと腰を下ろした。
「なんで、別れるとか言うんだ」
「ごめん、何となく言うなら今かなって思ったの」
「別れ話を、何となく始めるな」
「だっていつも、私たちって何となく何かが始まるじゃない」
「否定はしねぇけど、この旅行は何となく来たわけじゃない。部屋だって、アップグレードしたのは俺だぞ!」
そこでため息をついて、タケルさんは側に落ちていた旅行鞄に突然腕をツッコむ。
「これだって、何となく買ったわけじゃねぇ……」
言うなり取り出したのは、小さな小箱だった。
「それ、指輪とか入ってそうな箱だね」
「入ってんだよ!」
「え?」
「めっちゃ高いの入ってんだよ!」
「え?」
「だから雑な反応繰り返すな!」
怒りながらタケルさんが箱を上げると、見事なダイヤがついた指輪が入っていた。
「旅行でもして、雰囲気の良いところで渡そうってこの1ヶ月延々悩んでたのに、行きたがるのは熱海で秘宝館だし、旅館に入るなり別れようとか言うし、今めっちゃ死にたい気分なんだけど!!」
「死ぬのは、ダメだと思う。ファンが泣いちゃうし」
「まずはお前が泣け!」
言うなりタケルさんは私の手を掴み、勝手に指輪をはめてしまう。
「すごい、ぴったり」
「お前が寝てる間に必死に測ったんだよ」
「ご苦労をおかけました」
「……で、これ見ても気持ちは変わらねぇか?」
ぶすっとした顔で見つめられ、私は指輪のはまった薬指を見つめる。
「タケルさん」
「……何だ?」
「タケルさんは、私のこと好きなの?」
「それは、だな……」
タケルさんの苦しげな声につられて顔を上げると、彼は顔を真っ赤にしていた。
「え、照れてる?」
「当たり前だろ!」
「5万人の前であんな恥ずかしい台詞言ったのに?」
「お前の前だから恥ずかしいんだろ!」
逆ギレをしたあげく、タケルさんは私を乱暴に抱き締めるとキスをしてくる。
「今、キスで誤魔化そうとしてるよね?」
「言葉にするのは、恥ずかしいんだよ」
「声の仕事してるくせに」
「元々、引っ込み思案で口が悪いのを治したくて専門入ったんだよ俺は! そもそも声優じゃ無くてアナウンサーになりたかったくらいだし……」
「え、そうなの?」
「でも自分の意見とか全然言えねぇし、演技の才能が無駄にあるって言われて声優になったんだ」
演技でならどんな台詞でもためらいなく言えるのに、自分の言葉となるととたんに難しいのだとタケルさんはこぼす。
「でもお前は、好きって言わなくても怒らないし、側にいてくれるから甘えてた」
抱き締める腕の力を強めながら、タケルさんは声を震わせる。
「別れるなんていうなよ。何となく始まった関係だけど、俺はお前と離れるとか無理だ」
一生無理だと付け加えられた言葉は、タケルさんなりの愛の言葉だった。
どんな役にもなれるし、5万人の前でも恥ずかしい台詞を言える一方で、彼は私が思っている以上に不器用で情けない人なのかもしれない。
そしてそういう部分に、私は愛おしさを感じていた。「好き」だと言われなくても、もういいと思えた。
「私も、側にいたい」
「なら別れるとか二度と言うな」
「でも……」
「つか、なんで? 何が不満? 言ったら直すから全部吐け!」
不安と困惑の混じった声はあまりに必死だったから、私はついうっかり自分の考えを口にした。
タケルさんの彼女に相応しくないと思っていたこと。だから頑張るのを辞めようとしていたこと。
そして本当は「別れようか?」と告げた瞬間、胸が苦しくて泣きそうになっていたこと――。
それを打ち明けると、タケルさんは十回くらい「このバカ……」と相槌を打ち、そのたび私の頭を優しく撫でてくれた。
「お前がもし、もっと平凡な彼氏が良いていうなら転職を考えてもいい」
「それ、ファンが泣くよ?」
「お前が泣くより良いだろ」
「今の台詞、ちょっとキュンときたかも」
「ちょっとじゃなくて、もっとキュンとしろよ」
「してるしてる」
「お前、俺に雑だよな……。まあ、そういう所がその……好ましいんだけど」
「そこで好きって言えないところがタケルさんだよね」
「なんでか、その二文字はやたらと恥ずかしくて言えねぇ」
そう言ってから、タケルさんは恥ずかしそうにうつむく。
「この際だから白状するが、恋愛ゲームの仕事受けたのも、それが理由だからな」
「え?」
「仕事で連呼したら、お前にも言えるかなと思って」
「え?」
「その『え?』は驚きの方か? それとも馬鹿にしてるのか?」
「驚きだよ。私、タケルさんのことを馬鹿にしたことはないよ」
「でも、馬鹿っぽいだろ。未だにお前の前ではその……言えないし……」
それが悔しいのか、タケルさんは真っ赤な顔で口をモゴモゴさせている。
「でもそのせいで距離まで置かれかけたんなら、この手の仕事……もうやめようかな」
「だから、それはファンが泣くよ」
「じゃあもう二度と、絶対に、別れるとか言うなよ」
念押ししながら縋るように抱き締められ、肩にグリグリと頭を押しつけられると、今更のように申し訳な気持ちになってくる。
「うん、言わない」
「結婚もしてくれるか?」
「私でよければ」
「お前じゃないとだめだ」
好きとは言えないけれど、今の言葉は十分すぎる愛の言葉だ。
「蹴られるより、ずっといいや」
「おい、蹴られるって何だ?」
怪訝そうなタケルさんに、貫一お宮之像の前で別れるつもりだったというと、彼は小さく吹き出した。
「蹴らねぇよ。むしろ俺がお宮みたいにへたり込んでたトコだ」
「あ、確かに」
「だからもう二度と、いなくなろうとするな」
「うん」
「絶対だからな」
無駄な美声で念を押し、タケルさんは私にキスをする。
「何となく始まった恋だけど、恋は恋だよね」
優しい彼の笑顔を見ていると、そんな当たり前のことに私はようやく気づくことが出来る。
「私、思ってたよりタケルさんのこと好きみたい」
「『思ってたより』と『みたい』はいらねぇだろ」
「私、タケルさんのこと好き」
「……俺も、……だ」
「へたれだなぁ」
「わかってるよ!」
よく聞こえなかったけれど、彼が届けようとしてくれた愛の言葉を私は笑顔で受け取った。
なんとなくの恋【END】
行ってみると、貫一お宮之像の前は別れ話をするには向いていなかった。
音声解説が延々流れているし、特段道が広い訳でもないので長いこと立ち止まっていることもできない。
「なんか、よくあるがっかり名所だな」
「タケルさん、一応芸能人なんだからそういうこと言っちゃダメだよ」
「でもお前もちょっと思っただろう」
「黙秘します」
半ば認めたも同然だが、一応そう言った。
その後向かった秘宝館も今日は休館で、結局私達は早々にホテルへとやってきた。
早めのチェックインができそうだったので部屋に入ると、私はちょっと驚いてしまう。
「ねえ、予約した部屋とちがくない? 露天風呂とかついてるし広いよ?」
「広いにこしたことねぇだろ」
「でも広すぎるし、自動でアップグレードしてくれたのかな。お客さんあんまりいなさそうだし」
「……さあな」
素っ気なく言いながら浴衣に着替え始めるタケルさんに、私は思わず見惚れた。
昔はだらしのない身体だったのに、ライブやらイベントやらで歌ったり踊ったりするようになってから、タケルさんの身体はかなり引き締まった。
元々運動はできるようだが、私と出会った頃は売れないせいでかなり腐っていたらしく、色々と残念だったのだ。
「タケルさん、最近良い男になったね」
思わずこぼすと、タケルさんが得意げな顔をする。
こういうときに謙遜せず、調子に乗るところが私は好きだ。
「気づくのが遅すぎだ」
「うん、そうだね」
もっと早くに気づいていれば、こんなに好きにならなかったのになと思う。
タケルさんは、私にとっては無理めな男の人だ。
人気者で、容姿もそこそこ良くて、身体も逞しくて、無駄に声が良い。
そんな彼をつなぎ止めておくのは、ほどほどの私にはかなり無理がある。
「タケルさん」
「何だ?」
「別れようか」
貫一お宮之像の前で言えなかった言葉を口にすると、得意げだった顔がもの凄く間の抜けた物になる。
お陰で、言葉と一緒にこぼれそうになった涙が引っ込んだ。
「何の冗談だ」
「冗談じゃなくて」
「部屋に入って10分もたたずにそういうこと言うか普通!」
「ああそっか、せめてお風呂入れば良かったね」
「風呂の後でも言うなよ」
「じゃあご飯の後?」
いつが良いタイミングだったのだろうかと考えていると、私の前にタケルさんがどっかりと腰を下ろした。
「なんで、別れるとか言うんだ」
「ごめん、何となく言うなら今かなって思ったの」
「別れ話を、何となく始めるな」
「だっていつも、私たちって何となく何かが始まるじゃない」
「否定はしねぇけど、この旅行は何となく来たわけじゃない。部屋だって、アップグレードしたのは俺だぞ!」
そこでため息をついて、タケルさんは側に落ちていた旅行鞄に突然腕をツッコむ。
「これだって、何となく買ったわけじゃねぇ……」
言うなり取り出したのは、小さな小箱だった。
「それ、指輪とか入ってそうな箱だね」
「入ってんだよ!」
「え?」
「めっちゃ高いの入ってんだよ!」
「え?」
「だから雑な反応繰り返すな!」
怒りながらタケルさんが箱を上げると、見事なダイヤがついた指輪が入っていた。
「旅行でもして、雰囲気の良いところで渡そうってこの1ヶ月延々悩んでたのに、行きたがるのは熱海で秘宝館だし、旅館に入るなり別れようとか言うし、今めっちゃ死にたい気分なんだけど!!」
「死ぬのは、ダメだと思う。ファンが泣いちゃうし」
「まずはお前が泣け!」
言うなりタケルさんは私の手を掴み、勝手に指輪をはめてしまう。
「すごい、ぴったり」
「お前が寝てる間に必死に測ったんだよ」
「ご苦労をおかけました」
「……で、これ見ても気持ちは変わらねぇか?」
ぶすっとした顔で見つめられ、私は指輪のはまった薬指を見つめる。
「タケルさん」
「……何だ?」
「タケルさんは、私のこと好きなの?」
「それは、だな……」
タケルさんの苦しげな声につられて顔を上げると、彼は顔を真っ赤にしていた。
「え、照れてる?」
「当たり前だろ!」
「5万人の前であんな恥ずかしい台詞言ったのに?」
「お前の前だから恥ずかしいんだろ!」
逆ギレをしたあげく、タケルさんは私を乱暴に抱き締めるとキスをしてくる。
「今、キスで誤魔化そうとしてるよね?」
「言葉にするのは、恥ずかしいんだよ」
「声の仕事してるくせに」
「元々、引っ込み思案で口が悪いのを治したくて専門入ったんだよ俺は! そもそも声優じゃ無くてアナウンサーになりたかったくらいだし……」
「え、そうなの?」
「でも自分の意見とか全然言えねぇし、演技の才能が無駄にあるって言われて声優になったんだ」
演技でならどんな台詞でもためらいなく言えるのに、自分の言葉となるととたんに難しいのだとタケルさんはこぼす。
「でもお前は、好きって言わなくても怒らないし、側にいてくれるから甘えてた」
抱き締める腕の力を強めながら、タケルさんは声を震わせる。
「別れるなんていうなよ。何となく始まった関係だけど、俺はお前と離れるとか無理だ」
一生無理だと付け加えられた言葉は、タケルさんなりの愛の言葉だった。
どんな役にもなれるし、5万人の前でも恥ずかしい台詞を言える一方で、彼は私が思っている以上に不器用で情けない人なのかもしれない。
そしてそういう部分に、私は愛おしさを感じていた。「好き」だと言われなくても、もういいと思えた。
「私も、側にいたい」
「なら別れるとか二度と言うな」
「でも……」
「つか、なんで? 何が不満? 言ったら直すから全部吐け!」
不安と困惑の混じった声はあまりに必死だったから、私はついうっかり自分の考えを口にした。
タケルさんの彼女に相応しくないと思っていたこと。だから頑張るのを辞めようとしていたこと。
そして本当は「別れようか?」と告げた瞬間、胸が苦しくて泣きそうになっていたこと――。
それを打ち明けると、タケルさんは十回くらい「このバカ……」と相槌を打ち、そのたび私の頭を優しく撫でてくれた。
「お前がもし、もっと平凡な彼氏が良いていうなら転職を考えてもいい」
「それ、ファンが泣くよ?」
「お前が泣くより良いだろ」
「今の台詞、ちょっとキュンときたかも」
「ちょっとじゃなくて、もっとキュンとしろよ」
「してるしてる」
「お前、俺に雑だよな……。まあ、そういう所がその……好ましいんだけど」
「そこで好きって言えないところがタケルさんだよね」
「なんでか、その二文字はやたらと恥ずかしくて言えねぇ」
そう言ってから、タケルさんは恥ずかしそうにうつむく。
「この際だから白状するが、恋愛ゲームの仕事受けたのも、それが理由だからな」
「え?」
「仕事で連呼したら、お前にも言えるかなと思って」
「え?」
「その『え?』は驚きの方か? それとも馬鹿にしてるのか?」
「驚きだよ。私、タケルさんのことを馬鹿にしたことはないよ」
「でも、馬鹿っぽいだろ。未だにお前の前ではその……言えないし……」
それが悔しいのか、タケルさんは真っ赤な顔で口をモゴモゴさせている。
「でもそのせいで距離まで置かれかけたんなら、この手の仕事……もうやめようかな」
「だから、それはファンが泣くよ」
「じゃあもう二度と、絶対に、別れるとか言うなよ」
念押ししながら縋るように抱き締められ、肩にグリグリと頭を押しつけられると、今更のように申し訳な気持ちになってくる。
「うん、言わない」
「結婚もしてくれるか?」
「私でよければ」
「お前じゃないとだめだ」
好きとは言えないけれど、今の言葉は十分すぎる愛の言葉だ。
「蹴られるより、ずっといいや」
「おい、蹴られるって何だ?」
怪訝そうなタケルさんに、貫一お宮之像の前で別れるつもりだったというと、彼は小さく吹き出した。
「蹴らねぇよ。むしろ俺がお宮みたいにへたり込んでたトコだ」
「あ、確かに」
「だからもう二度と、いなくなろうとするな」
「うん」
「絶対だからな」
無駄な美声で念を押し、タケルさんは私にキスをする。
「何となく始まった恋だけど、恋は恋だよね」
優しい彼の笑顔を見ていると、そんな当たり前のことに私はようやく気づくことが出来る。
「私、思ってたよりタケルさんのこと好きみたい」
「『思ってたより』と『みたい』はいらねぇだろ」
「私、タケルさんのこと好き」
「……俺も、……だ」
「へたれだなぁ」
「わかってるよ!」
よく聞こえなかったけれど、彼が届けようとしてくれた愛の言葉を私は笑顔で受け取った。
なんとなくの恋【END】