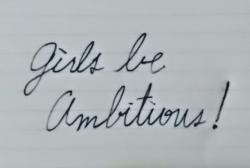「でもさ、イッテツって違うじゃん。いつもあたしのこと大切にしてくれてるし、優しくしてくれるし」
「それは…当たり前なんやないかなぁ」
「当たり前?」
「だって、ようこんなうちみたいなオッサン相手にしてくれとるなーって」
「イッテツ、自信持ちなよ」
あたしは大丈夫だから、と言った途端、泉は自らの意識の外にあった想いに気が付いたらしく、
「…よくみたらイケメンだしね」
と、照れくさそうに小さな声で言うと、軽くそっぽを向いた。
その週末。
アルバイトの帰り道、泉は一徹を駅前で見かけた。
誰かと話しているようである。
「…あ」
見るとそれは清楚な、紺色のワンピースがよく似合う黒髪の、切れ長の眼をした美女である。
雑踏のなか、何やら話していたらしいが、
「…まぁはるかのことかてあるから、このぐらいにするわ」
というような関西弁が風に乗って聞こえた。
「はるかって…誰だろ」
泉は一瞬、頭から全てが消えてしまうような気がした。