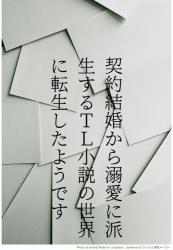***
キスで釣られた秋くんが猛烈に仕事をしている隙に、私が向かったのは寝室である。
寝室の棚には、想い出のアルバムが隠されることなく棚に並んでいる。
それを取り出し眺めては「あんなことがあったねぇ」「こんなことがあったねぇ」と二人で思い出話に花を咲かせることも多い。
しかし明らかに年齢も違うし、そもそも秋くんは人間ではなさそうだ。
だとしたら、もしかしてこのアルバムは偽物なのかも知れないと思い、一人の時にこっそり確認しようと思ったのである。
まず最初に、私は高校のアルバムを開け――
「……いま、おかしなものが見えたな」
そして、静かに閉じた。
思わず心の声を口に出したのは、自分を落ち着かせる為である。
それからもう一度、クラスの集合写真を見た私はその場に突っ伏した。
「秋くん……見た目変わってないぞ……」
集合写真でも、個別の写真でも、秋くんは40歳のおじさんのままだった。
おじさんが学ランを着ていた。
正直、予想外の展開すぎて私は混乱していた。
そもそも、このアルバム自体が偽物であるのではと私は疑っていたのだ。
それかアルバムは本物だが、実は鬼瓦おにがわら秋人あきひとなんて男は存在せず、写真が一枚もないという展開もあり得ると思っていた。
「でも、秋くんいるな……」
もの凄くおかしな絵面にはなっているが、秋くんはいた。
そして写真を見た限り、私達の間にある思い出の出来事は、確かに存在しているらしい。
修学旅行で一緒に京都に行った時の写真も、運動会の二人三脚で見事にコケたときの写真も、合唱コンクールで優勝してみんなで抱き合って泣いた写真も、親友のマサルが転校してきた初日にクラスのみんなでカラオケに行った時の写真も、アルバムにはちゃんと残っている。
ただし、秋くんの顔はおじさんだった。
今と全く変わっていなかった。
それから私は、中学校のアルバムを取り出した。
みると、やっぱり秋くんはいた。おじさんだった。
続いて小学校のアルバムを取り出してみると、やっぱり秋くんはいた。
やはりおじさんで、ランドセルが全く似合っていなかった。
最後に恐る恐る幼稚園のアルバムを開いてみた。
スモックを着たおじさんが、そこには写っていた。
外見と服装のギャップの凄まじさに、私は一瞬目眩を覚えた。
「どうしよう、謎が深まった」
嘘としか思えない写真ばかりが並んでいるが、何となくこのアルバムは本物だという気がしてくる。
偽造されたものではなく、それぞれの幼稚園や学校が普通に撮影し、編集し、生徒に配ったアルバムに違いない。
と言うことは、秋くんはやっぱりずっと私の側にいたのだ。
幼なじみであることは嘘ではなく、幼稚園から今の今まで私達は側にいたのだろう。
そしてその時からずっと、秋くんは年を取っていない。
それか歳はとっていても、老けないのかもしれない。なにせ鬼だから。
「いいなぁ」
思わず羨ましく思っていると、ふいに部屋の扉がガラッと開いた。
「仕事終わった!!」
言うなり入ってきたのは、もちろん秋くんである。
「ちょっと早すぎない?」
「ご褒美の為なら、俺は頑張れる男だ」
だとしたら、スモックを着て幼稚園に通っていたのも何かのご褒美があったからなのだろうか。
「ねえ秋くん、突然だけど幼稚園のこと覚えてる?」
「まあ、ほどほどには」
と言いつつ、黒歴史でも思い出したような表情を秋くんは浮かべた。
「私とは、そこで出会ったんだっけ」
「いや、その前からお前とは遊んでいた気がする」
「ああそっか、家がお隣だったしね」
「思えばあの頃から、環奈は可愛かったな」
しみじみという秋くんの顔に、嘘をついている気配はなかった。
「だから、お前が幼稚園に行くと言い出した時はすっごく寂しかったんだよな」
「……ねえ、それで同じ幼稚園来たとかそういうオチはないよね?」
「いや、その通りだ。婆やに土下座して、俺も幼稚園に行きたいとねだった」
婆やとは、両親のいない秋くんを育てた『ミツ婆ちゃん』のことだ。
顔がもの凄く怖いせいで『鬼婆』と近所の子供には恐れられていたが、私のことは今なお可愛がってくれる優しいおばあちゃんである。
「ねだったら、入れてくれたの?」
「最初は行く必要ないと怒られたが、幼稚園に行かないと環奈と遊べなくなると涙ながらに訴えたら許可してくれた」
そりゃあ必要ないでしょうねと内心突っ込みながら、私は隣に座る秋くんの肩にそっと寄りかかる。
「私と遊べなくなるの、そんなにやだったんだ」
「好きだったからな、お前が」
いつになく甘い声で言われ、私はついドキッとしてしまう。
スモック姿の秋くんは色々衝撃的だったが、それを見てもなお私は彼の色気にコロッとやられてしまうようだ。
「出会ったときから、俺にはお前しかいないとピンときたんだ」
「でも幼稚園のころだよ? 私、すっごくちっちゃかったし」
「けど小さい頃から環奈はこんな俺にも優しくしてくれただろ? 頑張って握ったおにぎりを俺にくれたり、本を読んでくれたり、ひとつしかないお菓子を一緒に食べようって言ってくれたり、そういう所が大好きだったんだ」
そのあたりの記憶は、私にも何となくある。
私は引っ込み思案で、基本的に友達を作るのが苦手だ。だからいつもいつも家の縁側で絵ばかり書いた。
そんなとき、垣根の向こうから秋くんがひょいと顔を出したのだ。
改めて思い出すと、小さな子供が隣の家をのぞき込めるわけはない。
そして目を閉じて思い出してみると、こちらを見ていた顔は今と同じものだった気もする。
私が絵を書くのを見て、秋くんは「上手だな」と褒めてくれた。それが嬉しくて、話しかけてくれた秋くんの姿がとてもかっこよくて、私は生まれて初めて「お友達になって」と彼に声をかけたのだ。
それからは垣根の隙間を通り、隣の家に忍び込んでは秋くんと一緒に遊んだ。
ずっとやってみたかったおままごとにも彼は付き合ってくれて、「じゃあ秋くんは奥さんね! 私は旦那さんになる!」なんて言いながらフリフリのエプロンを着せたこともある。
そんな無茶ぶりにも彼はいつも笑って付き合ってくれたから、私もすぐ彼の事が好きになったのだ。
だから幼稚園に行くことが決まったたときは、もう秋くんと遊べないのかと凄くがっかりした記憶がある。
「そういえば私、秋くんがいない幼稚園になんて行きたくないって泣いた気がする」
「そんなことも、あったかもな」
「もしかして、一緒に行くって言ってくれたのはそのせい?」
「さてどうだったかな……。俺も歳だし、そこまでは覚えていない」
覚えていないと言いつつ、私を見つめる顔はもの凄く優しかった。
そしてそれを見れば、彼がスモックを着てくれた本当の理由は何となくわかる。
「ねえ、幼稚園で一番楽しかった事って何?」
ちょっとした興味本位で尋ねてみると、秋くんが私を抱き寄せながら考え込む。
「おやつの時間かな」
「でも秋くん、いつも私におやつくれてたよね」
首をひねると、秋くんはにっこり笑う。
「おやつを食べる環奈を見るのが好きだったんだ。美味しいって言いながらほっぺを押さえる様が可愛くて可愛くて……」
思い出すだけではぁはぁしてきたと身悶える秋くんを落ち着かせながら、私は苦笑する。
「秋くん、私のこと好きすぎでしょ」
「ああ、大好きすぎて毎日困ってる」
本当に困っているという顔で、秋くんが私と額をコツンと合わせた。
「困るくらいなら、逆に私を嫌いになろうとは思わなかったの?」
「なれないから余計に困ったんだ。俺は多分一生、お前を愛することをやめられない」
幼なじみ設定に無理がある顔だし、彼は私に大きな嘘をついているけれど、その言葉と表情は本物だと思えた。
「どんな事があっても、俺はお前から絶対離れられないし離れない」
「重い愛だね」
「嫌か?」
「嫌じゃないから結婚したんだよ。よくよく考えるとさ、幼稚園の頃からずっと溺愛されてきたよね私。我ながら、良くあの愛を全部受け入れてきたと思うわ」
「だって環奈はずっと可愛いから、愛さずにはいられないだろ」
「いやでも出会って25年? 26年? ともかくずっとだよ? 飽きたときないの?」
「全くないな」
きっぱりと、秋くんは言い切った。
「そういう環奈はどうなんだ? 飽きたり、嫌だと思った事あるか?」
「これっぽっちもない」
途端に、秋くんの顔が甘く蕩ける。
でもその目の奥に、ほんの少しだけ寂しげな光が見えた気がした。
「じゃあこれからも嫌われないように、良い夫でいられるように頑張る」
「別に頑張らなくても良いよ。何があっても嫌ったりしないし」
「いやでも、そうは言っても何があるかわからないだろ? 俺は絶対死ぬまで大好きだけど、その愛が重すぎて嫌になるかもしれないし」
口ではそんなことを言っていたが、彼の不安はきっと別の理由だ。
「俺は、お前にだけは絶対嫌われたくないんだ……」
その言葉を、私は今までの人生で何度も何度も聞かされてきた。
そのたび「ありえないよ」と笑ってきたが、秘密を知ってしまった今は秋くんの不安もわかる。
多分彼は人間じゃない。
年齢も、やっぱりわからない。
そんな秋くんが私と一緒にいるのはきっと普通のことじゃないし、そのために彼は私を含めた色んな人を欺いてきたのだろう。
でもそれは全部、私と離れたくないからに違いない。
「嫌うなんて、ありえないよ」
だから今日も私は断言した。
いつもと変わらぬ、笑顔を添えて。
「私もね、秋くんが大好きなの」
言い終わる間もなくキスをされ、秋くんの大きな体が私をガシッと抱き締める。
その腕の力から、彼が全身全霊を込めて私の「大好き」に答えようとしているのがわかった。
「秋くん、今まだ朝の十一時だよ?」
「イチャイチャするのに時間は関係ないし、明日から環奈はまた忙しくなるだろう」
「……それ、もしかして今日は一日中イチャイチャしようってこと?」
「俺の奥さんは察しが良くて助かる」
まあ幼稚園の頃からずっと一緒にいるしねと笑って、今度は私のほうから秋くんにキスをした。
キスで釣られた秋くんが猛烈に仕事をしている隙に、私が向かったのは寝室である。
寝室の棚には、想い出のアルバムが隠されることなく棚に並んでいる。
それを取り出し眺めては「あんなことがあったねぇ」「こんなことがあったねぇ」と二人で思い出話に花を咲かせることも多い。
しかし明らかに年齢も違うし、そもそも秋くんは人間ではなさそうだ。
だとしたら、もしかしてこのアルバムは偽物なのかも知れないと思い、一人の時にこっそり確認しようと思ったのである。
まず最初に、私は高校のアルバムを開け――
「……いま、おかしなものが見えたな」
そして、静かに閉じた。
思わず心の声を口に出したのは、自分を落ち着かせる為である。
それからもう一度、クラスの集合写真を見た私はその場に突っ伏した。
「秋くん……見た目変わってないぞ……」
集合写真でも、個別の写真でも、秋くんは40歳のおじさんのままだった。
おじさんが学ランを着ていた。
正直、予想外の展開すぎて私は混乱していた。
そもそも、このアルバム自体が偽物であるのではと私は疑っていたのだ。
それかアルバムは本物だが、実は鬼瓦おにがわら秋人あきひとなんて男は存在せず、写真が一枚もないという展開もあり得ると思っていた。
「でも、秋くんいるな……」
もの凄くおかしな絵面にはなっているが、秋くんはいた。
そして写真を見た限り、私達の間にある思い出の出来事は、確かに存在しているらしい。
修学旅行で一緒に京都に行った時の写真も、運動会の二人三脚で見事にコケたときの写真も、合唱コンクールで優勝してみんなで抱き合って泣いた写真も、親友のマサルが転校してきた初日にクラスのみんなでカラオケに行った時の写真も、アルバムにはちゃんと残っている。
ただし、秋くんの顔はおじさんだった。
今と全く変わっていなかった。
それから私は、中学校のアルバムを取り出した。
みると、やっぱり秋くんはいた。おじさんだった。
続いて小学校のアルバムを取り出してみると、やっぱり秋くんはいた。
やはりおじさんで、ランドセルが全く似合っていなかった。
最後に恐る恐る幼稚園のアルバムを開いてみた。
スモックを着たおじさんが、そこには写っていた。
外見と服装のギャップの凄まじさに、私は一瞬目眩を覚えた。
「どうしよう、謎が深まった」
嘘としか思えない写真ばかりが並んでいるが、何となくこのアルバムは本物だという気がしてくる。
偽造されたものではなく、それぞれの幼稚園や学校が普通に撮影し、編集し、生徒に配ったアルバムに違いない。
と言うことは、秋くんはやっぱりずっと私の側にいたのだ。
幼なじみであることは嘘ではなく、幼稚園から今の今まで私達は側にいたのだろう。
そしてその時からずっと、秋くんは年を取っていない。
それか歳はとっていても、老けないのかもしれない。なにせ鬼だから。
「いいなぁ」
思わず羨ましく思っていると、ふいに部屋の扉がガラッと開いた。
「仕事終わった!!」
言うなり入ってきたのは、もちろん秋くんである。
「ちょっと早すぎない?」
「ご褒美の為なら、俺は頑張れる男だ」
だとしたら、スモックを着て幼稚園に通っていたのも何かのご褒美があったからなのだろうか。
「ねえ秋くん、突然だけど幼稚園のこと覚えてる?」
「まあ、ほどほどには」
と言いつつ、黒歴史でも思い出したような表情を秋くんは浮かべた。
「私とは、そこで出会ったんだっけ」
「いや、その前からお前とは遊んでいた気がする」
「ああそっか、家がお隣だったしね」
「思えばあの頃から、環奈は可愛かったな」
しみじみという秋くんの顔に、嘘をついている気配はなかった。
「だから、お前が幼稚園に行くと言い出した時はすっごく寂しかったんだよな」
「……ねえ、それで同じ幼稚園来たとかそういうオチはないよね?」
「いや、その通りだ。婆やに土下座して、俺も幼稚園に行きたいとねだった」
婆やとは、両親のいない秋くんを育てた『ミツ婆ちゃん』のことだ。
顔がもの凄く怖いせいで『鬼婆』と近所の子供には恐れられていたが、私のことは今なお可愛がってくれる優しいおばあちゃんである。
「ねだったら、入れてくれたの?」
「最初は行く必要ないと怒られたが、幼稚園に行かないと環奈と遊べなくなると涙ながらに訴えたら許可してくれた」
そりゃあ必要ないでしょうねと内心突っ込みながら、私は隣に座る秋くんの肩にそっと寄りかかる。
「私と遊べなくなるの、そんなにやだったんだ」
「好きだったからな、お前が」
いつになく甘い声で言われ、私はついドキッとしてしまう。
スモック姿の秋くんは色々衝撃的だったが、それを見てもなお私は彼の色気にコロッとやられてしまうようだ。
「出会ったときから、俺にはお前しかいないとピンときたんだ」
「でも幼稚園のころだよ? 私、すっごくちっちゃかったし」
「けど小さい頃から環奈はこんな俺にも優しくしてくれただろ? 頑張って握ったおにぎりを俺にくれたり、本を読んでくれたり、ひとつしかないお菓子を一緒に食べようって言ってくれたり、そういう所が大好きだったんだ」
そのあたりの記憶は、私にも何となくある。
私は引っ込み思案で、基本的に友達を作るのが苦手だ。だからいつもいつも家の縁側で絵ばかり書いた。
そんなとき、垣根の向こうから秋くんがひょいと顔を出したのだ。
改めて思い出すと、小さな子供が隣の家をのぞき込めるわけはない。
そして目を閉じて思い出してみると、こちらを見ていた顔は今と同じものだった気もする。
私が絵を書くのを見て、秋くんは「上手だな」と褒めてくれた。それが嬉しくて、話しかけてくれた秋くんの姿がとてもかっこよくて、私は生まれて初めて「お友達になって」と彼に声をかけたのだ。
それからは垣根の隙間を通り、隣の家に忍び込んでは秋くんと一緒に遊んだ。
ずっとやってみたかったおままごとにも彼は付き合ってくれて、「じゃあ秋くんは奥さんね! 私は旦那さんになる!」なんて言いながらフリフリのエプロンを着せたこともある。
そんな無茶ぶりにも彼はいつも笑って付き合ってくれたから、私もすぐ彼の事が好きになったのだ。
だから幼稚園に行くことが決まったたときは、もう秋くんと遊べないのかと凄くがっかりした記憶がある。
「そういえば私、秋くんがいない幼稚園になんて行きたくないって泣いた気がする」
「そんなことも、あったかもな」
「もしかして、一緒に行くって言ってくれたのはそのせい?」
「さてどうだったかな……。俺も歳だし、そこまでは覚えていない」
覚えていないと言いつつ、私を見つめる顔はもの凄く優しかった。
そしてそれを見れば、彼がスモックを着てくれた本当の理由は何となくわかる。
「ねえ、幼稚園で一番楽しかった事って何?」
ちょっとした興味本位で尋ねてみると、秋くんが私を抱き寄せながら考え込む。
「おやつの時間かな」
「でも秋くん、いつも私におやつくれてたよね」
首をひねると、秋くんはにっこり笑う。
「おやつを食べる環奈を見るのが好きだったんだ。美味しいって言いながらほっぺを押さえる様が可愛くて可愛くて……」
思い出すだけではぁはぁしてきたと身悶える秋くんを落ち着かせながら、私は苦笑する。
「秋くん、私のこと好きすぎでしょ」
「ああ、大好きすぎて毎日困ってる」
本当に困っているという顔で、秋くんが私と額をコツンと合わせた。
「困るくらいなら、逆に私を嫌いになろうとは思わなかったの?」
「なれないから余計に困ったんだ。俺は多分一生、お前を愛することをやめられない」
幼なじみ設定に無理がある顔だし、彼は私に大きな嘘をついているけれど、その言葉と表情は本物だと思えた。
「どんな事があっても、俺はお前から絶対離れられないし離れない」
「重い愛だね」
「嫌か?」
「嫌じゃないから結婚したんだよ。よくよく考えるとさ、幼稚園の頃からずっと溺愛されてきたよね私。我ながら、良くあの愛を全部受け入れてきたと思うわ」
「だって環奈はずっと可愛いから、愛さずにはいられないだろ」
「いやでも出会って25年? 26年? ともかくずっとだよ? 飽きたときないの?」
「全くないな」
きっぱりと、秋くんは言い切った。
「そういう環奈はどうなんだ? 飽きたり、嫌だと思った事あるか?」
「これっぽっちもない」
途端に、秋くんの顔が甘く蕩ける。
でもその目の奥に、ほんの少しだけ寂しげな光が見えた気がした。
「じゃあこれからも嫌われないように、良い夫でいられるように頑張る」
「別に頑張らなくても良いよ。何があっても嫌ったりしないし」
「いやでも、そうは言っても何があるかわからないだろ? 俺は絶対死ぬまで大好きだけど、その愛が重すぎて嫌になるかもしれないし」
口ではそんなことを言っていたが、彼の不安はきっと別の理由だ。
「俺は、お前にだけは絶対嫌われたくないんだ……」
その言葉を、私は今までの人生で何度も何度も聞かされてきた。
そのたび「ありえないよ」と笑ってきたが、秘密を知ってしまった今は秋くんの不安もわかる。
多分彼は人間じゃない。
年齢も、やっぱりわからない。
そんな秋くんが私と一緒にいるのはきっと普通のことじゃないし、そのために彼は私を含めた色んな人を欺いてきたのだろう。
でもそれは全部、私と離れたくないからに違いない。
「嫌うなんて、ありえないよ」
だから今日も私は断言した。
いつもと変わらぬ、笑顔を添えて。
「私もね、秋くんが大好きなの」
言い終わる間もなくキスをされ、秋くんの大きな体が私をガシッと抱き締める。
その腕の力から、彼が全身全霊を込めて私の「大好き」に答えようとしているのがわかった。
「秋くん、今まだ朝の十一時だよ?」
「イチャイチャするのに時間は関係ないし、明日から環奈はまた忙しくなるだろう」
「……それ、もしかして今日は一日中イチャイチャしようってこと?」
「俺の奥さんは察しが良くて助かる」
まあ幼稚園の頃からずっと一緒にいるしねと笑って、今度は私のほうから秋くんにキスをした。