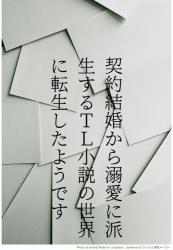***
歯を磨き、私の為にと朝食を作る秋くんには、やっぱり角が生えている。
最初は洗顔の時だけだったけれど、角が見える時間は少しずつ増えていいて、最近は朝食を食べているときも生えている。
「今日は、環奈が食べたいって言ってたフレンチトーストにした!」
そう言って出てきたのは、カフェのものにも勝る豪華なフレンチトーストである。
料理が得意な秋くんは、どんなものでも簡単に作ってしまうのだ。
そしてそのレパートリーはほぼ全て、私の好きなものだ。
秋くんは、とにかく私に甘い。
私が食べたいといったものは何でも作ってくれるし、それが市販品であればどんなに遠くのものでも買ってきてくれる。
ある時なんて、テレビに映ったフランスのマカロンを「食べてみたいな」といった翌日、食べに行こうと航空券を渡されたこともある。
そんな有様なのでなるべく物はねだらないようにしているが、何も言わないとそれはそれで「最近我が儘を言ってくれない」と拗ねるので、毎日のご飯は思うがまま食べたいものをおねだりすることにしている。
もちろん、家で作れる範囲のものだが。
「相変わらず、秋くんのご飯は美味しいし綺麗だしすごいね」
「そう言われる為に頑張ってる」
だからもっと褒めてと前屈みになってくるので、私はそっと頭を撫でる。
その際指先に触れた角は、硬くて冷たかった。
「環奈によしよしされるの、好きだ」
「結婚九年目の夫の台詞とは思えないよそれ」
「俺は死ぬまで言い続けるぞ。よしよしもされたいし」
顔も良くて、家事も仕事も出来る良い男だが、私の前では若干残念なのが玉に瑕だ。
私を甘やかすのが好きな秋くんは、私に甘えるのも大好きなのだ。
家の外では落ち着いた大人の男という雰囲気なの、私と二人きりになると飼い主にお腹を見せる柴犬状態である。
そこが可愛いと思ったからこそ結婚したのだが、もし彼が本当に人間でないのだとしたらちょっと心配だ。
角が生えているということは、十中八九彼は鬼だろう。
でも目の前にいる秋くんは角が生えていても柴犬である。それも「お腹撫でて」と四六時中身悶えている野性を忘れた柴犬だ。そんな有様で、鬼として生きていけるのかとつい心配になってしまう。
「環奈、よしよしのついでにキスもしないか」
「まずご飯食べようよ」
「じゃあご飯の後で」
「あ、その前にネームの確認してくれない? 秋くんのシナリオから、ちょっと代えちゃったとこあるから」
キスしたら仕事どころじゃなくなるからと思い、私は言った。
途端に秋くんは、この世の終わりを見たような顔をする。
「そんな顔しても駄目だよ? 私は今日お休みだけど、秋くんお仕事いっぱい溜まってるでしょ?」
見た目は鬼だが、秋くんはこう見えて、『乙女心の代弁者』とまで呼ばれる恋愛小説家さんなのだ。
ちなみに私の方は、少女漫画家である。
元々秋くんは私の描く漫画の原作者だったが、それをアニメ化する際にシナリオを書いたところ大好評で、以来恋愛映画のシナリオや小説も書くようになったのだ。
お陰で押しも押されぬ人気作家であるが、当人は「環奈の原作しかやりたくない」と贅沢な我が儘を言っては、できるだけ仕事を減らそうと日々画策している。
減った仕事の合間にやりたいのはもちろん私とイチャイチャすることで、いい年なんだからもうちょっと落ち着けよと思うことも結構ある。
――そう、秋くんは鬼であると同時に、たぶん……いやかなりいい年なのだ。
でも、私達は幼なじみである。
幼稚園から、小中高大学までずぅーと一緒だった。
しかし角が見え始めた頃に気づいたのだが、秋くんの容姿はどう考えても29歳には見えない。明らかに40そこそこなのである。
「……環奈とキスしたい」
そんな男が、十代の男でもそうそうしない甘え方をしてくるのである。
正直そこが可愛いとは思うが、外見のギャップはあまりに激しい。
「可愛い声だしてるけど、秋くんいくつなの?」
「29歳」
うん、明らかな年齢詐称だ。外見年齢も、精神年齢も全然あってない。
「秋くんってさ、中身10歳くらいだよね」
「正直、10歳になりたい。そうしたら仕事もしなくて良いし、ずっと環奈にくっついていられるし」
「10歳児とは結婚出来ないよ」
「……そ、それはそれで困るな。これはもう、絶対外したくないし……」
結婚指輪をじっと見つめる秋くんは、本気で困った顔をしている。
それがあまりに可愛かったから、私は立ち上がって彼にそっとキスをした。
「あとでもっといっぱいしてあげるから、今日はちゃんとお仕事してね」
「……ぁ、ぁぃ」
初心な乙女かと突っ込みたくなる真っ赤な顔で、秋くんは言った。
その頭からは角が消えていたが、やっぱりどう見ても目の前にいるのは40そこそこのおっさんである。
別に40歳でも良いけど、むしろ渋くてかっこよくて好きだけど、さすがにこのままスルーし続けるのには無理があるなと最近思うようになってきた。
何より、こんなおかしな状況を今の今まで全く疑問に思っていなかったのがおかしい。
確かに私は人より鈍いと言われるし、ぼんやりしているし、普通の人がすぐ気づくようなことに気づかずスルーすることも多い。
とはいえ夫が鬼であるならそれに気づくと思うのだ。
でも角が見えるまで、私は彼が人間でない可能性に全く気づいていなかった。
その上明らかに同い年ではないのに、彼とは幼稚園からずっと一緒にいたという記憶もある。
けれどよくよく思い出そうとすると、私は秋くんの若いときの顔が浮かばない。
もしかしたら私は、世に言う『化かされている』という状況なのかもしれない。鬼と言えば妖怪の代表格であるし、それくらいの力があってもおかしくない。
しかし何故、秋くんが私を化かしているのかはわからない。その目的も、察しがつかない。
彼が本物の鬼であるなら私を騙して食べる為――なんて可能性もあるが、もし食べるなら普通もっとピチピチな時に食べるだろう。
私は29で、仕事柄徹夜も多いし出不精で不健康なので、食べて美味しい要素はたぶんない。
もしくは私に特別な力があって、それを狙う悪い妖怪からこっそり守ってくれている――なんて夢女子的なことも考えたが、やっぱり自分の年齢を考えるとそれもない気がする。
その手の漫画チックな展開があるなら、普通十八歳くらいの時にもっとなにか起きていても不思議ではない。
でも私達の青春はアニメとコミケに費やされたし、妖怪が絡んだラブバトル的なことは皆無だった。
となれば、一体何故こんな状況になっているのか。
そんな疑問は日々膨れ上がり、さすがに無視するのも辛くなってきた。
だから私は、ついに覚悟を決めた。
秋くんが本当は何歳かなのか、今日こそは絶対に調べてやるのだ。
歯を磨き、私の為にと朝食を作る秋くんには、やっぱり角が生えている。
最初は洗顔の時だけだったけれど、角が見える時間は少しずつ増えていいて、最近は朝食を食べているときも生えている。
「今日は、環奈が食べたいって言ってたフレンチトーストにした!」
そう言って出てきたのは、カフェのものにも勝る豪華なフレンチトーストである。
料理が得意な秋くんは、どんなものでも簡単に作ってしまうのだ。
そしてそのレパートリーはほぼ全て、私の好きなものだ。
秋くんは、とにかく私に甘い。
私が食べたいといったものは何でも作ってくれるし、それが市販品であればどんなに遠くのものでも買ってきてくれる。
ある時なんて、テレビに映ったフランスのマカロンを「食べてみたいな」といった翌日、食べに行こうと航空券を渡されたこともある。
そんな有様なのでなるべく物はねだらないようにしているが、何も言わないとそれはそれで「最近我が儘を言ってくれない」と拗ねるので、毎日のご飯は思うがまま食べたいものをおねだりすることにしている。
もちろん、家で作れる範囲のものだが。
「相変わらず、秋くんのご飯は美味しいし綺麗だしすごいね」
「そう言われる為に頑張ってる」
だからもっと褒めてと前屈みになってくるので、私はそっと頭を撫でる。
その際指先に触れた角は、硬くて冷たかった。
「環奈によしよしされるの、好きだ」
「結婚九年目の夫の台詞とは思えないよそれ」
「俺は死ぬまで言い続けるぞ。よしよしもされたいし」
顔も良くて、家事も仕事も出来る良い男だが、私の前では若干残念なのが玉に瑕だ。
私を甘やかすのが好きな秋くんは、私に甘えるのも大好きなのだ。
家の外では落ち着いた大人の男という雰囲気なの、私と二人きりになると飼い主にお腹を見せる柴犬状態である。
そこが可愛いと思ったからこそ結婚したのだが、もし彼が本当に人間でないのだとしたらちょっと心配だ。
角が生えているということは、十中八九彼は鬼だろう。
でも目の前にいる秋くんは角が生えていても柴犬である。それも「お腹撫でて」と四六時中身悶えている野性を忘れた柴犬だ。そんな有様で、鬼として生きていけるのかとつい心配になってしまう。
「環奈、よしよしのついでにキスもしないか」
「まずご飯食べようよ」
「じゃあご飯の後で」
「あ、その前にネームの確認してくれない? 秋くんのシナリオから、ちょっと代えちゃったとこあるから」
キスしたら仕事どころじゃなくなるからと思い、私は言った。
途端に秋くんは、この世の終わりを見たような顔をする。
「そんな顔しても駄目だよ? 私は今日お休みだけど、秋くんお仕事いっぱい溜まってるでしょ?」
見た目は鬼だが、秋くんはこう見えて、『乙女心の代弁者』とまで呼ばれる恋愛小説家さんなのだ。
ちなみに私の方は、少女漫画家である。
元々秋くんは私の描く漫画の原作者だったが、それをアニメ化する際にシナリオを書いたところ大好評で、以来恋愛映画のシナリオや小説も書くようになったのだ。
お陰で押しも押されぬ人気作家であるが、当人は「環奈の原作しかやりたくない」と贅沢な我が儘を言っては、できるだけ仕事を減らそうと日々画策している。
減った仕事の合間にやりたいのはもちろん私とイチャイチャすることで、いい年なんだからもうちょっと落ち着けよと思うことも結構ある。
――そう、秋くんは鬼であると同時に、たぶん……いやかなりいい年なのだ。
でも、私達は幼なじみである。
幼稚園から、小中高大学までずぅーと一緒だった。
しかし角が見え始めた頃に気づいたのだが、秋くんの容姿はどう考えても29歳には見えない。明らかに40そこそこなのである。
「……環奈とキスしたい」
そんな男が、十代の男でもそうそうしない甘え方をしてくるのである。
正直そこが可愛いとは思うが、外見のギャップはあまりに激しい。
「可愛い声だしてるけど、秋くんいくつなの?」
「29歳」
うん、明らかな年齢詐称だ。外見年齢も、精神年齢も全然あってない。
「秋くんってさ、中身10歳くらいだよね」
「正直、10歳になりたい。そうしたら仕事もしなくて良いし、ずっと環奈にくっついていられるし」
「10歳児とは結婚出来ないよ」
「……そ、それはそれで困るな。これはもう、絶対外したくないし……」
結婚指輪をじっと見つめる秋くんは、本気で困った顔をしている。
それがあまりに可愛かったから、私は立ち上がって彼にそっとキスをした。
「あとでもっといっぱいしてあげるから、今日はちゃんとお仕事してね」
「……ぁ、ぁぃ」
初心な乙女かと突っ込みたくなる真っ赤な顔で、秋くんは言った。
その頭からは角が消えていたが、やっぱりどう見ても目の前にいるのは40そこそこのおっさんである。
別に40歳でも良いけど、むしろ渋くてかっこよくて好きだけど、さすがにこのままスルーし続けるのには無理があるなと最近思うようになってきた。
何より、こんなおかしな状況を今の今まで全く疑問に思っていなかったのがおかしい。
確かに私は人より鈍いと言われるし、ぼんやりしているし、普通の人がすぐ気づくようなことに気づかずスルーすることも多い。
とはいえ夫が鬼であるならそれに気づくと思うのだ。
でも角が見えるまで、私は彼が人間でない可能性に全く気づいていなかった。
その上明らかに同い年ではないのに、彼とは幼稚園からずっと一緒にいたという記憶もある。
けれどよくよく思い出そうとすると、私は秋くんの若いときの顔が浮かばない。
もしかしたら私は、世に言う『化かされている』という状況なのかもしれない。鬼と言えば妖怪の代表格であるし、それくらいの力があってもおかしくない。
しかし何故、秋くんが私を化かしているのかはわからない。その目的も、察しがつかない。
彼が本物の鬼であるなら私を騙して食べる為――なんて可能性もあるが、もし食べるなら普通もっとピチピチな時に食べるだろう。
私は29で、仕事柄徹夜も多いし出不精で不健康なので、食べて美味しい要素はたぶんない。
もしくは私に特別な力があって、それを狙う悪い妖怪からこっそり守ってくれている――なんて夢女子的なことも考えたが、やっぱり自分の年齢を考えるとそれもない気がする。
その手の漫画チックな展開があるなら、普通十八歳くらいの時にもっとなにか起きていても不思議ではない。
でも私達の青春はアニメとコミケに費やされたし、妖怪が絡んだラブバトル的なことは皆無だった。
となれば、一体何故こんな状況になっているのか。
そんな疑問は日々膨れ上がり、さすがに無視するのも辛くなってきた。
だから私は、ついに覚悟を決めた。
秋くんが本当は何歳かなのか、今日こそは絶対に調べてやるのだ。