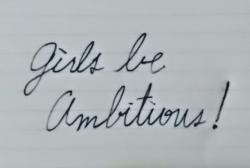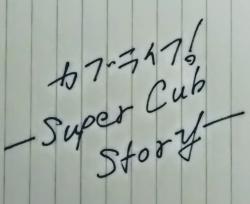合宿も後半になった頃、ダンスパートを担ってきた薫にフォーメーション練習のさなか、異変が起きた。
「足首が…」
練習は直ちに中断した。
病院で検査を受けると、
「右足靭帯一部損傷」
との診断で、どうやら練習をし過ぎたらしかった。
「だって夜中こっそり起きて、浴場の脱衣所で練習してたもんね…」
相部屋の英美里は気づいていた。
病院から戻って来た薫を見つけると、
「ちょっとえぇか?」
珍しく清正は個人面談をした。
「藤浦…気持ちは分からんでもないけど、過ぎたるは及ばざるが如しって言うてやな」
やんわりした物言いだが、
「まぁ責任感強いから、藤浦らしいっちゃあらしいけど」
「…ごめんなさい」
「夜中の練習そのものは悪いことではないけど、体を壊したら元も子もないやろ?」
そこで。
「藤浦に頼みがある」
と、来ていた茉莉江を呼び「ちょっと見てやってや」と頼んだ。