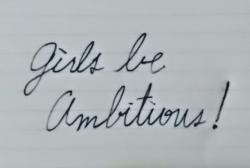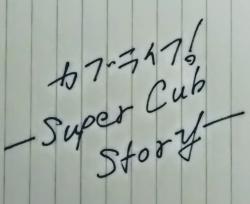少し間があって、藤子から返信があった。
「…死にたくなるぐらい悔しいけど、これが最後じゃないから、また頑張ってみるよ」
何か絞り出すような、様々な思いが渦巻いて綯い交ざったようなメッセージである。
「藤子が悔しがるなんて珍しいけど、よっぽど本気で書いたんだろうな…」
澪はメッセージに「国立は?」と返した。
今度はすぐ返事が来た。
「もちろん行くよ!」
澪は「じゃあ、シリアルナンバー3番空けて待ってる」と返した。
藤子は、
「ありがと。ほんとにありがとう」
何となくメッセージの向こう側で、藤子が泣いているような気がした。