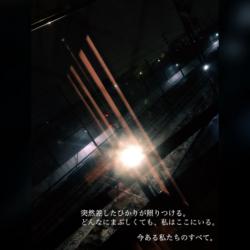三年ぶりの再会だった。宏紀と七海は中学二年、三年生の時に一緒のクラスだった。今、七海は長い黒髪だけど、その当時はショートヘアだったから、宏紀は記憶から探り出すのに少し時間がかかった。よく見ると、きれいで優しい顔立ちは全く変わっていなかった。幼いわが子を見つめるような綿のように柔らかい表情だ。私にはない、どこか大人っぽい感じと、女の子の心をも揺さぶる感じは羨ましい。
宏紀と七海は二年生の時、お互いにクラスにいることは知っていたけど、会話を交わしたことはほとんどなかった。でも三年生の時に体育祭、文化祭の実行委員を共にやったことをきっかけに交流を持つようになった。体育祭で優勝した時に、クラスをうまく牽引したことが先生から評価されて、文化祭の実行委員もやってほしいとお願いをされた。七海もやる気で、『次も深沢君とやりたい』と言った。
体育祭の優勝に続いて、文化祭のクラス対抗合唱コンクールも制覇できた。後に開催された、地元の中学校が集結して行った合唱コンクールでも二人は先頭に立ってクラスをまとめあげた。三年生のころのこの時期に二人の結束は固まり、親交が深まった。宏紀が中学の時に、一番仲の良かった女の子だった。
七海の表情は当時と変わらない優しさに溢れていて、何事にも真面目に取り組む優等生だった。でもすごく生真面目な部分はなく、人を迎え入れるだけの隙間も持ち備えていた。
宏紀は七海の笑顔が好きだった。その笑顔を見たくて、体育祭や文化祭もここまでやり遂げられた。でも告白はしなかった。そんな勇気は、当時の宏紀にはなかった。その時はただの仲の良い友達で十分だったのかもしれない。
宏紀と七海がメインストリートを歩いていく。
「偶然だね。学部も学科も一緒になるなんて」
宏紀がそう言った。慣れない女の子との会話に落ち着きがないけど、それを見せないように努めている。かつて好きだった人なら仕方ない。
「本当だね。大学が一緒とかならまだ分かるけど、学部も学科もだからびっくりだね。宏紀、こっちに住むの?」
「港南台から通うよ」
港南台とは、宏紀と七海の実家がある神奈川県横浜市にある。横浜駅から電車で二十分ほどの場所だ。
「遠くない? 私は大学の近くに住むよ」
七海も驚きの声を上げた。大学からだと、うまく電車を乗り継いでも二時間ぐらいはかかる。聞いていても気が遠くなりそうな時間だった。
「僕もできればそうしたいけど、お金ないし。親にも負担になるから」
「そっか。じゃあ、私は両親に感謝しないとね」
楽しみか不安かのどちらかと言えば、七海は楽しみの方が勝っている感じだった。慣れない環境にも楽しめる余裕も、七海の柔らかい物腰に繋がっているのかもしれない。
ふわふわと足跡を残す宏紀は俯いて自分の足の動きを見つめている。もしかしたら、宏紀も一人暮らしを検討し始めているかもしれない。七海が近くにいるなら心強いって。
「宏紀、スーツ似合うね」
唐突に七海が言った。歩きながら一歩引いて宏紀の全体像を眺めた。
「そう? ぎこちなさしかないけど……」
真顔でそう返した宏紀だったけど、内心嬉しいはずだ。
「そんなことないよ。似合ってると思うよ」
「ありがと……七海も似合ってるよ。なんかできる女って感じでさ」
顔を赤らめて宏紀は言った。『恥ずかしいなら言うなよ』って、私なら突っ込んでいたかもしれない。
「マジで? ありがとう。宏紀って、そんなお世辞も言えるようになったんだね。三年経つと変わるもんだ」
少し意地悪な感じで七海が言った。
「マジで言ってるんだけど」
七海の前では、妙に真面目な態度でいってしまう宏紀がいた。
「分かってるって。ねぇ、宏紀って、この後予定ある? 手伝ってほしいことがあるんだけど」
「何?」
大学の正門を抜けて記念すべき大学初日にさよならをする。
名残惜しさもなく宏紀は胸を小刻みに震わせながら七海と歩幅を合わせる。七海と目と鼻の先にある七海の借りたてのアパートに向かっている。正門から出て数分が経っただけでもうアパートが見えてきた。本当に目と鼻の先だ。『なんて短い通学時間だ』っていう羨望の気持ちは私を取り巻くけど、宏紀は緊張でかき消された。
「アパートの整理を手伝ってほしくて。色々持ってきたから一人じゃ大変で」
宏紀は、『僕は召使じゃない』と言わんばかりの表情で七海を見た。でも七海の頼みならと思って何も言わなかったんだろう。もっと中学時代の話ができるなら、何事にも変えられない。
「いいよ。段ボールに埋もれて過ごすことになるって感じか」
「そうそう。だから快く手伝って」
宏紀の腕をポンと叩いてお願いした。
「うん。どうせ帰っても暇だったし、いいよ」
七海はアパートの顔認証システムを利用して施錠を解いた。七海が住んでいる三階に上がり、通路を歩いていく。
中学時代に一番仲が良かった同級生とはいえ、一人暮らしの女性のアパートに入るから、再び鼓動の動きが加速する。と言っても、入居したてだからここのアパートの独特の匂いしかしないだろう。
七海が鍵を解除してアパートのドアを開けた。その瞬間、七海の匂いがかすかに宏紀を取り巻いていった。懐かしい記憶もついでに連れてきてくれた。思わぬ出迎えに宏紀は、催眠術をかけられたような感覚だった。
「ちょっと待ってて」
ヒールを脱いで、七海は出入り口のそばにある一つの段ボールの封を開けてスリッパを二つ出した。奥の部屋には他にも四つの段ボールが仲良く寄り添っていて、七海や宏紀に自由にしてもらえるのを心待ちにしているだろう。
宏紀の目の前にスリッパを置いて、七海は宏紀に中に入るように促した。
「ああ、ありがとう」
ゆっくり丁寧に革靴を脱いで中に入る。すごくきれいなアパートで宏紀もだんだん一人暮らしへのあこがれが膨らんでいく。七海も近くにいるならなおさらだ。
電気をつけて、奥の部屋に明るさが生まれた。買ったばかりのスタンドライトと空気清浄機がこれからの生活に向けて待機している。
「いい部屋借りたね」
宏紀は回転しながら部屋を見渡す。
「うん。お父さんが張りきっちゃって」
七海がスーツのジャケットを脱いでハンガーにかけた。
「そうだろうね。大事な娘を一人暮らしさせるんだから」
お父さんの気持ちを代弁する宏紀。妙に真面目な返答で、私がその場にいたら笑ってしまいそうだ。
「僕は、何をすればいいの?」
七海は居心地が悪そうにしている宏紀を見て、
「じゃあ、ここにある本とかCDをここの本棚に並べて」
「分かった」
宏紀はその場に座って段ボールを丁寧に開けた。七海は洋服をクローゼットに収納し始めた。
宏紀は割れ物を扱うようにゆっくり慎重に中身を出した。
「七海、この歌手好きだったよね」
CDを眺めて宏紀は言った。発売されたのは宏紀や七海が中学二年生の時にリリースされた曲で宏紀も一時期よく聞いていた。七海が勧めてくれたから、聞かないわけにはいかなかったんだろう。
「うん。今でもCD買ってるよ。ポスターとかステッカーとか付いてくるから」
「そうなんだ。それなら買いたくなるな。ライブとか行くの?」
「お金ないから行けてない。でもこれからは行きたいな」
文化祭の打ち合わせをしていた時、この歌手の話で盛り上がった。懐かしくてまた文化祭を牽引する覚悟が、ふつふつと宏紀の心に湧いてきているかもしれない。
「そうだね。今はどの曲が一番好きなの?」
七海は宏紀の隣に座ってCDを探し始めた。
近くで七海を見つめながら宏紀は動悸をすぐそばで聞いている。
「これ!」
七海はCDを宏紀に手渡して、タイトルを読み上げた。
「これ好きだったね、七海」
真面目に何かに取り組む、人を好きになる、みんなと何かをやり遂げる大切さを教えてくれた時期の記憶に花を添えてくれた曲が目の前にいくつも並んでいる。普通の段ボールにCDが並んでいるだけなのに、宏紀や七海にとっては抱えきれない思い出が詰まっているんだろう。
「覚えてるんだね」
「僕も何度も聞いたから」
七海は宏紀を見た。そんな聞いてくれていたんだって思ったのだろう、少しだけ口許をキュッと上げて笑みを見せた。
「何?」
真面目に反応する宏紀。
「別に……あ、そうだ。宏紀、いいもの見せてあげる」
一冊のアルバムを手にした七海が再び宏紀のそばに着く。三年間のブランクを埋めるようにまた少しだけ距離を詰めた。
「写真?」
ページをめくる七海にそう聞いた。
「これこれ」と、七海は四枚の写真がきれいに収められたページを軽く触れた。
一枚目は体育祭が終わった後に撮影されたクラス集合写真。全員、学校指定のジャージ姿でガッツポーズを添えてみんなが凛々しく写っている。二枚目は優勝旗を二人で分け合うように持つ宏紀と七海の写真だった。
「懐かしいね、これ」
自然に頬が緩む宏紀がいた。この時から三年経ち、こんな風に笑えた時もあったんだって、宏紀は昔の自分に話しかけている。
高校生の時は、いつもこのころに戻りたいって、宏紀は後ろを振り返っていた。親しい友達もいたけど、なかなかクラスに馴染めずにいた。周りの人の評価ばかりを気にして、本当の自分が出せなくなってしまった。表向きの関係だけを維持していくのが面倒になって、宏紀は一人でいることが多くなっていった。その時は、一人になることによって自由な生活が一時的に手に入ったけど、だんだん一人の寂しさに包まれるようになった。思い切って、高校を辞めようと考えたけど、特に何もやりたいことがなかった宏紀は、両親に反対にされて、自分の気持ちを抑え込むしかなかった。
ふらりとそよ風に誘われて、宏紀の通っていた中学校を訪れていた。
七海や、心許せる友達がいたころに戻りたい、そう宏紀は心の中で強く思った。
「でしょ? ここに来る準備をしてた時に、お母さんが持ってきてくれて、準備しないでアルバムを見てた」
「それで準備できないみたいな感じか」
七海が経験したものを脳裏で宏紀は描いて見た。
「そうそう。それでその日は懐かしい思い出を取り出して終わったみたいな」
「そういうのあるよね」
「うん」
七海は状況を共感してくれた宏紀に笑顔を見せた。
「西沢先生もいる!」
宏紀が次のページに話題を移すと、文化祭の後に中学三年生の時の担任の先生とクラスメイトと撮った写真も顔を出した。
「そうそう! 覚えてる? すごくジェスチャーの大きい先生!」
「もちろん覚えてるよ。この人の英語の授業大好きだったもん。ジェスチャーが大きくて、僕らに敬語使ってたよね?」
「そうそう!」
手を叩いて七海の記憶から西沢先生を取り出した。二人にとって印象に残る先生だったみたいだ。
「……このままだと整理できなくなるかもね」
宏紀が冷静にそう言った。本当はもっとこの時間を共有したかっただろう。
「そうだね……これはまた後で見ようか」
そう言って七海は手を付けたばかりの段ボールにもう一度手をつけた。
宏紀と七海は二年生の時、お互いにクラスにいることは知っていたけど、会話を交わしたことはほとんどなかった。でも三年生の時に体育祭、文化祭の実行委員を共にやったことをきっかけに交流を持つようになった。体育祭で優勝した時に、クラスをうまく牽引したことが先生から評価されて、文化祭の実行委員もやってほしいとお願いをされた。七海もやる気で、『次も深沢君とやりたい』と言った。
体育祭の優勝に続いて、文化祭のクラス対抗合唱コンクールも制覇できた。後に開催された、地元の中学校が集結して行った合唱コンクールでも二人は先頭に立ってクラスをまとめあげた。三年生のころのこの時期に二人の結束は固まり、親交が深まった。宏紀が中学の時に、一番仲の良かった女の子だった。
七海の表情は当時と変わらない優しさに溢れていて、何事にも真面目に取り組む優等生だった。でもすごく生真面目な部分はなく、人を迎え入れるだけの隙間も持ち備えていた。
宏紀は七海の笑顔が好きだった。その笑顔を見たくて、体育祭や文化祭もここまでやり遂げられた。でも告白はしなかった。そんな勇気は、当時の宏紀にはなかった。その時はただの仲の良い友達で十分だったのかもしれない。
宏紀と七海がメインストリートを歩いていく。
「偶然だね。学部も学科も一緒になるなんて」
宏紀がそう言った。慣れない女の子との会話に落ち着きがないけど、それを見せないように努めている。かつて好きだった人なら仕方ない。
「本当だね。大学が一緒とかならまだ分かるけど、学部も学科もだからびっくりだね。宏紀、こっちに住むの?」
「港南台から通うよ」
港南台とは、宏紀と七海の実家がある神奈川県横浜市にある。横浜駅から電車で二十分ほどの場所だ。
「遠くない? 私は大学の近くに住むよ」
七海も驚きの声を上げた。大学からだと、うまく電車を乗り継いでも二時間ぐらいはかかる。聞いていても気が遠くなりそうな時間だった。
「僕もできればそうしたいけど、お金ないし。親にも負担になるから」
「そっか。じゃあ、私は両親に感謝しないとね」
楽しみか不安かのどちらかと言えば、七海は楽しみの方が勝っている感じだった。慣れない環境にも楽しめる余裕も、七海の柔らかい物腰に繋がっているのかもしれない。
ふわふわと足跡を残す宏紀は俯いて自分の足の動きを見つめている。もしかしたら、宏紀も一人暮らしを検討し始めているかもしれない。七海が近くにいるなら心強いって。
「宏紀、スーツ似合うね」
唐突に七海が言った。歩きながら一歩引いて宏紀の全体像を眺めた。
「そう? ぎこちなさしかないけど……」
真顔でそう返した宏紀だったけど、内心嬉しいはずだ。
「そんなことないよ。似合ってると思うよ」
「ありがと……七海も似合ってるよ。なんかできる女って感じでさ」
顔を赤らめて宏紀は言った。『恥ずかしいなら言うなよ』って、私なら突っ込んでいたかもしれない。
「マジで? ありがとう。宏紀って、そんなお世辞も言えるようになったんだね。三年経つと変わるもんだ」
少し意地悪な感じで七海が言った。
「マジで言ってるんだけど」
七海の前では、妙に真面目な態度でいってしまう宏紀がいた。
「分かってるって。ねぇ、宏紀って、この後予定ある? 手伝ってほしいことがあるんだけど」
「何?」
大学の正門を抜けて記念すべき大学初日にさよならをする。
名残惜しさもなく宏紀は胸を小刻みに震わせながら七海と歩幅を合わせる。七海と目と鼻の先にある七海の借りたてのアパートに向かっている。正門から出て数分が経っただけでもうアパートが見えてきた。本当に目と鼻の先だ。『なんて短い通学時間だ』っていう羨望の気持ちは私を取り巻くけど、宏紀は緊張でかき消された。
「アパートの整理を手伝ってほしくて。色々持ってきたから一人じゃ大変で」
宏紀は、『僕は召使じゃない』と言わんばかりの表情で七海を見た。でも七海の頼みならと思って何も言わなかったんだろう。もっと中学時代の話ができるなら、何事にも変えられない。
「いいよ。段ボールに埋もれて過ごすことになるって感じか」
「そうそう。だから快く手伝って」
宏紀の腕をポンと叩いてお願いした。
「うん。どうせ帰っても暇だったし、いいよ」
七海はアパートの顔認証システムを利用して施錠を解いた。七海が住んでいる三階に上がり、通路を歩いていく。
中学時代に一番仲が良かった同級生とはいえ、一人暮らしの女性のアパートに入るから、再び鼓動の動きが加速する。と言っても、入居したてだからここのアパートの独特の匂いしかしないだろう。
七海が鍵を解除してアパートのドアを開けた。その瞬間、七海の匂いがかすかに宏紀を取り巻いていった。懐かしい記憶もついでに連れてきてくれた。思わぬ出迎えに宏紀は、催眠術をかけられたような感覚だった。
「ちょっと待ってて」
ヒールを脱いで、七海は出入り口のそばにある一つの段ボールの封を開けてスリッパを二つ出した。奥の部屋には他にも四つの段ボールが仲良く寄り添っていて、七海や宏紀に自由にしてもらえるのを心待ちにしているだろう。
宏紀の目の前にスリッパを置いて、七海は宏紀に中に入るように促した。
「ああ、ありがとう」
ゆっくり丁寧に革靴を脱いで中に入る。すごくきれいなアパートで宏紀もだんだん一人暮らしへのあこがれが膨らんでいく。七海も近くにいるならなおさらだ。
電気をつけて、奥の部屋に明るさが生まれた。買ったばかりのスタンドライトと空気清浄機がこれからの生活に向けて待機している。
「いい部屋借りたね」
宏紀は回転しながら部屋を見渡す。
「うん。お父さんが張りきっちゃって」
七海がスーツのジャケットを脱いでハンガーにかけた。
「そうだろうね。大事な娘を一人暮らしさせるんだから」
お父さんの気持ちを代弁する宏紀。妙に真面目な返答で、私がその場にいたら笑ってしまいそうだ。
「僕は、何をすればいいの?」
七海は居心地が悪そうにしている宏紀を見て、
「じゃあ、ここにある本とかCDをここの本棚に並べて」
「分かった」
宏紀はその場に座って段ボールを丁寧に開けた。七海は洋服をクローゼットに収納し始めた。
宏紀は割れ物を扱うようにゆっくり慎重に中身を出した。
「七海、この歌手好きだったよね」
CDを眺めて宏紀は言った。発売されたのは宏紀や七海が中学二年生の時にリリースされた曲で宏紀も一時期よく聞いていた。七海が勧めてくれたから、聞かないわけにはいかなかったんだろう。
「うん。今でもCD買ってるよ。ポスターとかステッカーとか付いてくるから」
「そうなんだ。それなら買いたくなるな。ライブとか行くの?」
「お金ないから行けてない。でもこれからは行きたいな」
文化祭の打ち合わせをしていた時、この歌手の話で盛り上がった。懐かしくてまた文化祭を牽引する覚悟が、ふつふつと宏紀の心に湧いてきているかもしれない。
「そうだね。今はどの曲が一番好きなの?」
七海は宏紀の隣に座ってCDを探し始めた。
近くで七海を見つめながら宏紀は動悸をすぐそばで聞いている。
「これ!」
七海はCDを宏紀に手渡して、タイトルを読み上げた。
「これ好きだったね、七海」
真面目に何かに取り組む、人を好きになる、みんなと何かをやり遂げる大切さを教えてくれた時期の記憶に花を添えてくれた曲が目の前にいくつも並んでいる。普通の段ボールにCDが並んでいるだけなのに、宏紀や七海にとっては抱えきれない思い出が詰まっているんだろう。
「覚えてるんだね」
「僕も何度も聞いたから」
七海は宏紀を見た。そんな聞いてくれていたんだって思ったのだろう、少しだけ口許をキュッと上げて笑みを見せた。
「何?」
真面目に反応する宏紀。
「別に……あ、そうだ。宏紀、いいもの見せてあげる」
一冊のアルバムを手にした七海が再び宏紀のそばに着く。三年間のブランクを埋めるようにまた少しだけ距離を詰めた。
「写真?」
ページをめくる七海にそう聞いた。
「これこれ」と、七海は四枚の写真がきれいに収められたページを軽く触れた。
一枚目は体育祭が終わった後に撮影されたクラス集合写真。全員、学校指定のジャージ姿でガッツポーズを添えてみんなが凛々しく写っている。二枚目は優勝旗を二人で分け合うように持つ宏紀と七海の写真だった。
「懐かしいね、これ」
自然に頬が緩む宏紀がいた。この時から三年経ち、こんな風に笑えた時もあったんだって、宏紀は昔の自分に話しかけている。
高校生の時は、いつもこのころに戻りたいって、宏紀は後ろを振り返っていた。親しい友達もいたけど、なかなかクラスに馴染めずにいた。周りの人の評価ばかりを気にして、本当の自分が出せなくなってしまった。表向きの関係だけを維持していくのが面倒になって、宏紀は一人でいることが多くなっていった。その時は、一人になることによって自由な生活が一時的に手に入ったけど、だんだん一人の寂しさに包まれるようになった。思い切って、高校を辞めようと考えたけど、特に何もやりたいことがなかった宏紀は、両親に反対にされて、自分の気持ちを抑え込むしかなかった。
ふらりとそよ風に誘われて、宏紀の通っていた中学校を訪れていた。
七海や、心許せる友達がいたころに戻りたい、そう宏紀は心の中で強く思った。
「でしょ? ここに来る準備をしてた時に、お母さんが持ってきてくれて、準備しないでアルバムを見てた」
「それで準備できないみたいな感じか」
七海が経験したものを脳裏で宏紀は描いて見た。
「そうそう。それでその日は懐かしい思い出を取り出して終わったみたいな」
「そういうのあるよね」
「うん」
七海は状況を共感してくれた宏紀に笑顔を見せた。
「西沢先生もいる!」
宏紀が次のページに話題を移すと、文化祭の後に中学三年生の時の担任の先生とクラスメイトと撮った写真も顔を出した。
「そうそう! 覚えてる? すごくジェスチャーの大きい先生!」
「もちろん覚えてるよ。この人の英語の授業大好きだったもん。ジェスチャーが大きくて、僕らに敬語使ってたよね?」
「そうそう!」
手を叩いて七海の記憶から西沢先生を取り出した。二人にとって印象に残る先生だったみたいだ。
「……このままだと整理できなくなるかもね」
宏紀が冷静にそう言った。本当はもっとこの時間を共有したかっただろう。
「そうだね……これはまた後で見ようか」
そう言って七海は手を付けたばかりの段ボールにもう一度手をつけた。