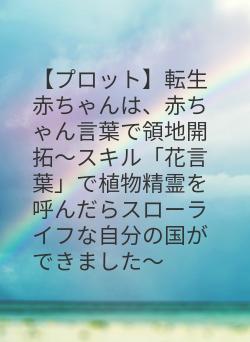かつて神の子に3人の騎士あり。
騎士ら地に下り3つの大陸を各々統治し、その地の娘を妻とす。
妻ら、夫の無事を祈りて、絹、麻、ベルベットにてマントを織る。
騎士らその名で呼ばれたり。
絹の騎士の国、交易にて栄え、麻の騎士の国、麦の穂にて栄え、ベルベットの騎士の国、奇異なる術にて栄えたり。
時移り、増長したる麻の騎士、絹の騎士の妻を奪いたり。
怒りたる絹の騎士、麻の騎士を討ち、彼の者の妻子を奴隷とす。
これ、王国の奴隷の祖なり。
奴隷を哀れみたるベルベットの騎士、彼らを救わんと兵と錬金術を用いて絹の騎士と戦いたり。
戦いは20年に及ぶも遂に絹の騎士、剣と神の加護にて勝利せり。
絹の騎士、神より2騎士の領土と領民を支配する権威を得たり。
ゆえに3大陸これ、絹の騎士のものなり。
騎士ら地に下り3つの大陸を各々統治し、その地の娘を妻とす。
妻ら、夫の無事を祈りて、絹、麻、ベルベットにてマントを織る。
騎士らその名で呼ばれたり。
絹の騎士の国、交易にて栄え、麻の騎士の国、麦の穂にて栄え、ベルベットの騎士の国、奇異なる術にて栄えたり。
時移り、増長したる麻の騎士、絹の騎士の妻を奪いたり。
怒りたる絹の騎士、麻の騎士を討ち、彼の者の妻子を奴隷とす。
これ、王国の奴隷の祖なり。
奴隷を哀れみたるベルベットの騎士、彼らを救わんと兵と錬金術を用いて絹の騎士と戦いたり。
戦いは20年に及ぶも遂に絹の騎士、剣と神の加護にて勝利せり。
絹の騎士、神より2騎士の領土と領民を支配する権威を得たり。
ゆえに3大陸これ、絹の騎士のものなり。