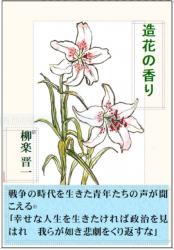「この次も僕のほうが先に来て待つことにするよ。近づいてくる絵里さんを、どきどきしながら見たいからさ、今日みたいに」
それを口にしたとたんに、僕はかすかな狼狽をおぼえた。絵里の気持ちをほぐしてやるつもりの言葉の中に、自分の気持ちがまぎれこんだような気がした。
「ごめんなさい、先にお礼を言わなくちゃいけないのに」と絵里が言った。「ほんとにありがとうございました、あのテープ。とっても素敵です、ショパンもシューマンも」
絵里に贈るために、ショパンとシューマンのピアノ協奏曲をダビングし、一週間ほど前に坂田に渡しておいた。それがよほど気に入ったのか、絵里はそれら二つの協奏曲のことを夢中になって話した。
「そんな風にして、ヘッドホンであのテープを聴きながら小説を読むのって、ほんとに素敵ですよ。BGMみたいな感じですけど、くりかえして聴いてます」
「気に入ったクラシックでも、そんなに聴けばあきるだろうから、別のものをダビングしてあげるよ」
「ごめんなさい」と絵里が言った。「なんだかおねだりしちゃったみたい」
しばらく話しているうちに、絵里の笑顔からかたさが消えた。二週間ぶりの二度めの出会いだったが、僕たちをうちとけた雰囲気がつつんでいた。
演奏が始まっても、僕は音楽に集中することができなかった。横にいる絵里を意識しながら考えた。会場を出てからそのまま駅に向かうというのでは、絵里に淋しい想いをさせるような気がする。どこかに立ち寄って、演奏会の余韻を楽しむとしよう。ふたりとも食事はすませていることだから、飲み物だけでいいだろう。
会場を出ながら絵里に誘いかけると、絵里はうれしそうに同意した。
地下鉄の駅へ向かう途中にケーキ屋があり、その2階が喫茶室になっていた。飲み物を注文すれば、特製のケーキがついてくる店だった。店の中の階段をのぼって、僕たちは喫茶室にはいった。
コーヒーとケーキはすぐに出てきた。絵里はケーキをながめ、それから僕を見て嬉しそうにほほえんだ。笑顔を絵里にかえしてから、僕はコーヒーカップをとりあげた。絵里はケーキの皿を両手で引きよせた。
演奏会の感想を語り合っていると、にこやかな笑顔を見せて絵里が言った。
「あの人の寝息、何だかとてもおかしかったですね。音楽が静かになると聞こえて」
演奏が始まってからまもなく、絵里の前の座席から寝息が聞こえ始めた。サラリーマンらしいその男の寝息は、となりの人に注意されるまで続いた。
「あの人も、きっと音楽が好きな人だと思うよ。わざわざ出かけたんだからさ」
「この前に会ったとき、松井さんはLPを聴きながら眠ることがあると言ったでしょ。音楽を好きな人って、かえってそんなことがあるのかしら」
「LPならば子守歌にできるけど、演奏会で寝てしまったらもったいないよ」
「演奏会が子守歌っていうのもぜいたくだけど、寝ちゃったら子守歌も聞こえないから、やっぱりもったいないわね」
絵里の言葉に僕が笑いだすと、絵里もいっしょになって笑った。抑えられたその声が、僕の耳には好ましく聞こえた。
「僕だって、場合によったら居眠りするかも知れないよ、あの人みたいに。マージャンで寝不足になったりすれば」
「マージャンをするんですか、松井さん」
「学生時代に、マージャンの好きな友達に誘われたんだ。洞察力が強くなるからやってみろって。僕もたまには遅くまでつき合ったけど、卒業してからは一度もやっていないよ。それほど好きなわけじゃないし、そんな暇もないからさ」
「兄は好きなんですよ、マージャン」
「そうか、意外な感じだな、坂田がマージャンをするとは。もしかすると、坂田の洞察力はマージャンのおかげかもしれないな」
「そんなに洞察力があるんですか、兄さんは」
「坂田の洞察力はそうとうなもんだよ。僕たちがこんな店に入ることだって、坂田にはお見通しだと思うな。だからさ、月曜日に坂田に会ったら、あいつは僕に向かって言うはずなんだ。演奏会のあとで絵里といっしょにケーキ屋に入って、二階の席でケーキを食いながら、うまいコーヒーを飲んだだろう。お前を見ただけでおれにはわかる」
絵里は控えめな声をあげて笑い、「松井さんは、私のこともそんなふうに洞察できますか」と言った。
「洞察って、絵里さんのことをかい」
「そう、たとえば、休みの日にはどんなことをしてるのか」絵里は両手で持っていたコーヒーカップをゆっくりとまわしながら言った。「あるいは・・・・ボーイフレンドはいるのかどうか・・・・たとえばそんなこと」
絵里がボーイフレンドという言葉を口にしたとき、僕は心の揺れをおぼえた。坂田が僕に絵里を紹介しようとしたのは、絵里にはつき合っている男がいないからだ、と僕は思い込んでいた。絵里の言葉を聞いて、もしかすると、絵里にはボーイフレンドが居るのかも知れないと思った。
「むつかしいな、ボーイフレンドについての洞察なんていうのは」
「だから・・・・そのことも含めて、ようするに私のこと」
「居るんだろ、ボーイフレンド」
「さあ、どうでしょう。どう思いますか」
絵里は僕に笑顔を向けたまま、コーヒーカップを口へはこんだ。
その様子を見て、絵里にはボーイフレンドがいないような気がしたけれども、僕は「もちろん居ると思うよ。だってさ、絵里さんをひとりにしておくなんて、もったいないからな」と言った。
絵里の眼が、笑顔の中で驚いたように大きく開かれた。絵里はコーヒーカップをテーブルに置き、カップに手をそえたまま顔をあげた。
「居ないんですよ、わたし、ボーイフレンドって。短大の頃だって。だからね、ボーイフレンドを持ってる友達がうらやましかったの」
「今までいなかったなんて不思議だな。もしかしたら、ボーイフレンドが欲しいと、本気で願っていなかったんじゃないのかな、絵里さんは」
「そういうのって、やっぱり縁だと思いませんか」
「銀行にもたくさん居るんだろ、良さそうな人が」
「そうね、一般論的にいい人は、いっぱい居るような気もするんだけど」
「なんだよ、一般論っていうのは」
「理想的な恋人の条件というのがあるんですって。そういう意味では、銀行にもいろんな人がいるんですけど、とくにこの人はというひとはいないのよね、わたしの場合には」
「一般論的な理想にこだわるわけじゃないんだろ」
「そんなことにはこだわりませんけど……いままでは、わたしと縁のある人に出会えなかったのよね、きっと」
絵里はコーヒーカップを取りあげると、それを両手でそっと支えるようにした。絵里のそのような仕ぐさがかわいらしく見えた。
「出会いを待つのもいいけどさ、縁を作るようにしたら、もっと早く見つけることができるはずだよ。男にだって同じことが言えるんだけど」
「男の人にとっても一般論的っていうか、そういうのはあるんでしょ」
「あるだろうな、たぶん。でも結果としてはやっぱり縁だろうな」
「いまつき合ってる人とは縁があったわけですね」
坂田が伝えたはずだから、絵里が佳子のことを知っているのは当然のことだったが、その言葉に僕は不意をつかれた。あのとき坂田になにも話さなければ良かった、という想いが心の端をよぎった。
それを口にしたとたんに、僕はかすかな狼狽をおぼえた。絵里の気持ちをほぐしてやるつもりの言葉の中に、自分の気持ちがまぎれこんだような気がした。
「ごめんなさい、先にお礼を言わなくちゃいけないのに」と絵里が言った。「ほんとにありがとうございました、あのテープ。とっても素敵です、ショパンもシューマンも」
絵里に贈るために、ショパンとシューマンのピアノ協奏曲をダビングし、一週間ほど前に坂田に渡しておいた。それがよほど気に入ったのか、絵里はそれら二つの協奏曲のことを夢中になって話した。
「そんな風にして、ヘッドホンであのテープを聴きながら小説を読むのって、ほんとに素敵ですよ。BGMみたいな感じですけど、くりかえして聴いてます」
「気に入ったクラシックでも、そんなに聴けばあきるだろうから、別のものをダビングしてあげるよ」
「ごめんなさい」と絵里が言った。「なんだかおねだりしちゃったみたい」
しばらく話しているうちに、絵里の笑顔からかたさが消えた。二週間ぶりの二度めの出会いだったが、僕たちをうちとけた雰囲気がつつんでいた。
演奏が始まっても、僕は音楽に集中することができなかった。横にいる絵里を意識しながら考えた。会場を出てからそのまま駅に向かうというのでは、絵里に淋しい想いをさせるような気がする。どこかに立ち寄って、演奏会の余韻を楽しむとしよう。ふたりとも食事はすませていることだから、飲み物だけでいいだろう。
会場を出ながら絵里に誘いかけると、絵里はうれしそうに同意した。
地下鉄の駅へ向かう途中にケーキ屋があり、その2階が喫茶室になっていた。飲み物を注文すれば、特製のケーキがついてくる店だった。店の中の階段をのぼって、僕たちは喫茶室にはいった。
コーヒーとケーキはすぐに出てきた。絵里はケーキをながめ、それから僕を見て嬉しそうにほほえんだ。笑顔を絵里にかえしてから、僕はコーヒーカップをとりあげた。絵里はケーキの皿を両手で引きよせた。
演奏会の感想を語り合っていると、にこやかな笑顔を見せて絵里が言った。
「あの人の寝息、何だかとてもおかしかったですね。音楽が静かになると聞こえて」
演奏が始まってからまもなく、絵里の前の座席から寝息が聞こえ始めた。サラリーマンらしいその男の寝息は、となりの人に注意されるまで続いた。
「あの人も、きっと音楽が好きな人だと思うよ。わざわざ出かけたんだからさ」
「この前に会ったとき、松井さんはLPを聴きながら眠ることがあると言ったでしょ。音楽を好きな人って、かえってそんなことがあるのかしら」
「LPならば子守歌にできるけど、演奏会で寝てしまったらもったいないよ」
「演奏会が子守歌っていうのもぜいたくだけど、寝ちゃったら子守歌も聞こえないから、やっぱりもったいないわね」
絵里の言葉に僕が笑いだすと、絵里もいっしょになって笑った。抑えられたその声が、僕の耳には好ましく聞こえた。
「僕だって、場合によったら居眠りするかも知れないよ、あの人みたいに。マージャンで寝不足になったりすれば」
「マージャンをするんですか、松井さん」
「学生時代に、マージャンの好きな友達に誘われたんだ。洞察力が強くなるからやってみろって。僕もたまには遅くまでつき合ったけど、卒業してからは一度もやっていないよ。それほど好きなわけじゃないし、そんな暇もないからさ」
「兄は好きなんですよ、マージャン」
「そうか、意外な感じだな、坂田がマージャンをするとは。もしかすると、坂田の洞察力はマージャンのおかげかもしれないな」
「そんなに洞察力があるんですか、兄さんは」
「坂田の洞察力はそうとうなもんだよ。僕たちがこんな店に入ることだって、坂田にはお見通しだと思うな。だからさ、月曜日に坂田に会ったら、あいつは僕に向かって言うはずなんだ。演奏会のあとで絵里といっしょにケーキ屋に入って、二階の席でケーキを食いながら、うまいコーヒーを飲んだだろう。お前を見ただけでおれにはわかる」
絵里は控えめな声をあげて笑い、「松井さんは、私のこともそんなふうに洞察できますか」と言った。
「洞察って、絵里さんのことをかい」
「そう、たとえば、休みの日にはどんなことをしてるのか」絵里は両手で持っていたコーヒーカップをゆっくりとまわしながら言った。「あるいは・・・・ボーイフレンドはいるのかどうか・・・・たとえばそんなこと」
絵里がボーイフレンドという言葉を口にしたとき、僕は心の揺れをおぼえた。坂田が僕に絵里を紹介しようとしたのは、絵里にはつき合っている男がいないからだ、と僕は思い込んでいた。絵里の言葉を聞いて、もしかすると、絵里にはボーイフレンドが居るのかも知れないと思った。
「むつかしいな、ボーイフレンドについての洞察なんていうのは」
「だから・・・・そのことも含めて、ようするに私のこと」
「居るんだろ、ボーイフレンド」
「さあ、どうでしょう。どう思いますか」
絵里は僕に笑顔を向けたまま、コーヒーカップを口へはこんだ。
その様子を見て、絵里にはボーイフレンドがいないような気がしたけれども、僕は「もちろん居ると思うよ。だってさ、絵里さんをひとりにしておくなんて、もったいないからな」と言った。
絵里の眼が、笑顔の中で驚いたように大きく開かれた。絵里はコーヒーカップをテーブルに置き、カップに手をそえたまま顔をあげた。
「居ないんですよ、わたし、ボーイフレンドって。短大の頃だって。だからね、ボーイフレンドを持ってる友達がうらやましかったの」
「今までいなかったなんて不思議だな。もしかしたら、ボーイフレンドが欲しいと、本気で願っていなかったんじゃないのかな、絵里さんは」
「そういうのって、やっぱり縁だと思いませんか」
「銀行にもたくさん居るんだろ、良さそうな人が」
「そうね、一般論的にいい人は、いっぱい居るような気もするんだけど」
「なんだよ、一般論っていうのは」
「理想的な恋人の条件というのがあるんですって。そういう意味では、銀行にもいろんな人がいるんですけど、とくにこの人はというひとはいないのよね、わたしの場合には」
「一般論的な理想にこだわるわけじゃないんだろ」
「そんなことにはこだわりませんけど……いままでは、わたしと縁のある人に出会えなかったのよね、きっと」
絵里はコーヒーカップを取りあげると、それを両手でそっと支えるようにした。絵里のそのような仕ぐさがかわいらしく見えた。
「出会いを待つのもいいけどさ、縁を作るようにしたら、もっと早く見つけることができるはずだよ。男にだって同じことが言えるんだけど」
「男の人にとっても一般論的っていうか、そういうのはあるんでしょ」
「あるだろうな、たぶん。でも結果としてはやっぱり縁だろうな」
「いまつき合ってる人とは縁があったわけですね」
坂田が伝えたはずだから、絵里が佳子のことを知っているのは当然のことだったが、その言葉に僕は不意をつかれた。あのとき坂田になにも話さなければ良かった、という想いが心の端をよぎった。