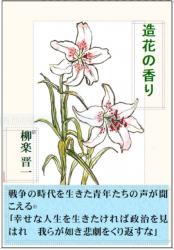寝床に入って身を横たえると、縁側の外からもの音が聞こえた。耳をすますと風の音だった。風に鳴る庭木の音に重なって低い轟きが聞こえた。かすかではあったが、それは確かに轟だった。母から聞かされていた海鳴りにちがいなかった。
冬の出雲はときおり厚い雲におおわれ、冷たい季節風にさらされる。日本海をおし渡ってくるその風が、山陰海岸に怒涛をもたらし、その轟きを陸地の内部へと運んでくる。母からそのことを聞かされ、冬の荒れる日本海を見たいと思っていた。かすかに聞こえる海鳴りに耳をすましつつ、その機会がようやく訪れたことを知った。
つぎの日、従兄といっしょに家を出たのは11時前だった。従兄は知人たちとの会食のために出雲市へ行き、そのあと松江に帰る予定だった。
バス停で従兄を見送ってから、ひとりで畑中の道を海へ向った。畑は砂地の丘にひろがっており、その先には松の林が連なっていた。林が近づくにつれ、海鳴りが次第に大きくなった。道は林の中へと続いていた。
林の中の砂の道には、いたるところに松の根がうねっていた。太い根をあらわにした松の巨木は、どれもみな風に押されるように傾いていた。松は根元を風にえぐられながらも、その太い根で自らの体躯を支えていた。そのような松の姿は、その場所が松の自生に厳し過ぎることを教えていた。
祖父と一緒に初めてその林を訪れたのは、僕がまだ小学生の頃であったが、そのとき祖父が語ってくれたところによれば、それらの松は防風林のために植えられたものだった。砂丘で松を育てるために払われた知恵や労苦が、出雲ではよく知られている、と祖父は語った。祖父の話を思いだしつつ松を見あげると、風と戦っている松が雄叫びをあげていた。
松風につつまれながら林を通りぬけると、眼の前に海がひろがった。僕は風を押しやるようにしながら、浜辺へ向かう砂の道をくだった。
僕は砂浜に立って沖合いを眺めた。波のかなたは厚い雲に溶けこみ、水平線はおぼろに見えた。風と怒涛の響きのなかで、僕は押し寄せてくる波を迎えた。塩を含む飛沫が頬を濡らした。
砂浜のどこにも、人影はむろんのこと、一羽の鳥も見られなかった。荒涼とした砂浜を右のかなたにたどった先が大社町だが、そのあたりの海岸は霧がかかったようにかすんで見えた。
出雲大社のあたりに眼をやりながら、夏の山陰旅行のことを思った。あの砂浜で絵里たちと遊んだのは、そして、今こうして立っている場所をあちら側から眺めたのは、前年の暑い8月だった。
砂浜に沿って防風林がつらなり、黒味を帯びた松の緑が、寒々とした風景にわずかな彩りを添えていた。
風になびくかのように傾いている松を見ているうちに、僕はようやくにして気がついた。校歌に詠われている磯なれ松は、防風林のこの松の樹だ。
寒さに対する身仕度はしていたものの、風に吹かれていると体が冷えた。飛沫で服がぬれていた。
浜辺をひきあげることにして、今いちど沖合に眼を向けると、荒涼とした灰色の眺めに、夕焼けの華麗な光景が重なった。砂浜におり立ったときから、その光景がくり返しては心に浮かび、僕の眼を怒涛のかなたに引きつけていた。
荘厳な入日のさまは、そして、夕映えに染まった絵里の横顔は、僕の脳裏にまだ鮮明だった。僕をみつめた絵里の瞳はありありと思いだせたが、風と怒涛の響きのなかで、遠い日のできごとのように思われた。
出雲へ出かける準備をしていた元日の午後、年賀はがきの束が配達されてきた。僕に宛てた賀状を選んでいると、ボールペンで書かれた絵里からの賀状があった。雪山の絵はがきを賀状にしたもので、文面には小さな文字がならんでいた。その文字に惹かれるままに、僕はその場で絵里からの賀状を読んだ。
〈あけましておめでとうございます。昨年はとても良い思い出を本当にありがとうございました。私とのことが松井さんにも良い思い出となりますよう願っています。せっかくの人生を幸せで楽しいものにするよう勇気をだして積極的にやってみます。友達と初めてのスキーに行きました。松井さんもスキーがお好きなら兄を誘って連れていって下さい。お幸せをお祈り致します。〉
絵里が書いた文字を見たのはそれが初めてだった。僕に対する気持をうかがわせる言葉がないことに、絵里の気くばりを感じた。
その夜、電気スタンドの明かりのなかで、絵里からの賀状をあらためて眺めた。
写真のわきにスキー場の名前が印刷されていた。スキーの練習をしている絵里を思い浮べつつ、絵里が書いた文字を読み直した。丸みをおびた小さな文字を見ながら、それを綴ったときの絵里の心のうちを想った。絵はがきに詰めこむように書かれた文字に、前向きに生きようとする絵里の気持ちが表れていると思った。
年賀状を眺めながら思った、絵里はこの賀状によって、僕を安心させようとしたのかもしれない。そうだとすれば、それはいかにも絵里に似つかわしいことだ。もしかすると、いっしょにスキーをした友達というのは、絵里の新しいボーイフレンドかもしれない。そのような男が早く現われて、絵里に楽しい日々を与えてやってほしいものだ。そのように思いながらも、淋しさに似た感情が胸の底を流れた。
僕とのことが良い思い出になったという言葉に、山陰旅行やホテルのことが、苦みを伴いながらも懐かしく思い出された。ハガキに眼をとめたまま僕は思った。絵里にとって、自分はすでに思い出の世界の住人になっているのだろうか。それにしても、僕とのことが良い思い出になっているというのは本当だろうか。
僕の胸のうちには、絵里をいとおしく思う気持が残っていたが、それは絵里に対する未練というよりも、むしろ懐かしさに近いものだった。絵里はすでに僕の思い出の人になろうとしていた。わずか2ヵ月で絵里がそのような存在になったのは、僕がそれを望んでいたからだった。
三鷹駅で別れてからも、絵里はしばしば僕の胸を訪れてきた。絵里が心に現われると、僕はすなおにそれを受けいれて、絵里とのことをふり返ることにした。そのついでに、中学や高校時代に片想いをした相手を思いだし、絵里とあの同級生たちは、自分の人生にとってどんな存在であろうか、と考えてみた。そして思った。絵里に対する想いがまだ残っていようとも、絵里もまた、いずれは懐かしいだけの存在になってゆくはずだ。そうなることを願っていれば、さほどに手をかさなくても、絵里は記憶の世界に入ってゆくに違いない。
やがて、絵里は期待に応えて足早に思い出の世界に入って行った。僕がいくぶんかはそれを手伝ったにしろ、わずか2ヵ月で、絵里は記憶の中の、それも極めて懐かしい記憶の中の女の一人になりつつあった。
体がすっかり冷えていた。僕は海に背を向け、防風林に向かって砂の坂を登った。遠くの方では雪が降りはじめたらしく、大社町のあたりはほとんど見えなくなった。真昼の太陽は厚い雲にとざされ、その在りかすらわからなかった。
海鳴りに松風が響きあい、防風林はさながら巨大な音響空間だった。松風につつまれながら歩いていると、思いきり大きな声を出したくなった。僕は声をはりあげて歌をうたった。無駄に抱えていたものを声とともに放出しているような、そして、僕を束縛しているものを解き放ちつつあるような気持になった。爽快な気分が胸を満たした。
歌いながら歩いて行くと、道を半ばふさいでいる松の根に出合った。傾いた松を支えているその太い根は、風に削られた地面から1メートルほどの高さにあった。通り過ぎようとして根に触れたとき、手のひらに伝わってくるものを感じた。
根に触れたまま僕は思った。この樹を植えた人の手も、この根に触れたにちがいない。樹を植えながら、その人はどのような想いを抱いていたのだろうか。風と戦う松の姿に想いをはせながら、祈りをこめて苗木をここに植えたことだろう。もしかすると、その人は心の耳で聴いていたのかも知れない、防風林のこの松風を。
防風林の造成に執念を燃やした人がいなかったなら、松の苗木を砂丘に根づかせることはできなかっただろう。人が根づかせた松の樹は、潮風に耐えて成長し、長い歳月を風と戦ってきたのだ。不屈の意志をもって松を育てた人に応えて、防風林は冬の季節風に立ち向かっている。防風林は砂の移動をおさえることにより、この地で畑作を可能にしている。松を植えた一人ひとりが忘れられた今も、この防風林はこの土地に生きる人々の生活を守っている。この防風林こそは先人が遺したまさに偉業だ。
あの校歌の歌詞が思いだされた。〈海よ西浜 磯なれ松に 高き理想仰ぐも嬉し 至誠一貫 先人の偉業を継がむ〉という歌詞には、その最初に防風林のこの松がうたわれている。人が植えたこの松の樹は、困難に立ち向かおうとする人に勇気を贈るはず。この松の樹はわれわれに不屈の意志でことにあたれと教えてくれる。人を鼓舞するこの松の姿が、そして、この磯なれ松のそのような力が、校歌の歌詞に表わされているような気がする。校歌の作詞者はどのような人だったのだろうか。その作詞者と詞に対して、僕は敬意とともに共感をおぼえた。
松の根にふれたまま僕は歌詞の一節を口ずさんだ。
「至誠一貫 先人の偉業を継がむ」
声は松風に消された。僕は松を見あげた。松は風と戦いながら雄叫びをあげていた。傾いた松を見ながら僕は思った、あの校歌の作詞者は、学童に励ましの言葉を贈るとともに、先人に対する感謝の気持ちを想起させようとしたのだ。防風林の恩恵を受けるこの土地の人々にとって、これらの松は何よりもまず、先人に対する感謝の念を呼び起こす存在なのだ。
冬の出雲はときおり厚い雲におおわれ、冷たい季節風にさらされる。日本海をおし渡ってくるその風が、山陰海岸に怒涛をもたらし、その轟きを陸地の内部へと運んでくる。母からそのことを聞かされ、冬の荒れる日本海を見たいと思っていた。かすかに聞こえる海鳴りに耳をすましつつ、その機会がようやく訪れたことを知った。
つぎの日、従兄といっしょに家を出たのは11時前だった。従兄は知人たちとの会食のために出雲市へ行き、そのあと松江に帰る予定だった。
バス停で従兄を見送ってから、ひとりで畑中の道を海へ向った。畑は砂地の丘にひろがっており、その先には松の林が連なっていた。林が近づくにつれ、海鳴りが次第に大きくなった。道は林の中へと続いていた。
林の中の砂の道には、いたるところに松の根がうねっていた。太い根をあらわにした松の巨木は、どれもみな風に押されるように傾いていた。松は根元を風にえぐられながらも、その太い根で自らの体躯を支えていた。そのような松の姿は、その場所が松の自生に厳し過ぎることを教えていた。
祖父と一緒に初めてその林を訪れたのは、僕がまだ小学生の頃であったが、そのとき祖父が語ってくれたところによれば、それらの松は防風林のために植えられたものだった。砂丘で松を育てるために払われた知恵や労苦が、出雲ではよく知られている、と祖父は語った。祖父の話を思いだしつつ松を見あげると、風と戦っている松が雄叫びをあげていた。
松風につつまれながら林を通りぬけると、眼の前に海がひろがった。僕は風を押しやるようにしながら、浜辺へ向かう砂の道をくだった。
僕は砂浜に立って沖合いを眺めた。波のかなたは厚い雲に溶けこみ、水平線はおぼろに見えた。風と怒涛の響きのなかで、僕は押し寄せてくる波を迎えた。塩を含む飛沫が頬を濡らした。
砂浜のどこにも、人影はむろんのこと、一羽の鳥も見られなかった。荒涼とした砂浜を右のかなたにたどった先が大社町だが、そのあたりの海岸は霧がかかったようにかすんで見えた。
出雲大社のあたりに眼をやりながら、夏の山陰旅行のことを思った。あの砂浜で絵里たちと遊んだのは、そして、今こうして立っている場所をあちら側から眺めたのは、前年の暑い8月だった。
砂浜に沿って防風林がつらなり、黒味を帯びた松の緑が、寒々とした風景にわずかな彩りを添えていた。
風になびくかのように傾いている松を見ているうちに、僕はようやくにして気がついた。校歌に詠われている磯なれ松は、防風林のこの松の樹だ。
寒さに対する身仕度はしていたものの、風に吹かれていると体が冷えた。飛沫で服がぬれていた。
浜辺をひきあげることにして、今いちど沖合に眼を向けると、荒涼とした灰色の眺めに、夕焼けの華麗な光景が重なった。砂浜におり立ったときから、その光景がくり返しては心に浮かび、僕の眼を怒涛のかなたに引きつけていた。
荘厳な入日のさまは、そして、夕映えに染まった絵里の横顔は、僕の脳裏にまだ鮮明だった。僕をみつめた絵里の瞳はありありと思いだせたが、風と怒涛の響きのなかで、遠い日のできごとのように思われた。
出雲へ出かける準備をしていた元日の午後、年賀はがきの束が配達されてきた。僕に宛てた賀状を選んでいると、ボールペンで書かれた絵里からの賀状があった。雪山の絵はがきを賀状にしたもので、文面には小さな文字がならんでいた。その文字に惹かれるままに、僕はその場で絵里からの賀状を読んだ。
〈あけましておめでとうございます。昨年はとても良い思い出を本当にありがとうございました。私とのことが松井さんにも良い思い出となりますよう願っています。せっかくの人生を幸せで楽しいものにするよう勇気をだして積極的にやってみます。友達と初めてのスキーに行きました。松井さんもスキーがお好きなら兄を誘って連れていって下さい。お幸せをお祈り致します。〉
絵里が書いた文字を見たのはそれが初めてだった。僕に対する気持をうかがわせる言葉がないことに、絵里の気くばりを感じた。
その夜、電気スタンドの明かりのなかで、絵里からの賀状をあらためて眺めた。
写真のわきにスキー場の名前が印刷されていた。スキーの練習をしている絵里を思い浮べつつ、絵里が書いた文字を読み直した。丸みをおびた小さな文字を見ながら、それを綴ったときの絵里の心のうちを想った。絵はがきに詰めこむように書かれた文字に、前向きに生きようとする絵里の気持ちが表れていると思った。
年賀状を眺めながら思った、絵里はこの賀状によって、僕を安心させようとしたのかもしれない。そうだとすれば、それはいかにも絵里に似つかわしいことだ。もしかすると、いっしょにスキーをした友達というのは、絵里の新しいボーイフレンドかもしれない。そのような男が早く現われて、絵里に楽しい日々を与えてやってほしいものだ。そのように思いながらも、淋しさに似た感情が胸の底を流れた。
僕とのことが良い思い出になったという言葉に、山陰旅行やホテルのことが、苦みを伴いながらも懐かしく思い出された。ハガキに眼をとめたまま僕は思った。絵里にとって、自分はすでに思い出の世界の住人になっているのだろうか。それにしても、僕とのことが良い思い出になっているというのは本当だろうか。
僕の胸のうちには、絵里をいとおしく思う気持が残っていたが、それは絵里に対する未練というよりも、むしろ懐かしさに近いものだった。絵里はすでに僕の思い出の人になろうとしていた。わずか2ヵ月で絵里がそのような存在になったのは、僕がそれを望んでいたからだった。
三鷹駅で別れてからも、絵里はしばしば僕の胸を訪れてきた。絵里が心に現われると、僕はすなおにそれを受けいれて、絵里とのことをふり返ることにした。そのついでに、中学や高校時代に片想いをした相手を思いだし、絵里とあの同級生たちは、自分の人生にとってどんな存在であろうか、と考えてみた。そして思った。絵里に対する想いがまだ残っていようとも、絵里もまた、いずれは懐かしいだけの存在になってゆくはずだ。そうなることを願っていれば、さほどに手をかさなくても、絵里は記憶の世界に入ってゆくに違いない。
やがて、絵里は期待に応えて足早に思い出の世界に入って行った。僕がいくぶんかはそれを手伝ったにしろ、わずか2ヵ月で、絵里は記憶の中の、それも極めて懐かしい記憶の中の女の一人になりつつあった。
体がすっかり冷えていた。僕は海に背を向け、防風林に向かって砂の坂を登った。遠くの方では雪が降りはじめたらしく、大社町のあたりはほとんど見えなくなった。真昼の太陽は厚い雲にとざされ、その在りかすらわからなかった。
海鳴りに松風が響きあい、防風林はさながら巨大な音響空間だった。松風につつまれながら歩いていると、思いきり大きな声を出したくなった。僕は声をはりあげて歌をうたった。無駄に抱えていたものを声とともに放出しているような、そして、僕を束縛しているものを解き放ちつつあるような気持になった。爽快な気分が胸を満たした。
歌いながら歩いて行くと、道を半ばふさいでいる松の根に出合った。傾いた松を支えているその太い根は、風に削られた地面から1メートルほどの高さにあった。通り過ぎようとして根に触れたとき、手のひらに伝わってくるものを感じた。
根に触れたまま僕は思った。この樹を植えた人の手も、この根に触れたにちがいない。樹を植えながら、その人はどのような想いを抱いていたのだろうか。風と戦う松の姿に想いをはせながら、祈りをこめて苗木をここに植えたことだろう。もしかすると、その人は心の耳で聴いていたのかも知れない、防風林のこの松風を。
防風林の造成に執念を燃やした人がいなかったなら、松の苗木を砂丘に根づかせることはできなかっただろう。人が根づかせた松の樹は、潮風に耐えて成長し、長い歳月を風と戦ってきたのだ。不屈の意志をもって松を育てた人に応えて、防風林は冬の季節風に立ち向かっている。防風林は砂の移動をおさえることにより、この地で畑作を可能にしている。松を植えた一人ひとりが忘れられた今も、この防風林はこの土地に生きる人々の生活を守っている。この防風林こそは先人が遺したまさに偉業だ。
あの校歌の歌詞が思いだされた。〈海よ西浜 磯なれ松に 高き理想仰ぐも嬉し 至誠一貫 先人の偉業を継がむ〉という歌詞には、その最初に防風林のこの松がうたわれている。人が植えたこの松の樹は、困難に立ち向かおうとする人に勇気を贈るはず。この松の樹はわれわれに不屈の意志でことにあたれと教えてくれる。人を鼓舞するこの松の姿が、そして、この磯なれ松のそのような力が、校歌の歌詞に表わされているような気がする。校歌の作詞者はどのような人だったのだろうか。その作詞者と詞に対して、僕は敬意とともに共感をおぼえた。
松の根にふれたまま僕は歌詞の一節を口ずさんだ。
「至誠一貫 先人の偉業を継がむ」
声は松風に消された。僕は松を見あげた。松は風と戦いながら雄叫びをあげていた。傾いた松を見ながら僕は思った、あの校歌の作詞者は、学童に励ましの言葉を贈るとともに、先人に対する感謝の気持ちを想起させようとしたのだ。防風林の恩恵を受けるこの土地の人々にとって、これらの松は何よりもまず、先人に対する感謝の念を呼び起こす存在なのだ。