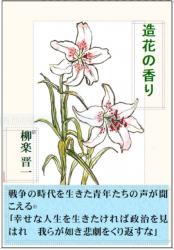プロローグ 雲海
飛行機が滑走を始めた。
遠くに見える空港ビルが、ゆっくりと窓のふちに入ってゆく。ヨーロッパを訪れてから初めてではないか、日ざしに映える建物を見るのは。こちらで過ごした一週間は、ほとんどいつも曇り空だった。
空港ビルが見えなくなった。あそこで絵里と別れてから30分あまりだ。自宅に向かっている絵里はまだ電車の中だろう。僕と過ごしたロビーでのひと時を、絵里はどんな気持ちで振り返っているのだろうか。
窓からの視界がのびてゆく。ロンドンの都心から遠くないはずだが、空港のまわりはどうやら田園地帯らしい。訪れる予定になかったイギリスだ。ここに立ち寄るために観光先を減らすことになったが、それと引きかえにして絵里との再会がかなった。1時間にも満たなかったとはいえ、初めて訪れたヨーロッパでの最たる思い出は、ヒースロー空港で絵里と語り合ったこと、ということになりそうだ。
もしかすると、絵里と会うことも、ヨーロッパを訪れた目的のひとつだったのではないか。幸せになっている絵里を見るために。その絵里に祝福の言葉を贈るために。絵里との再会をはたした今ではそのように思える。日本を発った一週間前には、ロンドンに立ち寄ることすら予定になかったのだが。
絵里がロンドンで暮らしていることを知ったのは、2ヶ月前の8月だった。ドイツへ出かけるまでに調べておきたいことがあり、東京へ日帰りの出張をした日だ。
暑い日だった。仕事をおえて建物から出ると、冷房で冷えた体に湿気がまつわった。太陽はビルのうしろに隠れていたが、暑さは少しも衰えていなかった。流れる汗をふきながら、僕は地下鉄の駅へ急いだ。
勤務先から直行してきた坂田と新宿駅で待ち合わせ、駅から歩いて行ける大衆酒場に入った。
上京したついでに坂田と会う習慣ができたのは、僕が名古屋へ移った10年ほど前からだ。上京するたびに会うというわけでもないが、その日はどうしても坂田と話したかった。ヨーロッパから帰ったばかりの坂田から、旅行の体験談を聞きたかったので、電話をかけて会う約束をしておいた。
僕の訪問先がフランクフルトということもあり、坂田はドイツでの体験から話しはじめた。幾つもの観光地を訪ねて、存分に見てきたという坂田がうらやましかった。学会が終われば間もなく帰国しなければならないので、僕の観光はフランクフルトとその周辺に限られていた。
坂田の話にしばらく耳を傾けてから、僕は口をはさんだ。
「お前でも、苦労したり失敗したことがあっただろう。参考にしたいからさ、そういうのがあったら話してくれないか」
「ということは、お前でもやっぱり不安なんだな」
「初めてのヨーロッパにひとりで行くんだし、それに、おれは英会話に自信がないからな」
「ヨーロッパはおれも初めてだから、パックツァーに参加するつもりだったけど、ロンドンにいる絵里と電話で話しているうちに、思い切って一人旅をしてみようという気持になったんだ。まだ話してなかったけど」と坂田は言った。「絵里はロンドンに行ったんだよ、4ヶ月ほど前に」
坂田の妹が結婚して横浜で暮らしていることは、数年前に彼の口から聞かされていた。その絵里がロンドンにいるとは、いったいどういうことだろう。
「だんながロンドンへ転勤になったものだから、絵里もいっしょに行って、向こうで暮らしてるんだ。そういうわけで、最初の二日ほどは絵里の家に泊めてもらって、ロンドンの付近を見てまわったんだが、その二日間で自信がついたんだよな、フランスやドイツもひとりで何とかなりそうだって」
「それにしても意外だな、絵里さんがヨーロッパで暮らしているというのは」
「急に転勤することになって、絵里もずいぶん心配していたんだよ、ロンドンで生活することに。ところがな、たった3ヵ月で慣れたっていうんだ、あの絵里が。案外とそんなもんだよ。お前も行ってみればわかるさ。慣れたにしてもゆだんはできないし、ときには困るようなことも起こるだろうけど」
ふだんは思い出すことさえなかった絵里が、いきなり身近な所に姿を現したような気がした。あれから10年以上が経っているから、おそらく絵里も変わっていることだろう。それにしてもあの内気な絵里が、ロンドンでどんな暮らしをしているのだろうか。
僕たちはそれから1時間ほど話し合ったが、絵里について触れることはなく、話題の多くは坂田の体験談だった。
それからの2ヶ月を、僕は時間に追われながら過ごした。休む暇もないほど忙しかったが、間もなく訪れるヨーロッパと、そこで暮らしている絵里のことが心にうかび、しばしば仕事の手をとめさせた。日本を遠く離れたロンドンで、絵里はどのような日々を送っているのだろうか。もうすぐそのヨーロッパへ行くことになる。ロンドンを訪ねて絵里に会ったとしたら、どんな出会いになるのだろうか。そのように、絵里との再会場面を想像したことすらあったが、ロンドンに立ち寄る予定はなかったので、再会は空想でしかありえなかった。
フランクフルトに着いたのは、学会が始まる三日前だった。その翌日には会場となる建物を訪ねて、場所の確認と会場の下調べをした。それらの用件をおえてから、時間をかけて街を歩いた。電気器具を扱う店があったので、ショーウインドウをのぞいて見ると、並べられている製品の多くは日本製だった。バブル経済が崩壊してから10年を経ても、日本の家電製品はブランドを誇示していた。
つぎの日は、路面電車に乗って市街を見物してから、中央駅でケルン行き列車の発車時刻を調べた。そのあとは早めにホテルへ帰り、学会で発表するための準備をした。日本にいるときから時差に備えておいたので、苦労するほどの時差ぼけは感じなかった。
英語での質疑応答には苦労したけれども、学会の場で僕は自分の役割をぶじにはたすことができた。二日間にわたって開かれた学会がようやく終わり、残っているのは観光を楽しむことだった。
学会が終わったつぎの日は、朝食を早めにすませて駅に向かった。ケルンの天候はわからなかったが、フランクフルトが曇っていたので、折たたみの傘をバッグに入れた。
列車がライン川に沿って走りはじめた頃から、僕は窓にはりついて外を眺めた。予想していたほどには広くない川を、大きな船が行き交っていた。白い鳥が数羽ほど、川面をかすめて飛んでいた。ぶどう畑の拡がる丘陵に古い城が姿を見せて、ラインをめぐる歴史を思わせた。最初の観光地にケルンを選んで良かったと思った。ライン川付近の風物を眺めることができたし、斜面に耕地が拡がる景観を日本の風景とくらべて、その土地に生きてきた人々の暮らしぶりを想うことができた。
ケルンに着くとすぐに大聖堂を訪ねた。壮大なその建物を見物してから、長いらせん階段を歩いて塔に登り、ケルンの市街とまわりの景観を眺めた。
大聖堂を出てからのあてはなかったので、付近の道をそぞろ歩いた。厚い雲に覆われていたため、誘われるようにして入った道は暗かった。前を行くふたりづれの他には人影がなく、走る車も見られなかった。狭い裏通りに添えられたアクセサリーのように、建物のすぐ壁ぎわに赤い車があった。通り過ぎてから振り返ってみると、小さなその車は永久にそこに停っているように見えた。建物に挟まれている道は静かで、石畳を踏む音が大きく鳴った。残響をともなう音を耳にしていると、歴史を語るその道を、過去に幾度も歩いたことがあったような気がした。10月の末とは思えないほどに寒くて、歩いているうちに体が冷えた。
表通りに出るとカフェが見えた。暖かいコーヒーに誘われるまま、僕は店に向かって足を速めた。
客のまばらな店でコーヒーをすすっていると、女の笑い声が聞こえた。ひくく抑えられていたけれども、その笑い声はいかにもうれしそうに聞こえた。僕は思わず声の主をさがした。少しはなれた席で、若いふたりづれが肩をよせあっていた。笑い声がふたたび聞こえ、女は男に体をよせて肩をゆすった。ふたりのうしろ姿を見ながら、並んで腰かけることを望んだのは女の方かもしれないと思った。いっしょに喫茶店などに入ると、絵里はいつも僕の横に並んだものだった。絵里を喜ばせるようなことを僕がしゃべると、絵里は肩をよせながら小さな声で笑った。
ささやき交わすふたりを見ていると、いきなり、絵里に会いたいという気持ちがわきおこってきた。絵里はロンドンにいるのだ。ここまでやって来ながら、絵里に会わずに日本へ帰るというのは、むしろ不自然なことではないか。会わないまでも、電話で言葉を交わす程度のことはすべきではないか。電話番号なら坂田に聞けばよい。そのような思案をしているうちに、絵里の声を聴いてみたいという気持ちがふくらんできた。
フランクフルトに帰りついたとき、日本では夜の11時に近い時刻になっていた。遅い時刻が気にはなったが、国際電話をかけることのできる公衆電話をみつけ、思いきって坂田に電話をかけた。
「ドイツにいると、ロンドンのすぐ近くまで来ているような気がするんだよ。ここまで来ていながら、絵里さんに声もかけずに帰ったら、絵里さんに対して失礼だろうと思うんだ」
言いわけがましい言葉を口にしてから、絵里の電話番号を教えてくれと頼んだ。
公衆電話の受話器をもどし、手帳に記した絵里の電話番号を見ると、新しいページの真ん中に、大きな数字が並んでいた。