♪ I'm A Fool To Want You
曲が変わった。この店のテーマ曲のようなものだ。
「春になって私は資格をとった。最短だったよ」
「頑張ったのだね、多分、彼もね」
「なんでもお見通しね?ママ。ハード・スケジュールの中でも何も言わず、毎日、送迎してくれたよ」
「彼の会社で仕事したのかい?」
「うん、給料もちゃんとくれたよ。特に色など付けずに規定通りにね」
「そしてくり返すんだね、僅かな時間を作って必死に会おうとする」
「でも、冬から春に変わって時間は加速するばかり・・・“また、明日“がさよならに近づくだけ」
♪ I'm A Fool To Want You
梅雨になった。
『きついよ、この湿気。やっぱりきつい』
冬、どんなに忙しくても大丈夫だったアイもこちらの梅雨の暑さには体調を崩してしまった。
『仕事は休めないよ、お金にならないだろう。ちょっと風邪がこじれただけ。風邪薬買って来て欲しい。心配ないって言ってもあなたは心配するでしょう?だから言わな〜い』
いつものように悪戯っぽく笑う。
彼は、薬屋に行って頭痛薬から風邪薬、胃腸薬を買って届けた。
彼女の部屋は店の寮のようなものだから、店のスタッフが突然来る場合がある。彼は部屋には上がらなかった。食事はインスタント物を用意するしかなかった。
アイは彼の仕事も休まなかった。彼との約束だから?それだけのはずがない。
“梅雨が終わるまで、あとどのくらい?”
“別れの夏まで、あと、どのくらい?”
加速する時間の中では逢うことが辛くなる。
♪ I'm A Fool To Want You
「時が過ぎて行くことが切ないね」
アイの過去の中にあたしも入り込んでいた。
あたしが作るグラスが濃くなっていることに気付いた。
それでもあたしもアイも酔い切れない、回想が夏に近づいて行く。
痛みが、心の痛みがあたし達を酔わせないのか?夏が近づく中、アイの身体は少しずつ回復して行く。
『もう、大丈夫だよ。でもね、この暑さは厳しい〜』
彼の会社の仕事も約束の三ヶ月が来て、ギリギリまで続けてもいいと言うアイの申し入れを彼は断った。
「それは何故だい?」
「組まれたシフトあるからだと思うよ」
「そんなことはどうにでも出来ただろう?」
「もう、夏だった。ママ、もう暑い夏がそこまで来ていたんだよ」
あたしもアイもグラスを呷るしかない。
「そして七月の初めから突然、彼からの連絡が途絶えたの」
アイは八月の頭に地元の祭りがあるから、それに合わせて帰りたいと言った。
「逢うのが辛くて、彼はアイを拒絶したのだね」
「カウントダウンに耐えられなかったんだよ。一日、一日、別れの日が近づくのは耐えられない悲しみだったよ」
そして、二週間が過ぎた。
『今日は店が早く終わりそうだから他の店で歌おうよ。いつもの駐車場で待っていて』
何事もなかったようなアイからの一通のメールで恋次郎は崩れてしまった。
冬はエンジンを切ってガタガタ震えながら待っていた駐車場で、今度は暑さで窓を全開にして待っていた。
『久しぶり!と言っても二週間かあ』
アイは二週間前と全く変わらない笑顔で路地を駆けて来た。
車で五分位の場所にある彼の行きつけのスナックに行った。
『ねぇ、恋次郎はあの娘が好きでしょ?私を出汁(だし)にしてここに連れて来たわけだ』
アイは平然と“麗”という名前の女の子を指差した。
『やばい、私たちの席に来るぞ』
『恋ちゃん、いらっしゃい、相変わらず可愛い女の子を連れて』
『よろしくう、私は恋次郎が麗ちゃんに会うための出汁(だし)ですう』
彼は、あたふたして何も言えないでいた。
アイはそんな彼を見て、笑いまくっていた。
『ねぇ、とっておきの曲を教えてあげるよ。でも悲し過ぎて、私がいなくなったら歌えなくなるから嫌か?』
アイは、サザンオールスターズの曲で“夢に消えたジュリア”を歌った。
夏に消えた恋人を想う歌。
歌詞の語尾に自分達に重なる部分があると、その曲を歌いながら彼に視線を向けた。
この別れはもう止められない。胸を抉るような叫び、そんな歌をアイは熱唱した。
「何故、俺の傍にいるんだ」
彼が聞いた。
『あなたもいつも居場所を失くして寂しい顔していたからさ。それにあなたは、優しさだけじゃ生きていけないって知っていたから、私、ちょっと甘えてみせただけ』
アイは深夜遅くまでやっているスナックで切ない歌ばかり歌って聞かせた。
『ねぇ、こんな切ない曲が好きだよね、どう私の好みと一緒じゃないの?』
どの曲も彼が好む切ない曲ばかり選んだ。
カラオケがやんだ時、アイは口ずさむように歌った。
『♪ 少し肌寒い夜 想い出の場所であなたと二人
星空眺めて寄り添ったね
白い車の中で後悔するなと
背中を押してくれた日からもう
どのくらい経つのだろう』
恋次郎が知らない曲だった。カラオケにもない。北海道出身の女性二人のデュオの曲だと恋次郎に教えた。
『♪ほつれた糸に落ちる涙
もう繋がるのは難しいけど
もう少しだけ信じたくて
いつまでも忘れられない
優しさがわすれさせない
苦しいよ今すぐ抱きしめてほしい
強くないから私
いつまでもあなたはずるいよ
もういい加減引き離して
じゃなきゃ私はこのまま
あなたを思い続けてしまうから・・・』
『この曲はconsado(コンサド)というデュオの歌なんだ。今度、続編が出来るのだって。忘れられない果てには何があるのかな?・・・ねぇ、私の地元のお祭りに来る?ねぇ、追いかけて来る?六三〇キロあるよ、私の故郷まで。私が教えた歌、悲しくて歌えなくなっても知らないよ?六三〇キロ、北に私は行くよ』
『ねぇ、追いかけて来る?』
本気なのか?試しているのか?彼はアイの目を視た。
アイはいつものように目を逸らした。
♪ ピアノの音
♪ 夢に消えたジュリア
これは、マリアのピアノなのか?
それとも、あたし達の心の中に流れているだけなのか?
カシャ
氷とグラスが触れる音。
「彼は何も答えなかった」
「ずるいと思ったかい?」
「思わないよ、それはその瞬間だけの夢だもん」
「そうだね、勇気と無謀は違うからね」
「ママの言葉は深いね」
♪ 夢に消えたジュリア
『バイトは昨日の夜で終わったんだ。今夜は友達の家に行くよ。お別れを言いにね。この街に来れたのは友達のおかげだし・・・明日の夜にはこっちを発つよ』
『そうだ、今夜は花火が上がるよ。どうだ?見に行かないか?』
『一緒に並んで見ない方がいいよぅ』
『どうして・・・』
『だって花火は綺麗だからさ・・・』
『想い出になっちまうからか?』
『花火を見る度に私を想い出しちゃうぞ』
アイはいつものように悪戯っぽく笑おうとした。でも、そこには唇を噛み締めるアイの横顔があるだけだった。
『明日の夜、見送ってね。初めて迎えに来てくれた私の車がある駐車場・・・間違えるなよ、いつも待ち合わせた店の近くじゃないからね』
明日なんて嘘だ。アイは、今夜中に発つつもりだった。
カシャ
氷とグラスが触れる音。
「夜、私は車の中で泣いていた。明日の夜にはもう田舎に着いていて、見送ることなど出来ない筈だった。私は黙って消えようとしていた・・・」
「彼がアイの嘘を見抜くと、気づいていたんだろう?」
「そうかな・・・」
「そうさ・・・」
「私、彼を振り切るためにアクセルを踏み込んだ。でも、その直後にブレーキを踏んでしまったあ。バカだね」
「ためらいのブレーキを踏んだアイを誰がバカだなんて言うもんか」
アイの車のヘッドライトが闇を裂くと、彼が浮かんだ。
動き出したアイの車は一瞬、止まって、また動き出す。
車の中のアイは泣きながら叫んだ。
『何故、来たんだ!』
アイは泣いている自分が信じられなかった。いつも強く、どんなに苦しくても前へ踏み出す私が泣くなんてありえないとアイは自分が分からなくなっていた。
彼が手を伸ばそうとした刹那、アイはアクセルを踏んだ。
アイの車のドアガラスが降りる。
彼は彼女の名を呼ぶ。
アイの声・・・
最後に彼の名がエンジン音に千切れて行く。
アイの車が加速する。
車のテールランプは灯らない。
ただ、遠ざかって逝く。
夏が来た。
別れの夏が来た。
遠くで花火の音が聴こえた。
カシャ
氷とグラスの触れる音。
「『それでよかったのか?僕はずるいよな』と彼がここで話したことがあったよ」
「勇気と無謀は違う・・・とママがさっき言っていたけど私もそう思うよ」
アイがグラスを合わせる。
「大人だね、アイは」
「難しいことは私、馬鹿だから分からないよ」
「アイも彼も小さい夢に想いを託したのだよ。私はここにいたバーテンダーの冬木が私を守るために犯した罪を許さない。でもね、私のために人生を棄てた冬木を待っているんだよ。冬木の想いはしっかりと受け止めているんだよ…」
♪ The way we were・・・
曲が戻った。
「ねぇ、ママ。彼が私を失くした時にママが作ったカクテル“Lost・・・”を私にも作ってもらえない?」
「あぁいいよ」
「メールをもらったんだ、私の誕生日に。私を失くした時にママが作ってくれたカクテルが心まで酔わせようとしたって。ジョークのようにごまかそうとしていたけど、マジだったと思うよ」
ジョークのようにしようとしているのはアイも同じだろうと言いたい言葉をあたしは飲み込んで、プリマス・ジン、スロージン、ライムジュース、アンゴスチュラビターズをカウンターに並べた。
プリマス・ジン、スロージン、ライムジュースを、それぞれ20ミリをシェイクして氷を詰めたロンググラスに注いで、トニック・ウォーターでグラスアップし、最後にアンゴスチュラビターズを1ダッシュ入れたら軽くステアした。
「Lost・・・だよ」

アイは、ケータイでカクテルを撮影していた。
「ママ、この画像を彼に送っていい?」
「あぁ構わないけど、アイがここにいると」
「私がここにいると分かったら彼はどうするだろう?」
アイは視線をあたしに向けた。今度は目を逸らさない。
アイは手慣れた操作でケータイから画像を送ったようだ。
「画像だけ送ったよ。文書は全く無し」
「ここへ来るよ、アイがLost・・・を送ったなら」
アイがLost・・・を少し口に含んだ。
「あぁ、シャープ!なんてシャープな切れ味。あぁ、でも、ママ、ふんわりと甘味が広がるよ、美味しいよ、このカクテル」
アイはしっかりとあたしの目を見て言った。
「ママ、お願いがるんだ、聞いてもらえないかなあ。お願い」
「あぁ、言ってごらん」
♪ The way we were・・・
ドアが開いてカウベルが鳴った。
恋次郎が少し息を切らして入って来た。
誰も居ないカウンター。私は今までアイが座っていたスツールの隣の席を用意した。
「帰ってしまったよ」
「そうか、でも正直なところ、少しホッとしている。彼女がまだ居たら僕はどうしたらいいか分からない、ここへ向かいながら足が止まりそうになったよ」
「アイがお前にカクテルを一杯奢りたいと」
「アイ?」
「アルファベットのiだと名乗ったよ。お前の前ではホントの名前だったんだろうけど」
あたしは、プリマス・ジン、スロージン、ライムジュースをシェイカーに入れてシェイクした。オールド・ファッションド・グラスに注いだ。
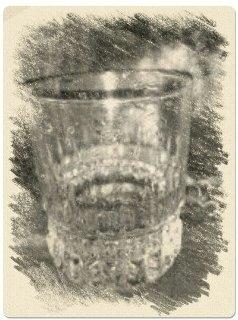
「久しぶりだなあ。でも、Lost・・・の材料だけど、グラスも色もいつもと違う」
「材料は同じでもレシピは変えたよ。このカクテルをお前に出す時は、Lost・・・という名前ではなく」
「えっ?なんて?」
「リメンバーと呼んで欲しいとお願いされたんだよ」
「リメンバー・・・」
「お前ならどう訳す?」
「忘れない・・・かな」
「良い言葉だね」
♪ 追憶
曲が変わった。
「この曲はスターダスト・レビューの追憶。彼女が教えてくれた一曲だよ」
『切ないぞ、この曲を覚えてしまっていいの?私を失くしたら悲しくて歌えなくなっても知らないから』
「って、からかいながら歌っていたよ」
ほんの十数分前、アイがお願いしたいと言ったのは一つではなかった。
「帰ってしまうのかい?」
『ねえ、ママ、私が帰ってから彼が現れたら、私が偶然会えたらいいなぁって思いながら、さっきまで飲んでいたよって』
「わかった、伝えるよ」
『それから、マリアさん、この曲を弾いて』
と言ってアイは、追憶を口ずさんだ。
♪ 追憶
『昔、この街に来た時は私の車の中は生活必需品でいっぱいだったけど、今日は空っぽ』
あたしはアイの言葉をそのまま伝えた。
恋次郎は、カクテル・リメンバーに手を伸ばした。
「それは君に帰る場所があるって意味だね」
恋次郎はいかにも隣に彼女がいるかのように呟いた。
そして、リメンバーを手首を返すだけで飲み干した。
彼女がグラスをロングからショートに変えて、更に氷も抜いてくれと頼んだ理由が、恋次郎にはちゃんと伝わっていた。
♪ 追憶
ここは、Foolという名のBar
愚か者が静かに酔い潰れるための店。
曲が変わった。この店のテーマ曲のようなものだ。
「春になって私は資格をとった。最短だったよ」
「頑張ったのだね、多分、彼もね」
「なんでもお見通しね?ママ。ハード・スケジュールの中でも何も言わず、毎日、送迎してくれたよ」
「彼の会社で仕事したのかい?」
「うん、給料もちゃんとくれたよ。特に色など付けずに規定通りにね」
「そしてくり返すんだね、僅かな時間を作って必死に会おうとする」
「でも、冬から春に変わって時間は加速するばかり・・・“また、明日“がさよならに近づくだけ」
♪ I'm A Fool To Want You
梅雨になった。
『きついよ、この湿気。やっぱりきつい』
冬、どんなに忙しくても大丈夫だったアイもこちらの梅雨の暑さには体調を崩してしまった。
『仕事は休めないよ、お金にならないだろう。ちょっと風邪がこじれただけ。風邪薬買って来て欲しい。心配ないって言ってもあなたは心配するでしょう?だから言わな〜い』
いつものように悪戯っぽく笑う。
彼は、薬屋に行って頭痛薬から風邪薬、胃腸薬を買って届けた。
彼女の部屋は店の寮のようなものだから、店のスタッフが突然来る場合がある。彼は部屋には上がらなかった。食事はインスタント物を用意するしかなかった。
アイは彼の仕事も休まなかった。彼との約束だから?それだけのはずがない。
“梅雨が終わるまで、あとどのくらい?”
“別れの夏まで、あと、どのくらい?”
加速する時間の中では逢うことが辛くなる。
♪ I'm A Fool To Want You
「時が過ぎて行くことが切ないね」
アイの過去の中にあたしも入り込んでいた。
あたしが作るグラスが濃くなっていることに気付いた。
それでもあたしもアイも酔い切れない、回想が夏に近づいて行く。
痛みが、心の痛みがあたし達を酔わせないのか?夏が近づく中、アイの身体は少しずつ回復して行く。
『もう、大丈夫だよ。でもね、この暑さは厳しい〜』
彼の会社の仕事も約束の三ヶ月が来て、ギリギリまで続けてもいいと言うアイの申し入れを彼は断った。
「それは何故だい?」
「組まれたシフトあるからだと思うよ」
「そんなことはどうにでも出来ただろう?」
「もう、夏だった。ママ、もう暑い夏がそこまで来ていたんだよ」
あたしもアイもグラスを呷るしかない。
「そして七月の初めから突然、彼からの連絡が途絶えたの」
アイは八月の頭に地元の祭りがあるから、それに合わせて帰りたいと言った。
「逢うのが辛くて、彼はアイを拒絶したのだね」
「カウントダウンに耐えられなかったんだよ。一日、一日、別れの日が近づくのは耐えられない悲しみだったよ」
そして、二週間が過ぎた。
『今日は店が早く終わりそうだから他の店で歌おうよ。いつもの駐車場で待っていて』
何事もなかったようなアイからの一通のメールで恋次郎は崩れてしまった。
冬はエンジンを切ってガタガタ震えながら待っていた駐車場で、今度は暑さで窓を全開にして待っていた。
『久しぶり!と言っても二週間かあ』
アイは二週間前と全く変わらない笑顔で路地を駆けて来た。
車で五分位の場所にある彼の行きつけのスナックに行った。
『ねぇ、恋次郎はあの娘が好きでしょ?私を出汁(だし)にしてここに連れて来たわけだ』
アイは平然と“麗”という名前の女の子を指差した。
『やばい、私たちの席に来るぞ』
『恋ちゃん、いらっしゃい、相変わらず可愛い女の子を連れて』
『よろしくう、私は恋次郎が麗ちゃんに会うための出汁(だし)ですう』
彼は、あたふたして何も言えないでいた。
アイはそんな彼を見て、笑いまくっていた。
『ねぇ、とっておきの曲を教えてあげるよ。でも悲し過ぎて、私がいなくなったら歌えなくなるから嫌か?』
アイは、サザンオールスターズの曲で“夢に消えたジュリア”を歌った。
夏に消えた恋人を想う歌。
歌詞の語尾に自分達に重なる部分があると、その曲を歌いながら彼に視線を向けた。
この別れはもう止められない。胸を抉るような叫び、そんな歌をアイは熱唱した。
「何故、俺の傍にいるんだ」
彼が聞いた。
『あなたもいつも居場所を失くして寂しい顔していたからさ。それにあなたは、優しさだけじゃ生きていけないって知っていたから、私、ちょっと甘えてみせただけ』
アイは深夜遅くまでやっているスナックで切ない歌ばかり歌って聞かせた。
『ねぇ、こんな切ない曲が好きだよね、どう私の好みと一緒じゃないの?』
どの曲も彼が好む切ない曲ばかり選んだ。
カラオケがやんだ時、アイは口ずさむように歌った。
『♪ 少し肌寒い夜 想い出の場所であなたと二人
星空眺めて寄り添ったね
白い車の中で後悔するなと
背中を押してくれた日からもう
どのくらい経つのだろう』
恋次郎が知らない曲だった。カラオケにもない。北海道出身の女性二人のデュオの曲だと恋次郎に教えた。
『♪ほつれた糸に落ちる涙
もう繋がるのは難しいけど
もう少しだけ信じたくて
いつまでも忘れられない
優しさがわすれさせない
苦しいよ今すぐ抱きしめてほしい
強くないから私
いつまでもあなたはずるいよ
もういい加減引き離して
じゃなきゃ私はこのまま
あなたを思い続けてしまうから・・・』
『この曲はconsado(コンサド)というデュオの歌なんだ。今度、続編が出来るのだって。忘れられない果てには何があるのかな?・・・ねぇ、私の地元のお祭りに来る?ねぇ、追いかけて来る?六三〇キロあるよ、私の故郷まで。私が教えた歌、悲しくて歌えなくなっても知らないよ?六三〇キロ、北に私は行くよ』
『ねぇ、追いかけて来る?』
本気なのか?試しているのか?彼はアイの目を視た。
アイはいつものように目を逸らした。
♪ ピアノの音
♪ 夢に消えたジュリア
これは、マリアのピアノなのか?
それとも、あたし達の心の中に流れているだけなのか?
カシャ
氷とグラスが触れる音。
「彼は何も答えなかった」
「ずるいと思ったかい?」
「思わないよ、それはその瞬間だけの夢だもん」
「そうだね、勇気と無謀は違うからね」
「ママの言葉は深いね」
♪ 夢に消えたジュリア
『バイトは昨日の夜で終わったんだ。今夜は友達の家に行くよ。お別れを言いにね。この街に来れたのは友達のおかげだし・・・明日の夜にはこっちを発つよ』
『そうだ、今夜は花火が上がるよ。どうだ?見に行かないか?』
『一緒に並んで見ない方がいいよぅ』
『どうして・・・』
『だって花火は綺麗だからさ・・・』
『想い出になっちまうからか?』
『花火を見る度に私を想い出しちゃうぞ』
アイはいつものように悪戯っぽく笑おうとした。でも、そこには唇を噛み締めるアイの横顔があるだけだった。
『明日の夜、見送ってね。初めて迎えに来てくれた私の車がある駐車場・・・間違えるなよ、いつも待ち合わせた店の近くじゃないからね』
明日なんて嘘だ。アイは、今夜中に発つつもりだった。
カシャ
氷とグラスが触れる音。
「夜、私は車の中で泣いていた。明日の夜にはもう田舎に着いていて、見送ることなど出来ない筈だった。私は黙って消えようとしていた・・・」
「彼がアイの嘘を見抜くと、気づいていたんだろう?」
「そうかな・・・」
「そうさ・・・」
「私、彼を振り切るためにアクセルを踏み込んだ。でも、その直後にブレーキを踏んでしまったあ。バカだね」
「ためらいのブレーキを踏んだアイを誰がバカだなんて言うもんか」
アイの車のヘッドライトが闇を裂くと、彼が浮かんだ。
動き出したアイの車は一瞬、止まって、また動き出す。
車の中のアイは泣きながら叫んだ。
『何故、来たんだ!』
アイは泣いている自分が信じられなかった。いつも強く、どんなに苦しくても前へ踏み出す私が泣くなんてありえないとアイは自分が分からなくなっていた。
彼が手を伸ばそうとした刹那、アイはアクセルを踏んだ。
アイの車のドアガラスが降りる。
彼は彼女の名を呼ぶ。
アイの声・・・
最後に彼の名がエンジン音に千切れて行く。
アイの車が加速する。
車のテールランプは灯らない。
ただ、遠ざかって逝く。
夏が来た。
別れの夏が来た。
遠くで花火の音が聴こえた。
カシャ
氷とグラスの触れる音。
「『それでよかったのか?僕はずるいよな』と彼がここで話したことがあったよ」
「勇気と無謀は違う・・・とママがさっき言っていたけど私もそう思うよ」
アイがグラスを合わせる。
「大人だね、アイは」
「難しいことは私、馬鹿だから分からないよ」
「アイも彼も小さい夢に想いを託したのだよ。私はここにいたバーテンダーの冬木が私を守るために犯した罪を許さない。でもね、私のために人生を棄てた冬木を待っているんだよ。冬木の想いはしっかりと受け止めているんだよ…」
♪ The way we were・・・
曲が戻った。
「ねぇ、ママ。彼が私を失くした時にママが作ったカクテル“Lost・・・”を私にも作ってもらえない?」
「あぁいいよ」
「メールをもらったんだ、私の誕生日に。私を失くした時にママが作ってくれたカクテルが心まで酔わせようとしたって。ジョークのようにごまかそうとしていたけど、マジだったと思うよ」
ジョークのようにしようとしているのはアイも同じだろうと言いたい言葉をあたしは飲み込んで、プリマス・ジン、スロージン、ライムジュース、アンゴスチュラビターズをカウンターに並べた。
プリマス・ジン、スロージン、ライムジュースを、それぞれ20ミリをシェイクして氷を詰めたロンググラスに注いで、トニック・ウォーターでグラスアップし、最後にアンゴスチュラビターズを1ダッシュ入れたら軽くステアした。
「Lost・・・だよ」

アイは、ケータイでカクテルを撮影していた。
「ママ、この画像を彼に送っていい?」
「あぁ構わないけど、アイがここにいると」
「私がここにいると分かったら彼はどうするだろう?」
アイは視線をあたしに向けた。今度は目を逸らさない。
アイは手慣れた操作でケータイから画像を送ったようだ。
「画像だけ送ったよ。文書は全く無し」
「ここへ来るよ、アイがLost・・・を送ったなら」
アイがLost・・・を少し口に含んだ。
「あぁ、シャープ!なんてシャープな切れ味。あぁ、でも、ママ、ふんわりと甘味が広がるよ、美味しいよ、このカクテル」
アイはしっかりとあたしの目を見て言った。
「ママ、お願いがるんだ、聞いてもらえないかなあ。お願い」
「あぁ、言ってごらん」
♪ The way we were・・・
ドアが開いてカウベルが鳴った。
恋次郎が少し息を切らして入って来た。
誰も居ないカウンター。私は今までアイが座っていたスツールの隣の席を用意した。
「帰ってしまったよ」
「そうか、でも正直なところ、少しホッとしている。彼女がまだ居たら僕はどうしたらいいか分からない、ここへ向かいながら足が止まりそうになったよ」
「アイがお前にカクテルを一杯奢りたいと」
「アイ?」
「アルファベットのiだと名乗ったよ。お前の前ではホントの名前だったんだろうけど」
あたしは、プリマス・ジン、スロージン、ライムジュースをシェイカーに入れてシェイクした。オールド・ファッションド・グラスに注いだ。
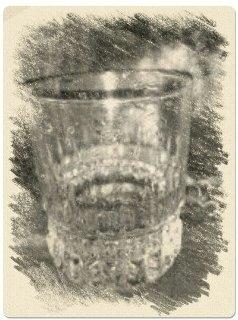
「久しぶりだなあ。でも、Lost・・・の材料だけど、グラスも色もいつもと違う」
「材料は同じでもレシピは変えたよ。このカクテルをお前に出す時は、Lost・・・という名前ではなく」
「えっ?なんて?」
「リメンバーと呼んで欲しいとお願いされたんだよ」
「リメンバー・・・」
「お前ならどう訳す?」
「忘れない・・・かな」
「良い言葉だね」
♪ 追憶
曲が変わった。
「この曲はスターダスト・レビューの追憶。彼女が教えてくれた一曲だよ」
『切ないぞ、この曲を覚えてしまっていいの?私を失くしたら悲しくて歌えなくなっても知らないから』
「って、からかいながら歌っていたよ」
ほんの十数分前、アイがお願いしたいと言ったのは一つではなかった。
「帰ってしまうのかい?」
『ねえ、ママ、私が帰ってから彼が現れたら、私が偶然会えたらいいなぁって思いながら、さっきまで飲んでいたよって』
「わかった、伝えるよ」
『それから、マリアさん、この曲を弾いて』
と言ってアイは、追憶を口ずさんだ。
♪ 追憶
『昔、この街に来た時は私の車の中は生活必需品でいっぱいだったけど、今日は空っぽ』
あたしはアイの言葉をそのまま伝えた。
恋次郎は、カクテル・リメンバーに手を伸ばした。
「それは君に帰る場所があるって意味だね」
恋次郎はいかにも隣に彼女がいるかのように呟いた。
そして、リメンバーを手首を返すだけで飲み干した。
彼女がグラスをロングからショートに変えて、更に氷も抜いてくれと頼んだ理由が、恋次郎にはちゃんと伝わっていた。
♪ 追憶
ここは、Foolという名のBar
愚か者が静かに酔い潰れるための店。

