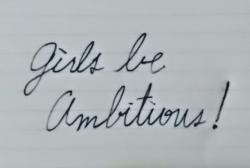というのも。
就職したあと京都にいた馨は、今はアニメーションの仕事を辞めて、家でウェブマガジンの編集の仕事を請け負っている。
「もう四十近いんだし、あんたの人生なんだから、親に縛られなくてもいい」
とは言うものの、姉のミカが東京の病理研究所へ転勤となって家を離れた以上、馨が光代の面倒を見るより他はない。
「一体ゴミ出しから何から、誰がせなあかんと思っとんねんな」
強硬に光代が横須賀を離れたくないと言ったからではないか…とでも言いたげな顔を露骨に、隠そうとも馨はしなかった。
馨にすれば、
「人間なんて誰も勝手で、自分が可愛いだけの生き物」
といったような概念で、半ば捨鉢ですらある。
それだけに。
たまたまインスタグラムで、一面満開のマリーゴールドに「いいね!」とボタンを押したのが切っ掛けで仲良くなっただけの、アメリカ人のアナスタシア・ステファノヴァ──飛行機で向かっている彼女である──が横須賀へやって来るという事自体、
「なんの酔狂で来るんかは、うちにもよう分からへん」
としか、関西弁の抜け切らない馨には思えないままでいた。