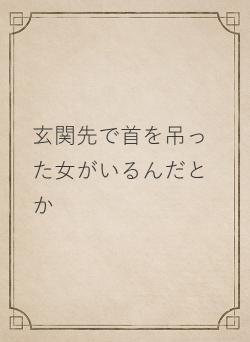間野さんは最後の力を振り絞って僕の痛みを取ったんだ。
でも、どうしてそんなことをする必要があった?
僕と間野さんはほとんど会話をしたことがなくて、付き合いも短くて……。
その瞬間、僕は思い出していた。
『親友だから』
『それでも、僕は間野さんを親友だと思ってる。そう感じることに時間や接点なんて関係ない』
「親友だから……?」
あの言葉が原因だとすれば、僕はどこまでもバカな男だ。
間野さんは親友を欲しがっていて、それなら僕が親友になろうと思った。
たかが、それだけのことで間野さんは……!
「和利、大丈夫?」
「ごめん若菜。僕、行かなきゃ……!」
でも、どうしてそんなことをする必要があった?
僕と間野さんはほとんど会話をしたことがなくて、付き合いも短くて……。
その瞬間、僕は思い出していた。
『親友だから』
『それでも、僕は間野さんを親友だと思ってる。そう感じることに時間や接点なんて関係ない』
「親友だから……?」
あの言葉が原因だとすれば、僕はどこまでもバカな男だ。
間野さんは親友を欲しがっていて、それなら僕が親友になろうと思った。
たかが、それだけのことで間野さんは……!
「和利、大丈夫?」
「ごめん若菜。僕、行かなきゃ……!」