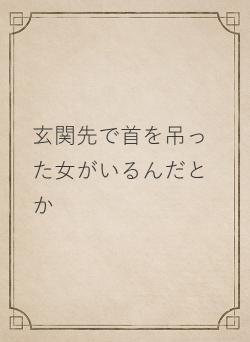なにより、僕が間野さんとまともに会話をし始めたのは昨日からだ。
それでも僕は間野さんに死んでほしくないと思っている。
生きていてほしくてたまらない。
好き。
そんな感情が胸の奥から押しあがってきたが、僕はそれを押し戻した。
今ここでそんなことを言っても間野さんを困らせるだけだとわかっていたから。
「親友だから」
僕がそう言うと、間野さんは目を見開いて僕を見つめた。
信じられないといった感情がその表情にあふれ出している。
「親友だからだよ」
僕は繰り返しそう言った。
「私と大富君って、そんなに接点ないよね?」
間野さんの冷静な言葉が胸に突き刺さる。
でも、ここで引くわけにはいかなかった。
「それでも、僕は間野さんを親友だと思ってる。そう感じることに時間や接点なんて関係ない」
自分でも無茶なことを言っているのはわかっている。
でも、そう言わずにはいられなかった。
間野さんに少しでも自分の生きるための道を選んで欲しかった。
「ごめん。もう面会時間が終るから」
間野さんはそう言い、頭までシーツを押し上げたのだった。
それでも僕は間野さんに死んでほしくないと思っている。
生きていてほしくてたまらない。
好き。
そんな感情が胸の奥から押しあがってきたが、僕はそれを押し戻した。
今ここでそんなことを言っても間野さんを困らせるだけだとわかっていたから。
「親友だから」
僕がそう言うと、間野さんは目を見開いて僕を見つめた。
信じられないといった感情がその表情にあふれ出している。
「親友だからだよ」
僕は繰り返しそう言った。
「私と大富君って、そんなに接点ないよね?」
間野さんの冷静な言葉が胸に突き刺さる。
でも、ここで引くわけにはいかなかった。
「それでも、僕は間野さんを親友だと思ってる。そう感じることに時間や接点なんて関係ない」
自分でも無茶なことを言っているのはわかっている。
でも、そう言わずにはいられなかった。
間野さんに少しでも自分の生きるための道を選んで欲しかった。
「ごめん。もう面会時間が終るから」
間野さんはそう言い、頭までシーツを押し上げたのだった。