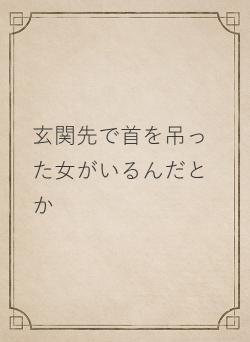強く頭を振って無理矢理自分の思考回路をリセットすると、勢いよく立ち上がった。
「宿題でもするか」
気を取り直して机に向かったとき、無意識に腕に手を伸ばしてカサブタをひっかこうとしてしまった。
また血が出るのにと思った時、指先につるりとした肌が触れて違和感を覚えた。
「え……?」
確認してみると、昨日ひっかいて血が出た部分が綺麗に治っているのがわかった。
逆側の腕だったか?
そちらも確認してみるが、傷もカサブタもない。
昨日ひっかいて剝がれたカサブタが、今日なくなるワケがない。
僕の両腕は元々傷なんてなかったかのように綺麗な状態なのだ。
何度も自分の腕を確認し、晃平君の傷が消えて行く瞬間を再び思い出す。
まさか、間野さんの言っていたことは本当だった……?
だとすれば『この能力は自分には使えないの』という、あの言葉も本物?
僕は間野さんの手から感じた微かな温もりを思い出し部屋から駆け出したのだった。
「宿題でもするか」
気を取り直して机に向かったとき、無意識に腕に手を伸ばしてカサブタをひっかこうとしてしまった。
また血が出るのにと思った時、指先につるりとした肌が触れて違和感を覚えた。
「え……?」
確認してみると、昨日ひっかいて血が出た部分が綺麗に治っているのがわかった。
逆側の腕だったか?
そちらも確認してみるが、傷もカサブタもない。
昨日ひっかいて剝がれたカサブタが、今日なくなるワケがない。
僕の両腕は元々傷なんてなかったかのように綺麗な状態なのだ。
何度も自分の腕を確認し、晃平君の傷が消えて行く瞬間を再び思い出す。
まさか、間野さんの言っていたことは本当だった……?
だとすれば『この能力は自分には使えないの』という、あの言葉も本物?
僕は間野さんの手から感じた微かな温もりを思い出し部屋から駆け出したのだった。