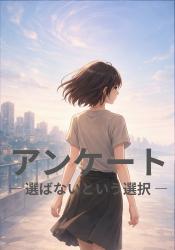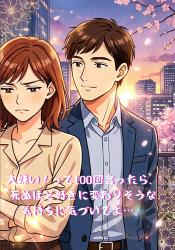それは、この村に代々伝わる、決して破ってはいけない掟だった。
なぜ双眼鏡で山を見てはいけないのか?
その理由は、村人たちの間で「くねくね」という恐ろしい存在の噂として語り継がれていた。
「くねくね」は、山奥に棲むという、人ならざる者。
その姿は、まるで、木の根が這いずるように、地面を這い、くねくねと動くことから、そう呼ばれているという。
その姿を見た者は、皆、精神を病み、廃人となってしまったという。
村人たちは、その恐ろしい噂を信じ、決して山を双眼鏡で見ることはなかった。
しかし、若者たちは、その言い伝えを単なる迷信だと考えていた。
「そんなもの、いるわけがない。」
そう思った若者たちは、好奇心から、こっそりと山を双眼鏡で覗き始めた。
ある日、村の若者、文雄は、山を双眼鏡で覗いていた。
彼は、山奥に、奇妙な動きをしているものを発見した。
それは、まるで、木の根が這いずるように、地面を這い、くねくねと動いていた。
文雄は、その奇妙な動きに、ゾッとした。
しかし、彼は、恐怖よりも、好奇心の方が勝っていた。
彼は、双眼鏡を離すことができず、その奇妙な動きを見つめ続けた。
すると、その奇妙な動きは、次第に、人間の形に近づいてきた。
それは、まるで、人間が這いずるように、地面を這い、くねくねと動いていた。
文雄は、その光景に、言葉を失った。
それは、まさに、村人たちの間で語り継がれていた「くねくね」だった。
文雄は、恐怖に震えながら、双眼鏡を落としてしまった。
恐怖のあまり、彼は、その場から逃げ出した。
しかし、彼の心は、すでに、恐怖に支配されていた。
文雄は、夜になると、悪夢を見るようになった。
夢の中で、彼は、くねくねに追いかけられる。
くねくねは、彼の背後から、這いずるように近づいてくる。
文雄は、必死に逃げようとするが、くねくねは、彼を執拗に追いかけてくる。
そして、彼は、ついに、くねくねに捕まってしまう。
くねくねは、彼の体を、ゆっくりと、ゆっくりと、くねくねと曲げていく。
文雄は、耐えられずに、目を覚ました。
しかし、彼の心は、すでに、恐怖に支配されていた。
彼は、精神を病み、廃人となってしまった。
村人たちは、文雄の姿を見て、再び、山を双眼鏡で見ることの危険性を思い知った。
「山を双眼鏡で見るな。それは、くねくねを見ることになる。くねくねを見た者は、皆、精神を病む。」
村人たちは、その言葉を、子供たちに語り継いだ。
そして、村人たちは、再び、山を双眼鏡で見ることはなくなった。
しかし、山奥には、今も、くねくねが棲んでいる。
夜になると、山からは、奇妙な音が聞こえてくる。
それは、くねくねが、地面を這いずる音なのか、それとも、人間の悲鳴なのか。
誰も、その答えを知らない。
なぜ双眼鏡で山を見てはいけないのか?
その理由は、村人たちの間で「くねくね」という恐ろしい存在の噂として語り継がれていた。
「くねくね」は、山奥に棲むという、人ならざる者。
その姿は、まるで、木の根が這いずるように、地面を這い、くねくねと動くことから、そう呼ばれているという。
その姿を見た者は、皆、精神を病み、廃人となってしまったという。
村人たちは、その恐ろしい噂を信じ、決して山を双眼鏡で見ることはなかった。
しかし、若者たちは、その言い伝えを単なる迷信だと考えていた。
「そんなもの、いるわけがない。」
そう思った若者たちは、好奇心から、こっそりと山を双眼鏡で覗き始めた。
ある日、村の若者、文雄は、山を双眼鏡で覗いていた。
彼は、山奥に、奇妙な動きをしているものを発見した。
それは、まるで、木の根が這いずるように、地面を這い、くねくねと動いていた。
文雄は、その奇妙な動きに、ゾッとした。
しかし、彼は、恐怖よりも、好奇心の方が勝っていた。
彼は、双眼鏡を離すことができず、その奇妙な動きを見つめ続けた。
すると、その奇妙な動きは、次第に、人間の形に近づいてきた。
それは、まるで、人間が這いずるように、地面を這い、くねくねと動いていた。
文雄は、その光景に、言葉を失った。
それは、まさに、村人たちの間で語り継がれていた「くねくね」だった。
文雄は、恐怖に震えながら、双眼鏡を落としてしまった。
恐怖のあまり、彼は、その場から逃げ出した。
しかし、彼の心は、すでに、恐怖に支配されていた。
文雄は、夜になると、悪夢を見るようになった。
夢の中で、彼は、くねくねに追いかけられる。
くねくねは、彼の背後から、這いずるように近づいてくる。
文雄は、必死に逃げようとするが、くねくねは、彼を執拗に追いかけてくる。
そして、彼は、ついに、くねくねに捕まってしまう。
くねくねは、彼の体を、ゆっくりと、ゆっくりと、くねくねと曲げていく。
文雄は、耐えられずに、目を覚ました。
しかし、彼の心は、すでに、恐怖に支配されていた。
彼は、精神を病み、廃人となってしまった。
村人たちは、文雄の姿を見て、再び、山を双眼鏡で見ることの危険性を思い知った。
「山を双眼鏡で見るな。それは、くねくねを見ることになる。くねくねを見た者は、皆、精神を病む。」
村人たちは、その言葉を、子供たちに語り継いだ。
そして、村人たちは、再び、山を双眼鏡で見ることはなくなった。
しかし、山奥には、今も、くねくねが棲んでいる。
夜になると、山からは、奇妙な音が聞こえてくる。
それは、くねくねが、地面を這いずる音なのか、それとも、人間の悲鳴なのか。
誰も、その答えを知らない。