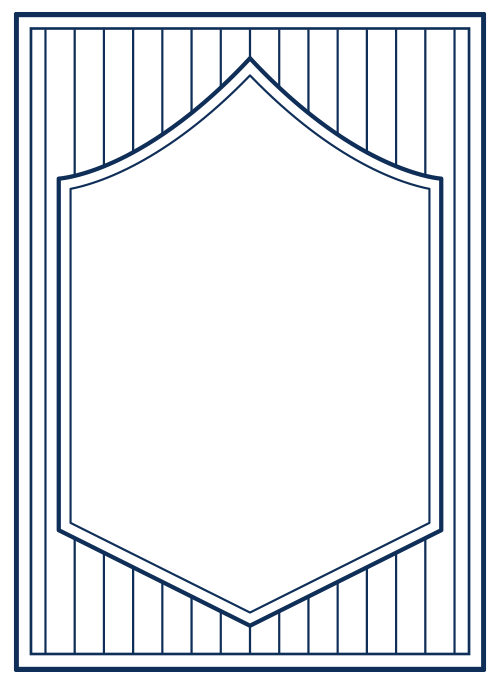この水尾で一番大きな守護主様のお屋敷にある、大広間へと繋がる襖。睡蓮が描かれた美しいはずのそれは、今の私にとっては分厚い壁のように感じた。
(ついにこの日が来た…)
緊張で震えそうになる身体を落ちつかせるために、深く息を吸い込む。
「雪乃様。こちらが嫁取りの会場になっております大広間です。」
「はい…ありがとうございます。」
ここまで連れてきてくれた、案内役の小龍の妖に向けて飾りが落ちないように気をつけて頭を下げる。
「それでは、定刻まで他の候補者様としばしお待ち下さい。」
小龍の小さな手が慎重にその襖を開いた。
桜木の蕾が膨らんできた季節の今日、この地、水尾を治める守護主の妖が''嫁取り"を行う。
かの平安の時代、長きに渡る人間と妖の大きな争いが起きた。激しい戦いだったが中々決着は付かずに結果、帝が公認した妖が治める地をつくることで和解し、その地を『妖地』と呼ぶことにした。
この地、水尾は、この国で五つある妖が治めている地、『妖地』の一つである。妖地ではもっとも強い妖が、『守護主』と呼ばれており、妖地を実質的に治める位の高い妖である。
その守護主は代々その妖地に住む人間を娶ることで、人間との関係の均衡を保っている。その人間が選ばれる儀式が『嫁取り』である。人間との血が混ざり、彫刻のように美しい人の身をもつようになった妖の伴侶。それは女にとって魅力的な地位ではあるが、その女の家にとってはその地に唯一人間が口出しできるようになることから多大な権力の象徴である。よって名家ほど力を入れる儀だ。
襖を開けた先には、同年代程度の若い女がその身を色鮮やかな着物で着飾り、正面を向き定位置の座布団に座っていた。
襖の音に気づいた女達が綺麗な顔がこちらを振り向き、新たに入ってきた者を品定めするような複数の視線と合う。
「………っ…」
着物の中の震える足に気づかれないように、ゆっくりと敷居を超えて進む。この花園のような場所に踏み入れるのは、気後れどころか眩暈までしてしまいそうだ。
この日のために今まで頑張ってきたのだから、大丈夫。そう自分に言い聞かせて、手を強く握る。
「この女が…柏和家からの候補、柏和雪乃様…なんて綺麗な装いをしていらっしゃるのかしら。」
横を通りかかった時に淡い青の着物の女がそう囁くように言ったのを皮切りに、皆の視線がより鋭くなって突き刺さるのを感じた。
咲き誇る牡丹が描かれた上等なつば紅色の着物。
毎日整えられた絹のような淡い青髪は団子にし、梅の花の櫛が刺してある。
唇には紅色の口紅ひかれてあり、華やさが全体の調子を整えている。
私のこれらの仕立ては全て名家、柏和家から用意されたものであり、装いだけならこの大広間にいる誰にも負けない高価で優美なものだ。
私の見目が多少悪くても、これだけ豪華なものをきていれば少しはましになるはずだ。
「あれがかの有名な妖術使いの…まさか本当に守護主様はあの方をお選びになるのでは…」
「噂の"龍に愛された子"ねえ」
自分の座布団に座ってもなお、小声で話す声が聞こえてくる。ある程度目立つとは思っていたが、予想以上に見られている。誰もが自分の方をちらりと盗み見ては、目を逸らしてを繰り返す。強張りそうになる顔を前に向けた。しかし、そんな事で怯んでいる場合ではない。
ーー私はあの方に絶対に選ばれなくてはいけないのだから。
私、柏和雪乃は水尾で富と財をなす三大名家、柏和家からの候補者である。正しくはその分家に生まれた。宿す妖力量自体は少なかったが、妖術の扱いに優れており、七歳の時、その能力を認められ柏和本家へと引き取られた。そこから妖術について、18歳の今日まで厳しい勉強をさせられた。
『妖力』は、妖地に住む人間が守護主からの恩恵として生まれた時から授けられる力であり、妖に対抗するすべの『妖術』を扱うための力である。
そんな妖術に適応できる者は、"守護主様に伴侶として選ばれる"それは、昔からの言い伝えだった。
必死に妖術を学んできた結果、私の腕前は、他の妖地の大臣や妖地へと赴かれた帝にも披露できるまで成長した。
また、私が今代の42代目守護主様との歳が近いことで伴侶候補に相応しいことからも、『龍に愛された子』として、次期伴侶だと言われるようになったのだ。
"皆が私に期待している"
だから絶対に選ばれなくてはいけない
*
嫁取りの儀が行われるまであとあと四半刻、と小龍から知らせが入った頃には、主人のいない座布団も片手で数えられるほどになっていた。
一方で私の緊張はなくなるどころか、身体が強張って全く落ち着ず、手の平の汗も止まらない。
一度御手洗いにでもいこうと考えて、大広間を出て、廊下を歩いていた時だった。
「いっ…….」
硬く尖った何かが、足袋越しに突き刺すように足に当たった。
「櫛?」
退けてみれば、桜の花の飾りがついた櫛があった。
かなり強く踏んだはずだったが、飾りの桜の花弁は一枚も砕けずに、新品のように輝いておりかなり高価な物に見える。誰かが落としてしまったのだろうか。
(壊れなくて良かった。)
そう思って拾い上げようとした時だった。
「何度、言えばわかるの!?あんなもの、貴方に似合うはずがないじゃ無い!」
手を伸ばして拾い上げようとした時、突然耳がつんざくような声が響いた。
広間にも響いてしまいそうなほどの、女の子の怒声。しかし、聞き覚えがあるその声に嫌な予感がして、今だに聞こえる声を頼りにして探し歩いた。
声の主は、ほんの少し歩いた先の六畳少しの候補者専用の着付け部屋にいた。頭には派手で大きな花のついた飾りをつけ、折り鶴が描かれた綺麗な赤い着物を着崩し下品にも化粧台に腰をかけ、床に座る女を見下ろしていた。
「雪華……何の騒ぎ?」
「あ、あ…お姉様!」
そう呼ばれるのは久しぶりだった。あれだけ騒いでいたのが一転、何ごともなかったかのように化粧台から降りると、手本のように綺麗な一礼をしてみせる。
顔を上げた時に、濃い化粧のじろりとした媚びた眼が浮き上がったように目立つ。
「お会いするのは昨年の新年の集まり以来でしたよねえ!実は私も嫁取りに参加するんです!」
「……そう。雪華もなのね。」
「雪乃お姉様の噂は常々聞いております。が…」
彼女は二つ下の実の妹だ。私が本家へ行った後も母と分家に住んでおり、会うのは年に数回、柏和家での集まりがある時や、冠婚葬祭で顔を合わせるぐらいだ。
それがまさか、雪華にも嫁取りの招待が届いているだなんて。
「それで、何をそんなに騒いでいたの。」
「聞いてくださいよ〜。水菜がかんざしを付けるっていうです。水菜にはもったいないじゃない。この妖力なし女に!」
「それってこれ?」
落ちていた桜の花びらがついたかんざしを見せれば、ずっと床に座り込んでいた女の肩がびくりと揺れた。
その瞳の奥が揺らめくように、釘付けになっている。
一つ離れた姉、柏和 水菜。
柏和家でありながら、その身に妖力を全く持たずに生まれてきた異色の存在。
妖力がない、ということは水尾の地に適合してないと言われており、良いところへ嫁げないとされ、出来損ないだと呼ばれて育ってきた。
彼女は参加しないのか、地味で昔に流行ったような草臥れた着物を着ている。
「……別につけたっていいじゃない。」
「はあ!?私より目立ってどうするんですか!水菜は参加しないんですよ!」
綺麗な顔をこれでもかと歪ませながら言うこの妹が、昔から苦手だった。いつでも強気で物言いするその姿を見る度、姉であるはずが押されてしまう。彼女のその根拠のない自信はどこからくるのか。妖術というものをもってなんとか自分を立てている私にとって羨ましかった。さぞ人生が生きやすいだろう。
しかし、今この妹に弱腰になっているなら、守護主様の隣に立つ人間に相応しいとはいえない。そう言い聞かせて、手に持つかんざしを地べたに座ったままの姉の髪に刺す。
「私はお姉様によく似合うと思います。」
・・・
定刻。
大広間に居る者は皆、正座して真っ直ぐに前を向いていた。守護主様のそば付きの小さな小龍の姿の妖はいらっしゃったが、守護主様の姿はまだお見えにならない。
「守護様の到着はもうちょっとかかるみたいで…す、すみません。」
少し焦ったような小龍が閃いた、とでもいうように話し出した。
「みなさま、ご存知の通り…現在、この国はそれぞれ水・火・風・雷を司る、龍・戌・蛇・狐・鬼のあやかしが守護主となって妖地をその地の平穏を保っております。長きの歴史にわたってきた水尾の地はその地名からも分かる通り、澄んだ水が有名でありこの恩恵は」
「長いな。」
「守護主さま!酷いです!」
低い声が聞こえた瞬間、皆一斉に頭を下げる。畳を見つめながら、ほんの一瞬だけ見ることができた守護主様が頭の中に残り続けている。堂々と前から入ってきた彼の美しく端正な顔と真っ白で絹のような髪。しかし頭には立派な角があり、人間でないことを示していた。
「嫁にする人間はもう決めてある。」
どくり、と心臓が波打ち、全身に緊張が広がっていく。習わし通りなら、候補者全員の紹介をお聞きになってから決めるはずだ。しかし、もう今発表させるような流れだ。
(お願い……お願い、選んでください。)
守護主様の御御足が畳から動かれる。
(あ…………)
守護主様の足袋は、私の目の前から遠下がり、ついには視界から消えた。その擦れる音が後方へ遠ざかるとともに、私の心も冷え下がっていく。
「お前、名前は。」
捻り出すようにして出た声は、無音のように聞こえなかった。しかし、守護主様には確かに聞こえたらしい。
「この女を俺の花嫁とする。どんな脅威からも守りぬくと龍の家紋に誓おう。だから、君を大事に囲わせてほしい。」
皆が頭を上げ、ゆっくりと振り返るのを感じてから、自分の目が痙攣するように震えるのを必死に動かして、見上げた。
「っ…………」
(なぜ、なんで…なんで!)
華やかなで飾りをつけた娘達の中から守護主様がその腕に抱いたのは、あの簪をつけたそぼらしい格好をした女。
ーー私の姉だった。
なぜ、姉が。口から転げ落ちそうになった言葉をすんでのところ押さえた時だった。
「は、」
地を這うような怒りとも、困惑とも言えるどす黒く冷たい声。そちらを見れば立ち上がり口を開けたままの妹が二人の方を指差していた。
「ちょっと、ちょっと!待ってください!そんな何の取り柄もない水菜より、妹である私の方が良いに決まってます!」
「もう決定されたことです」
「なんで!だってそんな…私の方が!」
小龍がいくら言ったって雪華は止まらない。髪を振り乱し、地団駄を踏み、今にも掴み掛かりそうな勢いで、皆圧倒されて言葉を失っている。
そんな中、淡々と小龍は地に落とすように静かに告げた。
「これから、柏和水菜様は龍の守護主様の伴侶とし、守護主のもとで過ごされることになります。」
ーー"これにて、嫁取りは終了致します。"
ぱんっと頭の中が弾けたようになって、心臓が嫌にばくばくした。真っ白で硬い雪が分厚く積もったようなこの気持ちは、後にも先にも味わうことはないだろう。
ーー
嫁取りから一カ月が経っても、気持ちは一向に晴れなかった。
「わたしは、選ばれなかった。」
自室の鏡の前に立ってみれば、酷い顔をした女がいた。相変わらず着物だけは美しいが、顔は自分ではないみたいに以前より醜くて見えてしまいそっと鏡に布を被せる。
布団さえ畳まずに起き抜けのまま放置している。脱ぎ捨てた服だって、そこら辺に転がっていた。
心の雪が降り積もって分厚くなり、溶ける気はしない。もしかしたら一生このままかもしれない。
嫁取りの後、私はどうやって柏和家に帰ったか覚えていない。ただただ、もう何も考えられなくて、一言二言当主様へ報告した気がする。
本家の奥様が部屋に勝手に入ってくるまで、3日は自室に篭った。外を歩くのが辛かった。自分がどういう目に見られているか、知りたくなかった。
「ああ……」
嫁取りで頭を下げたままだった自分が嫌でも思い出される。外にはどんなふうに思われただろうか。あんなに期待されていたのに。妖術の話は嘘だと思われただろうか。家では、柏和家の汚点と思われているだろうか。
襖が開き、奥様が入ってこられる。私が部屋から出なくなってからというもの、勝手に入ってくるようになった。
「あら、祝言への準備はできたの?」
「…はい。」
そしてついに今日、姉と守護主様の祝言の日を迎えたのだ。
浮かない顔を見た奥様はそっとその手を頬に添えた。そのひんやりとした体温が皮膚を通して伝わる。
「しっかりしなさい。"あの件"が露呈してからというもの此度の祝言に柏和家が呼ばれるのは、水菜様の温情とも言っていいわ。」
そんな温情などいらないのに、とはこの眉間に皺を寄せる奥様の前では口が裂けても言えなかった。私が選ばれなかった日から、この皺はより深いものとなっている気がする。
「祝言では、外の位の高い大臣や他の地の守護主様も参加なさるそうよ。こんな素晴らしい機会は滅多にない。もうこれを逃してはだめよ。良い人を見つけなさい。」
その声色は数日前から言われ続けた言葉と同じだった。外では、姉が選ばれた理由が、『家事が完璧だから』と噂が立った。その結果、昨日まで散々私に『次は家事を完璧にしろ、今すぐに』と言い続けた。
私がもう疲れたから、しばらくは休みたい、と言った。それでも、奥様はただ「家事を勉強しなさい」と同じことを言い続けた。私は頑張り続けなければいけない。
人生、大きな失敗があっても、時は止まらない。私は走り続けなければいけない。止まることは出来ない。
ーー頑張り続けなければ、人生は成功しない。
それが、ほんとうの幸せなのか。私は、今見える正解を選び続けなければいけない。
そっと窓の外へと顔を背ける。もう桜は散ってしまっているだろう。緑の葉しか見えない木を見て、あの日のことを思い出した。
*
「私、今すごく幸せなの。」
祝言の招待状が届く一週間前、久しぶりに外へ散歩に出かけて守護主様の屋敷を通りかかった際、姉が庭で掃き掃除をしている所に鉢合わせた。正直、話なんてしたいと思わなかったが、前の暗い表情が嘘のように嬉しそうにそう話す姉に死んでも悔しい顔はしたくなかった。
沢山の話をした。主に昔私が本家にいて、妹の雪華は物心つく前の頃の話だった。お姉様が池に落ちたときのこと、私がお手玉が下手くそで、二つだって回せなかったときのこと。話せば話すほど、お姉様は昔から器用だったと思い出した。反面、私は不器用でお姉様の後をついてまわっていた。
そして、ふとお姉様が言ったのだ。
「貴方にも幸せになってほしい」
自分の頭が何かに殴りさられたみたいに、熱くなって、それから急速に冷えるのを感じた。
ーーこの言葉を私に向けないで。
「そんなの…もう無理じゃない。」
嫁取りでは抑えられていた言葉が、溢れるように転げ落ちた。もう、止められない。
「私は、もう、お姉様以上に幸せになんて、なれない…なのに、どうしてそんなこと言えるの?」
こんなこと、言いたくない。
「お姉様以上に良い人のところへなんて嫁げない。それなのに幸せになってほしい?バカにしないで。上から目線も良いところよ!」
ふと、幸せになっても、自分は選ばれなかった人間だったと思い返して、比べてしまうだろう。私はそんな人生を歩み続けるなければいけない。
「お姉様が、嫁いだせいで…私は…!」
もう、幸せになんてなれないのだから。
「私のしあわせは…貴方のせいで…」
そこまで言って、自分が今、冷静になってしまった。
恐る恐る姉の顔を見る。そして後悔した。
そして、姉の言葉を聞いた時、私は理解した。姉が私以上に素晴らしいものを持っていると。だから、選ばれたのだと。
「ごめんなさい。でも、私は今初めて、貴方とちゃんと話せて、ほんとうのことをこうやって言ってくれて、姉妹になれた気がする。それが嬉しい。」
姉が、分家で酷い扱いを受けていたと知ったのは、その三日後だった。
「大変よ。」
私が選ばれなかったと知った時以上に真っ青な顔をした奥様の手には、一枚の文があった。水菜に対し下女のような扱いをして、時に罵詈雑言を飛ばしていたとのことがわかり、柏和分家の領地が取り上げる、との内容が書いてあったのだ。
私は最低な人間だった。
姉が受けてきたものに比べれば、私のやってきたも、気にしていることも、尊厳だって我儘に過ぎなかった。
その日、妖術を勉強した紙も、書物も全部、燃やして捨てた。これが姉への贖罪になるとは思えない、これでも足りないくらいに、きっと罪は重いだろう。
・・・
「何度思い出しても、見ているこっちがときめきましましたよ。まさか、水菜ちゃんが守護主様に選ばれるなんて。」
「ほんと。候補ではなくて、準備のお手伝いで来ていたみたいだけれど…見初められるなんてすごいわ…今日の花嫁衣装姿も可愛くて…お似合いでした。」
盆に乗って出された料理に手をつけようと持った箸が、魚の煮物をつついて終わる。それほどまでに、聞こえてきた女達の会話は不快で仕方なかった。
これだから、祝言になんて出たくなかった。
「おい…雪乃、お前すんごい顔してんぞ。」
隣で食事を取っていた時雨が、化け物でも見たような顔で私を見てくる。仙狸のあやかしと人間との混血の彼の生えた耳が怯えたようにぴくぴくと動いていた。
「この地、水尾にとって大事な日にそんな顔してるはずないでしょ。」
「いやしてたろ。つか、あいつらも名家なんだからあんま睨むなよ。」
おちょくるように言う彼だが彼なりの気遣いだ。
「別に。良いよ。」
「良くはないだろ。お前これから先どうすんだ。今までそのためにやってきたんだろ?妖地の外に出て生活するのは難しいだろうし。」
確かに、時雨の言う通り妖地で暮らし、しかも妖術しか能のない私が外で生きていくのは無理だろう。結局は、水尾から出ることはできないのだ。
「次、挨拶、柏和家。」
箸を置いて立ち上がる。魚は結局、一口も食べることはなかった。
通り過ぎる時に、近くで話していた女達の目とかち合う。その瞳が嘲笑うに爛々とした色をしていた。
「私はてっきり水尾三大名家の柏和家から選ばれると思っていたけれど。」
「水菜ちゃんも柏和家の分家じゃなかったかしら?」
「水菜ちゃんは確かに分家だけれど、仰々しい扱い受けていなかったでしょ。ほら、そう。一番大切にされていた"雪乃様"ね。」
「ああ…みんな期待してましたものねえ。"龍のあやかし様に愛された子"だと。柏和家の言っていた話は水菜だったんでしたかね。」
やはり、先程から私への当てつけで言っていたのだ。その声から逃れたくて、浅く瞼を閉じる。
守護主と花嫁様の正面に来る。嫌でも女の顔がはっきり見えた。
上等な白い着物から覗く肌は透き通るような美しさを持ち、黒髪の下の瞳は可憐だ。龍の花嫁になるために生まれてきたと言えるほどに美しい。
何も込めていないただの言葉を吐き出す。
「此度はおめでとうございます。ーーーお姉様。」
分家に残った腹違いの一つ上の姉。妖術が使えないどころか、生まれながらに妖力を宿していなかった、周りに無能と言われてきた女。
姉の相手が守護主様でなければ、私は素直に祝福できたのだろうか。
「誇らしいわ。」
そう言った奥様の言葉、家事をしろと言い続けたのと同じ口から出たとは思えなかった。
"幸せになってほしい。"
あの言葉がずっと反芻している。
「貴方の妹である雪乃から、ささやかな贈り物をさせていただきます。」
その声にはっとする。もう、そこまで挨拶が進んでいたなんて。
「雪乃、準備を。」
「はい。」
踵を上げ畳に爪先を立て、右足をついて立ち上がる。
深呼吸の代わりに軽く吸った空気は凍っていたように、重苦しい。姉と守護主様を交互に見る。
「それでは舞わせていただきます。」
何十、何百回とやってきた中で、今、この瞬間、一番大事な舞台。緊張していないわけではない。しかし、心臓の速さはいつもと変わらない。
手のひらに妖力を込める。私の妖力量は人の平均より、ほんのすこし少ない。要するに量は凡人。
ーーー"舞う"のは、私ではない。
手から出す、この妖力は目の前の守護主様が司る水のおかけで、透明な色をしている。そこに色はない。
背骨を作りそこから棘のように尖った骨を生やしていく。包みこむ、燃える赤い身はこいつ筋肉。守るための皮、その上に生える鱗は水を浴び、時に裂いていくはずだ。
二匹の鯉は流れる川の水と一緒に泳ぐ。宙を回って、一体になって、自然の摂理の通りに二匹も一つになる。
その地、水尾とその守護様と花嫁が永遠でありますように。そんな願いを込めて、妖術でできた鯉を舞わせる。
「素晴らしい。」
その守護主様の端正な顔は動かず、ただそう告げた。
本来ならこの舞いは嫁取りで披露するものだったのだ。それゆえに私を花嫁として選んで欲しかったなんて言えるわけがない。
*
席に戻るのはなんだか嫌で外で風に当たっていれば、和服を着て、髭の生えた男が近づいてきた。
「素晴らしかったなあ」
わざとらしいほどに、賞賛を表す拍手をして現れたのは、中年部とりの男だ。その舐め回すような視線に寒気がした。
「良い舞いだったがなあ…あれが柏和家の実力。といったところかねえ。古風で味のある舞いではあったが地味だな。」
これで隠しているつもりなのか、ただの嫌味なのか。つまり、彼が良いたいのは、私の舞いがそこまで噂になるほどの実力ではない。柏和家に神輿として担がされていただけだ。と言いたいらしい。
選ばれなかった、と言っても、こんな奴にまで、言われる筋合いはない。私がやってきた事にさえ、けちつけられるなんて。
そう言いたいが、私は花嫁ではない。候補ですらなくなった私はただの小娘だ。そうなったのは自分のせいだ。
気づかない、ふりをしろ。
「お言葉、ありがとうござ」
「お言葉ですが、」
重ねるように低い声がして、振り向こうとしたがその誰かに頭が掴まれて前に向けられた。誰だ、とは思ったが不思議と恐怖感はなく、そのまま中年の男を見ることにした。
「あ…あっ、あ………」
男の眼は見開かれたまま、小さく呻き声を上げて、まるで死んだ人間を見たような反応をしている。この意地悪い男にそんな顔をさせてしまうとはどんな人間か。柏和家当主?いやこんなに低い声ではない。
「先程の妖術舞いはかなり洗練されたものです。あのように繊細で美しい妖術の鯉は見たことがない。確かに夏の祭りで行われる妖術舞いは派手で明るいですが、所詮は子供が楽しむためのものです。」
「あ…あっあ…」
「緻密で美しい彼女の妖術舞いは、妖術を学んだことがある者なら誰もが分かります、彼女の努力に。」
心の奥底がじんわりと熱も持つように温くて、掴まれたままの頭をそっと下へ下げる。
ーー嬉しかった。ずっと言ってほしかった。
気を抜けば泣き出してしまうようで、息を詰める。それほどにこの大きな手の誰かは、私にとって意味のある言葉を言った。
捲し立てている後ろの誰かを、中年の男は聞いているのかいないのか、ずっと呻き声を上げているだけだった。この男のことだから、自分は批判したわけではないとか、言い返しそうなぐらいなのに。そしてやっとわなわなと震わせた唇を動かした。
「鬼の、守護主様……」
「え…」
"鬼の守護主"
今、こう言った。反射的に後ろを向けば、彼はもう掴んだ手を緩めていた。
顔は同じ視線になくて、自然と見上げれば、結ばれた燃えるような真紅の髪、満月のような瞳は夜の月を思わせる。180は超える上背からは威圧感すら感じる。眉目秀麗、その言葉に尽きるが頭からは龍の守護主とは異なる、まっすぐな鬼の角が生えていた。
雷を司る、鬼のあやかし。
現在水尾と対立しているとされる、蓮宵の守護主。
「良いね。君、気に入った。少し二人で話さない?」
*
わざわざお屋敷の奥にある部屋をお借りして、鬼の守護主様と私は祝言が終わるまでの間、お話をすることになった。ともかく、絶好の機会だった。他の地の守護主様とお近きになれる機は滅多にない。良い相手は見つからなかったとしても、これで顔見知り程度にでも慣れれば、奥様もお喜びになられるはずだ。
「なんであの時言い返さなかったの?」
「え…」
何度目だろう、彼の言葉に対してこんなに呆けた声を出すのは。龍の伴侶候補者であったこと、選ばれなかったことを話しても彼は気にする様子はなかったのだが、逆に淡々としていて拍子抜けてしまう。
「あれは確実に君への嫌味だった。」
「やはり…そうですよね。でも私は龍の守護主様には選ばれませんでしたし。」
自分で言いながら、また心に雪が積もるのを感じた。
「結局、妖術も意味のなかったことでした。だから、妖術を分かっていただけないのも、言われるのも仕方ないことだと思います。」
これは本心だったが、姉へのこともあった。姉が言われていたのは、きっとこれ以上酷い言葉だったのだろう。私に欠けているものは、もっと大事なことだった。そしそれが満ち足りることは、もしかしたら無いのかもしれない。
「そうかな?」
ふにゃりとそのお顔が笑った。鋭く、きりっとした印象を受ける顔のどこにそんな表情を隠していたのだろう。
「過去の自分の頑張りを否定すること、それは一番してはいけないことだ。そうしたら、君は、一生、次の一歩を進めなくなる。」
彼の放つ言葉で、自分の頭が冴えるように、鮮明になるのを感じる。
「認めなきゃいけない。」
強くて、優しい言葉だった。
「あの…」
ぐらりと、視界が傾いた。
「ああ…やっと、少し酔った?」
「よ、酔う?」
酒類は口にしていないはず、と考えたところで、さらに視界が揺れ、地面に倒れ込む、と思ったが衝撃はなかった。
動かない首で振り向けば、寸でのところで守護妖様の腕に体を支えられた。
夢中で手を伸ばすが、雲を掴んだように何もない。そんな私の手をそっと掴み、そのまま引っ張られるようにして抱き上げられた。
「な、何して……」
「妖力酔いだよ。君はすごく耐性があるみたいだけど。」
彼の胸板に手をついたことで、その下の筋肉を感じる。急に体格差を感じ、本能的な恐怖を感じた。厚い胸板、私を抱き上げている大きな手には血管が見える。
ーーー敵わない。
「こ…こわい……こわいです…」
多分、私なんてそのまま力を入れたら折れてしまうだろう。そんな気さえ感じる。
「そう」
その低い声は、聞いたことがなかった。どうとでもできるようはその圧倒的な強者の余裕の瞳が、弱者を前にそこにあった。
鬼だ。
牙を剥き、弱った獲物にとどめをさされるだけの、獲物になった気分だ。
「な、なんで……」
何か気に触れてしまった?それとも自然現象なのだろうか。そんな疑問を見透かしたように、金の瞳を細めた彼は話出した。
「水尾と蓮宵が対立しているのは知ってるよね?」
「はい…?」
「元は、水尾が原因だった。蓮宵に対して秘密裏に間者が入り込んでいることを、あの龍は黙認していた。間者が捕まり、その事実が明らかになった。」
何を言っているのか、そんな守護主様しか知り得てはいけないような情報を、なぜ私に。
「水尾は、謝罪をすべきだ。蓮宵に対して。」
全く意味がわからないのに、鋭い満月の瞳に捉えられたみたいに、指先も動けない。
「そこで…君が選ばれた。君は次期龍の伴侶とも言えるほど、妖術の扱いが上手く、龍に適応している人間だ。龍の妖力の一部を取り込むということは、龍の妖の一部の力に干渉できるようになる。」
「君を殺し、血肉を喰らうことでな。」
「は、」
「もちろん、当主の龍も最初は抵抗した。しかし、この提案なら良いと言ってね。利が生まれたんだ。君に汚名を着せて殺すことで、柏和家を潰すというね。」
ぐっと喉もとに手を当てられ、じわりと汗が浮き出ても、抵抗することは出来なかった。
「君は使われたんだよ。許可を出したのは君の姉だ。」
「そんな、わけ…」
"幸せになってほしい"この言葉が、嘘だったというのか。そんなわけない。とも思ったがああ、そうなんだとどこか頭の奥底では冷静に理解した。その方が酷いことを言ってしまった自分にとって都合が良かったかもしれない。
殺す、と告げられているはずなのに、何も怖くない。怖くはないが、許せなかった。
「口付けをしたいです。」
「え」
「お願いです。今生最後なのです。」
そっと彼のほおに触れる。妖だからこの世のもとも思えない美しい顔立ちしているが、触って初めて人間のように感じた。
「龍の伴侶候補として、今まで励んできましたのに、口付けも経験しないまま、この世を去るなんて…酷だと思いませんか?」
彼は何も言わなかったが、眉が少し下がったように見える。それを肯定として、ゆっくりとその白い首を触り、自分の方に近ける。口付けなんて、したことなかった。しかし、最初で最後が彼なら悪くない、なんて思ってしまう。
「守護主様、ご無礼をお許しください。」
その赤い髪の後頭部に手を置き、自分のほうへ引き寄せる。
そして、その整った唇な口付け、
ーーー妖力を吸い上げた。
「お前っ」
鬼の守護主様の満月のような瞳が、大きく開かれると同時に、彼を目一杯突き飛ばした。
「はあ…はっ……」
彼との距離ができる隙に、急いで立ち上がる。
身体に合わない妖力を取り入れたせいで、喉が焼けるように熱を持って痛みを訴えている。しかし、私の中の妖力が確かに満たされていくのを感じた。これで酔うことはない。
「人間は、身勝手な生き物です。常に自分のことしか考えていない。」
結局、本家の人間も、妹も、龍の守護主様も、聖人だと思っていた…姉でさえ。
「なら、私も多少は好きにさせていただきます。」
そうして彼に向けて妖術を放とうとした時、浮き上がるように力は抜け、目の前に暗闇が広がった。
ーー
ばたり、と音を立てて彼女が倒れる。打ちどころが悪くないと良いのだが。万が一にでも怪我などあっては大変なことになる。
「しかし…やられたな…」
酷い目にあったのは俺の方だ。ひりひりと痛む腕をさする。わざわざ頼まれて迎えに行ってはこんな羽目になるなんて。
彼女を起こしてやろうと立ち上がった時、けたたましい音が鳴った。
「はあ…」
西洋産の黒い受話器が震えながら鳴っている。もうそんな時間だなんて、意外と危なかった。渋々それを取れば、嫌な女の声が聞こえてくる。
「ああ…はい。俺だけど。……ええ?ほんとに喰らうわけないだろう。心配なら確認してもいいけど。第一鬼は人を食べるとかそんなのいつの時代の話だと…ああ…分かった。」
そっと抱き寄せれば、眠ったまま動かない彼女の長い睫毛の下の白い頬は打ち付けて少し赤くなっていた。
その頬を、先程の彼女にされたみたいにそっと撫でてやる。
「良いね。雪乃、彼女は合格だ。」
電話越しの人物がこの光景を見れば、殴られるかもしれない。
「雪乃は俺が面倒を見る。ええ…大丈夫だよ。
ーーお義姉さん?」
その柔らかい唇にそっとキスを落とした。